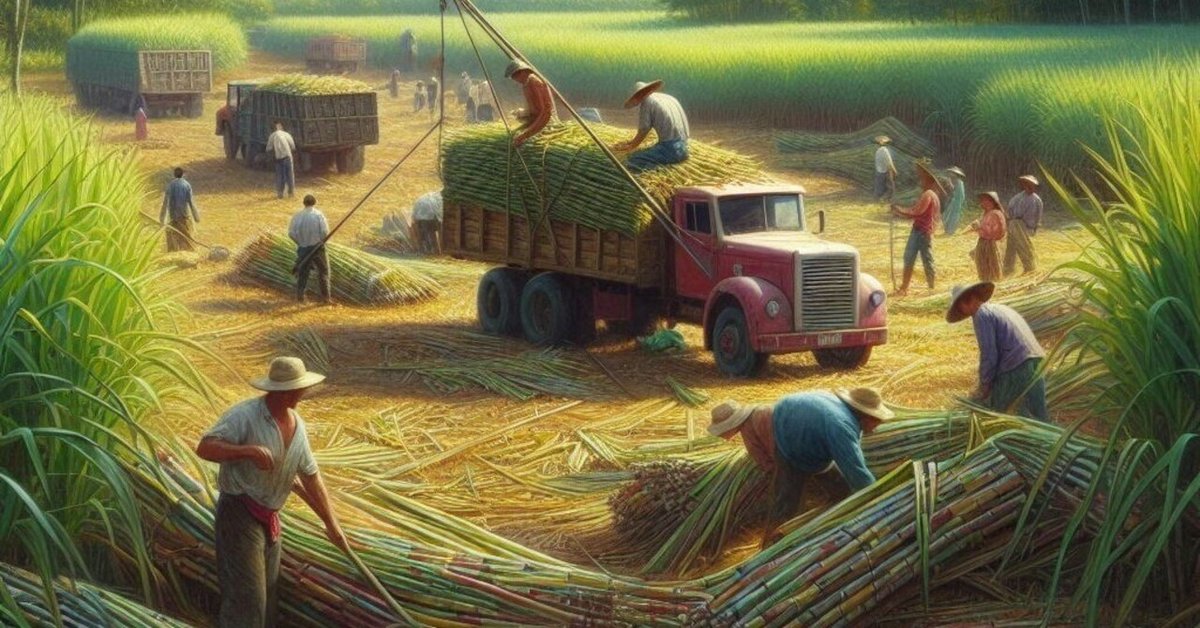
サトウキビ Ni28
農林28号 (母本:RK87-81 父本:F172)
生い立ち
1994年に沖縄で産まれ,1996年に宮古島に播種された.1999年に系統名RK96-6049と命名された.2011年に品種登録されNi28となった.黒穂病に強い早期高糖性品種.茎数型で株出し多収性を持つ.葉色が初期生育では黄色い.夏は緑色になるが冬季に気温が下がると紫色になる.成長亀裂が多い弱点をもつ.系譜を見るとF172の戻し交雑になっている.
時代背景
南北大東島は終戦後,さとうきび生産を最も早く開始した地域である.つまり育種の黎明期に作出された品種がいち早く導入され,同じく黎明期に導入された農業機械が定着した島である.品質取引以降,育種の過渡期を過ぎてなお,高糖性品種よりも重量取引時代の品種が多く,糖度と生産量を兼ね備えた品種の作出が望まれていた.育種サイドでも地域性が重視されており,大東地方向けの品種について試行錯誤していた時代である.
大東地方は慢性的な人手不足なため,植付けが思うようにできずに株出し主体の島となっている.株出しも1年から3年くらいまでは新植よりも多収となるが株年数が古くなると減収する傾向にある.これを解消するための品種改良が求められていた.
草型と特徴
葉の色に特徴があるが,夏の間はちゃんと緑色になる.未展開葉は直立し,先端だけ横向きに折れる.展開葉は水平になり弧を描きながら下向きになる.分げつは横向きに伸びるので畝の上には葉が多い.下垂するので葉が多い位置は最上位展開葉よりも下になる.これは分げつが斜めに伸びることが主な要因である.

以下,参考にならない勝手な考察
多段階株出多収性というのだろうか?何回株出しても単収が落ちない.それがこの品種の最大の特徴である.まず,黒穂病に強い.だから病気で弱るリスクが少ない.茎数型だから茎数が減らない,そして必要以上に増えない.個葉があまり大きくない.根が強く機械で引っ張っても抜けにくい.萌芽が早い.以上が多段階株出しに影響しそうなNi28の特徴である.その萌芽性の良さから3月に気温が上がり始めると製糖期に萌芽した芽が大きくなるのでトラッシュが増えるという欠点もある.
葉色について,緑色はクロロフィル,黄色はキサントフィル,赤はアントシアニンで,これらはどんなサトウキビも持っている物質である.普通はクロロフィル含有量が最も多いので緑色に見えるのである.クロロフィルが少なくなると葉の色はキサントフィルもしくはアントシアニンの色に依存するので黄色や赤に見える.Ni28はおそらくクロロフィルを作るのが苦手で分解するのは得意なのだろう.クロロフィルを増やすために他の品種よりも窒素を多めにする必要があるかもしれない.
さて,LAIは受光態勢が良く,群落の下の方で光を受ける形をしている.LAIは広がりやすく光合成も行いやすい理想的な形をしているがこの品種は節間があまり長くならないのか分げつが密集しているように生えるので株の上も畝の上も群落の上の方から暗くなる.つまりLAIが拡大しやすい特徴がある.密植に耐えられる構造ではないはずなのだが,萌芽した分げつは横向きに光がある方へ伸びるのであろう,茎数が安定しているので収量も安定するのである.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
