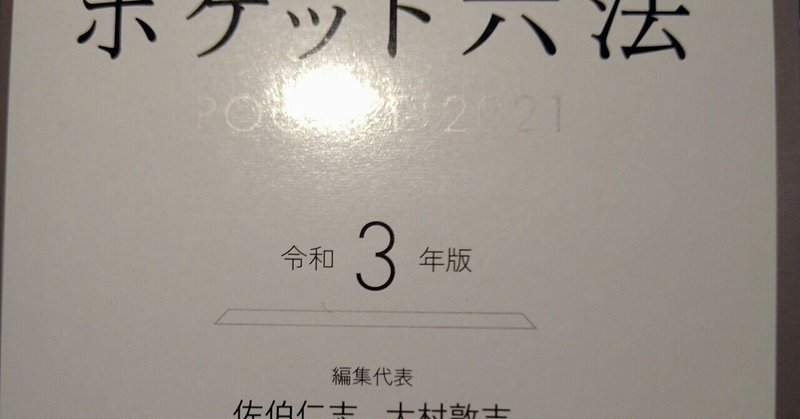
司法試験予備試験挑戦の学習面の振り返り、考察
1.はじめに(注意点等)
本記事は司法試験予備試験を目指した自分の学習方法等を振り返って考察したものです。
本記事の目的は、司法試験予備試験をこれから目指そうと考えている人(特に大学生)や司法試験予備試験受験生の人に参考にしてもらうことです。とはいっても、それ以外の人にとっても有益な情報があるかも知れないので、気が向いたら読んでくれると嬉しいです。
なお、筆者は司法試験予備試験未受験者です(詳細は、私の前回のnote記事を読んでください)。
あと、一応言っておきますが、勉強のやり方は人それぞれ向き不向きとかがあると思います。したがって、私の勉強方法や生活スタイルを参考にして成果が出なかったとしても、責任は負いかねます。
前置きが長くなってしまいました。以下本題です。
2.振り返り、考察
(1)そもそも何故『予備試験の大学3年次合格』を目指したのか
理由は3つあります。
理由1つ目は、自分にとってはこれが最短で法曹になる方法だったから、です。
早く法曹になれば、多くのメリットがあると考えました。例えば、早い段階で法曹としての収入を得られる、法曹として自分のやりたい事ができる、ロースクールの学費が不要になる、等です。
なお、大学3年次が最速な理由は、私が中央大学法職講座のカリキュラムに則って勉強していたからです。私は経済的理由で予備校には行きませんでした。
理由2つ目は、大学1年次の夏の試験の成績が思っていた以上に良かったことです。
自分は大学受験の際、中央大学が第一志望でした。そのため私は大学内で下の方のレベルに位置すると考えていました。しかし夏の試験の結果が思ったよりもかなり上位の方で、自分の実力に対して自信がつきました。これ以前までは、自分には予備試験なんて手に負えないと思っていましたが、自分の予備試験への可能性を感じたのです。
理由3つ目は、自分の周りの同期の人でも3年予備試験合格を目指している人がいたことです。当時その人は自分と同じくらいの成績だったので、自分も予備試験を目指して良いレベルなのだと再認識できました。
(2)勉強時間について
食事や睡眠、休憩や昼寝の時間といった、『物理的に勉強が不可能な時間』以外の時間を全て勉強時間にあてていました。したがって、少なくとも平日、休日共に、1日平均で12時間くらいは勉強していたと思います。この勉強時間から授業やその予習復習をする時間を引いた時間が自習時間(自分の好きな勉強を好きなようにできる時間)です。
この勉強時間スタイルは自分が大学受験の際に身につけたもので、実際に合格できたやり方でした。
しかし、大学受験と違って長期戦(最短でも司法試験合格まで2年はかかると思います)となる司法試験予備試験にはオススメできません。自分の場合は負荷が大きすぎました。ストレスがヤバいです。このやり方も、前回のnoteに書いた私のメンタル不調の原因の1つかとも思いますし。
また、勉強時間に拘りすぎると、勉強の質が落ちるかなとも思います。集中してない時間ができたりしてしまいます。
以上より、今となってはメリハリを重視して、もう少し時間を少なくして勉強するべきだと思います。
(3)基本書について
私は基本書を辞書的に使っていました。問題演習等でわからなかったところとかを読む感じですね。なので通読(頭から最後まで全ページ読む)はしていません。1年生の夏休みに通読しようとしたんですが、難しくて挫折しました。笑
使っていた基本書は主に、先輩や先生、同期に良いと聴いたものや、書店でちょっと立ち読みして自分が良いと思ったものです。
以下一応私の主として使っていた基本書をまとめておきます。なお、選択科目は勉強していないので書きません。
・民法→新井誠『民法講義録』
・刑法→大塚裕史他『基本刑法Ⅰ』『基本刑法Ⅱ』
・憲法→芦部信喜『憲法』
・民事訴訟法→高橋宏志『民事訴訟法概論』
・刑事訴訟法→宇藤崇他『リーガルクエスト刑事訴訟法』
・商法(会社法)→伊藤靖史他『リーガルクエスト会社法』
・行政法→中原茂樹『基本行政法』
(4)論文勉強法
大きな流れとしては、問題解く→ミス分析→論証集に一元化→インプット→問題解く…の繰り返しです。
問題を解くときは、原則全てフルスケールで答案を起案していました。答案構成のみと、実際に書いてみるのとでは、全然理解の確認の程度が違うので。答案構成のみにとどめるのは、フルスケールで書く時間が無いとき、問題が全然わからないとき(論点がわからないとか)、完璧な答案を書ける自信があるとき、くらいなもんでした。
『論証集に一元化』というのは、自分の論証集に書いていない論点についてのまとめや、良いなと思った参考答案等の論証を論証集にメモしておく事です。結構時間がかかる作業ですが、これを繰り返しやっておくと自分の弱点が発見できたりするし、「自分の論証集を見れば全て書いてある!」状態になるのでオススメです。「あの話どこに書いてあったかな〜」みたいに探したりする時間が節約できます。
(5)択一勉強法
自分は論文よりも択一のほうが苦手なので書くのがはばかられますが、基本的に論文と同じ流れで良いと思います。
択一の一元化ツールとして、『択一六法シリーズ』が有名かと思いますが、個人的には情報量が多すぎる気がしました。そこで私は自作のまとめノートを作っていました。
択一は論文と違って、出題範囲が広く、マニアックなところとかも聞かれます。なので、論文でも択一でも大事なところはしっかり、択一のみのところは直前期に、みたいにメリハリが大事かなと思います。
(6)長期的なスケジュール
基本的には中央大学法職講座のカリキュラムに則っていました。法職のゼミ等の予習復習を中心にやる感じです。普段の勉強はほぼ論文オンリーで、択一は試験の直前だけ気合入れてやっていました。
ただ、予備試験短答の直前には択一に全力を注ぎたかったので、2年生の12月末までには論文の重要部分の全科目網羅を目標にしました。つまり、会社法と行政法だけ法職よりも少し早めに始めた感じですね。
それで、年明けから択一の比重を増やして行き、直前期(3ヶ月前くらいから)には択一しかやらないつもりでした。
(7)法曹一貫教育(大学3年間で早期卒業してロースクールへ行くルート)と3年予備試験対策の両立は可能か
かなり厳しいと思いますが、不可能ではないと思います。
法律科目のGPAについては予備試験の勉強を本気でしていれば問題無くクリアできると思います。そこで問題となるのは、法律以外の科目のGPAです。この難関をなんとかして攻略できる人なら両立できるでしょう。
ちなみに私は予備試験第一に勉強していましたので、早期卒業は、あわよくば的な感じでした。法律科目で高評価を取って、なんとかGPAをつり上げてました。
3.おわりに
長文になりましたが、皆さんの進路等に役立てば幸いです。
コメント等あればお願いします。
お読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
