
ハイドンという体験
フランツ・ヨーゼフ・ハイドン(1732-1809)。オーストリアの田舎町で生まれ育ったこの男の魅力は一体何か。
まず彼の人生について軽く触れてみましょう。

こちら、ハイドンさんの御尊顔でございます。
年表(ザーッと)
1732年にローラウ(現在のオーストリアの最東端)で生まれ、少年聖歌隊に入るも友達の髪の毛を切ったり...と色々やらかします。結構なガキでした。その後屋根裏部屋での8年間のニート期間を経て、
1757年(25歳)からモルツィン伯爵の元で宮廷楽長、いわゆる作曲して演奏するのを取り仕切る仕事を始めます。この時期から本格的な作曲活動に着手します。そしてこの時、マリー・アンナ・ケラーという女性と結婚しますがこの人、「僕の人生最大の失敗は結婚だった」と言ってしまうほどのヤバい人でした(詳細はググってください)。10年間という長い別居生活ののち妻が先立ちますが、その呪縛からの開放感が弟子プレイエルへの手紙の中に綴られています。ゲスですね。笑
1761年(29歳)、エステルハージ家に就職します。そしてこの年から約30年間、とにかく曲を書きまくります。すごい量を。音楽好きの城主も出資し、楽団の規模は見る見る大きくなっていったのです...
1781年(49歳)、中年のおっちゃんになったハイドンですが、若きモーツァルト(当時25歳)と知り合います。離れた歳だったにも関わらず、意気投合し、お互いに曲を書き送り合います。
1790年(58歳)になると、これまで親しかった城主が死去。この次に城主になったアントンっていう人が、音楽に興味のないやつだったんです...音楽に対するお金もかたっぱしから減らされ、「音楽?聴かないかなぁ...年金あげるから仕事しなくていいよ」と、年金暮らしを言い渡されてしまいます。
ここでハイドンは一念発起。発想の逆転です。
やっと自由の身になったハイドンは、遠く海を隔てたロンドンで新しい人生を画策したのです。そこでモーツァルトとこんな会話をしました。
ハイドン「この機会にロンドンへ演奏旅行しようと思う。」
モーツァルト「え、ウソでしょ?だってもうすぐ60歳...簡単な旅じゃないですよ。だって英語も話せないじゃないですか!」
ハイドン「言葉は交わせなくても、僕の音楽はきっと分かってもらえるよ!(ポジティブ)」
モーツァルト「そうですね...絶対元気に帰ってきてください!また会えるのを楽しみにしています!」
1791年(59歳)、ロンドンへ旅立ちます。そして演奏会は大成功。
1792年(60歳)、無事ウィーンへ戻ってきました。しかし、そこにモーツァルトはもういませんでした。なんとハイドンの帰りを楽しみに待っていた若いモーツァルトが先に亡くなってしまったのです。まだ若かったのにお互いの気心の知れた大切な友人を失ったハイドンは深く悲しみましたが...
1794年(62歳)、なんと再びロンドンへの旅に出ました。この旅でも演奏会は大成功。しかも彼の作品だけではなく、彼のフォルテピアノの演奏を聴きたい人たちも多く押し寄せました。そこで20000グルデン(約4000万円)の報酬を得ます。当時の音楽家にしてはとんでもない額です。笑
1795年(63歳)、ロンドンへの移住も考えたハイドンですが、ウィーンへ戻ります。そこでエステルハージ家から「音楽に興味のなかった城主がいなくなったのでまた戻ってきて欲しい」と連絡があり、ハイドンはお世話になったエステルハージ家のために、再びゆるーく作曲を始めます。この時に宗教曲をたくさん書き上げます。
1802年(70歳)、この時代であれば、この年齢まで生きているだけで万々歳です。しかし夜も眠れなくなるほどの腰痛に悩まされ始め、演奏活動も作曲もできなくなってしまいます。
1809年(77歳)、ウィーンにて亡くなります。ナポレオン戦争の真っ最中、窓の外を見ると砲弾が降り注いでいた中、亡くなる最後の瞬間までウィーンの未来、そしてウィーン市民の様子を案じながら自分が作曲した国歌を弾いていたそうです。

↑ こちらがハイドンが亡くなった家の近くに落ちた砲弾。彼が亡くなった家にて展示されています。バスケットボールくらいの大きさでした。
亡くなったときの逸話は割と語り草となっていますが、実際にこうして砲弾を目の当たりにしてみると、やはりただ事ではなかったことがよくわかります。(と同時に、非常時でも人のことを心配できるハイドンさんすごいです...)
↑ ハイドンが作曲した「神よ、皇帝フランツを護りたまえ」
元々はオーストリア大公国を含む神聖ローマ帝国皇帝のために作曲され、その後第二次世界大戦後にドイツの国歌となりました。この国歌や歌詞は政治的にも翻弄された歴史があります..
↑ こちら、FIFAワールドカップの試合前に国歌斉唱するドイツ代表選手。
量と質と、発想と
弦楽四重奏曲、ピアノソナタ、交響曲をはじめ、多くの分野で大きな功績を残したハイドン。数にすると65のピアノソナタ、68の弦楽四重奏曲、そして104の交響曲。他にも宗教曲やピアノ/バリトン三重奏曲の分野においても、その数は夥しいものです。
例) もちろん、76歳で亡くなったハイドンとは反対に若くして亡くなった作曲家や、別の分野の作品を多く書いた作曲家もいますが、同時代の作曲家で比較すると以下の通りです。
モーツァルト(35歳没)は18のピアノソナタ、23の弦楽四重奏曲、21の交響曲。
ベートーヴェン(56歳没)は32のピアノソナタ、16の弦楽四重奏曲、9の交響曲。
シューベルト(31歳没)は21のピアノソナタ、15の弦楽四重奏曲、8の交響曲。
ハイドン以降のほとんどの作曲家は、この3つのどれかの分野において作品を残していますが、ハイドンがこれらの分野のパイオニアと言われるのには数だけでなく、ちゃんとした理由があるのです。
ピアノソナタ ~実験~
まず、約65曲にも及ぶピアノソナタ。
ピアノは一人で高い音から低い音、複数の音を出せる楽器なので、(基本的に)全て自分で完結できてしまいます。
これをうまく利用し、彼は一人で演奏できる鍵盤楽器によって音楽効果の実験をしていました。
彼がニートだった1750年ごろ(でもアクティブでした)、バッハの息子C.P.E.バッハのピアノソナタの楽譜を手に入れ、それに夢中になっていたそう。
C.P.E.バッハについてこう述べたそう。
彼のピアノソナタを全部習得するまで、この楽器を弾きすぎて壊さないようにしよう...!
そしてボクの曲を聴いた人は、ボクがC.P.E.バッハの曲をちゃんと勉強したことに気付くだろう!
C.P.E.バッハの曲もなかなか変わった曲が多く、ハイドンの音楽のように奇抜な発想が多く垣間見られます。おそらくハイドンの実験的な試みはC.P.E.バッハの作品からの影響を受けているでしょう。(こう思うことが、すでにハイドンの思うツボ)
当初ハイドンはピアノソナタに「ピアノソナタ」と名付けておらず、「ディヴェルティメント」とか「パルティータ」のようなバロックや初期古典の香りを引きずった名前をつけていました。鍵盤楽器のための作品は、ハイドンが中年を迎えたあたりからだんだんと需要が高まってきました。中流階級の趣味として手軽に弾けるソナタは持ってこいだったのです。と言っても、そう簡単な曲ではありません...(断言)
しかし面白い曲ばかりなのです。面白さ...ハイドン自身も腕の立つ鍵盤楽器奏者だったので、「あー、こんなこともやったら面白いかも知れない」というように、実験的な側面が多くみられます。

弦楽四重奏曲 ~1+1+1+1~**
次に68曲の弦楽四重奏曲。
ハイドンは「弦楽四重奏曲」という分野を初めて作った作曲家です。
元々はピアノソナタと同じく、ディヴェルティメントから派生しました。
「オーケストラだとデカすぎる...でもピアノだと物足りない...じゃあ4人で弾こうか」と言った形でしょうか。こちらでも多くの実験をしているのですが、4人のそれぞれの弦楽器奏者が違うことを演奏していると思えば、たまには同じことを一緒に演奏する、というような面白さを追求している感じがします。演奏者の異なるパーソナリティという面に照準を合わせた作品が多いです。
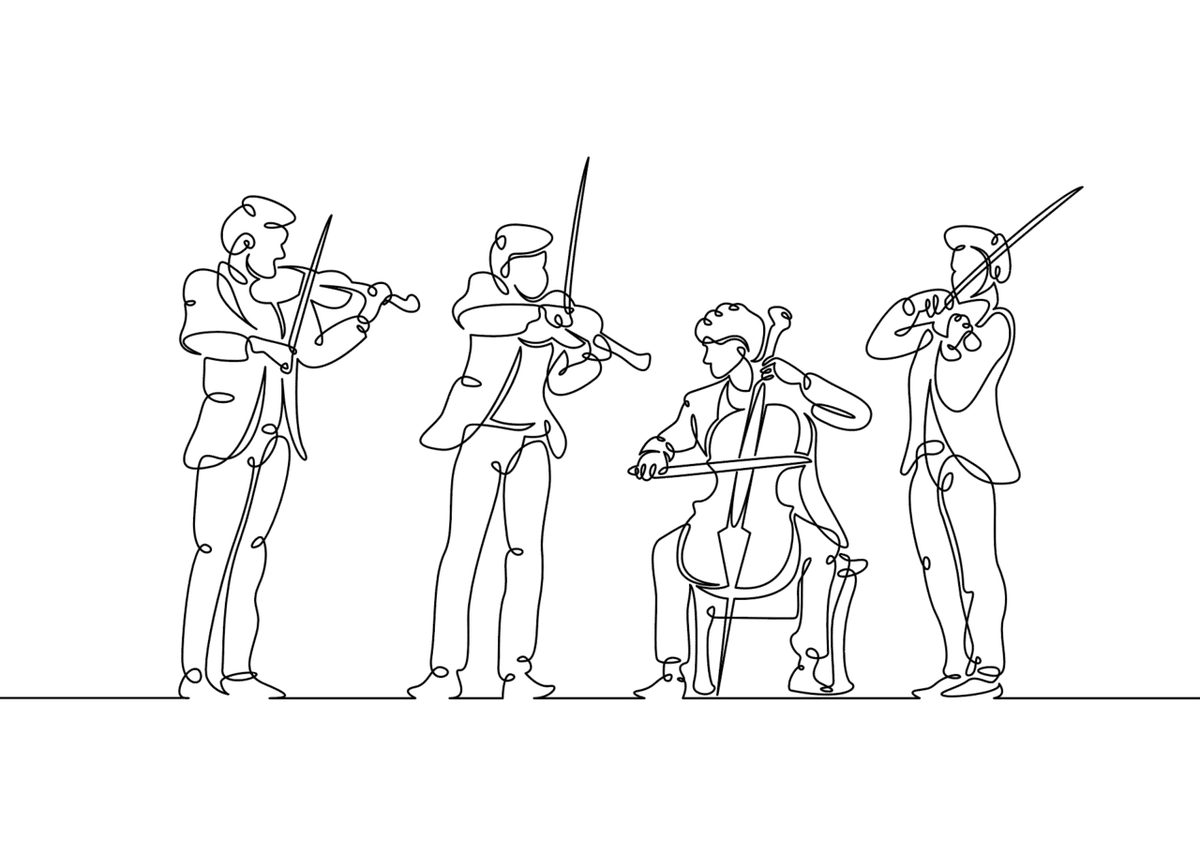
交響曲 ~体験~
はい、きました...交響曲です。全部で104曲あります。化け物です。
すでに若い頃(モルツィン家時代)から交響曲を書いていたのですが、彼の交響曲が爆発したのは、大貴族エステルハージ家に移ってからでした。そしてその爆発のきっかけはすぐに訪れます。
エステルハージ(47歳)「君が新しく入ったハイドンくん、だね?」
ハイドン(29歳)「はい!」
エステルハージ「なんか面白い曲を書いてほしい」
ハイドン「そうですか...ではお題をくれませんか?」
エステルハージ「んー...じゃあ『朝』『昼』『夕』で」
ハイドン「了解しました!!!」
こうして初期の交響曲第6-8番「朝、昼、夕」が生まれます。
それぞれ朝、昼、夕を表現した作品で、もちろん「朝」は朝焼けの情景から始まり、「夕」には嵐のような夕立ちが訪れます。しかしこれが実に効果的で面白いのです...普通なら交響曲の弦楽器は4パート、多くて5パートしかないのに、色々書いてたら7パートに増えてしまったり...!

↑ ハイドン: 交響曲第8番「夕」終楽章。弦楽器は下の7パート。

↑ モーツァルト: 交響曲第40番 第1楽章。 弦楽器は下の4パート。
こちらが一般的な弦楽器の編成です。
コントラバスのソロもあれば、楽器による語り(レチタティーヴォ)もあり...とここには書ききれませんが、普通ならあり得ないようなふざけたことをたくさんやっています。ふざけ…これは僕の主観ではなく、本当にふざけているのです。もちろんハイドン自身も自覚しています。これも、「エステルハージ伯爵の命令」の元、言い訳ができたからでしょうか。笑
そうしてハイドンは味を占めたように、面白おかしい曲をたくさん書きます。
例えば...
おならの音を、出そうな段階から表現 (交響曲第93番)
曲内で調弦を始めてしまう (交響曲第60番)
最後の最後で間違えたように別の楽章に戻る (交響曲第46番)
眠そうな音楽を演奏してから急に大音量で聴衆を叩き起こす (交響曲第94番)
一人ずつ舞台からいなくなって曲が終わる頃には誰もいない (交響曲第45番)
曲の終わりと見せかけて実は終わってないフェイント、聴衆が間違えて拍手(交響曲第90番)
一番最後で急に指揮者が楽器を弾き始める (交響曲第98番)
トルコの楽器登場 (交響曲第100番)
こちらも挙げればキリがありません...思っている10倍は面白いです。僕も「えーなにそれ」と思って聴いた記憶がありますが、実際聴いてみると知らない曲ばかりなのに、新しい発見や面白さがあり、なんだか新刊のマンガ(こち亀…?)を読んでいるような感覚でした。
このように、ハイドンの交響曲は聴衆にある種体験させるような作品、ふざけて笑いをも取ってしまうような曲がたくさんあるのです。実際に、ハイドンの交響曲を演奏会で取り上げて、笑いが巻き起こったり、フェイントにつられてしまうことは数多くあります。もはや聴衆を挑発するのです。(ベルリンフィルでの演奏会では曲間に拍手が2回起こり、ラトルと団員がニヤニヤしながら拍手が終わるのを待っている映像は観ていて本当に楽しいです)
ハイドン: 交響曲第60番終楽章、調弦の場面。
笑いをとるためにはどうしたらいいか、どうやったらみんなに分かりやすいか…などときっと考えてはその表現方法を試行錯誤していたことでしょう。
いわゆる「笑い」や「驚き」というのは他人事に対する感情であることが多いですが、ハイドンの作品の場合は、聴衆に体験させることによって共感型の笑いを生み出すこと、驚きを共有することができているのです。
104曲もある交響曲ですが、全てしっかりハイドンの血が通っています。「交響曲」というジャンルの先駆者であるだけでなく、彼のこうしたユーモアが200年以上の時を超えた今でもしっかりと生きているのです。天国のハイドンもきっとニンマリしていることでしょう...
大井駿

いいなと思ったら応援しよう!

