
【Kindle出版】干支の基礎知識/推命家必修~天干地支の哲理【干支の雑学】

Amazon紹介文より
一般の方には雑学としての知識でしかありませんが、四柱推命家やその他の東洋占術家にとって必ず覚えておくべき干支に関する最低限の教養です。
本来干支というものは占いとは直接関係がありません。甲骨文字の中の干支の使われ方は、たとえば日にちをあらわすものでした。もともと干と支はそれぞれ独立していたもので、序数としての意味を持っていたものです。
後に、陰陽・五行思想と結びついて、占術理論として体系化されたのは戦国時代(BC403~221)からだといわれています。
『史記』にいうところの殷墟(河南省安陽市小屯村)からおびただしい数の甲骨が発見され、甲骨文字の中に干支が刻まれたものをみることができることから、干支の出現はかなり古いものと推測できます。
甲骨文字とは、殷代の後期(BC1,550~1,050)、王朝における占いに用いられた文字です。当時は、行動のすべてが王を中心とする貞人(占って神意を正す人)による占い儀式の結果によっていました。
水牛の肩胛骨や、亀の腹甲の裏面を火で熱し、そこに現れたひびの様子によって吉凶を占っていました。その記録を亀版、牛版上に刻文として刻み朱を施し、刻文は聖化され神意が実現するものと考えられていたのです。
本来の干支は占いではなく、易の俗語でもない。 それは、生命あるいはエネルギーの発生・成長・収蔵の循環過程を分類、約説した経験哲学ともいうべきものである。 即ち「干」の方は、もっばら生命・エネルギーの内外対応の原理、つまりchallengeに対するresponseの原理を十種類に分類したものであり、「支」の方は、生命・細胞の分裂から次第に生体を組織・構成して成長し、やがて老衰して、ご破算になって、また元の細胞・核に還る――これを十二の範疇に分けたものである。 干支は、この干と支を組み合わせてできる六十の範疇に従って、時局の意義ならびに、これに対処する自覚や覚悟というものを、幾千年の歴史と体験に徴して帰納的に解明・啓示したものである。
本文より一部抜粋
■推命用語:甲木(こうぼく)
種子が発芽するにあたって「十」の形象のように亀裂する状態を指したもの。甲冑の意味を持ち、豆類などが春の気を受けてその硬い殻を破って芽を出し根を発し、あたかも兜を被ったカタチで地上に萌え出づるという姿を表している。




甲の性状:推命的解釈
甲尊・大木・剛毅剛直・勇猛果敢・勇気凛然若武者・武勇・義理人情・プライド・活動的・血気怒気・短気・社交家・秩序・ルール・妥協しない・孤高のリーダー・温情・相談役・支配欲・社会的貢献欲・批判精神・劣等感
■推命用語:乙木(おつぼく)
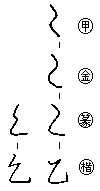
乙の字は折れ曲がって押し曲げられている様子。現在の軋轢の【軋】のもとの字である。 草木の芽生えの姿で、根も茎もくねくねと屈曲して軋然たる伸び方をしている象形を表している。 また神前に屈することを【礼】と書く。



乙の性状:推命的解釈
草花・乙女・女性的・柔らか・柔よく剛を制す・出世願望・安定・姑息・知略謀略・漸次的・慎重・特殊技能才能技術・自意識・意志薄弱・ストレス・一点頑固主義・トップの願望少なし・反権威・即断即決しない・様子見
★子(ね/シ)
五行配当:水(陽)
時刻:零時及びその前後二時間
方位:正北・黄経270度の冬至点を中心とした30度間
季節:十二月の大雪から小寒までの間
易象:地雷復
象形。子の原字に二つあり、一つは小さい子どもを描いたもの(A)。
もう一つは子どもの頭髪がどんどん伸びるさま(B)を示し、おもに十二支の子シの場合に用いた。
後に、この二つは混同して子と書かれる。
「孳」(「茲」のしたに「子」と書いたもの)の上部を略したもの。
「うむ・つとむ」とも訓む。
茲ジ(ふえる)字(親字から分化してふえた文字)と同系で、繁殖する意を含む。
また、絲シ(=糸。小さく細いいと)と同系で小さい意を含む。
大地に蔵された植物の種子が新しい生命を生み出す意があるところから十二支の首位に据えられたもの。
陰気極まって陽気の兆す一陽来復の「冬至」にあたり、暦では陽循開始の時候となる。
「子」は十二支の第一番目。万物を孳生するという意味の孳(じ)に由来。「墨池(ぼくち)」とも。


象形。子の原字に二つあり、一つは小さい子どもを描いたもの(A)
もう一つは子どもの頭髪がどんどん伸びるさま(B)を示し、おもに十二支の子シの場合に用いた。後に、この二つは混同して子と書かれる。
「孳」(「茲」のしたに「子」と書いたもの)の上部を略したもの。 「うむ・つとむ」とも訓む。
茲ジ(ふえる)字(親字から分化してふえた文字)と同系で、繁殖する意を含む。 また、絲シ(=糸。小さく細いいと)と同系で小さい意を含む。
大地に蔵された植物の種子が新しい生命を生み出す意があるところから十二支の首位に据えられたもの。
「子」は十二支の第一番目。陰気極まって陽気の兆す一陽来復の「冬至」にあたり、暦では陽循開始の時候となる。 万物を孳生するという意味の孳(じ)に由来。「墨池(ぼくち)」とも。



子の性状:推命的解釈
勤勉・節約・知性的・クール・冷静客観的・細かいところに気がつく・気配り・好奇心・変化を求める・器用・小才がきく・倹約家・利害に敏感・思い切り悪い・コツコツやる・損得勘定しすぎ
★丑(うし/チュウ)
五行配当:土(陰)
時刻:午前二時及びその前後二時間
方位:北北東・黄経300度を中心とした285度から315度に至る30度間
季節:一月の小寒から立春までの間
易象:地沢臨


象形。手の先を曲げてつかむ形を描いたもの。
すぼめ引き締める意を含み、紐ジュウ・ニュウ(締めひも)・鈕ジュウ(締め金具)などの字の音符となる。
殷代から十二支の二番めの数字に当て、漢代以後、動物・時間・方角などに当てて原義を失った。
紐という文字から「いとへん」をとったもので結んで解けないという意味を持つ。
寒気いまだ紐結(ちゅうけつ)して寒い。
渋滞の意味でもあり、植物が地中に芽生え伸ばし、根を張っていく状態を象徴したもの。



丑の性状:推命的解釈
決まったことを変えない・保守的・信用第一・理念を守る・決まりを守る・小金持ち的財運・正直・堅実・頑固・融通が利かない・けち・人懐っこい・涙もろい・弱気と強気が共存
Kindle電子出版
ペーパーバック(印刷版)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
