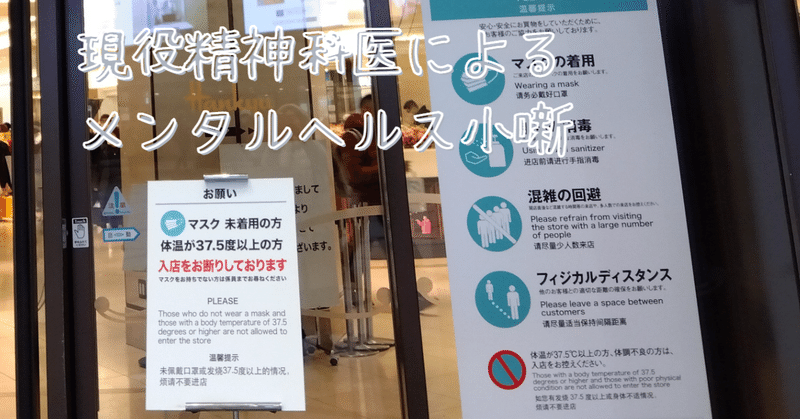
他人の不安を押し付けられる国・ニッポン~「お客様同士の不安」の「不安」って何?
マスク強要社会の愚かさ下らなさに気づいている少数の人々の支えになればと思い、この記事を書く。
もはやマスクは宗教のようである。ネットでのアンケート結果を見ていると、「マスク着用ルール」とやらがなくなったとしても6割以上がつけ続けたいと回答しているようで、暗澹たる気持ちになる。
その一方で、「外したいけど人目が気になる」「マスクを外すと何を言われるか分からない」等、外すこと自体への不安もまた、マスク社会を終わらせない。
どうしてこんなことになったのか。国や厚労省は、どこまで行っても「推奨」しかしていない。それを各種業界団体が拡大解釈し、義務化やお願いと言う名の強要が横行し、こんな異常が3年も続いているのだ。
教育現場やほとんど全ての労働現場においてマスクが義務付けられ、公共交通機関や施設では「マスク未着用入店お断り」の看板や張り紙が当たり前のように掲示され、目算であるが99%の人々が何の疑問も感じず、あるいは多少変だなと思っても黙って従っている。
ようやく5類変更やマスク着用は個人の判断にゆだねる、と言う報道が流れ始めてもマスクを外す人はほとんどいない。
強要、相互監視、忖度。あらゆる力が作用しあって互いを縛り付け合っているのが現状であるが、その中で際立つのが「お互いの不安解消のため」と言う文言である。航空会社や大手百貨店が堂々とをホームページ等に記載している。つまり感染対策とは関係ないことを強要する側も認めているのだ。
自分の不安を解消するために相手に行動変容を押し付けるなど、根本的に間違っている。
その視点が著しく欠如しているのが、この文言である。
嘆いてばかりでも仕方ないので、この「不安」とは何なのかを考えていく。
そのために、まず「不安」とは何かをおさらいする。
「現代臨床精神医学」という、医学部の精神科の講義でも使用される教科書にも書いてある。
不安とは、対象のないおそれ、すなわち漠然とした未分化なおそれである。内的で不明瞭で、源泉において葛藤を含む脅威に対する反応である。
未分化とは、「原始的な」とい換えてもよいだろう。つまり成熟した人間ではなくあらゆる動物において発生する外的刺激に対する生体反応に過ぎないのだ。
その機序をもう少し見ていこう。
生命体は視覚や聴覚、温痛覚などの外的刺激に常にさらされており、必要に応じて、あるいは不必要でも反応し、行動を決める。例えばオレンジ色の丸い物体を見たとき、網膜で光刺激としてそれを捉えることと、それが何であるかを認識するのは別である。その光刺激を受け取った瞬間に、脳内で無数の記憶のインデックスと照合される。「みかん」を知らない乳児は見えていてもそれが何か分からない。食べたことがなければ「みかん」と思うだけで何も行動は起こらない。「みかん」と言う学習と記憶があって初めて「みかん」であると認識し、同時に「みかん」の味や香りが惹起され、よだれが出てきたり食べようとする行動を選択したりする。
不安の話に戻る。
では、「不安」と言う情動が惹起されるのはどのようなときか。大きく分けて2通り考えられる。
1つは未知のもの。もう一つは、過去の恐怖体験である。
視覚や聴覚刺激に合致する記憶のインデックスが発見されなかった場合は未知であるので警戒せねばならない。
また、過去の恐怖体験が合致すれば、生命体は直ちに警戒態勢に入らなければならない。
警戒態勢に入った生命体はどうなるのか。再度、同じ教科書から引用する。
不安にはしばしば身体現象を伴い、これは胸がしめつけられる感じ(胸内苦悶感)、呼吸困難、動悸、冷汗、振戦、めまい感、頭痛などの不快な自律神経症状である。
不安に対して生じる身体現象は、生体がすぐに「逃げるか戦うか」の行動をとれるよう交感神経が優位になった結果である。
だが、ここで注意しなければならない。「不安」は常に正しいとは限らないから厄介なのだ。全ての感情がそうであるが、生体反応として生じた怒りや不安、緊張は、それを惹起させた記憶自体が間違っていれば、不必要または過剰に生じることもある。
では、マスク未着用者の存在により生じる「お互いの不安」とは何か。厳密にいうと、「お互い」ではない。「マスク未着用を受け入れられない者」の不安なのだ。
1つは、ウイルス感染に対する無知・無学による不安である。
ウイルスとは何か。感染経路を含めたウイルス感染が成立する要件は何か。少なくとももの2点を知っていれば、目の前にノーマスクの人がいただけで「不安」に駆られる必要などない。この程度なら、専門家でなくてもこの3年間にいくらでも学習する時間はあったはずであるのに、未だにノーマスクそれ自体を危険視する人々は、何も学んでいないので、彼らの不安は消えない。
もう一つは、恐怖の刷り込みによる誤作動的不安である。富岳の飛沫シミュレーションがあまりにも効果的に、人の呼気が汚物であるという歪んだ固定観念を多くの人の中に築き上げてしまった。しかし繰り返すが、もはや3年である。上記のウイルス感染に関する基礎知識の習得と併せれば、そして2019年まで人々がどのようにして暮らしてきたか、また既にマスクを捨てた諸外国がどうなっているかを冷静に考えれば、あの富岳のシミュレーションこそが洗脳であったことが分かるはずである。だがいつまで経っても学ばないので、彼らの不安は消えない。
不安とは、本来生命体が自分を守るために必要な情動である。しかし上記のように、不安は必ずしも常に正確かつ適切に作動するとは限らない。一般に、危機回避の域を超えた過剰な不安を「病的不安」という。
例えば、「飛行機が落ちたら怖いので乗らない」というのは理解できなくもないがいささか不安が過ぎるのではないかと誰もが思うだろう。
「交通事故に遭いたくないから一生涯外に出ない」選択をする人がいれば、もはや異常である。
断言する。
マスク未着用者に対する「不安」は病的不安である。
そしてそのような病的不安を基準としてその不安の解消を全ての労働者や交通機関の乗客や施設利用者や旅行者に押し付けてきたのが、今の社会なのだ。
では、ノーマスクへの不安はどうすれば解消されるのか?
全ての病的不安は、自分で解決するしかない。
「ウイルスに関する知識を自分で身に着ける」一択なのだが、もはや3年間も何も学ばなかった人々に、今さら学べと言っても一生学ばないだろう。残念ながら、狂った不安に駆られた人々に学習を呼び掛けても虚しく宙を舞うだけだ。
もはや「マスクを強要してはならない」と言う国からのメッセージの発出を以ってしか、マスク強要社会は終わらないだろう。
だが、それすら期待できそうにないほど、国もこの問題を放置し続けて来たし、今後もそのようなメッセージは発出されそうもない。
あまりに残念で絶望的な気持ちになる。
だが、ごく少数の「気づいている人」同士が支え合わなければならないのだ。オセロのように、一人ずつでも「歪んだ不安」に気づくように働きかけていかなければならないのだ。
せめてこのような記事を書き、同じ思いの人たちがこれを読むことで、自らの行動の支えになればと思う。
~おわり~
参考 現代臨床精神医学 改訂第11版 大熊輝雄 著
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
