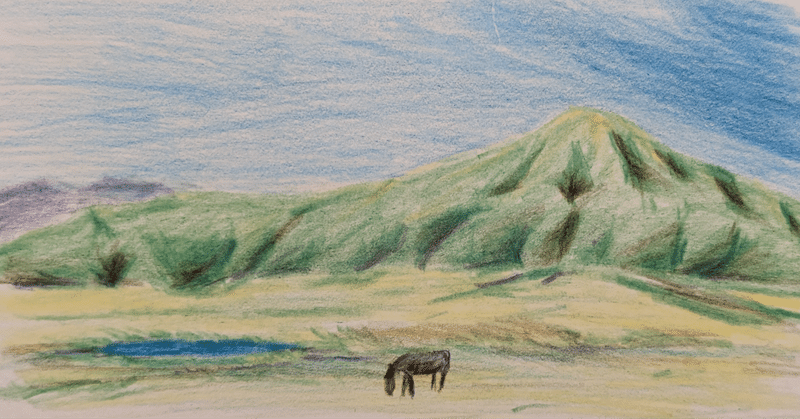
「安立町の隠れ家(コーエン兄弟の映画みたいな〝是非もない〟話) (井原西鶴・万文反古の翻案)
※伊原西鶴の「万文反古」は、主人公が、貧乏人が大事に集めたクズの山から手紙を見つけてそれを読み、世情を思うという日本の17世紀の書簡体小説です。岩波の新体系から翻案しています。
こんな手紙。
「去年の冬にこちらに参りまして、徳妙寺様の紹介状を持参しまして、(大阪市天王寺区の)上寺町に、兄弟で10日ばかり厄介になり、それ以来このお寺のご縁を頼りに住吉安立町のうちに必要最低限の小家を借り、バレないように表に古道具を並べて生活感を出し、下人の吉介に朝晩の食事を作らせ、事情がわからないように堺の浜の小魚を買って大坂の町々で行商させて、敵の隠れ家を忍び忍びに調べさせましたが未だに見つけることができず、武運が尽きたと思っておりました。
私たち2人が兄弟と言うこともできず、気の張る日々です。名字は隠し、名前も伝五郎、伝九郎と変えまして、姿格好も様々に変えて、私は膏薬売りになり敵を隅々まで探し、気を抜くことはありませんでした。
また弟の方は、次第にいい男になってきまして目立つので、商売に出しかねまして、普段は家にいさせておりましたら、前後に6〜7人の家来をつけているのに槍を持たないあやしい一行を見つけました。雨や風がないのに早駕籠の窓を閉じ、なんとなく忍ぶ有り様を見まして伝九郎それを追いかけ、窓の中を見ましたら頭巾を被っていて敵である戸平に間違いないと、防御着(帷子)は常に着込んで入り、刀を掴むを跡をつけ、打ちかかるタイミングを見合わせて、泉州の信太という里で駕籠が止まり、その人物が出茶屋の人に古歌の楠の木、葛の葉の裏道を案内させて、庄屋の中庭を進み始めたところで、ここだ、いまだ! と意を決して先へ回り(楠の木の)木陰から走り出て、
「横井尉左衛門が伜子(せがれ)、見忘れたか、奥関戸平! 逃れぬ所!」
と打ってかかりましたら、この侍が飛んで退き、
「やれ、待て! 人違い!」
と手を上げたところに伝九郎なお進んでまさに斬りつけようとすると、侍は溝川を飛び越えて大小の刀を腰から抜き捨てて無刀となって、家来たちが伝九郎に迫るのを止めて、
「私は岩塚団之丞といって、生国は越前の者ですが、おおかた見てわかるでしょうが、病気(疝気)で筋骨が痛み、主人にお暇を申し上げて熊野に湯治に行くところで、これは思いもよらない難義です。こちらは大勢なのでどうにでもできますが、若者の敵討ちの心がけで、早まって見違えたのだから、少しも遺恨はありませんよ」
と道理にかなったことを言う。
伝九郎それをよく聞き、少し考えて、本当に戸平にそっくりの顔だが、9歳の時に見たきりで、記憶がおぼろで慥かではない。殊勝にも刀を捨て私を安心させてから次第を話したし、戸平ならそんなに落ち着いた対応はできないだろうと思い、
「さては、わたしがそそっかしくしまして、すっかりご赦免ください。お年頃といい戸平と言う者に似ていてついつい間違えました。私の兄伝五郎が念を入れて戸平の顔を書き写し、いつも懐中に入れております。右目の上に2寸ばかりの傷があり、縮れ髪で首筋が太く、肌は浅黒いと書き付けがあり、一つ一つ見ますとほぼ一致しておりますのも不思議なものです」
と言いますとこの侍、横手を打って
「それは奇妙な他人の空似、危ない命を拾いました」と大笑いして「いまだ若年の身でこれだけの志、世に亡きお父上もさぞさぞご満足のことでしょう。この勢いならばすぐに敵討ちを果たせますよ。もし北国に来ることがあったら必ず訪ねてきてください」
と互いに礼を尽くして別れ、家に帰って様子を私に話しまして、詳細をよく聞けば、敵戸平に違いありません。
「これは武運が尽きた。次はいつの世にめぐり会うことができるだろう。きっと大坂に隠れていたのを大和路へ退去しようとしていたのに決まっている。しかし今回伝九郎に会ったので、考えてもっと遠くの国へ退去するだろうから、めぐり会うことはできないだろう。私の目にかからなかったことが惜しい」
と残念な顔つきをしていましたら、伝九郎が顔を真っ赤にして、
「たとえ人違いだと思ったとしても切りつけることができなかったのは、自分が臆病だったからです。私の命を捨てることに別条ありません」
としばらく後悔し、その日の夕方に家を出てからそのまま行方不明になってしまいました。おそらくあの戸平を再び討取る覚悟で出て行ったのです。
兄弟一緒に心を合わせ、雲を分け地を割き、乾坤の中は(この世にある限りは)探し出し、父の供養にと思ってきましたが、伝九郎がいなくなり、もう是非のないことになりました。
こう言う訳で、四月三十日に住吉の借屋をしまい、南都(奈良)に来ました。東大寺の末寺に知人がいます。今はまたそこに隠れて戸平の居処を探しています。あなた様におかれましては、五月下旬に江戸へ下る途中に住吉に寄るとのことでしたが、今回はお目にかかれません。そのお断りに、船宿中国屋勘六の方へこの手紙を残し置いておきます。
卯月二十七日 風越伝五郎
徳妙寺久兵衛様 」
この手紙をよくよく考えると、西国で父を討たれ、その仇を狙っていると見える。それにしても武士の身ほどままならないものはない。この志であれば、天理の必定を心にもって成し遂げるべき、だね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
