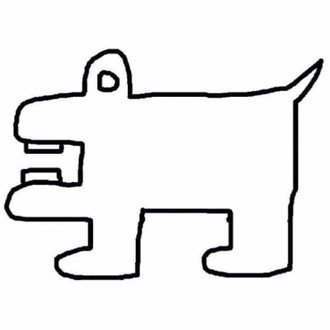文芸誌『エリーツ9』特集「四十五歳からの思春期」に寄稿
〈5/19付記:文学フリマ東京38は閉幕しました。寄稿した文芸誌『エリーツ9』は通販や書店での取り扱いがあるはずです。既にお読みくださった方には感謝を。これから読む予定の方には微笑みを〉
〈5/21付記:『エリーツ9 特集 45歳からの思春期』がBOOTHにて販売開始されています。書籍版2200円/電子版(PDF)1500円/書籍+電子版2200円。下記リンクより〉
*
二〇二四年五月十九日(日曜)文学フリマ東京38(会場:東京流通センター 第一展示場・第二展示場/入場料1000円)のブース Z23-24にて、文芸誌『エリーツ9』が頒布開始されます。文フリ会場では先行特別発売価格2000円予定とのことです。今後の通販や書店での販売などでは価格に変更がある場合もあります。
そこに菊嵜了というひとの文章が載っています。つまり、私、ryokikuzakiです。日記でも随想でもコラムでもなく、ジャンルが曖昧な、いつもの感じです。
『安全ピンと滑り台』というタイトルです。


「ボクもアイツも早い子は読んでる、まちで噂の、新/感/覚/文芸誌。俺たちゃ上級でも下流でも弱者でも勝ち組でもなく、エリーツなのさ。四十五歳がやってきた!ミッドライフクライシス!嗚呼それは果たして第二の思春期か、はたまた更年期か。取り戻せ野生、奪還せよ叡智、揺さぶるのは感性、ガチャは自分で回せ、手にとってページを開けば──これで君もエリーツだ」。
以下は長い前口上、またはあとがき、または載っている『安全ピンと滑り台』が〈どんな文章なのか〉についての補足です。意外な犯人や奇想天外なトリックが出てくるジャンルではないので未読の方でもお読みになれることでしょう。でも、先に書いとくけど、エリーツ公式でもなんでもないので、私が書いたページ以外の、他の方に関しての情報はないですよ。あと、ちょっと長いよ。ちょっとじゃないか。
*
発表に先行し、事前に読んでもらった何人かの友人たちの中に〈物語の主人公はXX(注:筆者)さんなのかなと思いながら読み始めると、鮮明なまでに既視感のある風景描写とその視点に他人ではなく自分自身の視点に切り替わった〉という感想があって嬉しかった。文章中の〈私〉から読者へ視点が途中で切り替わって欲しいなと願いながら書いたのだ。
〈時限装置つきの文章〉と評してくれた方がいた。まったくその通りで、たぶんいつか私自身も忘れてしまう感情が詰まっているはずだ。スパイ映画に登場する「このテープは自動的に消滅する」ガジェットのようなものだろう。
〈これはこの世に対する感想文なので、何かを言うなら私もまたこの世に対する感想文を書かなければダメだなと思いました〉と伝えてくれた方もいた。面白く読んだと褒められるよりも興奮させられたリアクションだった。
児童の保護者として似た環境に暮らす方から〈若い頃の趣味は一生続くと思ってたら全然違った、四十代のいま子が居なかったら生きがいを失ってしまっていたかもしれないと薄っすら感じていたことを物語を読みながら思い出した〉との感想もいただいた。私もそんなことをたまに思うことがある。並行世界の菊嵜。
私が以前からファンであり素晴らしい批評を書いている方に〈大阪の街の匂いがする文章でした。菊嵜さんが見た風景、その描写力。風景から派生した記憶と思考と祈り、それらが混ざり合って、改めて一つの風景として立ち上がる感覚〉と言ってくださって光栄だった。
〈フィクションかノンフィクションかわからない〉と評してくれた方もいた。鋭い。そこは意図していた。当初は随筆/随想風味が多分にあったのを担当編集者の意見によりバッサリ削除し、エッセイではなくしたのだ。だが、かといって小説かというと少し違うようにも思える。鉱物と小説の中間の文章となり書いているあいだも書き終えてから読み返してもわからないので──そのうち私はジャンルを考えるのをやめた。そして一旦、書き殴りのように最後まで書いてから、文章のスタイルだけを最初から書き直した。
先行して読んでもらっていた友人のひとり「loco2kit/ばんざいまたね」に熱い──というか強い感想を書いていただいた。〈文章塊〉! たしかに自分で再読しても塊っぽいな……と。
出典は示さないけれど、友人でもあり尊敬する映像作家/監督の方には、こんな言葉をいただいた。
(あえてこう書くけど)菊ちゃんの書く文章が好きだ。それは以前から思っていて、そして何回か影響されて自分も文章を書いてみた事があるけど、全然至らなくて「やっぱり向いてないな〜」と思って、それ以降は読む専になっている。
今回、発表される前にテキストを読ませてもらったけど、やっぱり文章が上手いなと思いつつ、ところどころにこれまでの文章の枠組みでは収まらない「何か」の兆候が垣間見えた。この枠組みを超えた先に菊ちゃんが行くのかどうかはわからないけど、以前からテキストを見ていた人間としては、その先に行った菊ちゃんのテキストを読んでみたいという気持ちはある。
地に足をつける(足をつけた……ではない)視点を持ちながら表現を続けるというのは意外と難しいものだ。菊ちゃんのテキストを読んでいるとそれをさらりとこなしているのに驚く。だからこそ次のフェイズが見え隠れする今回のテキストはスリリングだし、この先に生まれてくるであろうテキストも含めて読む価値のあるものだと僕は思う。
〝(あえてこう書くけど)〟というのは、普段は菊ちゃんって呼んでもらっているから。むしろそれはとても……少しくすぐったくって、同時に強く背中を押してもらった。
*
完成した文章の八千字ほどは、執筆の依頼が来たその日の夜に、寝ている子の横で、iPhoneのメモ機能で、二時間ほどで書いた。だから(既読の方に向けて書くと)本編ラストのシークエンスはそのまま体験談である。ここ数年noteに〈下書き〉のまま公開してこなかったり、公開を取り辞めた文章や文章の端書きが三十本弱、平均二千字とすると六万から七万字ほどがあり、それらからも部分的にエピソードを使った。
掲載された原稿は、文字数一万七千字強ほどだが、書いている途中で、五千字程度の、ひとつのエピソードを丸ごと削った。実のところタイトルに冠した〈安全ピン〉と〈滑り台〉のあいだに、前述の削られた五千字と同程度のボリュームで主題に沿ったエピソードが三つもしくは四つほどが、前述したnoteの〈下書き〉に端書きとして存在していた。
冒頭とラストはそのままで、本当ならばあいだに六から七万字くらいが挟まると〈物語〉としてはもう少し体裁が整うはずだ──ただし締め切り日さえ許せば。そして拘束時間に対する適切な金額のギャランティが提示されれば。なので、締め切りとギャランティ提示どちらも存在しない現在のところ長編版を書く予定はいまのところない。
以前にnote上で公開した『ファミチキ』という文章がある。noteで初めて値札をつけた。それは今回の『安全ピンと滑り台』も含めて、ここ数年考え続けてきた長いおはなしの一部として書いたものではあった。子連れでまちをゆくことに関する物語だが、いってしまえば子供を出汁にしたスープのようなものだ。
『安全ピンと滑り台』の執筆途中で、挿入するべきエピソードを指折り数え挙げていたら《こりゃあ、ぜんぶ書いたら終わらんぜ、あきらめが肝心だ》と、ある晩、子を寝つかせたあとの二十八時まで唸りながら、現在の構成へと作り直した。〈フィクションかノンフィクションかわからない〉のはその所為もある。物語未満、徒然なるまま以上といったところだ。依頼から〆切まで二週間ほどだったが、実質的な執筆時間は六時間+修正に四五時間ほどだろうか。PDF上やプリントアウトしての赤入れ以外は、ほぼiPhoneで書いた。
アニメとかヒーローとかどんなの観てるんと訊くと「テレビはピタゴラスイッチしかダメやって言われとる」と答えた六歳児、ドッジボールで相手の顔を叩きボールを奪っても保護者が他の大人とのお喋りに夢中で目を離しているから叱られない五歳児、事前に何も調べず何も持たずに市役所にきたものだからマイナポイント申請がわからず受付カウンターで苛々している保護者の足元にまとわりついているとオマエの顔ほんまブサイクやなほんまブサイクやオマエと罵られ表情がなくなっていった三歳児、駅の駐輪場で自転車のフロントチャイルドシートに乗せられたままアンタはもうイラつかせんなやイラつかせんなイラつくわほんまに二度とイラつかせんなよコラァと言われ続けながら笑顔の二歳児——私自身は、まちで出逢うそんな光景ばかりに目を奪われ、本来であれば苦しんでいたかもしれない中年の危機、ミッドライフ・クライシスが目に入らなかった。
お読みいただいた方ならお分かりだろうが、本文中に、あるマンガ作品の主人公と脇役についての例え話が出てくる。これは数年前に写真家・文筆家である平民金子氏との会話中、「もう子供が主人公なんやなと、自分はもう主役じゃなくて脇役やと最近思ってて」と言う私に、金子氏が「それってアレの第二部と第三部ということでしょう」と的確に表現した言葉を援用させていただいている。許可を得ずに無断で。本作における文責は筆者である私にあるが、あの表現を「的確だ」と感じた方がいたなら、それは平民金子氏の表現力の賜物だと思っていただきたい。『機動戦士ガンダム』と続編『機動戦士Zガンダム』に喩える案もあったが(未読の方には意味不明だね)、その場合は映画『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』などについても触れねばならなくなるのと主題がもうひとつ増えてしまう──いや、「四十五歳の思春期」という特集合わせであればそのほうが合致するのだが──こともあり、収拾がつかなくなるので、現在のかたちに落ち着いた。余談ではあるが、ガンダム監督の富野由悠季氏は1941年生まれなので「逆襲のシャア」公開の1988年は四十七歳なのであった。
世の平均寿命とされている歳まで、私の年齢ではまだ先は長いが、体力が残り少ないのを痛感する。身体面も知的にも。それらが失われる前に、なるべく多くのことを書き残しておきたいんじゃ、そういう気持ちがあるじゃーのん、どうか花束をそなえてやってください、それが執筆依頼を受けた理由のひとつでもあった。
もうひとつの理由は、原稿の依頼者が古い友人で、過去に共通の友人二人の死を真っ先に知らせてくれたことがあり、更には私よりも児童の保護者として先輩で、そこには恩義でも借りでもなく、友情という言葉でしか表現しようのない関係性があった。
なお「千五百字以上」との執筆依頼の連絡があった翌朝に八千字の初稿ラフを送りつけて申し訳なかった。十日間で細切れに第十三稿まで出したのに付き合ってくれて細部まで的確な意見を出し更には文字数が初稿の倍以上になってしまい随分とページ数をとらせてしまいすまないと思っている。タイトル案を二人で二十ほども出したあと、〈安全ピン〉というのは手榴弾の安全装置(グレネードピン)でもあるからタイトルは、Small Hand-grenade and Big Helter-skelterでもいいだろうかなと結局のところ仮題でつけていた最初の題名に戻して面倒をかけた。感謝している。
念のためここで確認しておくが、私の場合は、日付や曜日入りで日記としてのスタイルで書いているもの以外の文章において、文中に出てくる〈私〉はイコール作者ではない。ニアリーイコールのときもあるし、実際の体験や目にした光景に触発されて書いたものが圧倒的に多く、いま現在のところnote上に書いてきた文章のなかで、土曜の午後仕事で車を走らせていると空から円盤が降りてきてLSDとマリワナとバナナディンとニューロインをキメながらディメンション・スペース・ドライブでの超光速航行でシリウスとハビタブルゾーンまで旅をした俺は……といった内容は書いておらず、着想を得た出来事が欠片もない完全な作り話のエピソードは──これはまったくのところ私の創作能力の問題と限界で──これまでのところ、ほぼないのだが。詩人としての才覚がないのである。じっと手を見る。ない。
もし私がホログラフィック原理がトリックに使われたクローズド・サークルにおける密室殺人事件に遭遇したら、それに触発され書いた文章がハードSF本格推理小説になるかもしれない。つまるところ、書きたいものを書いているのではなく、書けるものを書いているのである。新たに題材を探して書くことができない。たとえばデイリーポータルZのライター諸氏などの記事は凄いなと自分には真似できぬなと感服する。
ここ数年のあいだで「なにか書きませんか」と、せっかくお声がけをしていただいたのに、何もお渡しできなかった方々には心からの謝罪を。タイミングと、そのとき書けることと、スケジュールとが、どうしても合わなかった。なにしろ子の入浴や寝つかせや急な発熱や小児科への通院や粘土遊びがあったのだ。
やがて、その頃に子が何歳になり何をしているか、もう私にはわからないほどの時が経つ。この地区一帯は海抜ゼロメートルで、温暖化の影響により海面がちょっぴり上昇した結果、堤防や排水などあらゆる会議で提案されたあらゆる手段が講じられたが、何もかもが間に合わなくなり、数十年かけて緩やかに水没、河を埋めてつくられた公園は再び河へと戻る。耐用年数が超えるごとに交換され何代目かになった大きな滑り台は少しずつ形を変えて同じ場所にあり続けたが撤去費用が無駄なので、その場に建ったまま水の底に沈むことになる。そんな遥か先のことではなく──二〇二四年
もういちど念押ししておくが、掲載される『安全ピンと滑り台』文中に〈私〉とあるのは、ハードボイルド私立探偵小説の一人称が〈俺〉だったり〈名無し〉であるのと、または新井素子作品の主人公が〈あたし〉であるのと、なんら違いはない。
更につけ足すと、前言を翻すようだが、たとえこのnote上にて綴ってきた文章が日記スタイルであっても、誰かが発した言葉を録音したわけでもなく、そのセリフは正確な表記にはなっていないことがあり、状況描写や他者が登場する時点で、その〈日記〉は既に現実の拵えものなのだと感じている。私が愛読する、ある日記の作者は「まるごと嘘とまではいいませんが、文章の前後のためにつくった会話のやりとりもあります」と語っていた。
私が書く〈日記〉は、数年後に私や子が読んだ際に困らないであろう日付は変えることもあるし(勘違い以外ではいまのところないのだが)、出来事の前後などは入れ替えたほうが描きやすい場合は平気で入れ替えをしている。ただし〈私〉が抱いた・心に沸き上がった・憤ったり胸を打たれた・感情に関しては、嘘を書いたことはないはずだ。私が四月二日に「本当はエイプリルフールって今日のことを指すんだぜ」と平気で言える人間だとしても、だ。
〈私〉の文章は、私小説とは呼べない。日常で起きた出来事を取捨選択し、書くべき優先順位をつけ、カメラの位置を決めて、ドキュメンタリー調演出を必要とされる私小説というジャンルは、先端科学を取り入れたハードSF並みには、フィクション度とアクチュアリティの匙加減のハードルが高いと感じている。
そこに欲望や生々しい感情が飾り気なく吐露されていても、フェイクとまではいえないが、モックではあると認識している。エグザジュレートとまではいかずともデフォルメはされているだろうと。
はたして私小説とモキュメンタリー映画『スパイナル・タップ』『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』とに差異があるだろうか。本当にあったことですよに嘘を混ぜるのと、フィクションですよに実際にあった出来事を混ぜる、この二つの違いは? こんなことは私小説を愛読してきたり、私小説家を自認・標榜しているひとはとっくに考え抜いていることだろう。ただ、文章執筆という行為にはカメラの存在や音の編集がない。多くのドキュメンタリー映像作家が直面する〈ドキュメンタリーの嘘〉ほどフィクション性への自己言及がそこにあるのかは、私には定かではない。
少なくとも私は、カメラやセリフの存在が気になってしまい〈私〉という一人称で私小説は書けなかったのである。誠実さが足りていないか、または覚悟完了していないのだ。
カメラを置いて人物へインタビューをした映像を編集して音をつけることによって、どれほど物語性を帯びさせることができるのかは、いくつかのインタビュー映像を演出してきた職業柄よく知っているつもりだ。そのインタビューがたとえノーカットの未編集だったとしても、カメラの置き方、照明のあてかた、インタビューする場所、いくらでも印象操作が可能だ。インタビュー相手が椅子から立ち上がってフレームの外に出て画面に映らなくなってから何秒間その画を映しっぱなしにするかといった些細なディテールですら、観ているひとの感情をコントロールできる。
過去に、ある事情にて、精神疾患の方が亡くなる前に書き綴ったノートを何冊かめくったことがある。生々しい〈私〉がそこにあった。それに比べると、私が過去に読んだ限りの私小説は、エロチックやグロテスクや露悪に塗れていて、人物がごく自然に活きいきと描写されていたとしても、圧倒的に〈整えられた〉文章だった──でも〈私〉って、整ってないだろ。人間って、そんなに読みやすくないだろ。
地面に吐き捨てる唾のような独り言めいた言葉がこれほどSNS上に溢れかえっている時代に、確かな文章力で書かれてリーダビリティがあり事実は小説よりも奇なりと思わせるエピソードが並んだ小説を自伝的小説や日日雑記スタイルと捉えることは可能だが、私小説だとは感じない。田山花袋が自身の分身的な人物を主人公に据えた『蒲団』や『少女病』は現在においては、そのままでは成立しようがない。太宰治が他人の口を借りて書いた『女生徒』『十二月八日』はどうだろう。
つまるところ書き手のスタンスがどうあれ、日記なのか随想なのか小説なのかを別ち切り離すのは、作風や文体で整えられ造られたスタイルでしかないのだ。開拓以前の北海道が舞台の映像作品で、整地に植樹されたカラマツが原生林として登場したら単純な間違いかロケーション予算の都合だろう。だが、劇中設定が開拓以前の北海道とされていたならば、そのカラマツは物語中では原生林足り得る。
田山花袋のいくつかはそれが小説でも紀行文でもまるで今でいうブロガーの記事かのように読めるし、太宰治のいくつかに作者の現実生活の状況や心情が投影されているよう感ぜられたなら、特殊スキルを持つ主人公オサーム・D・罪が活躍するキャラクター小説を津島修治が書いたのだ。筆名というのが、まずフィクションだ。筆名というのは、必ず縦PAN(正確にはTILT)で始まると決まっている〈スター・ウォーズ〉シリーズの、ファースト・カットみたいなものだ。
四十代とは何か——ひとつ何かしらの人生における命題があったとして、そこへアフォリズムに塗れた答えを出すよりも、どうしてそれを問うたのか、然るべき時期への問いかけだったのかを考える。格言・金言集を読むときには、歴史に残った言葉を答えた直前に、その解答者へ向けられた質問を想像してみる
'Although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it.'(世界は苦しさに満ちているけれど、超克にも満ちている/ヘレン・ケラー)でも、'Just because you fail once doesn't mean you're gonna fail at everything.'(あなたが一度の失敗をしたとして、あなたが全てを失敗するとは限らない/マリリン・モンロー)でもいい。人生の悩みや不安に関して端的に表した胸に迫る先人の言葉というものは常に、人生相談への解答だけではなく、いつか次に続く者たちへの質問が内包されている。
〝私の気づいたことは、いまこの目の前のお婆さんたちには他人のことを「厭な顔つきの奴だ」とか「あんなことを言われた」などという話題がないことだ。そんな神経は全然ないのだ。私は百姓になったが、都会で生活してきたので神経もこまかい。だから相手の言ったこと、目つき、態度がこちらの神経に伝わってくるのである。「インチキ百姓だナ、俺は」と私は気がつく。目の前のお婆さんのような平凡な顔つきに私はなりたくなる〟
(『深沢七郎コレクション 転』収録「生態を変える記」,kindle版,深沢七郎著,筑摩書房,2012)
私は「インチキ育児人だナ、おれは」と気がつく。
執筆時には特集の企画コンセプトしか聞かされていなかったので、書き終えてからのゲラで初めて知ったのだが、文芸誌『エリーツ9』は大変に豪華な執筆陣で、興味深く面白い記事が多く載っている。某氏や某氏の言葉には大いに感銘を受けた。
ただ唯一、まったく個人的に残念なのは、本来ならそこにいるべき書き手がひとり欠けていることだ。「四十五歳からの思春期」特集には、二〇一六年のある日以降、新たな文章を書くことが永遠になくなったその書き手の文章が載るべきだった。もう原稿依頼ができないので叶わぬ願いだ。その書き手が二〇二四年のいまでも書き続けていれば今年で四十八歳になる。ひとつだけ想い出を書く──ああそうだこのくだりは〈私小説〉でも別に構わない──その書き手が最初の単著を出す以前から知り合いだった。著作は話題となり、いくつかの新たな連載も始まり好評で順風満帆に見えたその書き手に、ある日、私は「次は〈東京〉について書いたらいいじゃん、それしかないでしょう」と軽口を叩いた。自身のことを赤裸々に書いた著作から生じたパブリック・イメージに絡めとられているかのように思えたから、なるたけ無責任な重くなく軽薄なことばに聞こえるような口調で。それから暫くして、本当に〈東京〉についての連載が始まった。私の軽口には「編集さんにも東京のことを書くのはどうかなって言われてるんですよね」と返答していたのに、書籍化が決まったあとで「XX(私)さんが東京のことを書けっていってくれたからですよ」などと言われた。いったい何人のひとにそう言ってるんですかと笑いながら、「それなら売れなかったらおれのせいだ、連載は読んでいましたし、本も買いますよ。でもあれは凄いから売れますよ、確実に届くところに届いて、代表作になりますよ。茨木のり子でいう『自分の感受性くらい』みたいなものですよ」と答えた。「出たらお渡しますよ」「いや、買いますよ」と話した。連載時から少し題名が変わって本が出た後に「書影を見てから実物を手にとってしばらく経っても表紙はずっと本人の写真なんだと思い込んでましたよ」と伝えると、「そんなわけないじゃないですか!自分の顔だなんて!──でもそう言っていただけるのは嬉しいですありがとう」とその書き手は照れながら言った。その書き手による「四十五歳からの思春期」特集に書かれていたはずの、載っていたはずの、文章を読みたかった。だから私は文章中で、ほんの数文字だけ、その書き手について触れた。名前は挙げないし、挙げないことで伝わらないならそれでいいし──と、ここまで書いていて、初めて気がついたことがある。いま書きながら心がザワっとしている。
前述した『安全ピンと滑り台』作中に登場する〈あの子〉には、着想を得た際にモデルになった人物が実在していて、作中の出来事は会話も含めてほぼ実体験そのままなのだが、今回、「四十五歳からの思春期」テーマで執筆依頼がきて、何故真っ先に〈あの子〉との想い出が浮かんだのか、どうしてラストにあのエピソードを置いたか、そういうことだったのかと腑に落ちた。「四十五歳からの思春期」特集に名を連ねているべき、その書き手の不在を作中の〈あの子〉へと無意識に投影していたのだ。あれほど悩んだタイトルは『スーパースター』でもよかったのかもしれない。その書き手はスーパースターのように輝き、スーパースターのように苦悩していたから。その書き手が今回『エリーツ9』へと参加できなかったことに、哀しみよりも憤りがある。最後に話してから、もう何年も経つのに、その書き手の新しい日々についての新しい文章が読めないことにまだ怒っている。怒り続けていくしかない。今年も11月になると、まだ冬とは呼びたくない秋の終わりに、少し冷たくなった北風が街や海や山や島に届きまだ少し残された草花の美しい穂を揺らすだろう。
たった一万七千字の文章を告知するために多くの言葉を費やしてしまった。告知の文字数が本編より多くなってしまったではないか(多くないです)。まあ、いいだろ、値札を貼ったら大声で宣伝して売るのだ。声を出さないほうがむしろ恥ずかしいのである。人気アンケートで二番手ならアンケート一位を目指して「打倒ハレンチ学園」と紙に書き机の前に貼るのである、やらないほうが恥ずかしいんだよ(週刊少年ジャンプ誌で『男一匹ガキ大将』連載時の本宮ひろ志と編集者とのエピソード)。『エリーツ9』は、売れて売れて売れまくってほしい。実のところ印刷にコストをかけ過ぎて微妙に赤字らしいのだ(笑い)。才能や知名度が足りなくても圧倒的不利な状況でも、手持ちのカードで手を変え品を変えハッタリでも自画自賛でも小狡くてもルール内で徹底的にやるしかないんだ。『アイシールド21』だと蛭魔妖一が好きだよ。掲載誌が売れようが売れまいがインセンティブがあるわけじゃないけど、ほら、おれいい仕事したからさ。ああしとけばよかっただとか、もっとやれただとか後で思いたくないのョ。
正直なところ、『安全ピンと滑り台』(別名『スーパースター』)、これで賞を獲りたい、読んだあなたの名前が冠された賞を。あなたが佐藤さんなら佐藤文学賞を、あなたが鈴木さんなら鈴木文学賞を。あなたがノーベルさんなら例外的にちょっとばかし変名でやってくれたほうがありがたい。
*
最後に。さあ、仕事だ。スイッチを切り替えよう。コマーシャル・フィルム制作時のポストプロダクション作業大詰めスタジオ内収録ブースにあるマイクの前でナレーション原稿を読み上げるかのように、声を張り上げて宣伝をしておく。あなたがご存知だったりファンだったりする、素敵なボイスの声優・ナレーターを頭の中で耳の奥でキャスティングしておくれ──
「ボクもアイツも早い子は読んでる、まちで噂の、新/感/覚/文芸誌。俺たちゃ上級でも下流でも弱者でも勝ち組でもなく、エリーツなのさ。四十五歳がやってきた!ミッドライフクライシス!嗚呼それは果たして第二の思春期か、はたまた更年期か。吹き荒ぶ風雨の中で、宮殿に住まう者も荒屋で身を寄せ合う者も、取り戻せ野生、奪還せよ叡智、揺さぶるのは感性、真実のガチャは自分で回せ、手にとってページを開けば──これで君もエリーツだ」
はいオッケーです今のテイク押さえでいただきます、もうワンテイクいきましょうか──はいオッケーす、ありがとうございましたっお疲れさましたー。
*
5/19(日)文学フリマ東京会場にてお待ちして──ません、そこに私はいません。卓にはどなたかがいるので、代金を渡して『エリーツ9』を入手してみてください。私の文章が退屈だったとしても、他の記事がとても面白いです。〈9〉とあるのはゼロゼロナンバーサイボーグのような人数ではなく発行されたナンバリングで第9号ということです。既刊の1号から8号まである過去のバックナンバーも面白いですよ。海猫沢めろん畢生の大作『ディスクロニアの鳩時計』私家版も販売開始。限定四百九十九部の初回版は異様に造本が凝っておりコストがかかり過ぎてそのままのかたちでは増刷ができないらしいので確実に入手したい方は要予約です。(5/16付記:海猫沢めろん氏のXアカウントによると〈取り置き・BOOTH、共に予約分完売しました。ありがとうございます。5/19文学フリマでの一般販売分もありますが、50部前後となります。また15時以降に予約キャンセル分を販売するかも知れません〉とのこと〉。
文フリ会場に行けない行かないかたには、これまでの8号と同様に『エリーツ9』はBOOTHでの通販も近日中に開始され、PDFによる電子版もきっと用意されるはずです、たぶん。私の知っている書店でいうと、大阪市此花区にある〈シカク〉というお店では『エリーツ』バックナンバーが販売されているので、『エリーツ9』も、そのうち取扱いがあるはずです。これで君もエリーツだ。エリーツになってほしい。なろう。中年の危機にエリーツになったら◯◯だった件とかなんとか言葉にしてみよう。
高校生の頃。《死にたくないというよりは、五十六億七千万年後まで生きて人類の行く末を見てみたいんだよな》と思っていた、本気で。実はいまでも少し思っている。生きよう。生きられなかった誰かの替わりにでもなく、崇高な何かのためでもなく、ただ生まれて生きている、その途中で世界やひとに出会う。
〈了〉
〈2024年4月9日 記〉
【プロフィール】
菊嵜了:育児人。映像や写真を撮ります。日々の暮らしを書いた日記と、暮らしで目にした光景に触発された文章を書いています。
タイトル:『安全ピンと滑り台』
作:菊嵜了
執筆:2024年03月13日 - 26日
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?