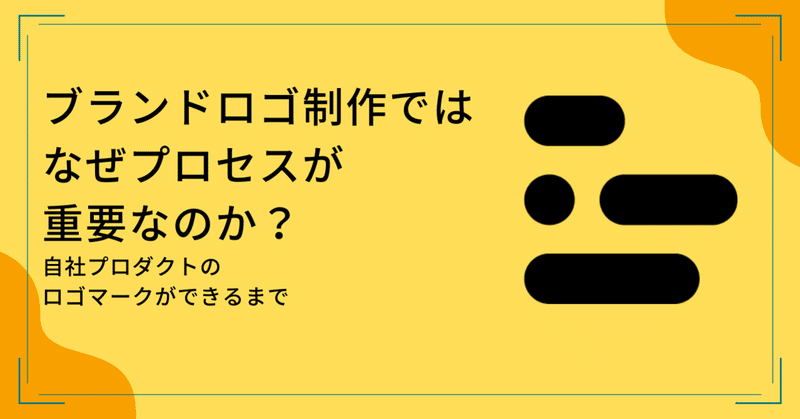
ブランドロゴ制作ではなぜプロセスが重要なのか?[自社プロダクトのロゴマークができるまで]
本日YELLtumのロゴマークの新デザイン、そして新たなキャンペーンのLPのリリースを行った。
そう言えばデザインの前に少し悩んだのがドメインだな、funかfanか。
普通にいけばfanなんだけどそれだと限定的だし(理由はデザインの部分にも記載されているが)結果としてはfunにした、この方がしっくりくるな。
今日はnoteの記事を2本公開した。
まずは本日公開したブランドロゴ、そしてLP/キャンペーン公開と共にこれからプロダクトの提供まで何をしていくか?
こう言った内容になっている。
解決したい課題をデザインとして可視化する事
まず新たなロゴマークはこの様なアウトプットになった。
普遍的な部分と情報の整理にはかなり気を使ったな。


今はコピー・タグライン・ステートメントなどのワーディングの作業に入っているが俺はプロダクトやサービスを展開するにあたりロゴマークと言うのは非常に重要だと思っている。
と言うのもブランドの頂点だからな、これはブランドマーケティングと言う視点だとかなり大事なんだ(視点というかマーケティングの出発はそもそもこう言う事だとも思っている)
タイトルにある解決したい課題、って言うのは自分たちのプロダクトは何を意味しているのか?これをグラフィックを用いてきちんと表現しないといけない、このきちんと表現する事、そして何を解決していきたいのか?そしてどう言った情報を伝えていきたいのか。
これを全て詰め込んだのがこのロゴマークになる。
久々にこう言う作業をしたけど面白い反面なかなか骨が折れる作業なんだよな。
アウトプットに関してはよく見かける透過された2色が重なる、って言うのも少し考えたけどちょっと古臭く感じたんだよな。
最近だとユベントスやルノーなんかはかっこいいと思ったよ。
当然時代の背景によって変化をするわけだが歴史のあるクラブ・企業は重厚感が違うよな。
新ロゴマークの情報整理
これはかなり頭を悩ませた所だ。
俺が悩んだ部分はコミュニティって言う部分だな、この意味。捉え方。
YELLtumの仕組みに関しては地域通貨なんかもかなり調べたし、マーケティングも改めて深掘りした。
どちらかと言えば仕組みに関しては簡単では無いが整理はついているがではコミュニティって言うのはどう言う事か?これの整理が難しかったな。
色々と調べてここはかなり参考になった。
京都大学のデザインスクールだな、細かくは割愛するが結構腹落ちする視点が多くてコミュニティの捉え方はここからインスパイアを受けた。
俺は通常のマーケティングに関してもデルフト工科大学からの影響は結構受けているんだけど学ぶと結構面白いんだよな。
少し芸術論にもなるが俺は芸術的な作品であっても情報の整理、そしてその整理が合致した条件下で作品が生まれると思ってるんだ。
芸術家でも晩年に抽象画になる作家は結構好きなんだよな、膨張はやがて線になると言うか情報の整理の完成系は常にシンプルになる事が正解なんだと思うんだよな。
エレメント
前述した情報の整理に関して、シンボルのエレメントはこの様な整理に最終的に落ち着いた。
こう言った整理が出来ると誰かに伝える時に楽になる、もちろんこの後このロゴマークが頂点としてコピー・ステートメント・タグラインなんかを決めていく感じだな。

①コミュニティの定義はコミュニケーションの過程である
②コミュニケーションは持続する
③これからのコミュニケーションは広く行われる
④YELLtumは過程に情熱を灯す
以下にはこの整理に至るまでの過程を画像でおいていく。









過去の記事はこちらから
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
