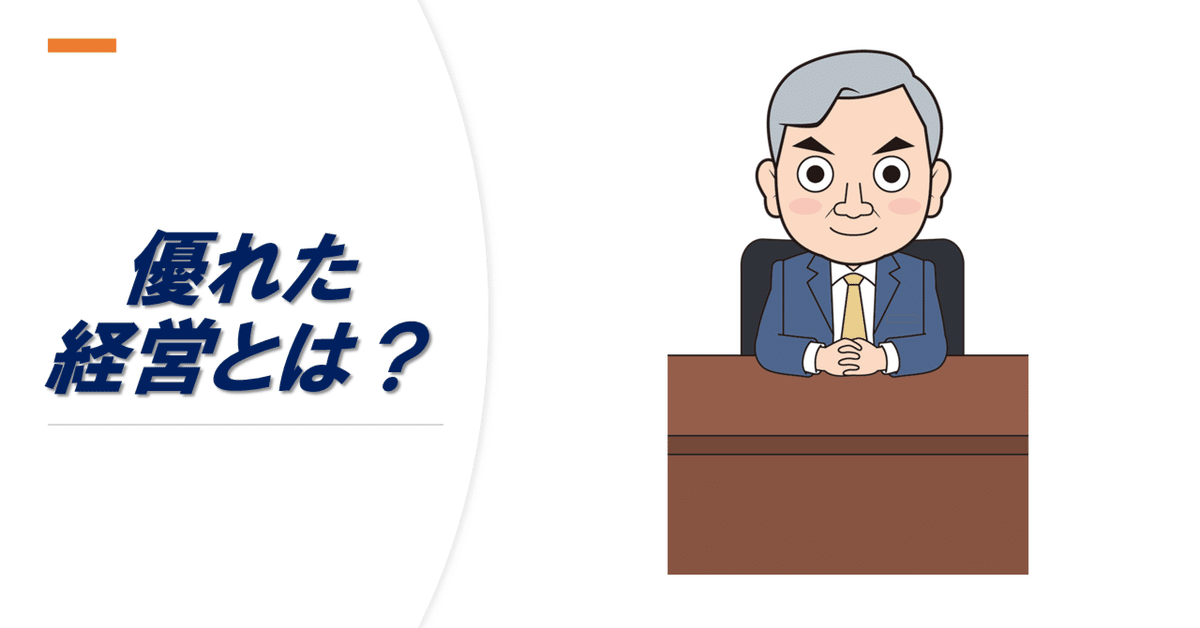
『稲盛和夫一日一言』 8月9日
こんにちは!『稲盛和夫一日一言』 8月9日(水)は、「優れた企業経営者」です。
ポイント:お客様により多くの利益をもたらすことのできる経営者は、自分の会社にもより多くのビジネスをもたらし、利益を呼び込むことができる。
2011年発刊の『京セラフィロソフィを語るⅡ』(稲盛和夫著 京セラ経営研究部編/非売品)の中で、利他の心、思いやりの心を持って事業を行うことの必要性について、稲盛名誉会長は次のように述べられています。
常に相手にも利益が得られるように考えること、利他の心、思いやりの心を持って事業を行うことが必要です。
それは、「自利・利他」という関係でなければなりません。「自利・利他」とは仏教用語で、自分が利益を得ることと、他人が利益を得ることとは、相矛盾するものではない、ということを表しています。
この教えは、江戸時代に京都で商人道を説いた石田梅岩(ばいがん)の「まことの商人は、先も立ち、我も立つことを思うなり」、つまり、相手も喜び、自分も喜ぶというのが商いである、という言葉にも通じるものです。
また滋賀県の近江商人の間では、昔から商人道として「三方よし」ということが言われてきました。三方とは、「買い手よし」「売り手よし」「世間よし」、そうでなければ、真の商売はできないということです。
私は「稲盛経営十二ヶ条」の第十一条に「思いやりの心で誠実に」という言葉を掲げています。商いには相手があり、相手を含めてハッピーでなければならない、つまり、商売の極意は、相手も喜び、自分も喜ぶということにあると思っています。
経営者は、従業員を守っていくため、また株主に対する責任を果たすために利益を上げていかなければなりませんが、何も競合相手をつぶそうなどという意図を持って競争しているわけではありません。
経営者というのは、みな利己の塊みたいな人たちではないかと思われている方もあるかもしれません。しかし、そうした利己、エゴだけでの経営では、その思いが強ければ強いだけ成功もしますが、その成功は決して長続きせず、やがては失敗して没落していくことになるでしょう。
一方、相手によかれかしと願う利他の心に基づく経営をしていると、周囲の協力も得られて、その企業は長く繁栄を続けていくことができるのです。
利他の心は、物事を判断するときに、自分さえよければいいという利己をベースに考えないようにする、つまり経営者が、社会に調和し共存していけるような戦略、戦術を組んでいくためにも必要なものなのです。(要約)
今日の一言には、「優れた企業を経営できる人は、お客様により多くの利益をもたらすことができる人だ。このような姿勢で経営のできる人は、自分の会社にもより多くのビジネスをもたらし、利益を呼び込むことができる」とあります。
何のために利益を追求するのか、という非常に本質的な問いかけに対する答えが「自利・利他」です。自分が利益を得たいと思ってとる行動や行為は、同時に他人、相手側の利益にもつながっていなければならない、自分が儲かれば相手も儲かる、それが真の商いということです。
「情けは人の為ならず」という言葉があります。誤った解釈もあるようですが、「人に親切にすれば、その相手のためになるだけでなく、やがてはよい報いとなって自分に戻ってくる」という理解が正しいとされています。
多少時間軸はずれるかもしれませんが、他人、相手によかれと考えてとる行動や行為が、巡り巡って自分をハッピーにしてくれると信じて、利他の心を実践していくことが大切なのではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
