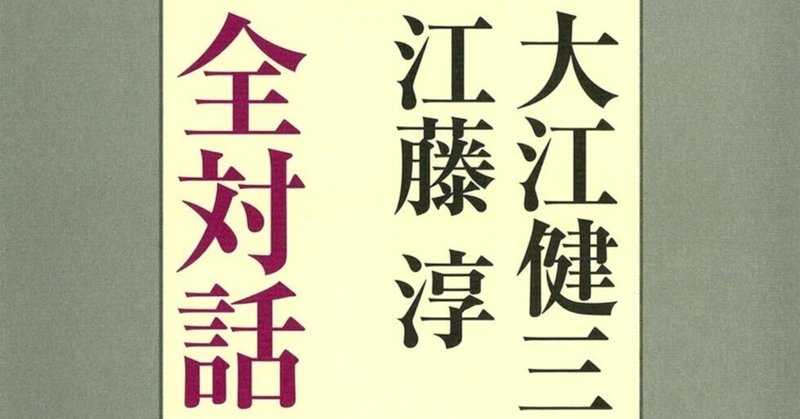
昭和の文学史を飾る大論争!?〜『大江健三郎 江藤淳 全対話』
◆大江健三郎、江藤淳著『大江健三郎 江藤淳 全対話』
出版社:中央公論新社
発売時期:2024年2月
大江健三郎と江藤淳の登場は、戦後の文学史の上で “事件” と呼ぶにふさわしい。かつて磯田光一はそのように書きました。本書はその二人による対談集です。1960年から70年の間に行われた対談四篇を収めています。
二人の対話は時に険悪なまでに対立します。
安保闘争をめぐって行われた1960年の〈安保改定 われら若者は何をなすべきか〉では、政治的立場を異にする二人の対論は当然ながら噛み合いません。大江が市民によるデモに積極的な意義をみているのに対して、江藤は明確に否定します。
〈現代の文学者と社会〉では『個人的な体験』が俎上に載せられるのですが、公表された作品とは別に大江自身が私家版的なテクストを書いたことを江藤が執拗に批判しているのが印象的です。作品を発表したのなら自信をもってそれを決定版としていただきたい、批評に応えるような形で作品を書き換えるのは批評家に対してかえって失礼だという論旨です。江藤がそのことに固執する理由が私には今ひとつよくわからなかったのですが。
また江藤が日本文学の正統性を儒学の伝統においているのに対して、大江は明治維新という大変革に画期を見出し「作家たちが、維新体験をしたために、明治以後の文学者の国家社会について正面から考えるという態度がもたらされた」との認識を示しているのも好対照です。大江が信奉した戦後民主主義に対しても江藤が懐疑的な態度をとり続けたこともまた自然だと思いますが、江藤のそのような歴史観からいかなる文学的成果が得られるのか私には不明のままです。
1968年、大江の『万延元年のフットボール』をめぐって行われた対談〈現代をどう生きるか〉では、二人の対立がさらに鮮明になります。江藤が執拗に作中人物の命名に関して疑義を呈しているのです。
「あなたの小説では呉鷹男とか密三郎とかいう奇妙な名前が出てくるでしょう。この名前を認めるか認めないかがいわば読者に対する踏み絵になっているのです」。これを「認めた」読者は「大江さんの主観的な世界にコミットすることを強要されてしまう」ことになるというのですが、そもそも小説を読むとは元来そういうことではないでしょうか。
ささいなことに拘泥する江藤の作品読解には肯んじえない点が多いけれど、併録されている柄谷行人の同時代批評は、おもいのほか大江に対しても手厳しい。大江は戦後の「民主主義」なる理念に酔うことによって、「現実の事物」や「現実の人間の関係から遁走していったにすぎない」と書き、それを自己欺瞞とまで呼んでいます。今の柄谷なら当時の大江に関してそのような辛辣なことを書くことはなかろうと思われますが、若い頃の大江には文学的な観点からも種々の批判があったことは事実でしょう。
その後、大江は精力的に書きつづけ、政治的な問題にも積極的に関与しました。海外からも高い評価を受けるようになったことを今の私たちは知っています。若い大江に向けられた様々な批判を現代の高みから一刀両断することには慎重でなければならないとも思います。
いずれにせよ、このような二人の緊張感に満ちた対話は昨今の文学界ではあまりみられなくなったことも確か。現代では互いに互いの作品を褒め合うような社交的な歓談ばかりが目につきます。大江と江藤は一時期断交していたようですが、それでも時間を経た後に再び語り合う機会をもちました。
昭和の文学史の一コマとして、江藤と大江の「論争」は話題を集めたといいます。はたして論争の名に値するほどの高尚なものだったのか、私にはよくわかりません。けれども二人の間に存在したらしい曰く言い難い文学的な紐帯のようなものを本書から感じ取ることも可能でしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
