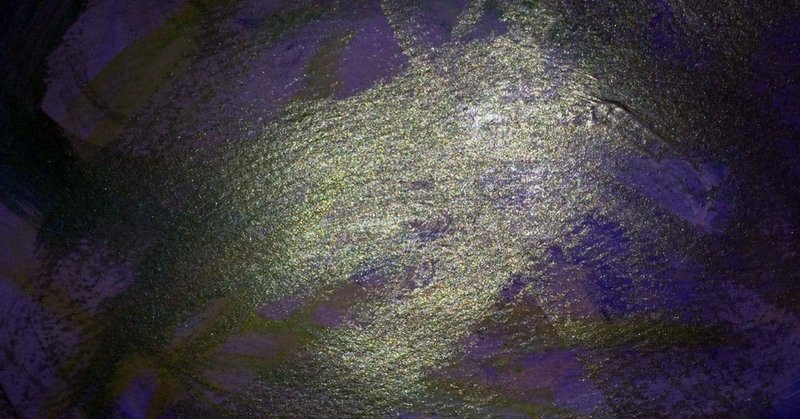
Photo by
chickii
090「老境」
いつか、貝をひろいに、山をのぼらなければならない日に、わたしは、折れた風見鳥のころがっている木陰をながめながら、生姜焼きを食べる。ならんですわっている老婆は、その腕よりも厚そうな、書類の束に、すばやく、目をとおしてゆく。老婆は、書類の内容を、ほとんど、おぼえていない。ある書類に、黄金比、という言葉が、たくさんでてきたので、黄金比、という漢字だけは、たしかにおぼえている。
測量士の男が、1枚の書類に涙をおとす。マイクロプラスチックが、彼の体内に侵入してゆく。彗星が地球から遠ざかり、娘の誕生日を、だれも知らないことを思いだす。
石でつくられた鈴が鳴っている。きわめて低い音が鳴るので、ほとんど、それを音として聞きうる人はいない。貝殻のような街灯が、登山道に、列をなしている。しばらくして、腸チフスに似た症状があらわれはじめる。弁当箱の底には、祖父の顔ばかり、うつって見える。もう、二度と火のつかない暖炉と、壁にかけたままの、ひびわれた姿見のことを考える。あれは、だれにもらったものだったか? 近所の家具屋で売っている、安物の姿見。わたしの部屋の壁に、今もはりついている……
顔に、一匹の蠅がとまる。右耳から、鼻のほうへ進んでゆく。乾いた枯葉が、食器棚からふってくる。わたしは、いよいよ、高熱にうなされる。やがて、子どもらに、ひとつの肉の切れはしとして、秋の終わりを証明するものとして、一枚の書類をささえるだけの、ありふれた、石のようなものとして、いつまでも、寄りそって走るために。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
