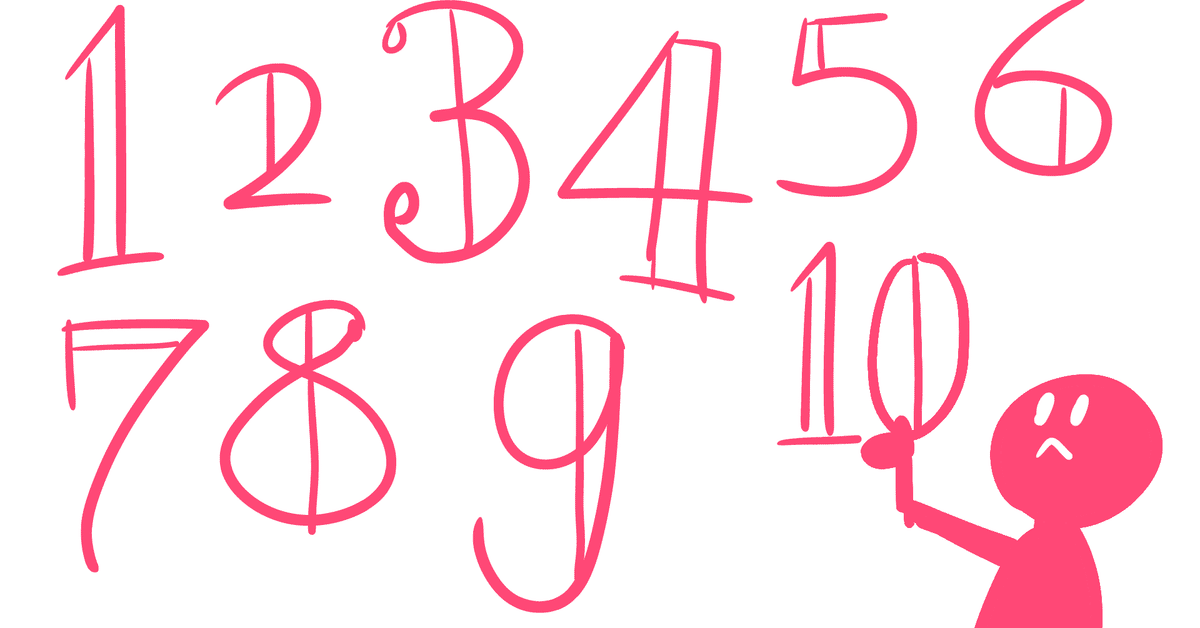
子どもに嫌われるための哲学~算数編~
先生:はい、それではきょうはたしざんをやりましょう。ここにみかんが2つあります。そちらにりんごが3つあります。あわせていくつありますか?
生徒:せんせい!みかんはふさにわけられます。なのになぜこのみかんを1つと数えるんですか?
先生:別にふさを数えてもいいですよ。ふさ24個とりんご3つをたすとあわせていくつありますか?
生徒:せんせい!ふさの中にはつぶつぶが入っています!
先生:別につぶつぶでもいいですよ。しつこいから先に言っておくと、別に個数を数えられるなら何でもいいんです。
生徒:何でもいいなんて許されるんですか?そもそも、みかんとりんごって別のものなのに数えてしまってもいいんですか?
先生:みかんでも素粒子でもなんでもいいです。
生徒:でも異なるものを足しても大丈夫なんですか?
先生:大丈夫です。いまあなたたちに教えているのはみかんの数え方でも、りんご数え方でも、素粒子の数え方でもなく、数えられるものに対する抽象的な算数の加算です。低学年の子どもにもわかるように言うなら、何にでも当てはまる考え方を教えているんです。いちいち個別具体の話なんか本質的ではないのです。だけれど、あなたたちは抽象的なものの考え方がまだできないから、みかんだ、りんごだと具体的なものに例えて教えているのです。だから、もしお望みなら素粒子とみかんを足し合わせても問題ありません。ウィトゲンシュタイン風に言うと言葉の意味の空間が異なる1リットルと1キログラムを足すことはできませんが、存在を意味する個数であれば、あらゆる対象が存在するものなので、数えることが可能です。これはプラトン風に言うところのイデアですね。個別的な対象なんぞはただお飾りです。
生徒:ちょっと何を言っているかわかりませんが、異なるものを足しても何個あるか「数える」ことができる以上は、みかんとりんごを足してもいいということですね。
先生:そうです。ただ、あなたが本当に疑問に持つべきなのは、なぜ私たちが「数える」ことができるのか、です。そもそもあなたはすでに、みかんやりんごを“1つ、2つ”と「数える」ことができますよね?でもそれって何なんですか?もちろん、数え始めなければ算数なんて成り立たない。でも、最初の最初、そもそも「1つ」が何なのか説明すらできない。さらに、それを「足す」って何なんですか?私たちはいったい何をしているのでしょうか。本当に私を困らせたいなら「先生、「1つ」って何ですか?「足す」ってなんですか?」と質問してください。でも、実はあなたはそれをすでに知っているから、ふさだの、つぶつぶだのを数えて満足できるのですよ。
※参考文献:
『ウィトゲンシュタイン入門』永井均著 ちくま新書(1995)
「数概念について」足立恒雄著 早稲田大学・理工学術院『数理解析研究所講究録第1625巻2009年1-11』
「人間がつくった最初の数-分数の起こりを考える数学的活動をつくる」伊達文治著 『上越数学教育研究,第33号,上越教育大学数学教室,2018年,pp.11-20』
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
