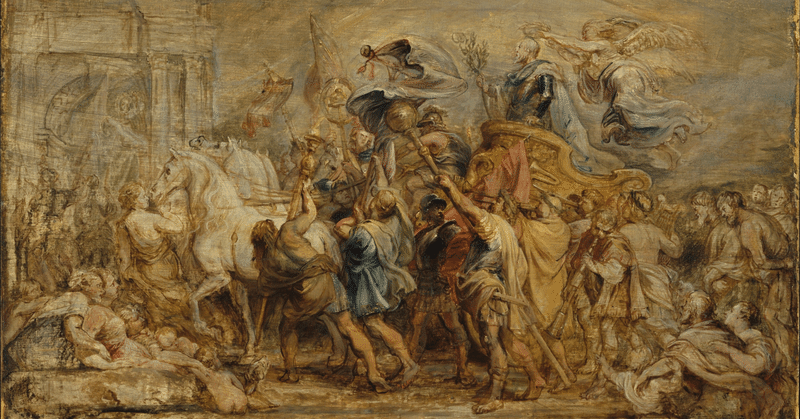
フラット、心理的安全性、失敗に寛容といった企業文化に対しての誤解
この記事は「paiza Advent Calendar 2022」の最終日25日目の記事です。
最終日はpaiza株式会社で社長をやっている片山がお送りいたします。
ちなみに、paizaはITエンジニア向け国内最大の転職・就職・学習プラットフォームです。(paiza.jp)
記事概要
先日、Twitterで流れてきて読んだ Harvard Business Review(以下HBR)の「イノベーティブな企業文化の残酷な現実」という記事(英文)が面白かったので、そのポイントと所感をまとめてみました。
内容としては、イノベーティブな企業文化には下記の事がセット必要であるという話です。
失敗には寛容だが、無能には寛容ではない
実験への意欲と高い規律性
心理的に安全だが、残酷なほど率直である
コラボレーションと個人の意思決定、説明責任
フラットで強いリーダーシップ、オーナーシップ
「失敗に寛容」、「実験の推奨」、「心理的安全性が高い」。「コラボレーションが活発」、「フラットな文化」といった革新的でイノベーティブな企業文化は自由で楽しいことばかりでなく、厳しい責任が伴うことも認識しなければならない。また、これらの文化は均衡を保つのが難しく、不安定である、といったものです。
※元記事が英文だったので、英文読まなくても内容が分かるように引用多めです。割と自分用の備忘録に近い内容となっています。
※翻訳はほぼDeepLで、おかしそうなところは自分の解釈で修正しています。
なぜイノベーティブな企業文化は難しいのか?
失敗に対する寛容さ、実験の推奨、心理的安全性、コラボレーションフラットな文化といった企業文化は、いろいろな経営に関する書籍にもたびたび登場しますし、シリコンバレー的な文化として、高い業績を上げるために必要なものとして認識している人も多いように思います。
しかしこれらの事を実践しようとするとなかなか難しく、いくつもの落とし穴にはまってしまって、高業績どころか、下手すると怠惰で堕落した組織になってしまったりもします。
失敗しても誰も責任をとらない、やりたい事だけをやる実験、心理的安全性というか一方通行の主張ばかり、コラボレーションという名の合議で意思決定がなかなかできない、フラットだが方向性がばらばら、など。スタートアップあるあるかと思います。
自分自身も、paizaではオープンでフラットな、自走性のある組織を作りたいと思いながらも日々試行錯誤をしています。しかしながら、こういった企業文化が望ましいというのは分かっていても、なかなか実現が難しい理由について、HBRの記事では次のように誤解が原因だ書かれています。
その理由は、革新的な文化が誤解されているからだと私は考えています。注目されるようなわかりやすい行動は、コインの一面でしかありません。その一方で、より厳しく、正直言ってあまり楽しくない行動も必要です。失敗に対する寛容さは、無能に対する不寛容さを必要とします。実験する意欲があれば、厳しい規律が必要です。心理的な安全性を確保するためには、残酷なまでに率直であることが必要です。コラボレーションは、個人の説明責任とバランスがとれていなければなりません。そして、フラットであるためには、強いリーダーシップが必要です。革新的な文化はパラドックス的なものです。この逆説が生み出す緊張を注意深く管理しない限り、革新的な文化を創造する試みは失敗に終わるでしょう。
https://hbr.org/2019/01/the-hard-truth-about-innovative-cultures
ではポイントごとに元の記事の引用含めてみていきましょう。
1.失敗には寛容だが、無能には寛容ではない
失敗からそのコストに見合った学びを得ることがポイントであり、非生産的な失敗に関しては寛容であってはならない、という内容です。一方であまりに厳しくしすぎるとチャンレンジすることを恐れるようになるため、失敗に対して寛容というはとても繊細なバランスが必要だというのが分かります。
自分自身の事を翻っても、最初に立ち上げた事業があまりうまくいかなかったが、そこであきらめずに、失敗した事業から得られた知見からpaizaのビジネスモデルにたどり着きました。失敗という心折れることから逃げず、学び取るということが重要ですが、失敗から学び取ってもう一度チャレンジするというのは全員ができるかというと、それなりの覚悟がないとできないことかもしれません。
生産的な失敗は、そのコストに見合うだけの価値ある情報をもたらす。生産的な失敗は、コストに見合った価値ある情報をもたらす。失敗は、それが学習につながった場合にのみ祝福されるべきである。「失敗を祝う」という決まり文句は的外れであり、私たちは失敗を祝うのではなく、学習を祝うべきなのです。
(中略)
単純なプロトタイプが、これまで知られていなかった技術的な問題のために期待通りの性能を発揮できなかったとしても、その新しい知識が今後の設計に生かされるのであれば、祝うに値する失敗と言えます。しかし、5億ドルもの開発費をかけて設計の悪い製品を発売しても、それは単なる失敗作に過ぎません。
https://hbr.org/2019/01/the-hard-truth-about-innovative-cultures
2.実験への意欲と高い規律性
新規事業などでもありがちですが、撤退ポイントを設けず、やってみないと分からないといって始めてしまい、辞め時が分からなくなるというのはよくありがちなダメパターンです。また撤退ポイントを決めていても、未練が出てずるずるやってしまいリビングデッドになってしまうというのはありがちです。
こうならないためには実験とセットで、何を検証するか、どうなったら撤退するかという高い規律が必要という内容です。
実験することは、キャンバスに絵の具を投げつけるような三流の抽象画家のような仕事をすることではありません。規律がなければ、どんなことでも実験として正当化されてしまう。
(中略)
負け組のプロジェクトを潰すことにもっと規律正しくなれば、新しいことに挑戦するリスクも少なくなる。
(中略)
アイデアの欠点を明らかにする確率を最大化する「キラー実験」を設計することが期待されています。
https://hbr.org/2019/01/the-hard-truth-about-innovative-cultures
3.心理的に安全だが、残酷なほど率直である
心理的安全性は色々なところで話題になることが多いワードです。心理的安全性という言葉のイメージから衝突を避けて本音を言わなくなってしまったり、部下から上司には何でも言えるが、上司は何も言えなくなってしまう、言いたい放題、言いっぱなし状態、みたいなことはよくありがちな失敗パターンです。
心理的安全性はアイデアに対して全員が率直である状態が望ましいので、全員が自分のアイデアに対して、残酷なほど率直な批判がされることを受け入れる必要であるという内容です。
これを全員に求めるのには、全員にそれなりの議論習熟度が必要になってきます。アイデアに対する意見と、個人に対する批判を話す側も聞く側も分けてできるスキルが必要ですし、今自分の意見にこだわってるな、といったメタ認知スキルも必要とされます。しかし日本の教育ではこういった議論やディベートを行うというのは従来あまりされてこなかったため、意外とアイデアに対する意見と、個人に対する批判を区別できないことが、それなりに多いように思います。
心理的安全性とは、個人が報復を恐れることなく、問題について正直かつ率直に話すことができると感じられる組織風土のことです。
(中略)
しかし、心理的安全性は双方向のものです。私があなたのアイデアを批判することが安全であるならば、あなたが私のアイデアを批判することも安全でなければなりません。なぜなら、率直な意見こそが、アイデアを進化させ、向上させる手段だからです。
(中略)
「残酷なほど正直な」組織は、必ずしも最も働きやすい環境とは言えません。部外者や新参者にとっては、攻撃的で硬派な人たちに見えるかもしれません。デザイン哲学や戦略、前提条件、市場に対する認識など、誰も言葉を濁すことはありません。誰の発言も(肩書きに関係なく)すべて吟味されます。
(中略)
このような文化を醸成する一つの方法は、自分自身のアイデアや提案に対する批判を求めることです。
https://hbr.org/2019/01/the-hard-truth-about-innovative-cultures
4.コラボレーションと個人の意思決定、説明責任
コラボレーションとは、合意形成や合議ではなく、協力を得たうえで個人が責任をとって意思決定し、説明責任を果たすことである、という内容です。
なんかとりあえずみんなで集まって話ををしたら、良いアイデア出てくるかも、と言って時間を使いすぎたり、みんなで決めようとして中々意思決定がなされず時間がかかる、というのはありがちな話です。
しかし、コラボレーションはしばしばコンセンサスと混同されることがあります。
(中略)
そして、コンセンサスは、迅速な意思決定と変革的イノベーションに伴う複雑な問題を乗り切るためには毒となってしまいます。最終的には、誰かが決断を下し、それに対する責任を負わなければならないのです。コラボレーションが機能するための説明責任文化とは、個人が決断し、その結果に責任を持つことが期待される文化です。
https://hbr.org/2019/01/the-hard-truth-about-innovative-cultures
5.フラットで強いリーダーシップ、オーナーシップ
フラットな組織は、ヒエラルキー型組織より強いリーダーシップがリーダーにも個人にもないと方向性が定まらず、カオスになってしまうという内容です。
フラットに経営層とコミュニケーションができるし、階層が少なく情報もオープンで、意思決定がスピーディーであるというのは良く求められる話ではあります。しかし、フラットだとマネジメントが行き届かなくなるためたいがいの場合は組織崩壊するし、情報をオープンにしてもメンバーが自ら情報を取りに行かなければ機能はしません。意思決定もフラットだが上に判断を仰ぐ中央集権的になってるとむしろスピードは停滞します。
明快な戦略と、戦略に基づいた一人ひとりのオーナーシップが必要、ということなので、これまた全員に求められるレベルが極めて高いと感じます。
文化的にフラットな組織では、人々は自由に行動し、意思決定し、意見を述べることができます。敬意は肩書きではなく、能力に基づいて与えられます。文化的にフラットな組織は、意思決定が分散化され、関連する情報源に近くなるため、通常、急速に変化する状況により迅速に対応することができる。ヒエラルキー型の組織よりも多様なアイデアを生み出す傾向があります。
(中略)
しかし、ヒエラルキーがないからといって、リーダーシップがないわけではありません。逆説的だが、フラットな組織には、ヒエラルキー型の組織よりも強力なリーダーシップが求められる。フラットな組織は、リーダーシップが明確な戦略的優先順位と方向性を定めることができないと、しばしばカオスに陥ってしまう。
(中略)
シニアリーダーには、説得力のあるビジョンや戦略(ビッグピクチャー)を明確にする能力が求められると同時に、技術や業務上の問題にも熟達した能力を持つことが必要です。従業員にとっても、フラットであるためには、自ら強いリーダーシップ(オーナーシップ)を発揮し、行動することに抵抗がなく、自分の決断に責任を持つことが求められます。
https://hbr.org/2019/01/the-hard-truth-about-innovative-cultures
まとめ
イノベーティブな企業文化は、次の3つの理由から、特に困難と元記事で指摘されています。
第一に、革新的な文化は一見矛盾するような行動を組み合わせる必要があるため、混乱を引き起こす危険性があります。
(中略)
第二に、イノベーティブな文化に必要なある種の行動は比較的受け入れられやすいものですが、そうでないものは、組織内の一部の人にとって受け入れがたいものになります。
(中略)
第三に、革新的な文化は相互依存的な行動のシステムであるため、断片的に実行することはできません。そのため、それぞれの行動がどのようにお互いを補完し、補強し合っているかを考える必要があります。
https://hbr.org/2019/01/the-hard-truth-about-innovative-cultures
「失敗に寛容」、「実験の推奨」、「心理的安全性が高い」。「コラボレーションが活発」、「フラットな文化」といった革新的でイノベーティブな企業文化は、えてして自由で、のびのびとした、キラキラした部分に目がいちがちです。しかし実際これらをやろうとすると、リーダーだけでなく、メンバーにも高いレベルが求められる、とても厳しくハードな規律と強さがセットとなる文化であることが分かります。
イノベーションを自由奔放なものと考えている人は、規律は創造性にとって不必要な制約であると考えるでしょうし、匿名性の高いコンセンサスに安住している人は、個人の説明責任へのシフトを歓迎しないかもしれません。
(中略)
失敗」しても無駄にはならずに、むしろ学習が得られる可能性が高くなります。また、失敗した実験に対して寛容であることは、近視眼的であるよりもむしろ賢明なことです。そして、フラットな組織では、情報の流れが速くなり、より迅速でスマートな意思決定が可能になります。
(中略)
このような文化は、楽しいことやゲームばかりではありません。多くの人は、実験や失敗、コラボレーション、発言、意思決定などの自由度が高まることに胸を躍らせることでしょう。しかし、このような自由には厳しい責任が伴うことも認識しなければなりません。しかし、自由には厳しい責任が伴うことも認識しなければなりません。
革新的な文化は不安定であり、均衡を保つ力の間の緊張は簡単に崩れてしまうため、リーダーはどの分野でも過剰な兆候に注意し、必要に応じてバランスを回復するために介入する必要があります。失敗に対する寛容さは、弛緩した思考や言い訳を助長しますが、無能に対する不寛容さが行き過ぎると、リスクを取ることへの恐怖を生みます。
https://hbr.org/2019/01/the-hard-truth-about-innovative-cultures
自分自身、オープンでフラットな、自走性のある組織を作りたいと思いながらも日々試行錯誤をしている身とては、この記事はとても刺さる内容でした。ぼんやりとこういう感じかなというのは日々感じていたけど、きちんと言語化されていると思考の整理としてとても有用な記事でした。
興味がある方は原文も読んでみてください。
最後に採用の宣伝。オープンでフラットな、自走性のある組織を作りたいと思ってる方は是非お声がけください!
paiza株式会社の採用情報
https://hrmos.co/pages/paiza/jobs
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
