
【本の感想】能狂言を知ることがこんなに面白いとは『教養としての能楽史』
意外にも!と言ったら失礼なのだが、面白かったのがこの本。
中村雅之『教養としての能楽史』
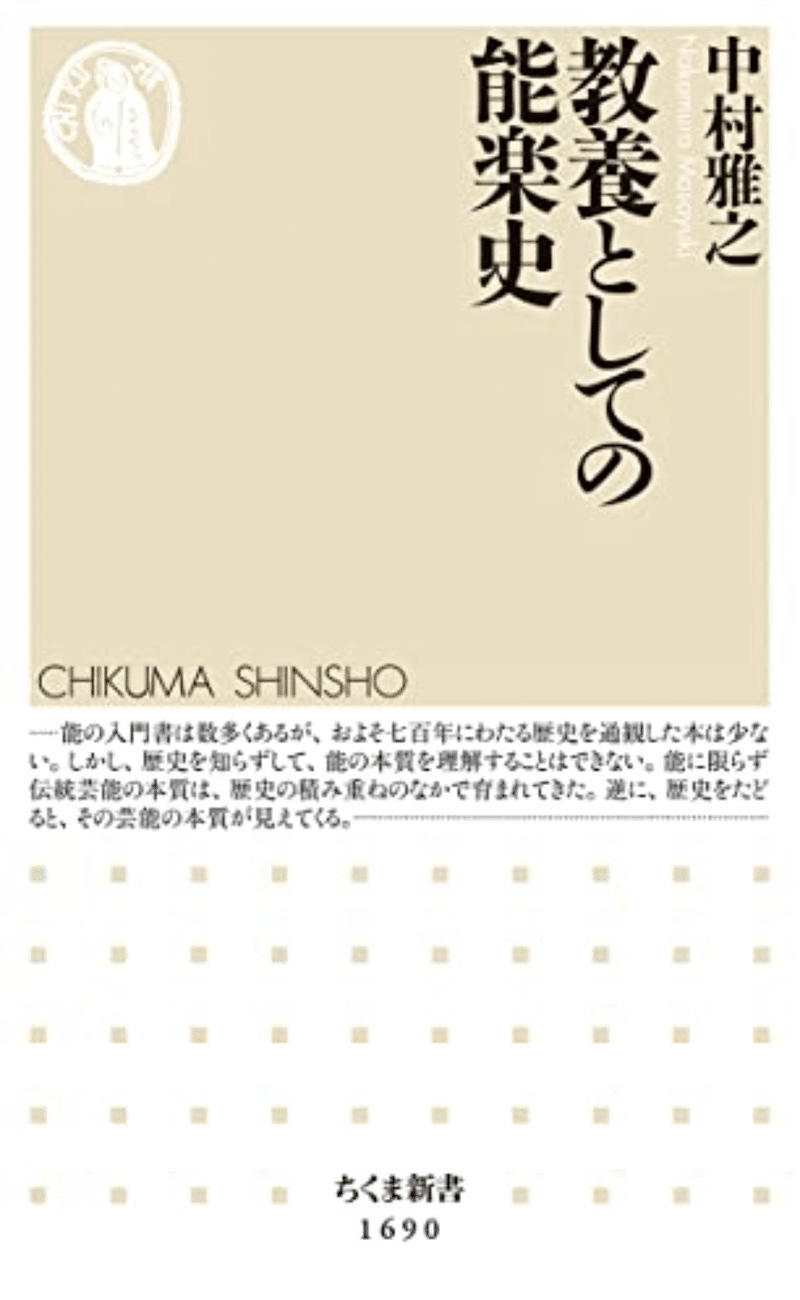
手に取る人、避ける人、いるのでは
能はもともともっとアップテンポ?
平安時代に起源を持つ能。そこから現代に至るまでの能楽の通史、なんだけど、これが面白いのだ。
人が関わって、まぁほとんど時の権力者が能とどのように接してきたか、でその位置がわかる。
でもだいたい能っていうと、
スローペースの謡とのろのろした動きで、なんだかつまらなさそうってのが多くの人のイメージなのではないだろうか。
この本によると、以前はもっとアップテンポだったというのだ。
実は謡を習っていたことがあるので、私自身は今の能をそれほどスローだと思わない。
ってことは結構早いじゃない?

禅問答?な翁
『能面翁』東京国立博物館所蔵
「ColBase」収録
世阿弥の存在が能の流れを作った。
写真の翁のように、ストーリーがなく
演じられることが目的の存在から猿楽、田楽と流れがあるなか、時の権力者に利用されながらも能楽師の意識によって芸術性を保っていた。
例えば足利義満と世阿弥。
まだティーンズの2人、義満は祇園祭を観るために世阿弥を伴って現れ、一緒に、それも同じ盃で御酒をのみながら観た。なんでも高貴な人(義満)が、下賤の能楽師を同じ席に座らせたことは驚きに値することらしく、さらに美しい少年世阿弥、という存在にも驚きが巻き起こったらしい。
なんかワクワクするわね!
お互いティーンズだからね!Youちょっと一緒に、じゃないのよ。
世阿弥は、足利義教の代になると疎んじられ佐渡に流され息子が先に亡くなり、と信じられないような人生をおくる。しかし著書『風姿花伝』を読むとプロデューサーとしての力量が素晴らしかったようだ。
この本でも、現代人の生き方にも通じることからよく読まれているとあり、意訳されるとその通りだよねーって内容のオンパレード。
いつか読んでみよう、『風姿花伝』。
さて、世阿弥の代わりに人気が出たのは犬王。
犬王ってアニメ映画になってるよね。
豊臣秀吉による箔付けとしての能。
時代は少し下がり、豊臣秀吉の天下。
秀吉ってほら、権威になるものを後付けにしなきゃならなかったでしょ、能って打ってつけだったみたい。

東京国立博物館所蔵
「ColBase」収録
観るだけにとどまらず晩年、習う!と言い出して、周りはおいおいやめたらどうですか、いやでも聞く耳持たないよね、誰も意見言えないし、でも迷惑なんだよね、状態。
その挙句、天皇の前で披露するぞ!大名も集まれ!となっちゃって1日かけて能を御所で天覧能。
面白いのは、徳川家康と、前田利家と3人で『耳引』という狂言に出たらしい(耳引は今は伝わっていない)。でお互いの耳を引っ張りあったりしたらしいんだけど、利家も家康も手加減したでしょうねー急に機嫌壊しても面倒だから、秀吉。
でもあの3人が衣裳を着て狂言、だなんて、見てみたい。耳を引っ張りあっておっとっと、とタタラを踏んだりしたのだろうか。
江戸時代は武家の能…だけど⁉︎
さてさて江戸時代。
能は武家のものとなっていたけれど、なんと何か祝い事があると「町入能」といって、江戸の町民を江戸城に招いて、能をみせるといった行事があったそう。
もちろん町の人全員が行けるわけではなく、誰々と決められていたが代わりに行っちゃうよ?はあったようで、お城の中にぞろぞろと町単位で決められた時間に鮨詰めで観能、お帰りにはお酒とお土産があったらしい。
ちょっと自分だけ多く飲まないでよ、こっちの分が無くなったでしょ!みたいないざこざもあったり、逆に観ている間はトイレにも行けないので、観客がいなくなったところにお土産があったり。
余談ですが、今は士農工商の順とは教えないので、武士は支配階級だからってのがあったとしても身分制度は以前思っていたのとは異なるみたい。
そして明治を迎え、戦前となる。
明治になると、大名家お抱えの能楽師の家系によって、辛酸を舐めた流派となんとか保てた流派とにわかれたようだ。
そして戦前、能や狂言の内容に検閲が入る。
貴人を扱っているものが不敬だとか、まぁよく理由を見つけること。
恐ろしい世の中だ。
そして戦後から現在に関しては、自由。
能の作品もまた謡曲も新作ができたり、三島も近代能楽集では観阿弥の作品をリライト(などと軽く言って良いのか!)してるしね。
能楽堂に観能、または狂言を観にいきたい。なかなか叶わないけど。
鬼滅の刃の狂言がなかなか良さそうだから計画したい!
ではまた!
【タイトル写真の出典】
『能狂言絵巻 下巻の内 『楊貴妃』』
筆者不詳 東京国立博物館所蔵
「ColBase 」収録
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
