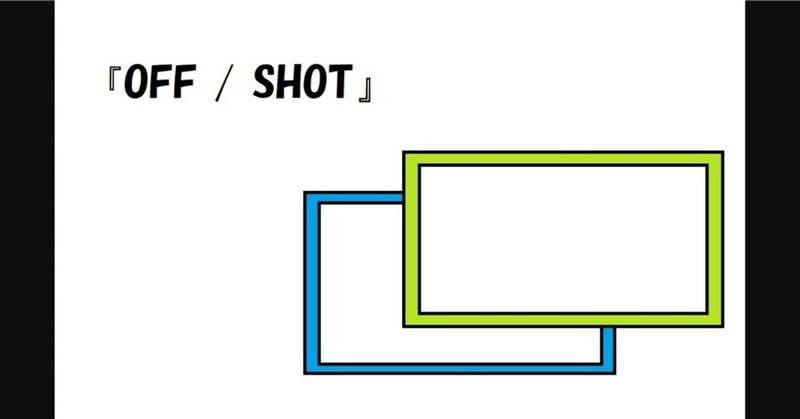
『OFF / SHOT』 2/6 《短編小説》
【文字数:約3,200文字】
お題 : #創作大賞2023 +(#イラストストーリー部門)
Back : 1/6
「……では、スタート5秒前! 4! 3!」
続くカウントで台本の中に全員が取り込まれ、翠那とモニカ・蒼瑠が演じる2人のキャラクターだけが命を与えられる。
『マーダー・バレット』は医師の桐原蓮華が、撃たれた人間の殺人衝動を呼び起こす銃を手に入れたことで始まる。やがて桐原は警察に追われて夜の学校へと逃げ込み、そこで銃の本来の所有者である悪魔、タチアナと出会う。
撮影しているのが2人の出会う場面で、始めは人間の桐原にタチアナの姿は見えない。窮地に立たされた桐原が悪魔の側に近づいていく演出として、教壇を挟んで向かい合う場面からタチアナが登場する。
「はぁ……はぁ……」
廊下側からの照明と赤色灯の狭間にいる桐原は、逃げる際に履物を失くしているだけでなく、足には無数の赤黒い擦り傷が芽吹いている。
「どうして、こんなことに……」
当の本人は痛みからの呼びかけなど聞こえていないらしく、手にしている狂気の孵化器を強く握りしめる。
今にも砕け散りそうな自我を抱きしめ、何も書かれていない虚無の黒板に体を預ける姿は、もはや手負いの獣ですらなかった。
《そんなに怯えちゃって……かわいい》
手を伸ばせば触れられる距離にいるタチアナの声は、まだ目の前の人間には届かない。
何度目か分からない投降の呼びかけに対して唇を噛んで、桐原は追われる原因となった凶器に弾を込めようとする。
空気中からリップと似ている鋼鉄を掴み取り、横に開いたシリンダーの物欲しげな穴に向け、かちり、かちりと硬いキスを繰り返した。
使用者の思念から作られる弾には限りがない。ただし、人間が扱うには代償が必要とされる。
《あなたの衝動から生まれた種は、とてもキレイ》
翠那はタチアナのまま、桐原に取り込まれているモニカを上目遣いで見つめた。銃を変えたおかげで奇妙な扱いにもならず、さっき中断した難所を抜けてカメラは回り続ける。
相手を射殺す桐原の両目が、ゆっくりと翠那に向けられた。
その瞬間、電気が走る。
金色の瞳から注がれる激情で気圧されそうになるけれど、余裕たっぷりの笑みを崩さないように全神経を総動員する。
「……だれか、そこに……いるの?」
人間が踏み越えてはならない境界へと到り、桐原とタチアナを隔てていた見えない壁が融解していく。
「こんばんは。それともはじめまして、かな?」
お互いを始めて認識した2人は見つめ合い、鏡に映った自分ではない他者を知ろうとするのは必然で、より強い動機を持っているのは人間の側だった。
教卓に肘をついた姿勢のタチアナを前にして、桐原は視線をそらすことなく、ただひたすら悪魔の中へと入りこんでいく。
「私は……あなたを、知ってる?」
「その銃を手にしたときから、私はあなたの中にいる」
タチアナは右腕を持ち上げて銃に触れ、桐原そのものへと指を滑らせていく。やがて青いブラウスに辿り着き、その下に隠された命の器が鼓動して、言葉によらない理解を届けた。
翠那もまた指先を通してモニカの緊張を読み取り、求められた以上の笑みを浮かべる。
「私は蓮華を探してた」
「タチアナが私を呼んだ」
もはや2人を隔てていたはずの境界は溶けあい、対峙しながら互いの中に溺れていく。
銃を手にした桐原の左手が、命の器とつながる右手を包み、
「「やっと会えた」」
泣きだしそうなモニカのアルトに翠那のメゾソプラノが重なって、一瞬だけの二重奏が響く。
古来より続く舞台演劇のようで賛否が分かれそうだけど、原作の世界観を踏まえれば普通というか、むしろ当然の展開だった。
役としてタチアナを演じているはずの翠那でさえ、虚構の側に取り込まれかけていたところで、
「カット! 映像チェックします!」
統括チーフの発したテノールによって現実に連行され、桐原もまた人間に戻る。
「あわわっ! すいません!」
教壇にもたれかかるような状態から、わりと強めに押されて上半身が持ち上がる。後ろに倒れてしまうほどではないと判断したら、さっき離れたはずの手というか腕が伸びてきて、今度はモニカの胸に抱きとめられた。
「ふぅ……」
「……ふぅ、じゃなくて」
どうにか衣装は汚さずに済んだけれど、さすがに黙っていられなかった。
翠那は思いがけない抱擁から抜け出して、目の前にいる新人を睨みつける。
「いきなり押したり引っ張ったりするの、止めてくれません?」
「……あ、あの」
反射的に謝罪しようとするモニカを遮り、翠那の本音をぶつける。
「意味もなく謝らないで。あたしたちは共同作業してるんだから、縮こまってるとこっちが迷惑。あとスイッチみたく切り替えるんじゃなくて、ゆっくりと着水する感じ、わかります?」
「着水……」
繰り返した後で、なぜかじんわり涙目になる。勢いで言い過ぎただろうかと後悔しかけたら、
「さっきの『愛の富士着水』みたいに……」
ただの思い出し泣きだと分かり、肩から一気に力が抜ける。
『愛の富士着水』は国際テロ組織に政府要人だと勘違いされ、誘拐そして拉致監禁された家族が逃亡するという物語だ。中盤、富士山の北に位置する湖に夜間着水する場面があって、たぶんそのあたりを思い返しているのだろう。
「お父さんお母さんが傷だらけになって、子供を守るんですよね」
「……まぁ、そうですね」
出演作を関連づけられて嬉し恥ずかしの複雑な心境になりつつ、せっかくなので利用させてもらう。
「あの2人だって怖かったはず。地面に降りるのに高さが足りなくて、でも水面ならって発想を変えた」
「だけど無傷ってわけにもいかなくて……はっ!」
不意に声を上げたモニカは予想通り、ろくでもない結論を導き出す。
「翠那さんと私は一心同体、これがまさしく共同作業なんですね……」
「ええと、まぁ……そんな感じで、よろしくお願いします……」
思考の道のりはブラックホールだけど、いちおう翠那の目指していた場所に着水した。
そこに統括チーフの声が投げ込まれる。
「チェックOKです! 次はカット45でお願いします!」
監督たちの承認が得られたからには、最終的にいくらか編集が行われるにせよ、ほぼそのままさっきのやり取りが配信される。
その光景を想像して、わりとよくある胸の痛みに顔をしかめた。
画面の中にいるタチアナと桐原は架空の存在であり、演じた翠那とモニカ・蒼瑠とは関係ない。それでも何かしらの共通点や類似性を見出し、役者は求められた理想に近づこうとする。
両者はまったくの無関係とも言い切れず、これまで演じたものが溶け込んで今の翠那を作り上げたわけで、それらに対する評価からは逃げられない。
「ちょっと寒いですか?」
「あ、いえ……平気です。OKになるか心配だったので」
スタッフの1人に気づかわれ、翠那は意識せず自分の腕をさすっていたことに気づいた。復活したモニカはそれを見逃さず、演出のために赤黒く汚された白衣を持ち上げ、
「これならまだ予備があるそうですよ?」
などと冷え過ぎ対策として勧めてくる。たしかに腰から足の指先まで、破れや傷みがあっても膝上スカートにタイツ着用なら寒いはずがない。
一方の翠那は半袖のセーラー服で、襟と袖口それに下のスカートは孔雀の羽を思わせるピーコックグリーンが美しい。ただし透け感を出すために生地は薄く、うっすら体のラインが出るようになっている。
もちろん撮影でNGが出ないよう対策済みだけど、防寒という点では無防備に等しい。
「大丈夫です、ありがとう」
普通に返したつもりなのに、なぜかモニカの表情はふにゃふにゃしている。
「……はい、何かあったら言ってくださいね」
「え、ええ……」
さっきまで演じていた桐原のように、体と心の距離を近づけてくる。顔が良いのはともかく、モニカの中にも別人の存在があることを考えたら、なぜか胸がちくりと痛んだ。
Next : 3/6
なかまに なりたそうに こちらをみている! なかまにしますか?
