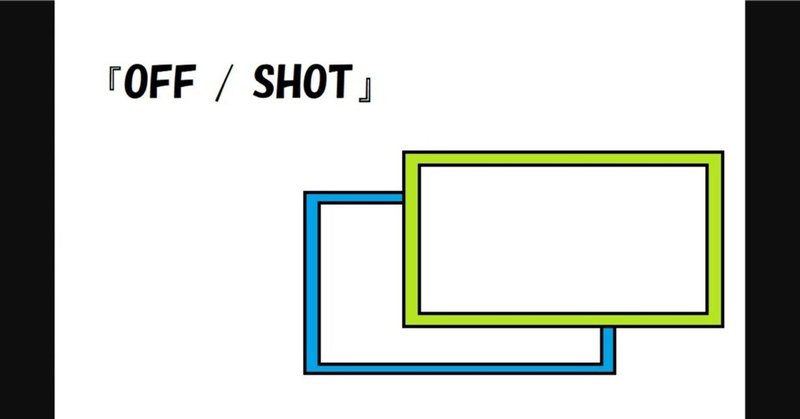
『OFF / SHOT』 3/6 《短編小説》
【文字数:約3,200文字】
お題 : #創作大賞2023 +(#イラストストーリー部門)
Back : 2/6
次のカット45は『マーダー・バレット』の中で、唯一と言っていい平和な場面だ。
タチアナを認識した桐原は、向かい合っていた教壇から生徒用の机に座るよう促す。まるでクラスメイトのように並んで座る2人は、しばし外の喧騒を忘れて語り合う。
渡されている台本にはお手本みたいな話題が添えられており、監督のものらしき「アドリブ歓迎!」という場違いに明るい注釈が踊っていた。
「どうしてタチアナはそんなにカワイイの?」
カメラ位置を変えながら数パターン撮っておき、それらを編集でミックスさせることにより、画面に動きを与えるらしい。
「タチアナと会うために私は生まれてきたんだね」
流れを把握するためのリハーサルでは台本通りで問題ないし、世界観を壊さなければ何を喋っても構わない。それなのに、
「もしもタチアナが妹だったら絶対に守る」
さっきからケーキにハチミツと砂糖を振りかけただけでなく、飴細工でコーティングされたような台詞ばかりが届けられる。胸焼けと酸欠で表情が崩れるのを狙っているとしたら、これはもう挑戦状に他ならない。
リハーサルが終わった途端、翠那はタチアナの仮面を投げ捨てた。
「……っはぁ!」
「どど、どーしたんですか!?」
モニカは継ぎ目のないシームレスで戻り、さっきの切迫感に押しつぶされそうだった桐原の面影は消え失せている。
「……ねぇ、蒼瑠さん」
「もう水くさいなぁ、私のことはモニカでいいですよ」
「じゃあモニカ、何なのあれ」
「あれ……?」
この世で無意識の悪意が最も危険とされるのは、本人の中に罪悪感が芽吹かないばかりか、むしろ良い行いだと勘違いしているためだ。
「いくらアドリブOKだからってやり過ぎでしょ」
これまでのモニカなら指摘されて謝り、どうすれば良いかと指示を仰ぐまでがワンセット、のはずだった。
「……私はこれが正解に近いと思います」
その言い回しは自分の中で作品を咀嚼して、ある程度の意見が固まっていることを示している。
途中でリハーサルを止めなかった監督たちも翠那たちのやり取りを見守っており、なぜ自分なりのアドリブを入れたのか、その理由を知りたがっているようだ。
「どういった流れでそう思ったのか、皆さんにも分かるよう話してください」
理由が明確でない直感は芸術作品などであれば許されるかもしれない。ただ、複数の人間が関わる制作現場において、言語化されないものを共有するのは難しい。
ぼんやりした消極的な賛成と、イメージを共有した納得の賛成とでは、完成したものが同じになることはありえない。
しばらく黙っていたモニカは、
「そうですね……」
言葉を整理するためか視線を下げ、それから自分に注目している人間すべてに伝わる声量でもって話し始めた。
「この作品の原作『朝と夜の境界線』だと、桐原蓮華は主人公の主治医という設定です」
「あんまり詳しく描かれてないけどね」
「ちなみに翠那さんは誰が一番お気に入りですか?」
「……それ、今は関係ないでしょ」
唐突な問いかけで塩対応になったけれど、モニカは「関係あります」と譲らない。仕方なく無難な主人公だと返す。
「いいですよね、幼馴染と張り合うところなんて特に──」
「それで?」
脱線してブラックホールに吸い込まれそうな気がしたので、被せるようにして先を促す。
「あ、すいません、関係があるっていうのは原作4巻の59ページなんですけど……」
すらすらと出てくるあたり、何度も読んだことが窺い知れる。
「主人公が町を歩いている場面で、すごく小さくなんですけど桐原がいるんです」
「……そうだった?」
記憶にあるのは主人公の姿だけで、それ以外の人物は線のみで簡単に描かれていた気がする。
翠那は同意を求めるように周囲を見回したけれど、首を傾げたり曖昧に笑みを作ったりで、明らかに共通の認識になっていない。
モニカに対する不穏な空気が漂い始めたところで、
「もしかして、これ?」
翠那のマネージャーがスマートフォンを差し出して、渦中の人物へと確認を求めた。
「これ、これです!」
2人の指先が置かれた画面を見ても、線のみで表現された人物は桐原と結びつかない。それでも顔を近づけて注意深く観察したら、あることに気づいた。
「……この人、もしかして白衣を着てる?」
「正解です! ぱちぱちぱちぱち!」
よほど嬉しかったのか音声つきの拍手で称えてくれたけれど、納得の賛成にはまだ足りない。
「意外な登場シーンなのは分かった。でもこれとさっきの台詞がどうつながるの?」
「制作前の顔合わせで原作者の先生がいらっしゃいましたよね?」
「ええ、あたしたちが桐原とタチアナのイメージぴったりだって、喜んでくださってたけど」
「顔合わせが終わってから私、あの場面に桐原がいた理由を訊ねてみたんですよ」
「……たいした度胸ね」
演じる役者を通り越して熱狂的なファンと認識されたモニカは、描かれていない裏設定のようなものを教授され、原作に登場しないタチアナとの関係性にも話が及んだらしい。
モニカは「先生がおっしゃいました」と、信仰を説く聖職者みたいな前置きをして続ける。
「桐原にとってタチアナは、子供のときに亡くした双子の妹の生まれ変わりなんだって」
「……そんな設定あった?」
またしても共通の理解を外れて異次元に向かって走り出し、この場にいる誰もがモニカの妄想あるいは虚言ではないかと疑っている。
好意的に考えるなら役者のモチベーションを上げるための、いわゆるリップサービスだろう。公式に出されていない限り、こうして口外されたところで個人の見解に収まる。
だが、モニカの瞳は濁りのない金色どころか、むしろ輝きを増しているようにさえ見える。
「どうして双子の妹がって話は、さっきの町の場面から考えていくと分かるんですけど、桐原がどこに向かっているのかがポイントなんです」
「たぶん休憩中とかじゃないの」
面倒になってきて投げやりに答えたら、またしても音声つきの拍手を返された。
「そうなんですよ! 休憩なら白衣を脱げばいいのに、それをしていないってことは……?」
あなたならもう分かりますよね、という期待に満ちた眼差しを向けられても、いったい何がどうなってモニカのアドリブにつながるのか、糸口の切れ端すら見えてこない。
翠那は左右に向けて両手を開き、「降参です」と肩をすくめた。
「ふっふっふっ……仕方ないですね」
整った容姿による勝ち誇った表情は、相手に怒りや苛立ちを与えず敗北感のみを植えつけるらしい。
それから熱狂的ファンが語ったのは、まさしく原作者の手による番外編だった。
休憩中と思われる桐原が、白衣のまま外に出たのは主人公を追うためだった。担当している患者ではあるけれど、わざわざ犯罪めいたことをするのは暗い感情があるからで、それは主人公の幼馴染と関係がある。
原作1巻で桐原への診療を勧めたのが幼馴染であり、彼女に亡くした妹を重ねている桐原は、幼馴染に感じる親愛、主人公への嫉妬、主治医としての責任という3つの感情に苛まれている。
やがてそれらに押し潰された桐原が原作6巻、今回のスピンオフ作品の元となった事件を起こし、ひっそりと物語から退場する。
「撃たれた人間の殺人衝動を呼び起こすっていうのは、桐原が扱うからそうなっているだけで、主人公が扱う能力の変異版らしいですよ」
「つまり主人公に関わったことで、桐原は退場することになった?」
「そうなります。桐原とタチアナの関係も、卵か先か鶏が先かって話です」
「……う~、何かもう、頭がパンクしそう」
与えられた膨大な情報が渦を巻き、ぐらぐら煮立って吹きこぼれそうだ。
熱するのが止まらない湯沸し器となった翠那に向けて、モニカはこれ以上なく簡潔にまとめてくれる。
「だから桐原はタチアナが大、大、大好きなんです!」
Next : 4/6
なかまに なりたそうに こちらをみている! なかまにしますか?
