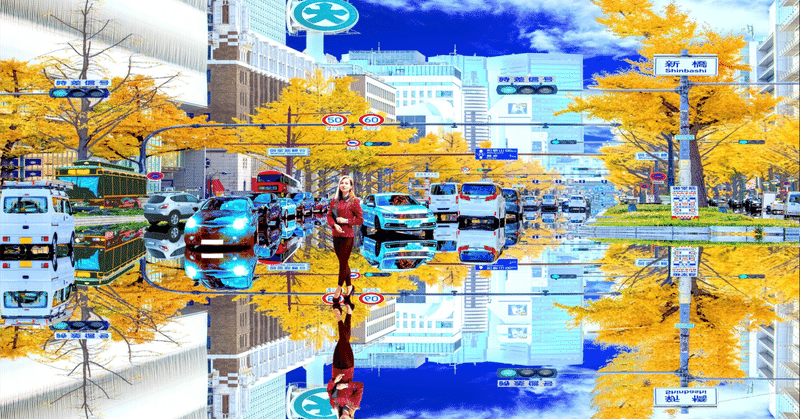
バリア・フリーの階段
1
晩秋の朝のことだった。
いつものように、鉈屋町の惣門道を通り『あったかホーム』に出社すると、突然、栗林所長に、
「赤城さん。今日の午前11時に社長がいらっしゃいます。アナタにお話があるそうですよ」
と、すまし顔で言われた。一週間前にも私は栗林から、こう言われていた。
「アナタは、この仕事には向いていませんね。一人で行動することが多いし、協調性にも欠ける。変な発言も多いし、言動もちょっとおかしいです。服装も乱れているし食べ物に執着し過ぎです」
さんざん言われた挙げ句、極め付きはこれだった。
「しかも、この前の研修先で600円の食い逃げをしましたね?一週間だけ猶予を与えます。この一週間でアナタの行動を観察します。それから改めて判断します」
栗林からは高飛車な香水の匂いがした。
このグループ・ホームは、まだオープン前で、男女合わせて二十名が契約社員として採用された。利用者が入居していない段階での半年間の試用期間中での出来事だった。ほぼ全員のスタッフがヘルパー2級以上の資格を取得しているので、ある程度の予備知識は把握していたが、実際に利用者と接触する介護をしていないため、未熟なスタッフが多かった。とはいえ、働きはじめてたった半月ばかりで解雇となると、あまりに惨めだと思った。
一般に、グループ・ホームとは、精神疾患者向けにイギリスで提唱されたのが始まりとされ、病気や障害などで生活に困難を抱えた人達が、専門スタッフの援助を受けながら、共同で生活できる場所のことである。そこで利用者は、食事介助や入浴介助等の機能訓練を受けることができる。家庭的で落ち着いた雰囲気の中で過ごせるよう、一組が5人から9人の少人数制で成り立つ。利用者各自の居室があり、共同で生活する居間やスペース・キッチンやお風呂やトイレ等がある。利用者の中には、社会的入院(症状は回復しているのに帰る家がない・アパートを借りたくても保証人の成り手がいない・病院から強制的に追い出された等)を強いられている方達が多く、そのためにグループ・ホームが存在している。
施設で働くスタッフの主な仕事内容は、利用者達とのコミュニケーションであり、食事や掃除、洗濯や排泄等の自立支援のお手伝いである。運営側は、厚生労働省から、精神障害者社会復帰施設や精神病院等を経営する〈地方公共団体〉〈社会福祉法人〉〈医療法人〉〈公益法人〉と定められていて、国と県から合わせて年間300万円が助成金として支給されるという。それは、毎年度末頃、主に介護スタッフの給与としてである。
採用されてから最初の一週間の仕事内容は、概ね、職員研修として町内の公民館を使い、スタッフ同士の自己紹介をしたり、笑顔作りをしたり、普段使う店で体験した出来事などを語り合ったりした。その間、『あったかホーム』には、施設用の荷物が届き、10月13日からは新築の施設の中での作業だったが、それは私にとって最も苦手とする世間話や人間関係だった。スタッフは、男性が3人、あとは女性で、年齢も20代から60代までと幅広い。よく、デパートや高層ビルの火災現場では、人々が先を争い出口に一斉に押し寄せ、パニックに陥ることがあるという。たが、災害時でも、自分は間違いなく助かるという保障があれば、理性的な行動が取れる。試用期間中のグループ・ホーム内でも、そういった作用が働いていなかったと言えば嘘になる。買い物に行くにしても、キッチンで料理を作るにしても、二十人全員が1つの仕事を取り合うようになり、正直、何をしていいのか分からなかった。人がやっている仕事を見ているだけで、そこに無理矢理割り込んでまで仕事をするという度胸が、三十路で独身の私には無かった。
「何を言われるんだろう…」
という不安が鼓動になっていた。いつも通り、スタッフ達の雑談を聞きながら、どことなく私だけ孤独を感じていた。
午前11時となり、再び栗林に呼び出され、玄関入口近くにある三畳一間のフローリングの個室に来るよう指示された。
個室のドアをノックし、ゆっくりとドアを開けると、そこには既に鬼頭社長が斜に構えて椅子に座っていた。鬼頭は六年前まで、医療機器メーカーの社長だった。看護師だった栗林とは県立病院で知り合ったと、公民館での社長講話の際に自らの経歴を話していた。亡くなった父親である先代の社長の跡を継ぎ、二十九歳で社長になってから二十三年間、販売事業に携わっていたが、六年前から介護事業に移行したとの事だった。既に、本社のある宮城県・福島県と合わせて六つものグループ・ホームを設けている。岩手県へは新規参入であった。また、自らの土地や財産を担保に入れての事業なので、経営者としては利益を優先せざるを得ないという趣旨のことも、この時話していた。
「座って」
「はい」
深々と頭を下げると、テーブルを挟み恐る恐る椅子に腰掛けた。栗林も入って来て、鬼頭の隣に座った。重苦しい空気が辺りに漂っていた。
「一週間前にも栗林から聞いているだろうが、やはり君は、介護の仕事には向いていない」
最初に口を開いたのは鬼頭だった。
「なぜですか?」
会社で強制的に受けさせられたインフルエンザ・ワクチン接種後の副作用で、頭が朦朧として左右に揺れていた。
「まだ試用期間中ですし、まだ利用者さんも入居していないし、何か具体的なヘマをしたという訳でもない筈です」
声がうわずった。
「か、解雇ですか?!」
「いや、解雇ではない」
黙って聞いていた鬼頭が口を開いた。
「解雇という形になると、君の経歴にも傷が付くと思って、自主的に辞めてくれるように頼んでいるんだがね」
「私は何もしていません。この仕事を続けさせて下さいっ!!」
本当にこの一ヶ月間、人の仕事を見ているだけで、殆ど何もしていなかった。
「トータル的に君はこの仕事には向いていないと言っているんだよ、分かるかね?」
「いえ、解りません」
「とにかくもう帰っていいから、午後の分のお給料もちゃんと払うから」
鬼頭は、ブラインドの隙間からこぼれる陽の光で照り輝いている頭部を然りげ無く片手で掻いた。
「と、言う事ですので、もう帰ってよろしいですよ」
何か反論しようと思ったが、栗林が先に淡々とした口調で制した。納得はいかなかったが、二人の圧力の様なものに押し出される風にして、私は黙って席を立っていた。ロッカーの鍵を開け、荷物をまとめると、同僚のスタッフ達にお別れの挨拶をした。中には、予め話を聞いていたスタッフもいたらしく、淋しそうに手を振ってくれる人も何人かいた。
─ゆっくりと家路を辿りながら、通勤時にはよく大慈清水の水を飲んだことを思い出していた。しばらくここを通ることもないだろう。確かに自分でも、そそっかしい点がある事は分かっている。初めてこの井戸水を飲んだ時は、この水に段組みの表示がされてあることすら気が付かなかったのであるから。真っ先に口にした水が、四番井戸の洗濯すすぎ水であったことは、たらふく飲んでから気が付いた事であった。
目にいっぱい涙が溢れていた。凍てついた空気が流れたかと思うと、項垂れた首に、冷たいものが当たっていた。ポツポツとそれは次第に強くなり、気が付くと、灰色だった道路一帯が真っ黒になっている。慌てて軒下に入ると、思わず携帯電話を取り出し、年の離れた友人の岡目純にすべてを話した。
「それはひどい…」
岡目純は定年退職されているが、現役時代は労働組合《みちのくユニオン》で先頭を切って活躍してきた、社会運動一筋のツワモノである。弱者の味方で、今まで多くの経済的弱者を助けてきた。彼と知り合ってから、まだ半年間しか経っていないが、私はこれまでも何度か彼に助けてもらった事がある。その岡目純が言うのだから確かだった。
「それで、どうしたの?」
「帰りました。みんなにお別れの挨拶だけして…」
すると岡目純は、冷静にこう言い放った。
「今からでもいい。そのグループ・ホームに電話をして、明日から出社すると言いなさい」
「えっ、なんでですか?!」
頭がこんがらがった。
「貴女はまだ、解雇だと言われた訳ではないんでしょう?」
「はい」
「だったら大丈夫。試用期間中は間違いなく働けるから」
「でも、もう来なくていいって」
「そんな事はないです。会社は貴女が出社すれば、黙って椅子に座っていても給料を支払う義務があります。ここで働きたいという意志を伝え、出社するのです」
ホッと胸を撫で下ろした。
「分かりました」
言われた通り、急いでグループ・ホームに電話を掛けた。
「はい。認知対応型あったかホームです」
栗林の声だった。
「もしもし、赤城桃子です。明日からいつも通り出社しますので、よろしくお願い致します」
「こちらはもうノータッチですので、本社に電話して下さい❗」
直ぐに電話を切られた。早速、仙台市の本社に電話をすると、本社側ではまだ事情を聞かされていなかったのだろうか、「分かりました」と曖昧な態度だった。
再び、岡目純に携帯でこの事実を伝えると、
「大丈夫。俺も若い頃、会社の専務に"辞めろ‼辞めろ‼"と言われ続け、それでも三年間仕事場に通った経験がある。阿呆になれ。阿呆を決め込むんだァッ❗❗」
と怒鳴った。
この時私は、本気で阿呆を決め込むつもりでいた。親ですら、
「そっだな会社さ行ぐ必要ね。結局お前には合わねがったんだがら、ハローワークさ行って、早ぐ次の仕事さ探せっ❗」
と言って、取り合わなかった。それでも私は、岡目純を信じていた。信じるしかなかった。岡目純の言葉を胸に、11月3日、誰よりも早く『あったかホーム』に出社した。
2
午前8時15分。
『あったかホーム』の扉を開けると、栗林が玄関入口で待ち構えていた。
「あら?」
とぼけた表情とよそよそしい態度で、栗林は対応した。
「お早うございます」
「お早う」
目深にかぶっていた帽子を取り、頭を下げると、いつも通り外履きから内履きに履き替え、中に入ろうとした。その途端、
「ちょっといい?」
と、栗林が私の腕を掴んだ。
「ちょっといい?社長をお呼びしますので、仕事はいいから待っててもらえる?」
昨日と同じ個室で待つよう指示された。暖房も電気もない薄暗い個室で、寒さに震えながら椅子に腰掛けていた。昨日は取らなかったが、今日はテーブルの上にNoteと鉛筆を用意した。岡目純からの助言で、鬼頭との会話を逐一メモすることにしたのだ。
三十分待っても、鬼頭は現れなかった。その間、スタッフ達は居間で日課の掃除をしている様だった。
「桃ちゃん、一体何をしたのかしら」
「さあ」
今居る個室と入居者用の居間とは、薄い壁一枚でしか隔てられていないため、スタッフ達の会話が逐一漏れていた。途中、ケアマネージャーが挨拶もなしに個室に入って来て、リモコンで暖房と電気を点けてから出て行った。ケアマネージャーなんて肩書きだけで、ケア(世話・管理・配慮)のマネ事だな、と内心皮肉って思った。
─結局点けざるを得ないのだから
午前9時3分。
ようやく鬼頭が現れた。何の前触れもなしに、驚くほどいきなり扉を開けて入って来た。咄嗟に椅子から立ち上がると、挨拶をして頭を下げた。鬼頭の方は、挨拶もせずにチェッと小さく舌打ちをした。これが、介護施設を経営する立場の人間がする事だろうか…と一瞬疑問を持った。
「昨日言ったこと、よく分からなかったの❓」
「昨日は具合が悪くて帰りましたが、私はまだ辞めていません。この仕事を続けさせて下さい!!」
「言ったよね?君はこの仕事には向かないって。トータル的に向いてないって」
「私は、雇用契約期間通り働くだけです」
「ダメッ❗❗今日で終わり」
そう言って、鬼頭はまばたき一つせず私を睨み付けた。そして、手に持っていた雇用契約書をチラつかせながら、それを読み上げて見せた。
「契約期間は、期間の定めあり。平成二十一年十月一日から平成二十一年十二月三十一日は、毎度更新。試用期間の入社六ヶ月間は試用期間とし、勤務態度や能力などを判断した後に、本採用になります」
そうは言っても、私がいちいちNoteにメモをするものだから、鬼頭は、そのNoteを気にする様に眉をひそめた。
「君はこれにサインをしたんだよォ❗」
「はい。6ヶ月後には正社員になれるものだと解釈しました」
そんな悪びれない態度に、鬼頭は急に声を荒げ、
「昨日はなぁ~、ああいう風になぁ~、ハッキリと言わなかったのはなぁ~、君の方から辞めてくれればいいと思ったんだがなぁ~、今日は解雇だッ❗」
と、痰を絡ませた様な声で怒鳴った。
「解雇だ❗」
「いえ辞めません」
「解雇だ❗」
「いえ辞めません」
こういったイタチごっこが、暫く続いた。
「オレとお前が、こうやって対等に話をしてること自体、おかしいんだぞッ❗❗」
「それなら、具体的にその解雇理由を仰って下さい。そうでなければ、納得いきません」
「それを言ったら─」
鬼頭は、ニヤッと口元に笑みを浮かべた。
「それを言ったら、君の悪口になってしまうよ」
…嫌な予感がした。
「どういった内容ですか?聞く権利があります」
鬼頭は、拳を口元に持ってきて大きく咳払いをすると、今度はファイルからプリント用紙を手早く取り出し、それを読み上げた。
「まず、研修先で昼食のお代わりをした」
「それはあの時…ご飯があまりにも少量だったので『もうちょっと食べたいですね』と冗談半分に言ったんです。そしたら、スタッフの方が気を利かせて、無言で冷凍保存してあったご飯を電子レンジで温めて出したんです。せっかく出してくれたので頂いただけで自分から『お代わりしたい』と言った訳ではありません」
この職場では御世辞すら一切使わず機械的に食事介助した方が正解な気がした。
「あと、『夜間にお風呂に入っていいのか?』と尋ねたそうじゃないかね?」
「それは、私ではありませんっ!!」
それは雑談の中で、六十代のスタッフが『夜間にお風呂に入れるんですか?』とケアマネージャーに尋ねた。当然、施設のものを勝手に使用する事は良くない。だが、確認の為に同じ質問を聞いただけだった。
「いや、それだけじゃないよ。君は自由奔放でチームプレーがとれない。注意散漫で一人で行動している事が多いし、一人で立って珈琲を飲んでいた事も報告されている。何度も同じ事を聞くし、察知して分かるような人間ではない。奇行が多いし、このままだと何れはトラブルに発展しかねない。何だかんだと目立つんだよ、君はぁ~❗」
「奇行って一体なんですか?!」
─言葉の暴力だ。
いや差別用語だ、そう思った。表現の自由とはよく言うが、今日を境に悪口という暗示に囚われ一生消えない心の傷として残るものだとも思った。仕事ができる、できないという以前に根本から人間性を否定された気分だった。解雇理由に、いちいち反論していたのでは切りが無いと思ったが、相手のペースに巻き込まれたくはなかった。人間は失敗しながら覚えていく生き物ではないだろうか?以前、スタッフ同士の雑談で、介護経験のある二十代女性スタッフは誤って利用者に睡眠薬を飲ませてしまったという失敗談をしていた事がある。また、三十代男性スタッフは誤って利用者の洗濯機に漂白剤を入れてしまった話をしていた。逆に、利用者から泥棒扱いされたスタッフもいたし、利用者から殴られて鼻血を出したというスタッフもいた。ヘルパー2級という資格は、通常は誰でも取得できる資格ではあるが、資格を取得していたとしても介護職に携わらない人が多い。なぜならヘルパーの仕事は"答えが有るようで無いのが難しい"という事らしい。そんなスタッフ達でも180日以上の実務経験があれば、更に上のヘルパー1級を受講できる権利を得ることが出来る。長く働いていけば、それだけステップアップできるチャンスが増えるという事だ。
それにしたって、公民館での研修でも『ほうれん草』と学び『報告・連絡・相談』の頭文字通り分からない事は、何度でも聞いて確認する様に言われた。ルールを暗黙の了解の様に曖昧にしておき、そこからハミ出た目立つ人間を排除する卑怯なやり方だと思った。だったらいっその事、壁にルールでも書いて貼っておけば良い。珈琲を飲むタイミングも全自動コーヒーマシンを使用した全スタッフの訓練の一環であり『立って飲むな』『座って飲むな』等の指示も受けていない。これではまるで私一人が勝手に珈琲を作り勝手に珈琲を飲んでいたという乱暴な言い方だ。
服装だって『ジーパン以外の軽装で』というルールしか定められておらず、私も含め、ほとんどのスタッフが普段着や私服で出社していた。誰もが、ジャージでの作業だけは拒んだからだ。利用者さん達が入居されてから服装の件については再度検討しよう、という話だけで未だにこの問題は解決されていなかった。けれど私は一週間前、毛玉付のセーターを捨て、内履きとジャージを買い揃えた。解雇するならその代金返せ、と心の中で叫んだ。
「自分の権利ばかり主張するなら、こっちにも考えがあるよ」
鬼頭が踏ん反り返った。
「え?!」
「顧問弁護士をつけるッ❗」
いやらしく笑った口元から金歯が光った。
「私も、今ここでは即答できかねますので、労働局と労働組合に相談をしてから改めてお電話差し上げます」
椅子から立ち上がると、鬼頭が慌てて怒鳴った。
「本来は、第三者に相談すべき事ではないんだぞォ❗この場だけの話なんだぞッ❗」
「失礼します」
鬼頭の困惑した表情を横目でチラッと見て、私は『あったかホーム』を後にした。
3
私は早速、岡目純からのアドヴァイスを受け仙台市の本社に電話する事にした。「解雇は受け入れられないから十二月三十一日迄の雇用を継続して欲しい」と要求し、更に「解雇理由を口頭ではなく文書で提示したものを送って欲しい」と要求した。それに対し、二日後の十一月五日、本社側から送られてきた《解雇予告通知書》には、この様な事が書かれていた。
《解雇予告通知》
当社は貴殿を契約社員として登用するのを前提に六ヶ月の試用期間を設けて、通常の範囲での新人教育・指導・助言を行いました。しかしながら、貴殿の勤務実績・業務の習熟度・業務遂行能力を慎重に検討した結果、下記の通り契約社員への登用を見送るとともに、平成二十一年十一月十日を以って解雇することに決定しました。何卒ご理解の程よろしくお願いします。尚、本通知は労働基準法規定の三十日前の解雇予告通知であることをご了承おきください。
記
一、契約社員に登用しない理由
出勤状況・勤務状況・業務遂行能力等を総合的に評価して、契約社員への登用が不適当と判断されたため
二、解雇予告手当て支給額
六千十二円×三十五日=二十一万四百二十円(うち、退職所得にかかる源泉所得税なし)
三、解雇予告手当て支給日
平成二十一年十一月十日
この文書を受け取ったその日のうちに、石割桜のある裁判所の前で岡目純と会い、二人で医大通りにある『みちのくユニオン』に出向いた。そこでの助言通り、その日のうちに「解雇理由をもっと具体的に提示したものと、解雇予告手当ての支給額にある内訳を教えて頂きたい」と要求した文書を書留で本社へ郵送した。
二日後の十一月七日、それに対する文書が書留で送られてくる。
本日、貴殿より簡易書留にてお問い合わせいただきましたので、ご回答いたします。
一、解雇理由を口頭ではなく、具体的に提示した証明書をいただきたい事
答…解雇予告通知書に記載してあります
二、解雇予告手当て支給額にある六千十二円×三十五日の内訳を教えていただきたい事
答…解雇日を平成二十一年十一月十日としたことから、労基法では、当社に三十日分以上の解雇予告手当ての支払い業務が発生することから三十五日分としただけです
労基法(労働基準法)には、こう書かれてある。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」と。
更に、2008年3月1日には労働契約法も施行されている。基本的には、たとえ試用期間中であっても、会社側の一方的な判断基準で従業員を解雇する事は許されない。
解雇するなら、面接の時点で不採用にするべきなのだ。
─世の中には、不当な解雇が横行している。
いや寧ろ、労働者に対する人権は犬や馬の扱いに等しく、職場でこれを是正するには「基本的人権の砦である労働組合への加入が不可欠である」と岡目純も言っていた。「そうすれば、如何に自分の人権が蹂躪されているかがよく分かる」と。
もし、労働契約法がまだ施行されたばかりで曖昧で明確な基準がないとするなら、その時代の人間がその時代に沿って考え、主張し、是正する事は決して悪い事ではない。そうでなければ進化はできない。人間はあくまで進化し続ける生き物なのだ。足並みを揃えながら…。
「クッキー‼」
「ラッキー‼」
「ウィスキー‼」
といった三分開き、五分開き、七分開きの笑い方作りも、作り笑いなら卑猥な笑顔に見えるし、人間の第一印象は6秒で決まり、6秒で判断されるといった方針も、正直心が無い気がした。
夜の帳が下りる前の師走の空に、木々の枝が、まるで影絵のように幻想的な雰囲気を醸し出していた。紺碧の空には、淡い紅色の雲が溶け込み、白紫色に染まった夕暮れが本格的な冬の到来を告げようとしている─。
その時、手に持っていた携帯電話の着信が光った。
「はい」
岡目純からだった。
「今、どこにいる?」
「あったかホームの建物の前です」
「どうだ、建物には何人くらい入っている様だ?」
窓もカーテンも閉められてはいるが、利用者の部屋の明かりは外からでもハッキリ分かる。
「3つです」
「3つ?」
「はい」
「やはり、昼食代だけが原因ではない様だな…」「そのようですね…」
私は、栗林に指摘されたその日に、研修先へ行き、お詫びをして忘れた昼食代は支払ってきた。「払えと言わなかった側にも管理責任はある」と『みちのくユニオン』の責任者は言っていた。「例の件はどうなった?」
「今、本社側に労働組合との団体交渉に応じるよう要求している段階です」
電話の向こう側で笑い声が聴こえた。
「そうかぁ、これで少しは『あったかホーム』も簡単に従業員のクビを切れない事を悟るだろう。これからの事もあるしな。それにしても、入居者がたった3人では、残された従業員が心配だな」
本来満室であれば、18室点灯していなければならない2階建ての『あったかホーム』の部屋の電気は、3つしか灯っていなかった。
残りの部屋は冷え冷えとして、人が住んでいる気配はない。─介護入居者の希望が思いのほか募らなかった─それが、解雇の本当の理由だと、私はこの時確信した。
オープンしたばかりの『あったかホーム』の建物は、周囲の景観と比べると、多少違和感がある様にも見える。しかし、ここ数十年による小世帯の高齢化、閉じ籠もり、相続による土地の売却、空地化など景観の変化に伴い、ここら辺一体も近代化の波に飲まれつつある。複雑に絡み合った大きな時代のうねりと共に…。
「ところで、解雇予告手当てはちゃんと入金されてあったか?」
「はい、お給料も。『みちのくユニオン』の方からは、解雇予告手当てすら貰えない労働者も多いのに、貰えただけでも良かったんだよ、と褒められましたが、私はこのまま引き下がるつもりは有りません。これからも闘い続けていくつもりです‼」
《完》
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
