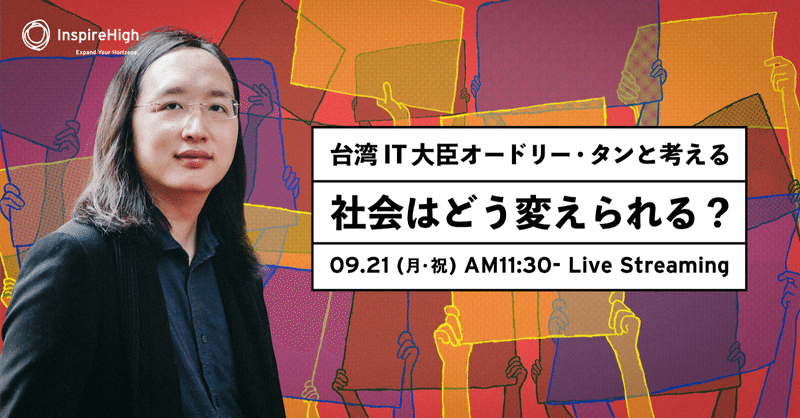
Unmuteでいこう!
以下は昨日書いた記事だ。
1. オードリー・タン氏とは
スタバで大変なことが起こっている。なんだかわからないけど涙が出そうだ。 私は今、スタバで、Inspire High (素晴らしい機会を与えてくれて感謝!) 主催の、台湾の若きデジタル大臣、オードリー・タン氏のウェビナーを聞いているのだ。
(2020年9月22日時点でアーカイブで視聴可能なので、ぜひ聴いてみてほしい)
タン氏はIQ180のいわゆるギフテッドと言われる天才で、8歳から独学でプログラミングを始めた。自分の好きな学びをするためには大学に行くなどして10年はかかると言われていたのに、中学生になったある日、オンラインサイトのarXivで、大学の研究者が最新の、時には発表前の最先端の学術的な研究を公開していることを知り、それから彼女は、研究者とメールでやり取りをするようになる。(メールなので、先方はタン氏がまだ中学生だとは気づかずに対応してくれたそうだ)
すると、彼女は中学で教わっていることが、すでに時代の先端からはまったくかけ離れた、極めて遅れた知識だと気づいてしまう。体は男性でも自分の認識としては女性であると、自身の性に対して違和感を感じていたこともあり、結局中学2年生で学校を中退した。
ただ、その中学の校長先生が素晴らしい方で、タン氏が学校に行く必要性を感じないと、大学の研究者たちとのやり取りのメールを見せると、「わかったわ。私が記録を変えておくから、あなたは学校に来ないで自分の学びを続けなさい」と、自分の職責を超えた対応でタン氏の希望を受け入れてくれた。もちろん政府に知れたら校長はクビである。
結局彼女は14歳で中学を中退、その後15歳で初めての起業、シリコンバレーに渡り天才プログラマーとして起業、アップル社の顧問も努めたが33歳でビジネス界から引退。台湾のひまわり学生運動の際にネット中継を担当して祖国の民主化に貢献し、35歳で、台湾史上最年少でデジタル大臣として入閣した。
最年少、中学中退、トランスジェンダーと、台湾史上初のことばかりの異例の大臣で、コロナ禍のマスク管理アプリなどの数々の功績を上げているが、彼女の特に素晴らしいところは、政治的信条として「Radical Transparency(徹底的な透明性)」を徹底しているところだ。
彼女は毎週水曜日、ソーシャルイノベーションラボと呼ぶバーチャルな会議室で働き、誰でもがそこを訪れ、彼女と交流することが出来る。そして週に2回は台湾各地をまわり、それもまたイノベーションラボで共有している。
大臣室には誰でも取材に行くことが出来るが、唯一の縛りは、「取材をすべて公表すること」だという。殆どのことを秘密裏に行い、取材は統制が取られ、おまけに根回し後のシャンシャン採決が当たり前の日本の政治家とは大違いである。
2. Inspire Highのウェビナー
Inspire Highは、毎回第一線で活躍するガイドを招いた無料のウェビナーを開催している。(一部アーカイブ視聴は有料)基本的には13歳〜19歳までの若者が参加出来るものだが、大人は、You Tubeで視聴だけ出来る。私の娘はまだ13歳まで数ヶ月足らず参加出来なかったが、13歳になったらぜひ参加させたいと思う。
ウェビナーの前半は、タン氏(Inspire Highではこうしたスピーカーを「ガイド」と呼ぶ)の略歴やコロナ禍で台湾がどのようにしてマスク管理アプリを作り、効果的に使ったか? などの話。後半は、参加の子供たちが、「自分を取り巻く環境の問題点に対して、どのように世界を変えていったら良いか?」という視点でアウトプットと質問をし、タン氏(ガイド)がフィードバックするという内容だった。
ただ聞くだけのウェビナーではなく、こうして若者にアウトプットの場を設け、ガイドと直接対話することにより、より深い経験として落とし込める構成になっている。
3. 参加者からの質問とタン氏からのフィードバック
質問の一部を紹介しよう。
Q1,日本は世界第二位の万引大国だが、商品タグをつけるなどして防げないか?
A1, 万引をするのは、経済的な理由と、ただの楽しみやクールだからという理由とがある。経済的な理由ならばフードバンクなどのセーフティネットが必要だが、楽しみから万引する場合は、ホワイトハッカーのように万引防止システムを作れるようにして、社会的問題を解決するほうがクールだと思えると良いだろう。
Q2,学校には階段しかないので、車椅子の人が登校出来るようにエレベーターをつけたい
A2,イノベーションラボでは、エレベーターを設置する際、動きが遅い人、動けない人にも対応出来るように音声認識で動かせるようにしている。学校にはこうしたテクノロジーを使う場面がたくさんある。
現在台湾のスタートアップが5Gで取り組んでいるのは、ファイバーもWi-Fiも必要なしで、誰でもヘッドセットでバーチャルな教室に参加出来るシステムだ。それによりお年寄りでも体が不自由な人でも、世界中誰でもが授業に参加出来るのだ。
ブロードバンドへのアクセスは人権だと考えているので、5Gを展開する時は、中央から一番遠い田舎から実践する。大学生が地方のパートナーとコラボレーションして、ブロードバンドが生活を変えていくという可能性を共感して欲しいと考えている。
4. タン氏から若者へのメッセージ
このように、タン氏はそれぞれの質問に対して、テクノロジーの実例なども示しながらとてもフレンドリーに答えていくのだが、途中、タン氏がミュートのまま話しだして、進行役の男性が「あ、ミュート外してください」と注意を促す、という場面があった。
最後の総括ではそれにひっかけて、若者たちへのメッセージとしていた。
「社会を改革するのに一番大切なことは、フィードバックです。皆さんもアンミュートにしてフィードバックしてください。人間誰でも、自分が知らず知らずのうちにミュートにしてしまって声を出さずにいることがある。社会に対して声を上げるのは、大学を出て18歳以上でないといけないということはないのです」
ただし、こうも付け加えていた。
「声を上げるのは誰かが話し終わってからにしましょう。誰かを攻撃するのではなく対話をして、誰一人取り残さない社会を作るのです」
これは、彼女が活躍したひまわり学生運動で、学生が国会を占拠したものの、短期間のうちに無血で民主化に導いたという成功体験からだけの言葉ではないだろう。2016年に彼女がデジタル大臣に就任したことで保守派から反発を買ったこと、2018年に一度政党が負け、そして2020年1月の総統選で新たに返り咲いたという経験から、民衆を味方に出来ない政治は存続できないと、骨身にしみてわかっているからこその言葉だろう。
だからこそ、コロナ禍で誰一人として取り残さないようデジタルテクノロジーを駆使してマスクアプリを作ったり、徹底的に民衆と対話したり、テクノロジーから誰一人取り残されないような政策をとったり、透明性を保つ努力をしているのだ。
5. タン氏の在り方と日本の子供をとりまく環境
私が今日特に感動したのは、タン氏が誰とでも対話をする姿勢である。正直、彼女にとって日本の学生と対話する時間や労力をさくことは、直接政党の得になることではないだろう。
13歳から19歳という他国の若者たちと、こうしてフラットに対話する機会を持っている政治家が、はたして日本にいるのだろうか?次回の選挙の得になる票田の方にしか向いていない政治家が圧倒的多数なのではないだろうか。
それから、タン氏の中学の校長先生のように、大人の都合でなく、その子が本当に伸びるためのサポートや教育を与えることが出来る先生がどれだけいるのだろうか?
子供が不登校で好きな事をやりたいといった時に、子供を否定せず可能性を潰さす、全面的に信じてやらせてやれる親はどれだけいるのだろうか?
大人がこうした対応をするのは困難ではある。しかし子供たちが育つ過程で、こうした大人たちに出会えることが、彼らの未来を変えていく。そしてこの大人の姿勢こそが国力の差を生むのだと思う。
2019年11月の日本財団の調査では、日本の18歳の「自分で国や社会を変えられると思う」という質問への答えは9カ国中ダントツ最下位の18.3%だった。この質問だけでなく、希望をはかる質問に対して、日本の18歳は7つともすべて最下位のネガティヴな返答をしている。
これは、子供の意見を尊重して聞くことなくインプットのみを優先させる教育、子供の自由を校則で押さえつけ服従する子が良い子だとする学校の在り方、そして、私達大人が国や政治に対して希望を抱かず、それに対して声もあげずにただ文句を言う姿勢などから、子供たちが未来に期待も希望も抱けない現状を作っているからなのではないだろうか。
6. タン氏との対話を通して得られたマインドセット
今日こうしてタン氏と対話した若者たちの心のなかには、確実に一つの種が植えられたのだ。
「自分も大人に意見を言っていいんだ。大人は自分の意見に耳を傾けてくれる。自分の意見が尊重される世の中がある。世界は自分たちで変えていける」というマインドセットが、参加した若者を、ひいては日本を変えていくのだと思う。
そうした場を作る大人がいること、そしてその現場に立ち会えた感動で、今これを書いているが、コロナのおかげでこうしたオンラインプログラムが格段に増えて、私達は無料で秀逸な情報に触れることが出来るようになった。
「リアルで動けなくてもオンラインででも良いから、世界とつながって世界を見よう! そのためには最低限の英語力とデジタルスキルを身につけよう! 自分が動けば、世界は変わる!」
と、若者だけでなく自分をも鼓舞する言葉でウェビナーの感想を締めくくりたい。
サポート頂いた金額やお気持ちを、インプットのために遣わせていただきます。そして、それをより昇華したエネルギーに変換してアウトプットし、循環させたいと考えています。どうぞよろしくおねがいします😊
