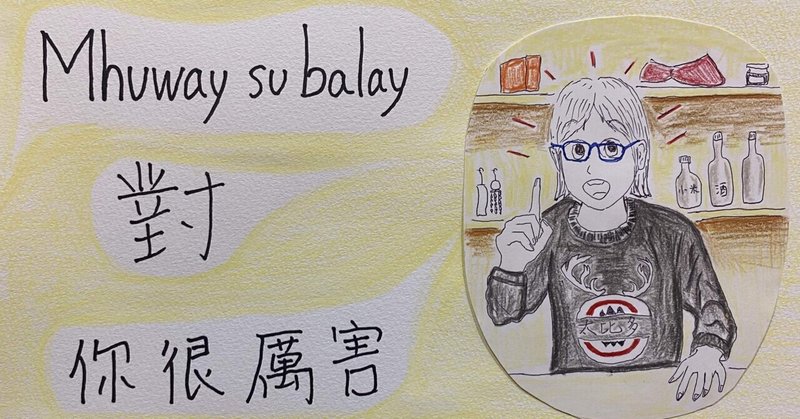
太魯閣で出会った人々(3) 族語を習う旅のはじまり
反復訓練
緑水のカフェから天祥に向かってまたスクーターを走らす。この間、何度も何度も続けざまにモホワイッスバーライ(ありがとう)の発声練習をした。このようにカタカナで記すと簡単なように見えるが、モとマの中間音、イッスかワイッスか、バーライかバーレイかどちらにも聞こえる。組み合わせ多数のため喋り続けていないとこんがらがってくる。ある瞬間に他ごとを考えて練習が途切れるととたんにわからなくなってしまう。スクーターをとめて耳にスマホをあててまた聞き直す。こんなことを何度か繰り返しながら天祥に向かった。しかし、この反復練習がこの後すぐ役に立った。
先入観とその克服
天祥ではまずセブンイレブンに入った。ここでも若い男性の店員さんが歌っていた。客と会話する時以外はずうっと歌っていた。ハミングなんてものではない、大きな声で歌っている。それがまた実にうまい。響き渡るような声で聞き惚れてしまう。それで私の頭の中に一つの概念が浮かぶ。「太魯閣族は歌が好きで歌がうまい民族だ」と。たった2例で判断すべきではないというのが常識ある人の態度だろう。しかし、この時点で出会った太魯閣族は5人。そのうち2人が「話す時以外は歌っている」「客が目の前にいても歌っている」「しかも聞き惚れるぐらい上手い」「男女各1名のバランス」。偶然ではないと感じてしまった。しかし、その後台湾で暮らす中で「歌とか踊りとかスポーツとか、原住民をステレオタイプ的に見るコメント等にストレスを感じている人がいる」らしいことを、ネット上のコメントを通じて知った。それで私も大いに反省し今ではこの先入観を捨てた。振り返ってみると、その後に出会った太魯閣族の人達は誰も歌ってはいなかった。この日の出来事は何という偶然だったのだろうか。
初めて使った族語
天祥では太比多という名の土産屋さんにも寄った。店先で温かい食べ物を出してくれる。ここには前日の夕方に一度来ていた。11月中旬の夕方に太魯閣渓谷をスクーターで走ると寒い。台南で暮らしている感覚のままTシャツ+ウインドブレーカーという薄着で来てしまった。観光バスの後ろを排気ガスをあびながら、その温かみを有り難いと思いながら走って来た。もちろん体に悪いことはわかっている。寒さで多少震えながら店先で臭豆腐などを注文していた。「寒いの?中で食べていったらいいよ」と若い女性店員さんが勧めてくれた。一人旅をしているとそんな一言が心にしみる。ああ、この店にはもう一度来たいなあと思った。次の日、つまり帰る日なのだが朝もう一度スクーターで走って来た。お土産品の小米酒などを抱えて会計してもらう。お金を払ってお釣りをもらう時、ドキドキしながら言ってみた。
「モホワイッスバーライ」
ちょっとだけ間が空いた。店員さんの顔がぱっと明るくなり「そうだよ、あんたすごいね!」と返ってきた。生涯で初めて使った族語。ここに来る約30分前、あの緑水のカフェで教えてもらったばかりの言葉だった。
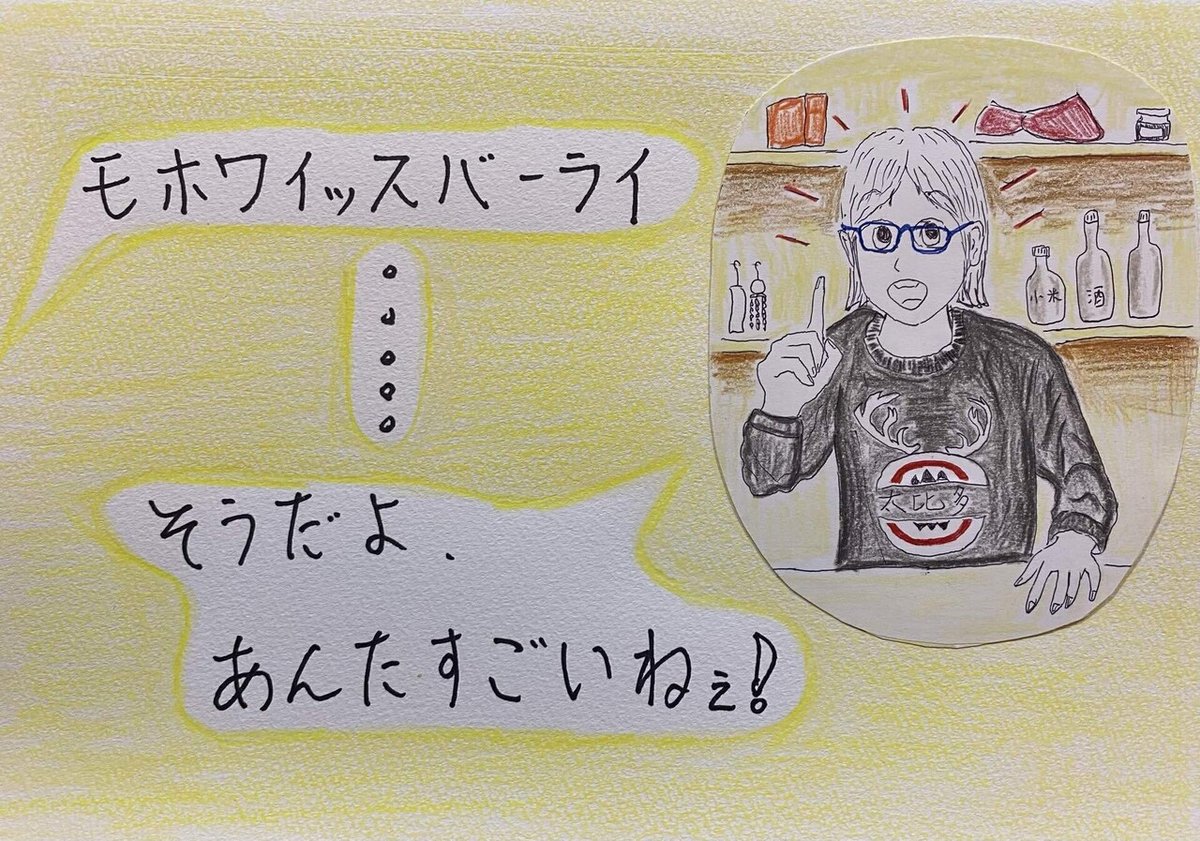

ああ太魯閣は楽しい
新たな土地で人に出会うと方言または族語を教えてもらう。それが週末の旅の密かな楽しみとなっていった。そのきっかけを作ってくれた彼女たちにもう一度会いたいと思った。もう少し族語を学習し単語を10個覚えてから太魯閣に行こうと決めた。そうこうしているうち年が明けて2020年コロナ禍が始まった。感染が落ち着いた初夏に再び太魯閣を訪問したとき、緑水のカフェはすでに休止状態だった。テラスのテーブルと椅子が片付けられ、ガラーンとして誰もいなかった。

天祥のセブンイレブンも太比多も人が入れ替わっていた。思い出を共有できる人は誰もいなかった。私に初めて族語を教えてくれた人達も、私の族語を初めて聞いてくれた人も、その後一度も会えていない。緑水のカフェが再開するのを期待しながら太魯閣にはかれこれ7回か8回行った。正確な回数は忘れた。しかし、あの店員さん達はどこに行ってしまったのだろうか。
彼女たちを探し繰り返し訪問するうちに、他の多く太魯閣族の人たちと出会うことになった。そして、その楽しさが原住民族の母語・族語を一つ二つ覚えて使って見ると言う自分なりの交流のスタイルに変化して行った。

台湾には他にもまだ多くの原住民族がいて、各民族とも咲き誇るが如く自民族の文化活動を展開している。活力が有りとても素晴らしいし、結束している有り様は羨ましくもある。しかし、それは繰り返された歴史、外来政権との力関係の中で失われていった民族の伝統を取り戻すための切実な活動でも有ると思われる。日本の統治も主たる原因の一つだ。だから、一つ二つの族語を教えてもらうときにも使うときにも感謝と敬意の気持ちを込めた態度で接して行く。(完. 太魯閣編)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
