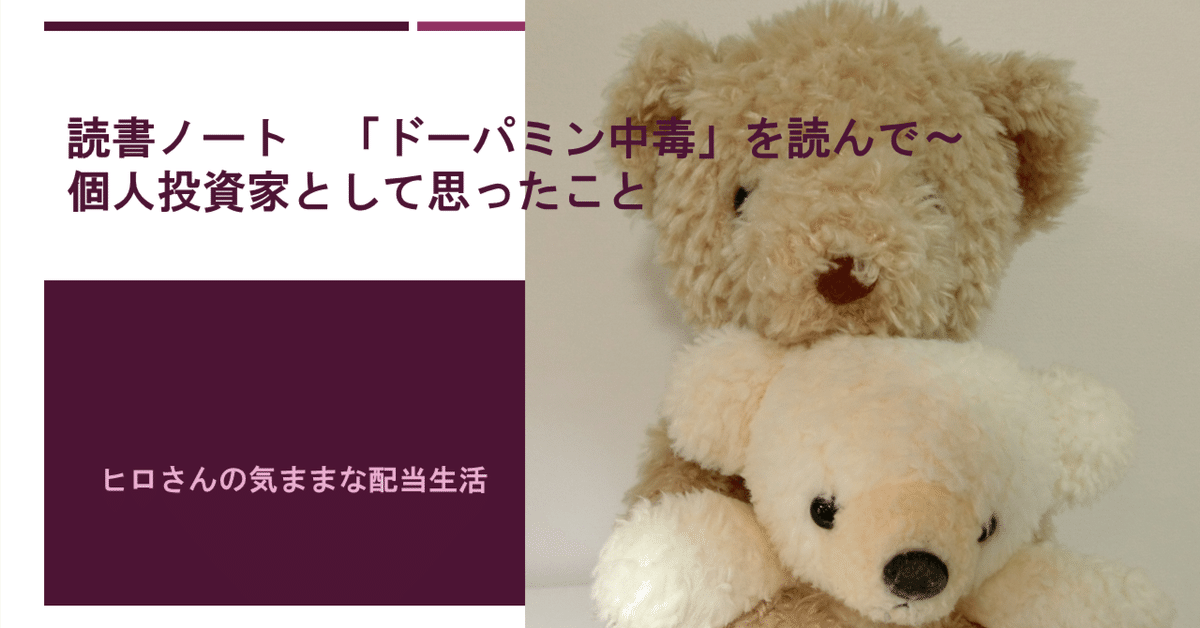
読書ノート:アンナ・レンブケ著「ドーパミン中毒」新潮社~個人投資家の目線から
スタンフォード大学教授で精神科医アンナ・レンブケによる「ドーパミン中毒」は、恩蔵絢子氏の翻訳により2022年10月に新潮新書として出版されています。アマゾンでは2023年7月23日時点でもう210件のレビュー(評価平均4.3)があり、本書が日本でも大きな衝撃を持って迎えられたことがわかります。著者レンブケさんは現職の医学部教授・精神科医ですので、薬物などについて専門的な内容も含んでいますが、知識がなくても本書の意義は十分理解できます。私も、非常に学ぶことが多く、思いがけず本書のすばらしさに感動しました。個人投資家としても、科学的な根拠に基づいて人間の脳活動や心の状態を理解することは重要だと思います。ただ日々の経済状況を追い求めのではなく、自分が投資によって何を目指し、どのような精神状態で投資活動をしているのかを客観的に理解することで、自己制御と広範な学びを目指していけるのではないか、と思い、本書をレビューしてみます。
「ドーパミン中毒」の概要と学び
「ドーパミン中毒」は3部に分かれており、第1部快楽の追求、第2部セルフ・バインディング、第3部苦痛の追求のように構成されています。
第1部快楽の追求では、著者レンブケさんの診療を受けに来た依存症のクライアント(患者?)の例を紹介し、そもそもドーパミンが脳内でどのように働き、なぜ依存症を引き起こすのか、とくにドーパミンの過剰かつ習慣的な分泌がどうしてよくないのか、を詳しく説明しています。クライアントの例は極端な依存症の症状を示していますが、近年の常にネットにつながった状況(ドーパミン経済)で依存症がとくに先進国で容易に発生する状況と理由が理解できます。ドーパミンの過剰を促す環境により全般性不安障害がひろがり、世界における新規うつ症が1990年から2017年の間に倍増したこと、疾患の広がりが豊かな国に多く、精神だけでなく痛みなどの身体症状にまでおよぶことが指摘されています。ドーパミンが薬物、アルコール、精神活動からどのように分泌されるか、というメカニズムは多様で興味深いですが、私はこの点についてコメントする知識はありません。ドーパミンは生理的なものだけでなく、ギャンブルや読書(著者自身が官能小説の依存症だったそうです)からも出ます。ドーパミンは動物にとって必須の神経伝達物質で、これがなければ、目の前においしい食べ物があっても、食べようとせず餓死してしまうラットの例が紹介されています。しかし、ドーパミンが長期的、高頻度で過剰に出続けるようになるとその原因について依存症になるだけでなく、適度なドーパミンの分泌を生む日常の小さな喜びや満足を感じなくなってしまうのだそうです。偶然にテレビでパチンコの依存症男性のインタビューを見ていると、もうパチンコで頭がいっぱいになり、仕事をさぼり、家族にうそをつき、最後は生活の破綻寸前までいったと話していました。この方はパチンコによる強烈なドーパミンにより、仕事や家庭、自然などの美しいものに喜びを感じられなくなっていたのでしょう。私たちは依存症とまで言えなくても、ついゲーム、SNSやネット動画に夢中になりがちですが、日ごろから十分に気をつけたいですね。
第2部のセルフ・バインディングは具体的な依存症の治療~過剰なドーパミンのコントロール~を扱っています。快楽には耐性があり、より強い刺激を漸進的に求めるようになること、しかし、ドーパミンを出す行為をやめる、あるいは制限することにより、困難ではあっても元の穏やかな喜びに満足できる状態に戻れると主張しています。これは過剰な快楽から元へ戻ろうとするホメオスタシス(恒常性)の働きによるもので、シーソーのたとえでわかりやすく説明されます。アルコールやドラッグなど生理的なものはもちろん回復が困難ですがですが、作者の読書依存でさえドーパミン過剰からホメオスタシスの力を取り戻すためには、電子書籍リーダーを捨てる、などの荒療治が必要だったようです。もちろん、食べ物のようにいくら過食症を治したいと思っても完全にやめることができないものもありますが、程度を制限するというのは依存症にとって大変な苦労が必要です。
第3部は「苦痛の追求」と題がついていますが、ここの題のつけ方は理解に苦しみます。実際には、第7章のみが、苦痛(冷水浴、ランニング、エクストリームスポーツ、ワーカホリックなど)からも依存症になりうる、という事例を紹介していますが、むしろ圧倒的に面白く、勉強になるのは第8章「徹底的な正直さ」と第9章「「恥」が人とのつながりを生む」ではないでしょうか。私たちは徹底的な正直さを育むことで「より自発的で自由な存在になっていく」(p. 192)、「偽りの自己を見せようとしなくなると、私たちは自分自身や他者に対して開かれる」(p.196)と説き、そのあとで正直な大人とうそをつく大人により子供がマシュマロを食べるのを待てる時間を計測する実験を紹介しています。第3部の後半は、自己の体験も正直に話しながら、嘘を排除し、恥を率直に受け入れることがいかにドーパミン過剰に頼らず、長期的な報酬を望むようになり、社会性や深い人間関係を育てるかということが、説得力を持って語られていて圧巻です。著者は薬物治療だけで依存症や重い精神疾患が治癒できることはなく、マインドフルネスや(脳を含めて)自分自身を偽らないこと、家族や社会とつながっていくことでホメオスタシスが回復する(精神科医として投薬治療はしていますが)と述べています。
感想とお礼の言葉
本書では、最後に「結論—シーソーの教訓」としてドーパミンの過剰をいかにコントロールする方法が、簡潔にまとめてありますが、関心を持たれた方は、このすばらしい本全部を通読していただきたいと思います。これは、カバットジンらのマインドフルネスの書籍と同様に、わくわくする気分にしてくれるものではありません。正直、マインドフルネス系の本を読むと、少し元気がなくなりますよね。しかし、日ごろ私たちが依存症気味になっているアルコール、食品、ネットゲーム、ギャンブルやSNSなどから一歩引いて、おだやかな日常の小さな喜びへと関心を向けることの大切さを気づかせてくれます。ドーパミン過剰社会が攻撃的で自己中心的な自我を育てるとすれば、本書はその反対に科学的なマインドフルネスに導いてくれるものです。私が関心を持つ投資でも同じことかな、と思います。ただ短期的な報酬を目指し、ゼロサムゲームやデイトレードで過剰な快楽を求めず、投資を通じて経済を学び、世界全体が良くなるよう希望をもってのんびり勉強を続けていきたいと思いました。
最後に本書は恩蔵絢子氏によりとてもていねいに、わかりやすく翻訳されています。すばらしい「訳者あとがき」も含めて本書を日本で紹介してくださったことに対し恩蔵氏にも感謝いたします。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
