
『原子力の哲学』と絶望に向けて #読了
今回は、おもしろかった新書をとりあげてみる。
ずばり、『原子力の哲学』(戸谷洋志.2020:集英社新書)である。
映画『オッペンハイマー』の公開から1カ月弱が経ち、やや話題性が過ぎたころに書き起こしています。

注目に至ったのは、筆者である戸谷先生である。
著書として
『Jポップで考える哲学:自分を問い直すための15曲』(講談社文庫:2016)
『親ガチャの哲学』(新潮新書:2023)
『恋愛の哲学』(晶文社:2024)
など、小難しい言葉や概念から説き進める哲学書ではなく、すごく身近なキーワード、トピックから「あ~、そう考えられるのか」と、率直に”考えること自体を深める”
そんな読書体験をさせていただけた先生である。

とてもおもしろい良本なので、そちらもぜひ一読
さて、では『原子力の哲学』はどんな本だったか。
ひとことで言えば、”原子力(核・核兵器)”というトンデモナイ技術に対して、人はどういう風に考えることが「正しいのか」。
それを、7人の哲学者の思想とともに、彼らがどのように「正しさ」を論じたかをつづる。
という内容である。
「核」とは、じつに強大な力を持った兵器である。
そういう認識を持っている。
戦争の悲劇や、科学技術の暴走、世界の終焉シナリオなどでは、もほや代名詞として違和感がない。
そんなものに対して、我々は、すぐに「悪いものだ」と決めつけてはいないだろうか?
何かを「悪」と言い切るには、それ相応の理由がいる。
なぜ「悪」なのだろうか?
そういう視点を掘り下げることでようやく、人類を滅ぼすことも容易いこの「原子力=核」について、正しい批判ができるのではないだろうか。
その思考の手助けとして、本書に紹介された哲学者と、彼らの思想をすこし記していこうと思う。
7人がそれぞれ、じつに魅力的な視点で論じている点がおもしろかったし、この考えとこの考えは真逆な立場だったり、同じことに注目しているけど着地点が違う、など。それぞれを見比べることで、また新たな発見の面白さがあった。
1.原子力の思考 マルティン・ハイデガー
原子力(この場合は「核兵器」)の登場~発展が、第二次世界大戦中の1940年前後であるため、やはりこの巨人も論じてました。
ドイツの実存現象学の親分、ハイデガーである。

彼は、兵器としての「原子爆弾」ではなく、「原子力(=技術)」によって象徴される「発展していこうとする世界の在り方」に注目した。
人間の思考が社会にどう影響するのか、その過程で犯すある種の”過ち”の解決策として、人間の思考の在り方を考える。
まず第一に、人間の歴史にとっては初めてである「原子力時代」そのものについて思考すべきであり、それをせずに反核・反原子力の理屈は成り立たない。人間においては、「原子力」がいったい何を可能とし、何が実現でき、さらに何を犠牲にするのか、そうした諸々は言葉通りに未知なのだ。まずはそのことを自覚するべきなのだ。
また、その思考において、「たった一つの解決策」を求めることについやすことをハイデガーは拒否する。未知のものについて、「〇〇という危険性があるが、~~で解決できる!」という答えを求めるのは当前なのだろう。しかし、よくよく考えればそれは未知への理解ではなく、一つの解釈が生まれているに過ぎない。魔法は自然の精霊たちの力によるもので、自然との調和によって魔法を使える!というのに似ている。
そうした二者択一の論理を、思考の停止ととなえ、来るべき「原子力時代」による危機とハイデガーは捉えた。
『放下』(1959),『技術への問い』(1962)
2.世界平和と原理力 カール・ヤスパース
原子力の哲学、2人目。こちらも、ドイツから、精神科医でありつつ、その独自な実存主義哲学をつくりあげた、わたしの大好きな偉人でもあります。カール・ヤスパースである。

強大な兵器である原子爆弾に対する解決策は、「世界平和」であるとヤスパースはいう。
これからもわかるとおり、ヤスパースはハイデガーよりも明確に、原子力(正確には「核兵器」)の危険性に注視している。核による3つの破局を述べている点にもそれは表れている。
同じように、技術による核の危険性を、技術では解決できないとする。だからこそヤスパースは、全核の廃棄によってなりたつ、という立場をとった。つまり、世の中の核を全部ポイッとしちゃえばいいというのだ。だがこれは現実的にうまくいかないのは容易にわかる。なぜなら、核という強力な武力を管理するのは、あくまで臆病で貧弱で、武力武装の安心を求め続ける「われわれ人間」であるからだ。
そこでヤスパースは、すべての人間が理性的に思考し、共同性を作り上げる「民主主義の平和」をもとめる。政治や政府の問題ではなく、すべての地球人がこの問題に関与することをもとめる。
一方で、この立場を「全体主義」による世界の支配とは区分する。全体主義は人類の自由を死滅させ、そうした国家が核武装するのなら、各人も武装が必要である、という論理になる。世界平和のためには、民主主義の平和が成り立たねばならない、という論も述べている彼は、強制される平和ではなく人類すべてが望んでいる思いの実現=平和の実現を正しいと考えている。
ただヤスパースの態度は、他の思想家と比べて楽観的で、「原子力は、人間の思想によって、管理可能で有益なものである」と聞こえる。この立場は、とくに原子爆弾ではなく、原理力による社会の変遷=原子力時代の到来に危機を感じていたハイデガーと対立する。
・『現代の精神的課題』(1951),『現代の政治意識-原爆と人間の将来』(1958),『真理・自由・平和』(1958)
3.想像力の拡張 ギュンター・アンダース
わたしはこの方を存じ上げませんでした。すみません…。
しかし、その思想はとても面白かった。前者二人があくまで哲学者として論を展開しているのに対し、彼は「作家」という目線で、原子力の哲学を論じた。そのキーワードもまた「想像力」である点が面白い。
ドイツの作家、ジャーナリスト、エッセイスト、詩人であるギュンター・アンダース。

「核兵器」の危険性を、強力な兵器という点においたのはヤスパースと同様だ。しかし、アンダースは「目的を超えた道具」ということなった視点の言い方で表現した。つまり、核兵器はなにかの目的の達成のための道具にとどまらない、その対象(さらには使用者も)を破壊してしまうような道具だと考えた。
そうすると、核兵器を今まで通り、ただの道具としての兵器だけで論じることはできない。原子力の脅威の本質を、人間の想像力を超えた、破局を想像できないもの、という想像力の有限性にアンダースはみたわけだ。
ゆえに、その解決策は「想像力の拡張」である。ハイデガーも言っているが、核兵器は人間にとって初めての事態だ。そうすると、核兵器についての自由な思考や言葉というものも、じつはわれわれからは奪われているといえるのだ。
そのために、核兵器問題の解決に文学性の有用性を訴えていることも、アンダースの思想の特徴だ。フィクションという、現実を超えた想像力の拡張によって、語りえない未知の脅威に相対する際の「正しさ」が共有され、人間の道徳の拡張も可能とするという考えだ。この点は、民主主義的な共同性の樹立=「交わり」を訴えたヤスパースと対照的で、個人的な感覚に対してのアプローチだと述べられていた。
・『時代おくれの人間』(1956),『核の脅威-原子力時代についての徹底的考察』(1981)
4.世界の砂漠化 ハンナ・アーレント
ハイデガーが近代ドイツ哲学にあたえた影響は量り知れない。そんな巨人の影響をうけた人物も数多い。その中でも、名が知られているのが、彼の生徒でもあり、恋仲でもあった、女性哲学者。
前述のアンダースの最初の結婚相手、ハンナ・アーレントである。

ヤスパースの教え子でもあるアーレントは、政治という哲学テーマを常に持っていた。それは、全体主義というナチス・ドイツにかかわる問題意識にもみられる。
そこで彼女の哲学の軸でもある、政治についての考えをみてみる。
いわく、人間の生活には、私的領域(私的欲求によって必要だから成り立つ、家族の領域)と公的領域の二つがある。
政治は、この公的領域において行われる。そこは自分の私的利害を超え、市民(他者・社会)の利害のために生活が成り立つため、自由で平等な空間である。
その「世界」は人工物によって成り立ち、自然とは区別されつつも自然によって条件づけられる(「世界」=人工<自然)。対して原子力は、本来地球には存在しない力、宇宙に匹敵する力である。それは「世界」を根底から覆す破壊力を持ち、すなわちただちに人工によって成り立つ政治の条件を破壊してしまう。
それはつまり、人間が勇気をもって行動をおこす自由な場が失われることである。そうした社会では、私的利害を超えた他者への公的行動はなくなり、自らの命を保護する私的な行動だけが唯一の関心になってしまう。これを、アーレントは「世界の“砂漠化”」と呼ぶ。
アーレントの思想は、生命への脅威よりも、自由への脅威に注目している。
この世界の砂漠化(=世界の破壊)という状況を乗り越えるために、新たな活動を起こすことを挙げる。市民が立場を超えて議論し、原子力の在り方について同意できる答えを探求すること。すなわち、原子力時代に適した公的領域の必要を求める。
これはヤスパースと対照的で、核兵器によって我々の生命がどれほど失われるか、という議論に注目している限りは、人間の自由は着々と“砂漠化”が進行するだろうと考える。
ただし、人々の議論=対話によって、核兵器への対抗を図る態度は、ヤスパースのそれと通底しているともいえる。・『人間の条件』(1958),『政治の約束』(2007),『過去と未来の間-政治思想への8試論』(1977)
5.未来世代への責任 ハンス・ヨナス
ハイデガーの影響を受けたもう一人として挙げられていたのがこの人物。
ドイツの実存主義哲学者であり、「恐怖」というキーワードで原子力技術の危険を論じた、ハンス・ヨナスだ。

ヨナスの倫理学は、未来世代への責任というテーマを持つ。
科学技術という道具は、その時点では“善い”とされているものも、未来的には“悪い”結末に繋がってしまう。そんな単なる因果では測れない側面があるという。
それを踏まえてヨナスが注目したのは、核兵器よりも原子力発電の方だ。なぜなら、核兵器はすでにその破局的な危険性が認知されているのに対して、原子力発電は一見すると、人間への福祉へ貢献してる“善い”存在に見え、その危険性が十分に検討・自覚されているといえないからだ。
この場合の原子力発電の危険性は、単なる放射性廃棄物の問題だけではなく、それによってもたらされる社会的―経済的-生態的なシステムの崩壊まで広げて考えている。
そうした未来に対する、最悪の未来への想像、破局への恐怖によって、この問題を思慮しようというのが「恐怖に基づく発見術」というヨナスの提案だ。
また、兵器ではなく、科学技術の恩恵である原子力発電のほうを問題視する点で、アンダースを批判している。それはハイデガーも同様で、彼が原子力時代において“不気味”に恐れたのは、そうした原子力発電によって安心しきった人々の、危険性に対する無関心、思考の停止であるという点で似ている。
しかし、この問題の解決としてヨナスがあげるのは恐怖の想像であり、その媒体としてSF文学の有用性を指摘した点については、アンダースの態度にも似ている。
ただ、彼の思想の問題点として、彼の倫理思想の根底は想像であるということ。「恐怖の発見術」は最悪の未来の想像に支えられる、そのためにはリアリティが求められる。にもかかわらず、この未来への想像=予言は、その未来が到達することを阻止するために用いられる。ここに大きな矛盾を抱えている。
・『責任という原理-科学技術文明のための倫理学の試み』(1979),
6.記憶の破壊 ジャック・デリダ
さて、これまでドイツ哲学が中心であった原子力の哲学。
しかし、キュリー夫人に始まり、世界有数の原子力国家であるフランスの哲学も触れなくてはいけない。
ということで、近代フランス哲学の巨匠。差異の哲学、脱構築などの概念で知られる、ジャック・デリダが取り上げられる。

デリダの思想は、核の脅威を運命として論じている点(ハイデガー)、科学的合理性に基づく予測の有限性の指摘(アンダース)、また核の脅威を記憶の問題として論じる(アーレント)など、ほかの思想家と重なる点が多い。しかし、発明・出来事・彷徨宿命といった諸概念を駆使するところに、彼の独創性があり、だからこそ難しい……
簡潔に示しておくと、デリダの思想の根底は「予測不可能なものに、どう理屈立てをするか」だと思えた。
彼の諸概念である「発明」によれば、発明とは“既存の何かを組み合わせて新たに何かを作り出すこと”ではない。“既存に基づくことなく、まったく新しいことを生み出すこと”である。
引用すれば、発明=それまで不可能であると思われていたものの実現であり、原子力も核も戦争も、いわば発明といえる。
発明はそれまでの文脈から予測できない、予測不可能性をもっている。いわば運命的に「到来」すると考えられる。
しかしそれを哲学が扱えるために、「到来」にはそれを受け入れるための仕組みや社会があって成り立つとした。そこにみえるテクスト(言葉)の繋がりによって、予測不可能性を突破しようとしている。のではないかな……?
彼への批判の一つに、核戦争には現実指向対象が存在しないという彼の主張だ。だが実際に広島・長崎への原爆投下は行われた。これにデリダは、「これは古典的な通常戦争の終わりであって、核戦争の始まりではない」と指摘するにとどめているが、これは現実指向対象としての広島・長崎を意図的に忌避していると見える。また彼の核批評の評論の執筆者に、日本人が含まれていなかったことも指摘されている。
この指摘は、核批評について語る者が立場としては常に、使用者である。核批評はその立場を超えられない=使用者と被害者の対話が実現しないことを示していると考察されていた。
・『プシュケー』(1987),
7.不可能な破局 ジャン=ピエール・デュピュイ
さて原子力の哲学、最後の刺客は、原子力という技術を現実に利用するにあたって、まず考えねばならない視点。「原発事故」という災害の危険性というテーマから論じたフランスの思想家。
ジャン=ピエール・デュピュイである。
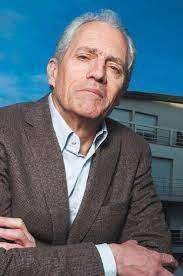
デュピュイは、デリダと同じように核の破局の予測不可能性を指摘したうえで、これを乗り越えるための大胆な形而上学的思弁を展開する。
原発事故などの破局に対して、「なぜ防げなかったのか」という批判は付き物。それによって、のちの危機管理能力は向上する。
がしかし、破局は予測できるという前提に立っている時点で、そうした危機管理能力は破局に対して、脆弱であるといえる。
なぜならば、予測できるという破局の想定は、「起こってみるまでは分からない」わけで、われわれはその想定を、じつは「実際に起こると信用しきれていない」のだ、とズバリ指摘した。
この問題に対して彼が提案するのは、過去→未来の構図ではなく、未来→過去という逆転の構図だ。
科学的な実証性に基づく未来予測ではなく、文学的な想像力によって先の運命を表象し、未来を固定することの必要性だ。つまり、予測し得る範囲に原子力の範囲を固定することで、破局の予測不可能性を停止させる、という逆転の発想に近いものである。
ただ注意しなければならないのは、それは破局の未来の忘却ではなく、起こりえたかもしれない破局のシナリオは存在し続けるとすることを求めることだ。
・『チェルノブイリ―現代の「悪」のカタストロフィ』(2006),『ありえないことが現実になるとき―賢明な破局論に向けて』(2002),『ツナミの小形而上学』(2005)
まとめ
『原子力の哲学』を読んでいるときは、ある一つのテーマを様々な視点で掘り下げてみる討論会を覗き見ている気分だった。
感想として、自分ではどうにもできないような強大な力に相対する、もしくはその可能性が身近になったときに、自分はどう考えていくことができるのか、が鍛えられた気がする。
もしそのピンチな状態を、”絶望”と喩えるなら、この読書によって得られたのは、現代科学技術への批判だけにとどまるものではなく、もっともっと広い意味、”絶望への向き合い方”も問いかけれるものだったと、わたしは思う。
〆
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
