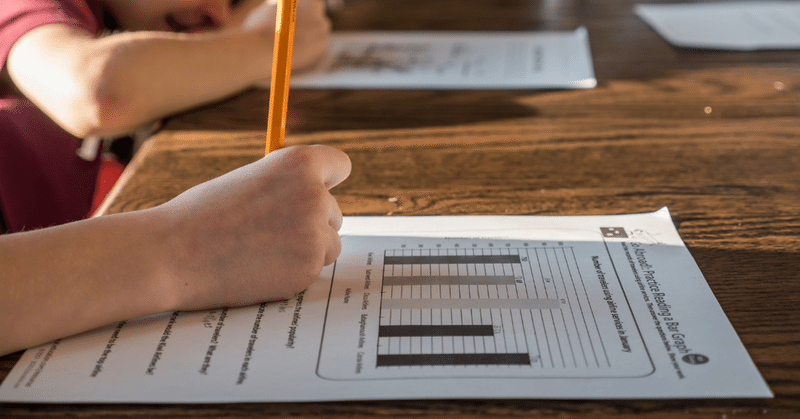
公認心理師試験に合格した理学療法士が国家試験対策を伝える②〜向き合い方編
公認心理師試験に合格した理学療法士(執筆・投稿時点では登録していないので公認心理師ではありません)が、その経験から考える国家試験対策をお伝えするnoteの第2段です。
第1段はこちらから。このnoteを書くに至った詳しい経緯もこちらの序文に書いてあるので、そちらもご覧ください。
第2段となる今回のnoteでは、国家試験の問題への向かい方、それを前提とした試験対策・勉強への向かい方について書いていきます。
対象となる方、注意点
この記事では、今後国家試験を受ける予定もしくは可能性のある方を対象にしています。
国家試験と言っても色々なものがあるので、あくまでも『理学療法士』と『公認心理師』の試験を受けた経験から書かれたものであることをご承知ください。
例えば、『医師』の試験なんかは私の経験してきた試験とは難易度が大きく異なるでしょうし、『電気通信の工事担任者』なんかは医療関係の試験とは異なる特色を持つ可能性があります。
ご自身が受験を予定している試験と照らし合わせ、どの程度参考にするかを検討いただけると幸いです。
もう少し詳細に対象となる方を絞っていくと、次のようになるかと思います。
・国家試験を受験する予定・可能性がある
・国家試験は難しいというイメージ
・初めての国家試験、どのように向き合い勉強を進めれば良いかわからない
・これまでの勉強は暗記中心
・本(活字)を読むのが苦手
・国試の過去問見てみたけれど、難しいと感じる
・国家試験の範囲が広大すぎて心が折れそう
・未知の知識を求められる問題が出たときの対処法が全く分からない
このどれかに該当する方には、参考になる考え方が提供できるのではないかと考えています。
また、〜①で紹介した方法を拡張する意味でも使えることを書いているので、シンプルに①の続きとして読んでいただいても良いかと思います。
ただ、注意点もあります。
このnoteの①でも書きましたが、楽に受かる方法というのをお伝えすることはできません。
時間も労力もかけて国家試験対策に臨む気持ち・やる気があるけれども、その方法がハッキリせず、「これで良いのか?」とモヤモヤした気持ちで勉強を続けているような方には、参考にしていただけると思います。
この記事の構成
タイトルに「〜②」とある通り、連載形式になっています。
おおまかな内容の分類として、
①は、国家試験対策としての勉強の方法を(これがメイン)
②は、試験問題やその対策への向き合い方について(これは国試に限らないかも)
③は、勉強する時間や勉強習慣の作り方について(社会人向け)
といった内容を書いています。
国家試験対策の勉強の仕方だけを読んでみたい方は①だけ、勉強に関してもう少し深いところまで読みたい方は①と②、今回の私のように仕事をしながら国家試験に挑戦しようという方で時間をどのようにして作れば良いかわからないという方は③も読んでいただければ良いように構成しました。
ちなみに、①〜③を全部読みたいという物好きな方は、個別で購入されるよりもマガジンで購入いただく方がお得になるように設定しています。
国家試験で出題される問題の解き方
note①の序文で長々と書いているので、②では早々に本題を進めていきたいと思います。
まず、こちらの問題をご覧ください。
問137 20歳の女性A、大学2年生。1か月前から男性Bと交際している。AはBが誰か別の人物と一緒に食事をしたり、自分が知らないうちに出かけた話を聞いたりすると不安が高まり、Bの行動に疑念を抱くという。AはBの行動を常に確認しないと安心できず、Bがソーシャル・ネットワーキング・サービス<SNS>に投稿する内容を常に確認し、Bの携帯端末の画面に表示される通知を頻繁にのぞき込んでしまう。そのことでAとBは言い争いをし、関係が悪化する状態が繰り返されている。
Aの状態として、最も適切なものを1つ選べ。
①感情の誤帰属
②恋愛の色彩理論におけるアガペ型
③愛の三角理論におけるコミットメント
④とらわれ型のアタッチメント・スタイル
⑤同一性地位<アイデンティティ・ステータス>理論における早期完了
これは第5回公認心理師試験で実際に出題された問題です。
Twitter上では、『愛の三角理論』というパワーワードが話題になった問題です。
愛の三角理論もそうだけど、恋愛の色彩理論におけるアガペ型って何なんだよw#公認心理師試験
— g-moll (@pianosonata4) July 17, 2022
公認心理師試験
— もりもり (@moritako1121) July 17, 2022
『愛の三角形』というパワーワードから目が離せなかった。
今年の公認心理師流行語大賞は、
— カナミール@第5回公認心理師試験合格! (@rH1ZsBUn8NZ5gwL) July 17, 2022
「愛の三角形」
「俳人」
で決定でいいんじゃないでしょうか
もちろん私も『愛の三角理論』なんて初めて目にした単語でした。
むしろ、その他の選択肢もほぼ初めて目にするものでした。
にも関わらず、④を選択して正解できていました。
運が良かったと言えばそれまでですが、鉛筆を転がすなどして完全にランダムに選択した訳ではなく、可能な限り論理的に考えて導き出した答えでした。
この問題に直面した私が何をどのように考えて正答を導き出したか。その過程を説明していきたいと思います。
読んでくださってありがとうございます。 いただいたサポートは今後の勉強、書籍の購入に充てさせていただくとともに、私のやる気に変換させていただきます。

