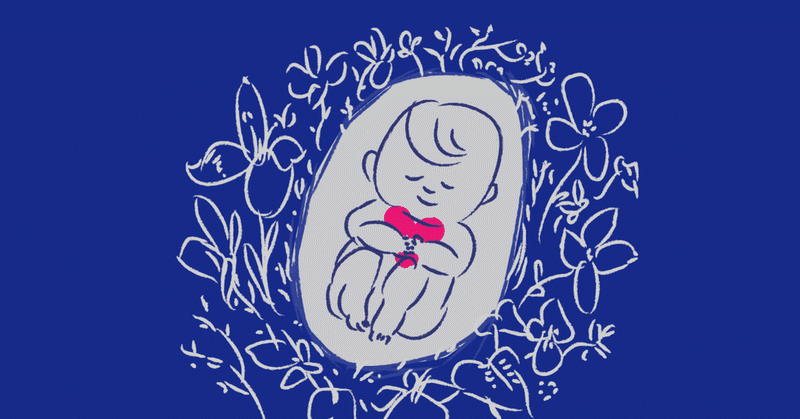
子どものする事は全て遊び1〜胎児期から新生児期の発達をサポートする〜
子どもは遊ぶことが仕事と言われます。
確かに子どもは常に遊んでおり、食事や睡眠といった生命活動に必要な活動以外の活動は全て『遊び』と言っても間違いではありません。
遊びの内容は発達段階によって変化していき、その時その時で適した遊びを行います。
そして、この遊びが発達・成長に深く関わっているのです。
実は胎児期から始まる『遊び』について、どのような段階を追って変化していくのかを考えてみたいと思います。
今回は胎児期と新生児期の『遊び』について書いていきます。
この記事を読むと、
✅️胎児期から始まり変化していく子どもの『遊び』が理解できる
✅️子どもの成長に合わせた『遊び』を知り、サポートできるようになる
✅️各発達段階における子どもにとっての課題を知り、『遊び』を通してサポートできる
胎児もすでに遊んでいる(胎児期)
母親のお腹の中にいる胎児期においても、すでに『遊び』を始めていると言うことができます。
お腹の中の胎児は、どのような遊びをしているのでしょうか。
例えば、母親のお腹の皮膚越しに感じられる外界の光や音、母親の心音や血液の流れなど、様々な感覚を感じています。
手足を動かすことで固有感覚を感じ、自分の体や子宮の壁に触れることで触覚を感じます。
母親の動きによって重力の変化(前庭感覚)を感じます。
このように、胎児期から多くの感覚を経験し、こういった活動の全てを『遊び』と捉えることができるのです。
この時期に親ができる働きかけは何かあるのでしょうか。
例えば、お腹越しに話しかけてあげること、胎児がお腹を蹴ったときには軽くお腹を叩いて反応してあげることなどでしょうか。
胎児期は直接面と向かうことはできませんが、お腹越しに『遊び』をサポートすること、一緒に遊んであげることはできるのです。
産まれてすぐも遊んでいる(新生児期)
胎児ではお腹のなかで無重力状態でしたが、産まれると重力の影響を受けることとなります。
そうなると、それまでできていた手足の動きが一時的にできなくなり、反射に支配された運動に限定されてしまいます。
一方、お腹の中ではできなかった呼吸が始まり、泣くこともできるようになります。
産まれてすぐの時期は自分で動くことができないため、不快感を全て泣くことで示します。
自分が泣くことで周囲の人々が不快感の原因を取り除いてくれる、という経験を繰り返すことで、泣くことに意味を見出します。
同時に、母親を中心とした周囲の人々との信頼関係の構築にも繋がります。
さらに、嗅覚で母親の母乳の匂いを嗅ぎ分けることも、母親との関係構築に繋がるようです。
この時期は手足を使って何かをするというような『遊び』よりは、様々な感覚を感じ取りながら、母親を中心とした周囲の人々との信頼関係を構築する、ということが課題になります。
この時期に大切なのは、子ども自身が何か(主に泣くこと)をした結果、周囲の人々が反応してくれる、不快感を取り除き、問題を解決してくれる、という経験を積み重ねることだと考えられます。
この時期に周囲の大人は、「なんで泣いてるんだろう?」「何をしても泣き止まない…」という悩みに頭を抱えることになると思います。
しかし、不快感を取り除いて泣き止ませることだけが大切なのではなく、泣くことに対して何か反応してもらえるという経験をすることに意味があると考えると、すぐに泣き止ませなくても大丈夫と思えるのではないでしょうか。
極端な言い方かもしれませんが、泣いているのも一つの遊びと捉えると、母親・父親のストレスが少し軽くなるのではないでしょうか。
まとめ
今回は胎児期と新生児期における『遊び』について書いてみました。
まだ自分の意志で手足を自由に動かせない時期であっても、様々な感覚を感じ取りながら、外界や周囲の大人との関わりを試行錯誤しています。
この時期に自分が何かをすると反応が返ってくるという経験を繰り返し積み重ねることによって、周囲の大人との信頼関係を構築すると同時に、その後の「やってみたい」に繋がっていくと考えられます。
大人からするとほとんど寝ているだけに見えても、胎児・新生児の頭の中はとても活発に活動しています。
そんなことを知っていると、一見何をしているのかわからない、ただ泣いているだけの子どもに対して、より積極的に関わることができるようになるのではないでしょうか。
次回(下記の記事)では、もう少し動けるようになった時期の『遊び』について考えていきたいと思います。
もっと深く学びたい方へ
『子どもの感覚運動機能の発達と支援-発達の科学と理論を支援に活かす』
子どもの発達について学ぶとき、本書を主に参考にしています。
一般的な成長過程はもちろん、疾患別の内容も盛り込まれています。
読んでくださってありがとうございます。 いただいたサポートは今後の勉強、書籍の購入に充てさせていただくとともに、私のやる気に変換させていただきます。
