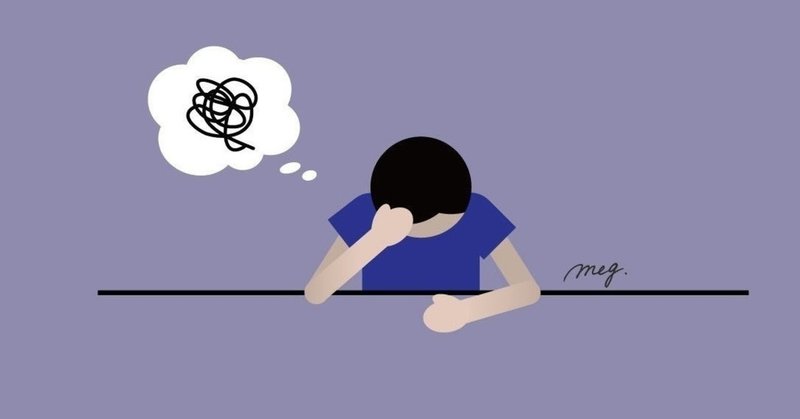
いつか我が子に伝えたい哲学
哲学とは何でしょうか。
そもそもはギリシャ語の「philosophy」という語を西周(にしあまね)という人が「哲学」と翻訳したとされます。
「phylosophy」は「知(sophy)を愛する(philo)」の意味だそうです。
広辞苑では、次のように説明されています。
①物事を根本原理から統一的に把握・理解しようとする学問。(中略)認識論・倫理学・存在論・美学などを部門として含む。
②俗に、経験などから築き上げた人生観・世界観。また、全体を貫く基本的な考え方・思想
②の意味に重点を置いて簡単な言葉で言い換えると、『「人生とは何か?」「世界とは何か?」というようなことを考える学問』といったところかと思います。
私自身、これまで生きてきて、子どもの頃から色々な疑問を持つことが多くありました。
「何のために勉強するのか?」
「何のために生きているのか?」
こんなことは誰もが一度は考えたことがあるかもしれません。
今回は、いつか我が子も持つであろうこんな疑問、いつか質問されそうな疑問に、今の時点で何と答えるかを考えてみたいと思います。
このnoteを読むと、
✅️勉強することの意味や目的を考えるきっかけになる
✅️人生とは何かを考えるきっかけになる
✅️子どもからの難しい質問に答えられるようになる(かも)
人は何のために勉強するのか?
子どもに「なんで勉強しなきゃならないの?」「なんのために勉強するの?」と聞かれたとき、あなたは答えられますか?
このような疑問は、小学生くらいの頃に多くの人が考えることではないでしょうか。
勉強が嫌で、もっと遊びたいのに、大人はみんな口を揃えて「勉強しなさい」と言う。
算数での四則計算ならまだしも、社会科で丸暗記を求められる内容なんか生活で役立つ気がしない。
そうなってくると、「何のために勉強しなきゃならないんだ!」と怒りにも似た感情が湧き上がってきます。
一般的な社会人が一日に勉強する時間は6分と言われています。
1日は1440分あるにもかかわらず、そのうち6分しか勉強しないらしいです。
もしかすると、「なんのために勉強するのか?」に答えを得られないまま大人になった結果、社会人になってまで勉強したくないと考える方が多いのかもしれませんね。
では、人は何のために勉強をするのでしょう?
もしも子どもにこの疑問を投げかけられたら、人生を楽しむためと答えたいと思います。
人生とは有限であり、世界の全てを完璧に理解して死ぬことはできないでしょう。
それでも、知らない世界を一部でも知ることができるのは楽しいことです。
だからみんな旅行をして、自分の知らない土地を歩いたり見たりするわけですよね。
知らない土地を歩くとき、そこを何も知らない状態で見て回るという楽しみ方もあるかもしれませんが、そこがどういう土地なのか、どのような歴史を経て現在そのような形になっているのか、ということを知っていた方が、より深い意味で楽しめるのではないでしょうか。
旅行に限らず、新しいことを学ぶということは、それ自体が自分の世界を拡げていくことです。
理科で習う内容などは、誰かが過去に確かめたことです。
その全てをこれから自分が実験したり調査して確かめることは難しく、人生が何回あっても足りないでしょう。
そうであるなら、誰かが既に確かめてくれたことを本で知ることができるのは非常にありがたいことですよね。
私自身がそうでしたが、子どもの頃は何のために勉強するのかわからず、勉強することは嫌いな方でした。
それが今では、朝5時前に起きて、作業や勉強(読書)を欠かさない生活を送っています。
なぜか?勉強することが楽しいからです。
そして、今勉強できているのは、子どもの頃に勉強すること自体を練習してきたからだと考えています。
つまり、子どもの頃に、義務教育で勉強することというのは、その教科の知識を得ること以上に、『勉強すること』を勉強(練習)するという意味合いが強いのではないかと考えています。
人は何のために生きるのか?
何か大きな壁にぶつかると、こんなことを考えるかもしれません。
壁にぶつからなくても、純粋に疑問に思うことかもしれません。
そのときの子どもの状況によっても答え方は様々かもしれませんが、基本的には人は楽しむために生きていると答えたいと考えています。
遊ぶために生きていると言い換えても良いかもしれません。
この世界で生じる事象というのは、その多くが相対的なものです。
絶対的なものなど、ほとんどないと思います。
絶対的に楽しい出来事などは存在せず、楽しくない出来事があるから楽しい出来事があるのです。
そういう意味では、楽しくない出来事、辛いことがあったとしても、それは楽しい出来事があるために必要なことなはずです。
人生には嫌なこと・辛いことが続く時期もありますが、その中でも(相対的に)楽しい出来事はあるはずです。
それに多く気付けるというのが、豊かな人生だと考えます。
毎日の仕事が嫌だと思う社会人も多いのかもしれませんが、それは自分が選んだ仕事のはずです。
その仕事が苦痛で仕方ないのであれば、辞めてしまえば良いと思います。
嫌だけど何とか続けられるというレベルなのであれば、それは家に帰ってからの生活や週末の休みの日を相対的に楽しくするためのスパイスになっているのかもしれません。
仕事自体が楽しいと思える仕事に出会えた私は、その中で相対的に嫌なことがあっても、仕事を楽しんで続けられています。
人生が終わるときに「楽しかった」と思えるような選択をしていく、そのために嫌なこと・辛いことを経験しながら生きていくのではないでしょうか。
まとめ
子どもからぶつけられそうな疑問について考えてみました。
このような考えをそのまま子どもに伝えても、きっとすぐには理解できないでしょう。
私自身からのメッセージとしてはこのようなことを伝える意図を持ちつつ、子どもとは対話することが何よりも大切だと考えます。
大人の意見を押し付けるのではなく、現時点で子ども自身が何をどう考えているのかを聞く。
いきなり全てを伝えられなくても、子どもが悩んでいる内容を評価して、次に進むためのちょっとした助言をする。
そんな風に関わってあげたいと考えています。
読んでくださってありがとうございます。 いただいたサポートは今後の勉強、書籍の購入に充てさせていただくとともに、私のやる気に変換させていただきます。
