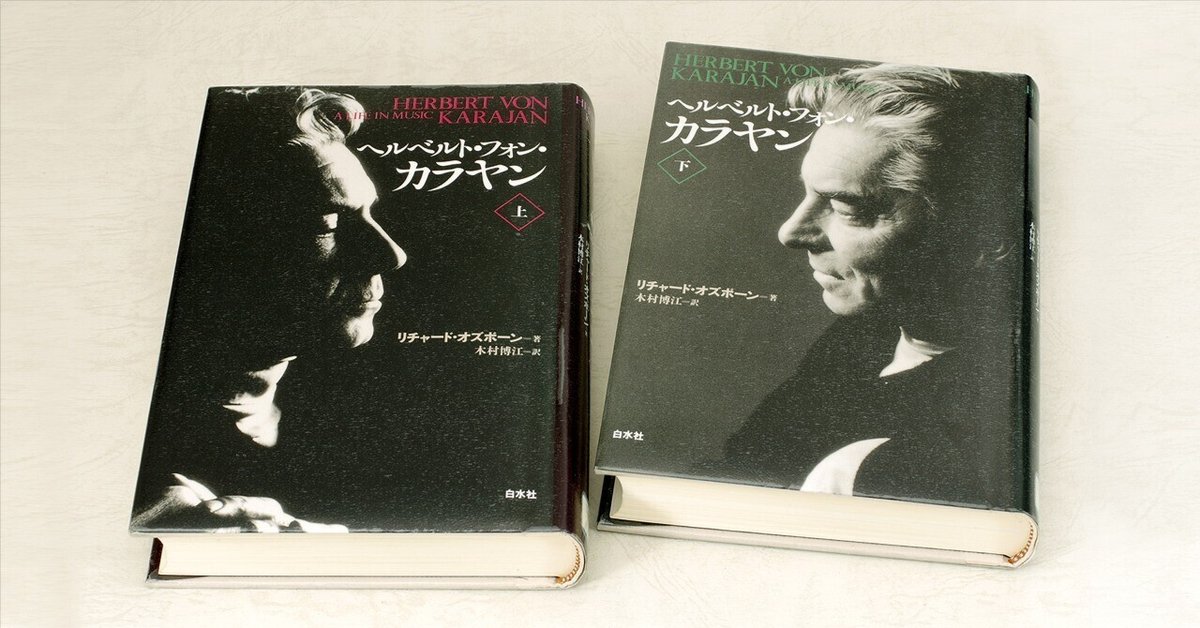
「ヘルベルト・フォン・カラヤン」
リチャード・オズボーン著 白水社刊 2001年7月
カラヤンの生涯についての本は数多とあるなかで、比較的中立で、おそらくもっとも詳しいと思われる書籍。
上下2巻、本文のみで900ページほどあります。
著者は英国の批評家で、カラヤンとの対談を綴った書籍「カラヤンの遺言」を死の直後に出版し、基本的には中立的立場ながら、批判的な立場に立つ人には批判的な姿勢が見え隠れする、というスタンス。原著の出版は1998年。
大著なので幼少期の記述が非常に充実していることのほかに、戦時中の活動、フルトヴェングラーとの関係、ウォルター・レッグとの関係(=EMIとフィルハーモニア管弦楽団)、ザビーネ・マイヤー事件からベルリンフィル辞任に至る経緯などが非常に詳しいのが特徴で、要するにこれは批判的な立場に立つ人に対する暗黙の反証ともいうべきところに重点が置かれているとも捉えることができるわけです。
戦後まもなく1946年の連合国による非ナチス委員会においてカラヤンのナチス疑惑については公式に否定され、お咎め無しとされたのですが、1980年代に入ってカラヤンのナチス時代の疑惑を追及する動きが盛んになり、本人もこれに対してまともに反論するといったことを避けたことが疑惑のイメージをさらに拡大することとなったようです。
本書では戦時中のカラヤンについて詳述するとともに、付録のほうでナチス入党の登録記録の検証と先述の非ナチス委員会においてカラヤンが提出した宣誓証書についての記述を収録しています。
これによると、カラヤンは1933年の3月または4月にザルツブルクで入党手続きを行い、4月8日付で党籍番号1607525を得たが、これは事務処理が無効あるいは中断され、ドイツに移住後ウルムで再登録を行い、5月1日付で党籍番号3430914として正式にナチスの党員となった。
カラヤンの弁によれば道義的責任については議論の余地があるとしても指揮者という公職に就くにはナチスに入党することは政治的立場以上に処世術として必要なことだったとのこと。
戦後カラヤンは1935年にアーヘンの地区長の要請によりナチスに入党した、との誤った情報を周囲に語っていたようであり、1933年に2度も入党手続きを行ったという点について明らかにしたくなかった様子が窺われます。
1933年という年は1月30日にヒトラーが内閣を組織し、3月23日には全権委任法が制定され、ナチスの独裁が制度的に確立した重要な転機に当たります。
1933年と1935年では入党への積極性という点で天と地ほど大きな開きがある。
ナチス関与の積極性を小さく見せたいという心理が働いたのは間違いないところだと思われます。
一方でカラヤンの2番目の奥さんは1/4ユダヤ人であり、彼女はカラヤンと結婚するにあたりゲッベルスに直談判までしていますが、R・シュトラウスと同様に著名人の伴侶に1/4ユダヤ人が居る件はナチスとしても黙認するとの姿勢であり、カラヤンについてもこれに倣ったということでしょう。
非ナチス委員会にカラヤンが提出した宣誓証書にはカラヤンが積極的なナチスの活動家でなかった証拠として
・ヒトラーの不興を買って(フルトヴェングラーなどのような)ドイツの代表的指揮者とは見做されていなかった
・奥さんが1/4ユダヤ人であった
ことを挙げていますが、(今から見ると微妙に我田引水と思われるフシはあるものの)概ねこの主張には根拠があると認められたことで、戦後に活動停止が解除されたわけです。
フルトヴェングラーやR・シュトラウス、ギーゼキングや他の音楽家同様、ドイツに残って活動を継続していた音楽家はナチスとの関係は常にグレーゾーンの中にあると思われますが、カラヤンについても道義的には脛に傷持つ身ではあるものの、その程度は上記の音楽家と比べて突出しているわけではなく、過度に問題視するほどではなかったとみてよいのではないかと思われます。
カラヤンの場合、あまりにも戦後の名声が巨大化しすぎたこともあり、ベルリンフィルとの不仲が取り沙汰されるようになった80年代になってからのバッシングが大きくなった面もあったと推察します。
その点で興味深いのは、そのバッシングともいえる現象と関連する事象として、クロード・ルルーシュ監督の『愛と哀しみのボレロ』の中で、カラヤンがモデルとなっている指揮者がアメリカ公演の最中にユダヤ人からの妨害で客席を買い占められ、批評家2人しか観客が居なかったというエピソードが登場する。
これは元になるエピソードがあったと聞いたことがありますが、それはどこまでが本当の出来事なのか?
本書の記述によると、ボルティモアで買い占めと不買運動があったことは記述がありましたが、観客が2人ということはなかったようです。
これはやはり映画的フィクションということになるかと思います。
フルトヴェングラーの死去後、急遽代役としてベルリンフィルの戦後初のアメリカ公演に参加したカラヤンですが、招聘元のコロンビア・アーティスツはカラヤンでなければ公演そのものをキャンセルすると通告、カラヤンも同行する条件として音楽監督としての地位は終身であることを保証すべし、との条件のもとに行われました。
ボルティモアのほかにユダヤ人による妨害はあったものの、戦時中よりの純正ドイツ系音楽家によるクラシック公演は長らく行われていなかったこともあり、基本的には大成功であったとのこと。
本書の中で音楽家としてのカラヤンの姿というものが垣間見られる部分としてたびたび出て来るのがトレーナーとしての優秀さについての発言です。
各時代に出会った音楽家が異口同音に語ることとして、指揮者としてのカラヤンの指示が如何に適切でその感性が優れていたか、という発言が非常に多い。
指揮者は演奏家として音楽を形作るのは当然のことですが、リハーサルを繰り返して楽譜に書かれた作曲家の指示を音楽に変換していく、という作業は単なる音楽のプロデューサーとしての立場以前に、個々の演奏家に対してあるべき演奏の具体的な方法を指示していく、という極めて機械的で、実務的な作業の繰り返しが必要となります。
アマチュアでも合奏を経験した人ならこの点は非常に理解しやすい部分かと思いますが、プロともなると数回のリハーサルでその指揮者の目指す音楽をオーケストラ全員に伝える必要があり、ツボを押さえたトレーナーとしてのテクニックがないと到底そのような制限された時間内に自身の音楽を形づくることなどできるはずがありません。
この点に関してカラヤンは若い頃から突出した才能に秀でていたおかげで早くから成功を収めることができたようです。
そのためには音楽に対する深い考察と適切なダイナミクスやバランスを実現できるビジョンが必要で、カラヤンに接した多くの音楽家がこの点を高く評価していたようです。
カラヤンの場合、こうした確かなテクニックに加えてその上昇志向というべきか出世欲が相まって史上稀に見る成功を収めたということが言えるのではないかと思います。
一方で大著であるのですが個々の音楽に対する具体的姿勢といったものは本人が書いていないうらみもあって意外に記述が少なく、その点では内容的にやや淡泊な印象を受けます。
とはいえ、特定の作曲家や曲に対する意外な思い入れや録音に対する姿勢など、想像していたところとは異なる印象を持つところも少なくありません。
特に少ない記述ながら録音する気がありながら実現しなかった曲などは興味深いところです。
その中にはショスタコーヴィチの交響曲第8番、シベリウスの交響曲第3番、オルフの「カルミナ・ブラーナ」などがあり、逆にブラームスのピアノ協奏曲の第1番などは実演などにおいてもなぜか忌避していたとのこと。
シベリウスの交響曲第3番や「カルミナ・ブラーナ」などはあと数年長生きしていれば録音された可能性があったようなので、実現していたならと思うと残念でなりません。
また本書の最後の方で最も記述が詳しいのがベルリンフィルのザビーネ・マイヤーの入団事件から辞任に至るまでの経緯で、200ページ近い分量を割いて詳述しています。これは著者が没後まもなくから執筆をはじめていることと、晩年カラヤンと親交があったことから自然と記述に力が入ったものと思われます。
このような組織と個人の関係性で問題が起きることの常として個人の力の及ぶ範囲とその内容を双方がどのように妥協点を見出すか、という点に尽きるわけで、結局のところ両者はその調整に失敗した、という当然の成り行きであったことが見てとれます。
30年にも及ぶ関係でこれまで主席指揮者であるカラヤンが団員の採用に関して明文化された決定権を持たなかった、という実務的なことが問題なのではなくて(それまでもゴールウェイやザイフェルトなど問題児は居た)そのことが明文化されていなければ問題を解決できないところまで両者にミゾが出来てしまったことが問題だったといえるでしょう。
時間の経過とともに修復不能な状態に陥っていくさまは基本的に淡々とした記述に終始している本書の中にあって非常に読み応えがありました。
辞任後から死に至るまでの記述は非常に簡単で、大賀典雄がカラヤン邸を訪れているときに亡くなった経緯が書かれた後、埋葬されるところで本文は終了となります。
不世出の指揮者としてその死後について各界への影響は言うまでもなく、簡単でも記述があった方がしめくくりとしては良かったかと思いますが、死去後まもなく執筆された書籍という点から致し方ないところだと思います。
既に死後35年、後の世代の指揮者も次々と鬼籍に入っており、あれほどの巨匠といえども歳月の流れは容赦なく訪れて、巨匠指揮者の時代は過去のものとなり、音楽メディアも実体のあるディスクからデータ、そして配信へと移り変わって音楽を巡る環境も大きく変化を遂げる中にあって、一人の指揮者が業界の帝王などと呼ばれる高みに到達する時代は今後二度とないであろうことを思うと、時代の寵児としてカラヤンの生きた時代とその生涯の軌跡を追うことは単なるノスタルジーの域を超えて大変興味深いのでした。
