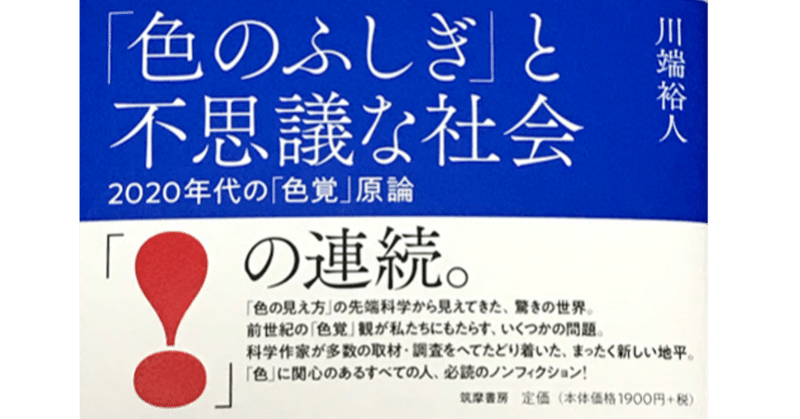
『「色のふしぎ」と不思議な社会』レビュー

『「色のふしぎ」と不思議な社会』
2020年代の「色覚」原論
川端裕人(著)
◇
『夏のロケット』、『川の名前』、『銀河のワールドカップ』、『雲の王』に『青い海の宇宙港』……などなど、ワタシ的に超ツボな、ぐっとくる小説の数々を書かれている川端裕人さんなのですが、最近はノンフィクションも多く出されています。ナショナルジオグラフィックで『「研究室」に行ってみた。』なんて連載もこなされていて、さすがの一言。
◇
さて、本書は、そんな川端裕人さんがここ数年取り組まれていたという「色覚」のお話です。
「色覚」、つまり、色の感覚、ですよね。
困ったことに、これ、感覚ですから人によって強く感じられたり弱く感じられたりも当然します。(感受性、ですね)
全体的に強弱がある場合もあれば、色のスペクトルによって青色に敏感な人がいたり、赤色が感じやすいって人もいるわけです。
この色についての感受性センサーの得手不得手が、昔は「色盲・色弱」なんて言われていました。最近はようやく「色覚特性」なんて言われるようになってきたようですが、ただ、このセンサーの性質は親から子へ遺伝してしまうので、「先天的色覚異常者」なんて呼ばれて差別にもつながっていたとのこと。
実際に、一般的でない色の感じ方をする(色覚特性を持つ)と、特定の職業につけなかったり信号を見誤って危険だという論で、昭和の時代には公然と進学や就職の差別が行われ、結婚や子供を作ることへの制限の理由にもなっていたそうです。
異常者と言われても、本人に自覚もなければ本人のせいでももちろんなく、親の遺伝が子に報い、かつ治療法がないわけです。
学校で健康診断の時に友人たちの前で検査され、結果を知って驚き、異常者と烙印を押され、親を怨む……なんてことが、実際に起きていたとか……。(実際、著者の川端さんも小学校で色弱と判定されて愕然とした過去があるそう)
よほど人と色覚が食い違っていれば自覚することもあるでしょうし、こうした検査で洗い出されるのは往々にして未自覚の軽い色弱で、ほとんどのばあい生活には何ら支障はなかったそうです。
さすがに差別的だと、2004年に学校での色覚検査は廃止されたので、こうした昭和な時代はもうはるか過去のこと。と思っていましたら、なんと、2016年に事実上「復活」してしまったのだそうです。
復活の後押しをした眼科医らは「将来(一部の就職とかにひびくので)苦労するぐらいなら先に教えた方が良い」と言います。が、そのために何ら生活に支障のない子どもたちに「異常者」の烙印を押してしまうことがはたして正しいことなのかどうか、またあの差別的な時代に後戻りしてしまうのではないか、と、著者は警鐘をならすのです。
◇
ここで、川端さんらしいなーと思うのは、「色覚」、色の感覚についての理解を、感覚という人間の内側の方向(そして人間どうしの社会的な面)だけでなく、物理的・科学的な方面、「色」についての理解からも進めていくところです。
冒頭でかのアイザック・ニュートンの言葉「光そのものには色はついていない」(『光学』(Opticks)1704年)を引用し、そもそも色って何なのさ? というところを掘り下げます。
私自身、「色」ってやつは、目が感知できる電磁場のある領域(可視光線)のスペクトル中の、特定部分の波の強さ。という具合に、工学的な理解をしていました。
それが、同じ周波数の光線を見ても観測する人によって感じる色が微妙にずれてるみたい。ふしぎ! と常々思っていたので、このあたりの科学的な解説は大変興味深く、おもしろく読めました。
読んでみてあらためて、やっぱりふしぎ! です!
(色相が円環をなしているところなんて、あいかわらずやっぱり謎ですw)
◇
そして、ヒトのセンサーと神経系・脳でどのように信号が処理されて、世界が色づいて見えるのか(感じられるのか)。と、工学系から医学系へ話が移り、色覚検査方法自体の謎へと迫ります。
驚くべきことに、昭和の時代に子どもたちに「異常者」の烙印を押したあの色覚検査に(実際に有効ではあるようなのですが)、どのくらい有効性があるのかどうかのエビデンスはどこを探しても存在しないのだそうです。(英国でそれを疑問に思って検証した論文はある)
(ここで、エビデンスや、スクリーニング、感度、特異度、擬陽性などの知っていて損のない用語の詳しい解説も入っていて、とてもためになりましたw)
この検査自体が正常と異常というレッテルを貼るための基準となって、ほんらい緩やかに分布する個性(の多様性)でしかないはずの色の感じ方の少数派に対して「負のラベリング」をしてしまうわけです。
川端さんは、この電磁場への感受性スペクトラム分布は、同様に差別対象であった自閉スペクトラム症についての昨今の社会の対応が参考になるのではないかと言います。(自閉スペクトラム症=ASDについては、一般とされる層からひとつながりの分布である(=個性)と認知されてきており、支援の手も広がっている)
◇
「負のラベリング効果」で自分自身を障碍者と決め込み、社会から排斥され(たと思い込み)、社会もそれを積極的に否定しない。――学校の一斉検査によってレッテルを貼られ、優生思想によって国や学術機関は「良いことをしている」と思ってさらにそれを後押しして……。と……。
川端さんは、社会環境全体が共鳴箱のようになって、「色覚」というたんなる感覚の違いを大げさに増幅していったのではないか、と、色を音に例えて語ります。
昭和のころに激しく鳴った色覚への差別という大音響の残響は、21世紀になって20年もたったのにいまだに響いているのではないか。と。
◇ ◇ ◇
音も、電磁場同様、連続体であり当然スペクトラム分布は計測できます。(色覚は感覚なので、また別の問題なのだけれど)社会に鳴り響き共鳴した人々のスペクトラムも、同様に物理的に計測できる世界が来たら、すべてが連続したスペクトルの一部。多様性の一部であって、差別なんてそもそもなくなるだろうになあ。なんてことを読んでいて感じてしまいました。
◇
以上、読み終わった興奮のまま、長々つらつらとレビューのような感想のような紹介文を書き連ねてしまいました。
誰もが感じている筈の「今見えている色は、他人と100%同じ色とは限らない」という感覚の違いという「ふしぎ」と、その違いが社会にもたらした様々な問題の「不思議」を、本当の意味で知ることのできる、1700年代の『光学』ならぬ2020年代の『色覚』原論。
色にまつわる、ふしぎ・不思議に興味のあるすべての方におすすめの、たいへん知的にエキサイティングで、社会的にもいろいろと考えさせられる、とても意義深い本でした。
―――
よろしければサポートお願いします!いただいたサポートはクリエイターとしての活動費にさせていただきます!感謝!,,Ծ‸Ծ,,
