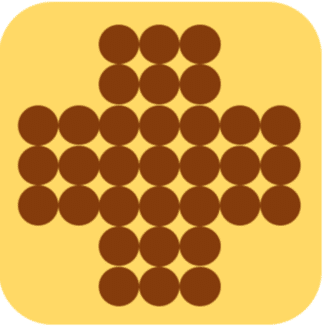ビジネス文書の書き方は、すべてボドゲの「ルール」から教わった(2)
前日の記事からの続きです。

4 準備
準備が必要ない、いきなり始まるゲームもあります。その場合は、この項目はルールブックから完全削除します。
あるいは、ゲームが2フェーズに分かれている場合。
身近な例で言えば「Reversi(リバーシ)」みたいなやつ。こういった場合は第1フェーズをここ「4」で書くのも、良いかもしれません。
注:「2フェーズ」あるゲームとは、たとえば、第1相:コマ配置フェーズ、第2相:コマ戦闘フェーズという感じで、ゲームの前半と後半とで、プレーヤーの行動がガラリと違ってくるゲームのことです。

5 遊び方(How to Play)
自分のターン(手番)で実行できることを、選択肢を与えながら書きます。
今回説明のために使用したWanTuゲームは、行動に選択肢のない1本道のゲームだったので、選択肢アリ、の場合にはどう書くかを説明しておきます。
行動の選択肢があるゲームの場合の書き方
(今回の説明用の、架空のゲームです)
文例
・・・・
自分のターンで行える行動は以下のA,B,Cの3通り。これらのうちから任意の1つを選んで実行したらターン終了し、相手のターンになる。
A 新しいコマを出す。
B 相手のコマと自分のコマとの位置を交換する。
C パスする。
次に、A,B,C それぞれの詳細説明を記す。
A:新しいコマを出す
ゲーム盤の一番手前の列に空いているマスがある場合は、新しいコマを出すことができる。その場合には・・・・(以下略)
!以下略って変ですよね。架空のゲームなのに!
・・・・・・
こんな感じで書いていきます。

5bと6 特異的な条件や、5aに書ききれない諸注意
自分のターンでできること、自分のターン内に、やらなきゃいけないこと。そこに意識を集中して、わかりやすく説明文を書くのは大事です(5a部分)。
でも、その書式のせいで逆にかえって「あー。どこにも入れ込む場所がない。大事なルールなのに。どこに書けばいいの?」ってなっちゃうルールも、あります。
これって、ボドゲあるあるですよね!
それらの「特異的」あるいは「はみだし」ルールは、5bあるいは6の位置にまとめて書きましょう。
まず、「基本的・標準的」な「ターンでの行動」をしっかりと理解・納得させてから(5a)、
その直後に、まとめて「特異的な変なことが起こった時」や「ターンを中断してでも、ターンの途中であっても処理しないといけない緊急案件」だの、そういった「はみだしルール」を書く。
こうすれば、読んでいて理解しやすくなると思います。
蛇足かもしれないですが「はみだしルール」とは、例えばこんな感じのルールを想定しています。文例を示します。
(今回の説明用の、架空のゲームです)
文例
・・・・
もしも、ドローしたカードが「黄色」だった場合には、その時点ですぐに、自分の手持ちのカード全部を「カードの捨て場」に出さなければならない。また、その時点をもってターンは中断&終了となり、次のプレーヤーのターンとなる(以下略)
・・・・・・
こんな感じになります。

7 勝利条件を再表示(勝利条件がわかりにくいモノの場合)
これは必要に応じてです。例えばOthelloみたいなゲームだったら、書いてはいけません。くどいです。
一方で、WanTuのようにルールが「奇妙」な場合は、ここでもう一回書いたり、あるいは詳細な解説を入れたりすると、読者に向けては親切になります。説明文は、あえて意図的に「裏側から表現」するのも効果的です。
「いちばん最後に、ルール通りに手持ちのコマを置けた人が負け」
「ルールに従おうとする時、手持ちのコマを盤面に置けなくなった人が勝ち」

8 バリアント(バリエーション(派生)ルール)
バリエーションがあるならば書く。ないなら書かない。この項目には、特に注意すべき点はありません。
***
さて、いかがでしたでしょうか。
ビジネスの場面で言う「ロジカルシンキング」って、まさにこういう論文構造だと、言えませんか?言えますよね?
いや、実は私、そういうビジネス関連本って、意図的にできる限り最小限しか読まないことにしてるんで、正直なところあまり知らないんですけど。
でも私が、この「ラジくまる式表記法」を意識的に用いて作ったビジネスプレゼン資料は、同僚から「わかりやすい。読みやすい」と褒められた回数はホントに多数です。上司にほめられた回数も、まあまあ・・、くらいにはあります。効き目はあるなぁと体感しているところです。
ビジネスにも使える!ラジくまる式ボドゲルール表記法でした!
ということで。では。
いいなと思ったら応援しよう!