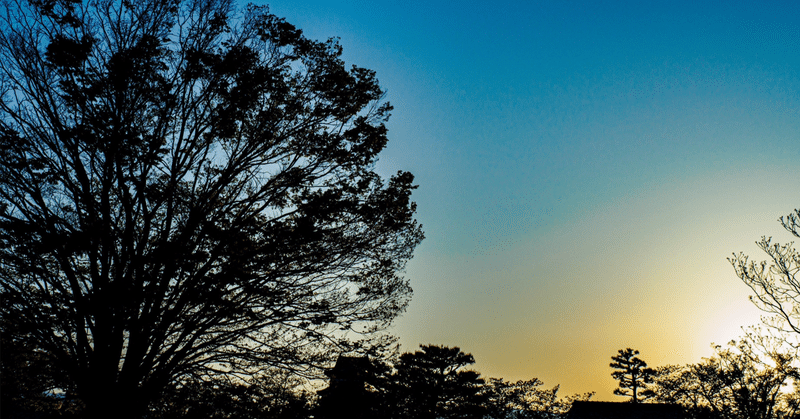
ファイナンス(企業財務)の基本⑤:投資の意思決定で使う「DCF法」の理解は、実はこんなに簡単だった
前回は、「割引率」について書きました。
今回は、投資の意思決定で使う「ディスカウンテッド・キャッシュフロー法(DCF法)」について、書いていきたいと思います。
まずは簡単に、前回のおさらいです。
割引率とは?(前回のおさらい)
「割引率」とは、将来手に入るであろうキャッシュを「現在価値」に換算するときに使う、「利子の逆のようなイメージの数値」です。
「割引率」には、下記2つの特徴があります。
将来生み出されるキャッシュフローのリスクが高いと判断すれば、割引率は高めに設定される
リスクとは「将来のキャッシュフローがばらつくこと」
(バラツキの大きさ = リスクの高さ)
ここで、ファイナンスでいう「リスク」という言葉について補足しておくと、
「バラツキの大きさ = リスクの高さ = 不確実性の高さ」となります。
投資の意思決定に必要な考え方
ここで改めて、基本的な投資判断の方針(正確には、数ある中のひとつ)を書きます。
その投資によって、将来生み出されるであろうキャッシュフロー
(将来キャッシュフロー)を見積もる。適切な「割引率」を設定して、将来キャッシュフローを現在価値に換算する。
「投資額 < 将来キャッシュフローの現在価値」であれば、投資をする。
上の判断を実行するための必要情報は、シンプルに下記の3点です。
将来のキャッシュフロー
期間
割引率
以下のDCF法の説明の後に、簡単な例で考えてみることにします。
ディスカウンテッド・キャッシュフロー(DCF)法とは?
実は、DCF法について「その考え方自体」は、すでに上に書いてしまっております。改めて、「DCF法とは何か」を言語化すると、下記のようになります。
DCF法
DCF法とは「資産価値を、当該資産が生み出すキャッシュフローにもとづいて求める方法」です。DCF法では、すべての資産の貨幣的価値を、それが将来生み出すキャッシュフローの現在価値として計算します。

それでは、DCF法を使って、「投資する/しない」を考えてみましょう。

上の例ですと、将来のキャッシュフロー、期間(5年)、割引率(10%)がわかっているので、DCF法による投資判断ができそうです。
1〜5年目の将来キャッシュフローをそれぞれ現在価値に換算して、足し合わせると「200/(1.1)^1 + 200/(1.1)^2 + ・・・ = 758万円」となります。
一方、投資額は800万円です。そのため、この場合は投資してもペイしないため「投資しない」という判断となります。
「意外と、シンプルな考え方だな」と思って頂けたでしょうか?
実際には、もう少し細かく考えるべき点がいくつかあるのですが、大まかなイメージとしては、上のような形となります。
今回は、ここまでにします。
次回は、「投資の意思決定」で使うDCF法について、もう少しテクニカルな内容を紹介していきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
