
#16 『君のクイズ』で2023年を総括する
アクセスしていただきありがとうございます。
今年も残すところあとわずか。そこで今回はこの1年を振り返るべく、2023年のクイズ界に起きた大きな出来事について総括していきます。
今年の初めに、『#1 卯年にクイズの歴史は動く』という記事を投稿しました。
(出来ることなら、ここにリンクを貼り付けたいところですが、すみません。やり方が上手くないので、このページの上にある私のアカウント名をタップして、同記事をアクセスしていただけると幸いです)
これは歴史に名を残すクイズ番組の開始と終了が卯年に集中していることを中心に述べているのですが、歴史が動くのは何もクイズ番組に限ったことではありません。例えば、前回の卯年の2011(平成23)年には現地時間2月16日、アメリカの人気クイズ番組『ジョパディ』にて、世界的コンピューターメーカー、IBMの作成した質問応答ソフト、“ワトソン”が、クイズ対決で人間の著名な解答者2名に勝利し、最高額賞金を獲得しました。
IBMといえば、1997(平成9)年、チェスシステム“ディープブルー”を世に送り出し、当時最強と言われた人間のチャンピオンから勝利を収めたことで、人間がコンピューターに負けた、という出来事が驚きをもって報じられました。コンピューターソフトの次なる野望は、8×8の64マスの盤面から、人間が扱う膨大な量の言語。無謀と思われたプロジェクトの全容、その詳細については『IBM 奇跡の“ワトソン”プロジェクト 人工知能はクイズ王の夢をみる』(スティーヴン・ベイカー著 土屋政雄訳 早川書房)でお確かめ下さい。
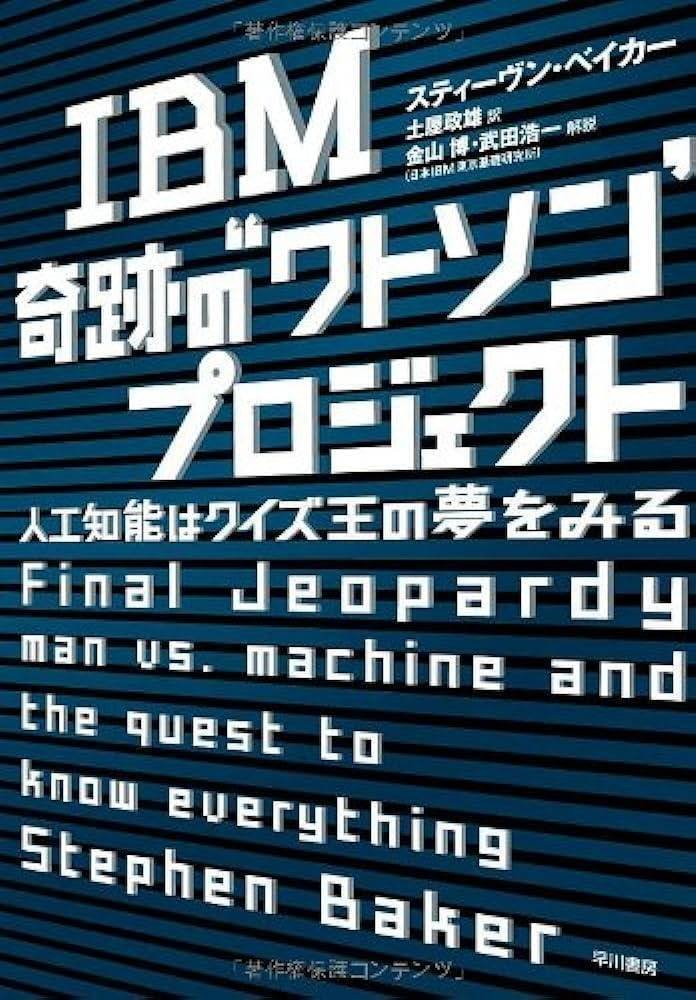
話が若干逸れましたが、このように、卯年はクイズを通して世の中に一石を投じる出来事が起きる。そんな年と言えるのではないでしょうか。
では、今年2023(令和5)年はどうか。1つ挙げるとすれば、競技クイズを題材にした小川哲(おがわ さとし)の長編小説『君のクイズ』(朝日新聞出版 以下、本書)が大きな話題になったことではないでしょうか。2022年10月に上梓された本書は様々な媒体に取り上げられ、大きな反響を呼びました。その勢いで、今年の本屋大賞にノミネート。さらに7月、芦沢央(あしざわ よう)の『夜の道標』とともに、第76回日本推理作家協会賞長編および連作短編集部門を受賞しました。
そんな小川氏の作品は、このnote内でも多くの方が感想を述べられています。それに追従するかたちにはなりますが、ここでは『君のクイズ』がこれからのクイズ界に何をもたらすのか、という点を軸にしながら考察します。
※なお、これより以下の文章には物語の核心に触れる描写や記述、いわゆる“ネタバレ”の要素が含まれています。その点に留意してお読み下さい。

あらすじ
テレビの生放送で行われている競技クイズNo.1決定戦『Q-1グランプリ』。その決勝戦に駒を進めた三島玲央。対するは、東京大学医学部4年生の若きクイズスター、本庄絆。先に7問正解すれば勝利、逆に3問不正解で失格となる、いわゆる“7◯3☓”方式の早押し対決は、互いに一歩も譲らず、両者6問正解の大接戦。運命の1問を迎えたその時、事件が起きる。まだ問題文が読まれていないにもかかわらず、本庄がまさかの“ゼロ文字押し”で正解。誰もが呆気に取られるなか、優勝賞金1千万円を獲得した。これは番組が仕組んだヤラセか、それとも彼の真の実力か。ネット上に多くの推測が飛び交うなか、当事者となった三島は複雑な感情を抑え、この謎の“正解”を突き止めようと奔走する…。
考察
本書について、そもそもこれがミステリー小説にあたるのか、という疑問を投げかける方も多数いらっしゃいました。確かに、本書の初版の帯には、「卓越したミステリー」の文字、さらに伊坂幸太郎や新川帆立といった第一線で活躍するミステリー作家の推薦文も載っていますので、異論を挟みにくいところがあります。
日本推理作家協会賞受賞に際し、小川氏は「『ゼロ文字解答』という冒頭の謎は、魅力的な推理小説の舞台設定としてではなく、単に僕の小説家としての『怯え』から生まれたものです。『クイズに興味のない人に、どうしたら続きを読んでもらえるのか』と考え抜いた結果、誰もが分かる謎が作品の主題となりました」という言葉を残しています。このことから、小川氏はあくまでも本書を、クイズがテーマの小説とし、ふたつの側面からクイズについて描こうと試みたのではないでしょうか。
1つ目は、競技クイズ(ここでは読み上げ式の早押しクイズを指す)のエンターテイメントとしての可能性についてです。
多くの方が書評で述べられているように、本書の一番の見どころは、クイズが題材となっていることです。なかでもクイズをしているときの、クイズプレイヤーの思考回路が具体的に活字化されている新鮮さは、今までの文学作品にはありませんでした。
それを可能にしたのは、本書の一番最後、参考文献に交じって謝辞が述べられた、2人のクイズプレイヤーの存在です。1人は、社会学者・東浩紀に師事した経歴を持ち、競技クイズNo.1の実力との呼び声も高い、徳久倫康(とくひさ のりやす)。もう1人は、伊沢拓司らとともに『高校生クイズ』(日本テレビ)で優勝を決め、そのイケメンぶりがオンエアで話題を呼び、秋に開催された文化祭に大勢の女性が殺到したという逸話を持つ、小川氏の大学の後輩、田村正資(たむら ただし)。テレビのクイズ番組に多数出演したことのある2人と、小川氏は以前からプライベートでの交流があったということで、彼らへの取材により『Q-1グランプリ』をはじめとする本書に登場した数々のクイズ番組の内情については、実体験に基づいたリアリティーが保証できると考えられます。
また、一部の方がご指摘するように、本書の展開は、日本で2009年に公開された映画『スラムドッグ$ミリオネア』を彷彿とさせます。インドのスラム街で育ち、十分な教育を受けてきたとは言い難い青年ジャマールが、国内で人気を誇るイギリス発の世界的クイズ番組『WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE?』(日本でも2000年代前半にレギュラー放送された『クイズ$ミリオネア』)に出場。順調に正解を重ね、最終問題を前にして不正を疑われ、警察から取り調べを受けます。潔白を証明すべく、自らの半生を振り返ることで、すべての問題に正解するまでの過程を語るそのストーリーは、「クイズとは人生そのものである」という本質を突いた傑作です。本書はそれをフォーマットとして採用していることが分かります。

その一方で、小川氏は現在の競技クイズについて、構造的な観点からすでに機能的限界を迎えている、という認識を持っている可能性があります。
その根拠に、2020(令和2)年7月に発行された芸術総合誌『ユリイカ 特集*クイズの世界』に小川氏は寄稿しています。そこで語られているのは、小川氏が『高校生クイズ』をきっかけにクイズに興味を持つようになったこと、いつか競技クイズをテーマにした小説を書きたいという夢を抱いていること、徳久と知り合いになってからいろいろなクイズを出して、その強さの秘密を探るため彼を問い詰めたこと、そして競技クイズには、独特な文法が存在し、クイズプレイヤーたちはその文法のなかでクイズに解答していると気付いたこと、などが挙げられます。
「独特な文法」とは、例えば本書に登場する“確定ポイント”という表現が代表的です。
“確定ポイント”とは、問題文のなかでクイズの答えが確定するポイントのことを意味します。問題が読まれる前、無限に存在していた選択肢は、問題が読まれるにしたがってその数を減らしていき、やがてどこかのタイミングで1つに絞られます。クイズプレイヤーは誰よりも先に答えを確定させ、早押しボタンを押して答えるために、他の人が知らない知識や情報を頭のなかにインプットしています。己の脳内にある膨大な情報を、高速な計算で処理して答えを出しているのです。
ですが、そこには大きな落とし穴があります。
“確定ポイント”は、他者と共有された時点で、“確定ポイントではなくなる”ということです。
この現象について伊沢拓司は「最適化されたポイントであったはずの『ここで押せる』は、競合他社多数のレッドオーシャンとなり、そこで押してもランプを点けられる可能性は下がっていく。(中略)競技クイズにおいては一問の問題で早押しランプを点けられるのは一人であり、すなわち最速をとれない限りそれは最適ではないのだ。ボタンを押された瞬間、押し負けたすべてのプレイヤーはその問題に対するコミット権を失う。まずはボタンを点けること、これがクイズの基本だ。このようにして、スピードに賭けているプレイヤーがこの押しをしだすと、それが広まりスタンダードとなっていく。(中略)つまり、研究による最適点は、それが生み出された瞬間から徐々に腐敗を始める」と分析しています。さまざまな大会で「最適化されたポイント」が披露されれば、たちまちSNSで拡散され、多くの人に共有される。いつしかそれがスタンダードとなり、誰よりも先にボタンを押すことができるテクニックではなくなる。そこから誰よりも一歩先に押せるポイントをなんとしても探し出す。そのようないたちごっこが繰り返された果てに、早押しボタンが点灯してから、出題者が問題文を読むのを中断するまでのわずかな時間の間に、勢い余って発音する声を聞き取って答えを確定させる“読ませ押し”や、出題者の唇の動きを見る読唇術といったテクニックが生まれる、という循環ができているのです。
では、出題者は彼らのそのような暴走を止めることはできないのでしょうか。その答えとも言える記述が本書にあります。
自分で問題を作ったことのある人間なら誰でもわかると思うが、作問者は「できることなら誰かに正解してほしい」と思っている。正解の「ピンポン」という音は、解答者だけでなく、出題者も肯定する音なのだ。解答者の世界と、出題者の世界が重なりあって、答えがひとつに確定する。それこそがクイズの醍醐味だ。だから意地悪な問題はよほどの事情がない限り出題しない。
共依存しているかのように、出題者は解答者に歩み寄ることさえある。このような現象に陥る理由は大きく分けて2つ考えられます。
1つ目は、問題文の“美しい/美しくない”という考え方。
具体例を挙げれば「日本で1番高い山は富士山ですが、春先に吹く強風のことを一般的になんと言うでしょう?」という問題文には、文法上に大きな問題こそありませんが、これでは、前半の「日本で1番高い山は富士山ですが」の部分が無駄になってしまうという、文章に無駄のあるのを好まない考え方のことです。「日本で1番高い山は富士山ですがー」と来れば、せめて「日本で2番目に高い山はなんでしょう?」あるいは「世界で1番高い山はなんでしょう?」と続くのがセオリーである。このような考え方が共有されることで、問題文は定型化を一層進めることになります。
2つ目は、出題者と解答者の関係性による構造的な問題です。
クイズ界最大規模とされている、大学4年生以下の学生が対象の短文早押しクイズ大会「abc」は制度上、卒業して社会人になった元参加者が次の大会を作ります。そのため、参加者の気持ちがわかるので、なるべくみんなが全力を出せる環境を整えようと、配慮の行き届いた問題になっていく、と徳久は指摘しています。
クイズプレイヤーは解答者であると同時に、出題者でもある。クイズの世界がギブアンドテイクの関係で成り立っていることを象徴する典型例のひとつです。
これらを踏まえて言えることは、現在の競技クイズは、出題された問題を解くための知識やひらめきがあるかどうかで競う、というそれまでクイズが持っていた大前提を結果的に破壊し、一部の人たちの暗黙の了解で築き上げられたクイズの文法を熟知しているかどうかという、知識以外の要素で勝敗が決してしまう。問題文のコードと正解さえ知ってしまえば、それらを暗記するだけでクイズ王と呼ばれる可能性がある。極端に言えば「頭を使わなくてもクイズができる」環境が醸成されたのです。
一般的に「クイズの勉強」といえば、クイズで出題されそうなジャンルの知識を蓄えることをイメージされる方も多いかもしれません。しかし、クイズプレイヤーにとってその言葉は、誰よりも問題文を先読みするために、クイズ特有の文章構造を理解する、ということを意味しています。彼らはそこに日夜心血を注いでいるのです。
これについて小川氏は次のように表現しています。
一流のクイズプレイヤーは、優れた記憶力と判断力、知識と経験、勘や鋭い読みを持ち合わせている。しかしそれゆえに、クイズプレイヤーとして、クイズの文法に則って知識を追求する行為は、ある地点から人間として知ることの喜びを追求する行為と齟齬をきたしてしまうかもしれないのだ。そのことは、小説家の僕にとってたいへん興味深いことだった。
本書のストーリーに話題を戻しますが、『Q-1グランプリ』の総合演出・坂田泰彦が、本庄の“ゼロ文字押し”で物議を醸した生放送の終了後、番組スタッフとの連名で公式ホームページにリリースした声明は極めて印象的です。それが競技クイズの、現状と今後の運命をほのめかす内容にも取れるからです。
第一回『Q-1グランプリ』放送後より、みなさまから数多くのご意見をいただいております。競技クイズの大会で、このような事態になったことをたいへん遺憾に思っております。
外部スタッフによる調査の結果、演出面でいくつか不適切な部分があったことがわかりました。この結果は直ちに不正を認めるものではありませんが、競技クイズの普及、振興を目指した本大会が、結果として混乱を招くことになってしまった原因は、ひとえに我々の実力不足にあります。我々がクイズを愛する気持ちに嘘偽りはありませんが、ご期待を裏切られたように感じる方もおられ、誠に申し訳ございません。
本番組は競技クイズの頂点として今後も年に一度開催を続けていく予定でしたが、このままではすべての視聴者のご理解はいただけないものであることから、今回のような形での次回開催は中止とさせていただくことになりました。
物語の結末を申し上げるならば、『Q-1グランプリ』において、出題者が解答者に事前に答えを教えたり、解答者が不正な手段を用いて解答したりというヤラセは存在しませんでした。ですが、それ以上に厄介なのは、競技クイズは出題者から解答者に対する過度な忖度が常態化しており、そこから両者の間で予定調和が生じ、“内輪ウケ”が蔓延したことで、外部の者からは到底理解できないレベルに達してしまった、ということです。それこそが異常なスピードで解答するプレイヤーに対し「クイズなんてどうせヤラセでしょ?」、「彼らはマジックを使ってクイズに答えているに違いない」という誤解を産み出す元凶となっているのです。そこに解答者の超人的能力にフォーカスした過剰な演出が追い打ちとなり、本庄の“ゼロ文字押し”を後押し、混乱を招きました。
2023年の国内のニュースを見渡すと、内輪の論理がまかり通り続けた結果、自浄作用を失った組織が、多くの損失と悲劇を生み出した事例をいくつも見てきました。個別の言及は避けますが、競技クイズ界もそれと同じ体質であると言えるのではないでしょうか。
お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、現在地上波でレギュラー放送されている多くのクイズ番組では、読み上げ式早押しクイズを採用していません。全くないわけではありませんが、以前と比べると、主流ではなくなっているのは事実です。読み上げ式早押しに頼らない、あるいは、同じ早押しでも、映像問題を使用した出題形式に取って替わっているのです。
その一方で、人員や予算の関係でやむを得ないとはいえ、クイズサークルやオープン大会で出題される問題は、インスタントに作ることができる読み上げ式早押しクイズに依存している傾向が根強く残っています。
伊沢や徳久などの著名なクイズプレイヤーたちは、多くの人にクイズをやってほしい、とクイズのさらなる普及を訴えています。そのためには「クイズを愛する者への冒涜」ともとれる、現在の競技クイズという名の「派閥」が、新しい時代の出題形式を模索し、適応するための「解体的出直し」を決断しなければならない局面に迫られているのです。それができなければ、文化として衰退の一途を辿る運命だとしても、致し方ないのかもしれません。
というわけで、私の考察は以上です。
みなさまにとって2023年はどのような一年だったでしょうか。
私としましては、記念すべきnoteデビューイヤーでございました。ここまで一年間続けることができたのも、たくさんの方のアクセス、スキ登録、フォローのおかげでございます。これまで記事を読んでくださった方、今日初めて読んだという方、そしてまだ読んだことのない方、すべての方に感謝申し上げます。これからもクイズにまつわる記事をアップいたしますので、どうかひとつよろしくお願いいたします。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。よろしければ“スキ”登録お願いいたします。
参考文献・記事
『QUIZ JAPAN vol.16』 セブンデイズウォー
『東大生クイズ王 伊沢拓司の軌跡Ⅰ~頂点を極めた思考法~』 伊沢拓司 セブンデイズウォー
『ユリイカ 特集*クイズの世界』 青土社
『クイズ早押しの微分学 ~4文字の「最速押し」が「最速ではなくなる」理由~』 ねとらぼ 2017年9月13日
また、日本推理作家協会賞のHPを参考にしました。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

