
渇いた心にファンタジーを
こんにちは。
今日は、神話や小説に登場する数々の生き物の中で、私が好きなものをいくつか紹介しようと思います。統一性は全くないのでご注意ください。
ドラゴンやペガサスなどは、名前を聞くとなんとなくイメージがわきますよね。
空想の生き物のイメージにも普遍性があるんだと思うと、なんだか不思議な感じがします。
色んな作品に登場しながら語り継がれてきた生き物たちは、見ているだけで心をふわりと浮き立たせてくれますよ。多分。
・グリフォン
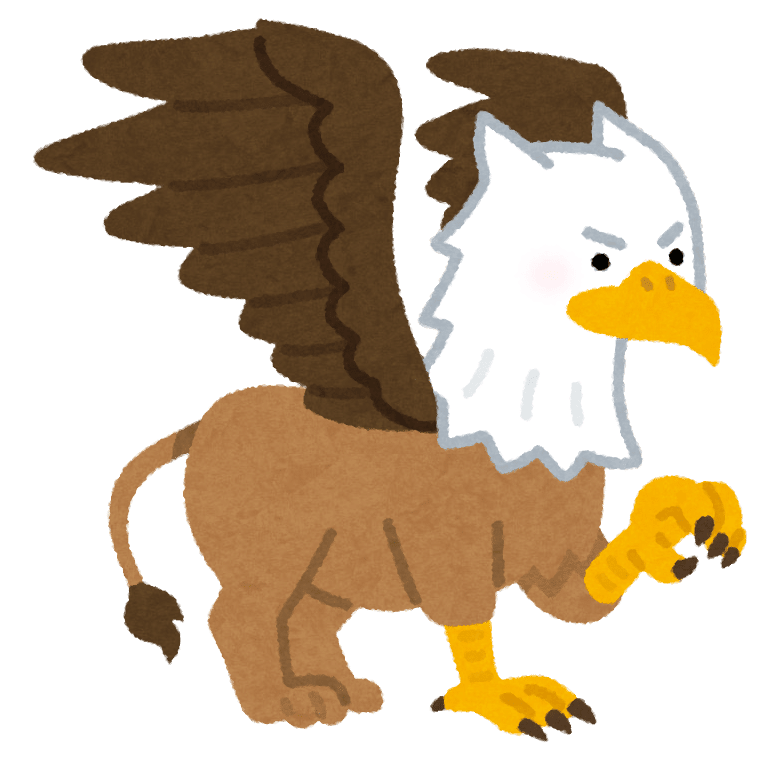
下半身はライオン、上半身と翼は鷲の姿をした幻獣。私は『ドラえもん 新・のび太の日本誕生』という映画に登場していたのを見てその存在を初めて知りました。
伝説の生き物としての歴史は古く、ヘロドトスの『歴史』に既に記述が見られるそうです。
知識や王家の象徴として、多くの紋章に描かれてきました。
ちなみに見た目がよく似ている「ヒッポグリフ」は、グリフォンと雌馬の間に生まれた子供です。
・麒麟
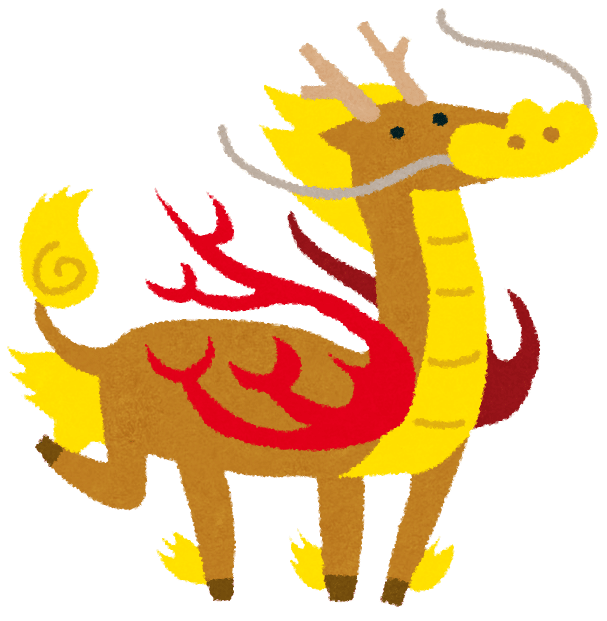
キリンビールのシンボルとして日本でもおなじみですね。
中国神話に登場する生き物で、顔は龍に、体と角は鹿に、尻尾は牛に、蹄は馬に似た姿をしています。
『礼記』によると、麒麟は泰平の世に現れる神聖な生き物である「端獣」の1つと考えられているそう。「端獣」の中でも特別な4つの生き物は「四霊」と呼ばれ、麒麟の他には応竜、霊亀、鳳凰がそれに当たります。
性格は、虫も殺せないほど穏やか。(かわいいかよ)
・デュラハン
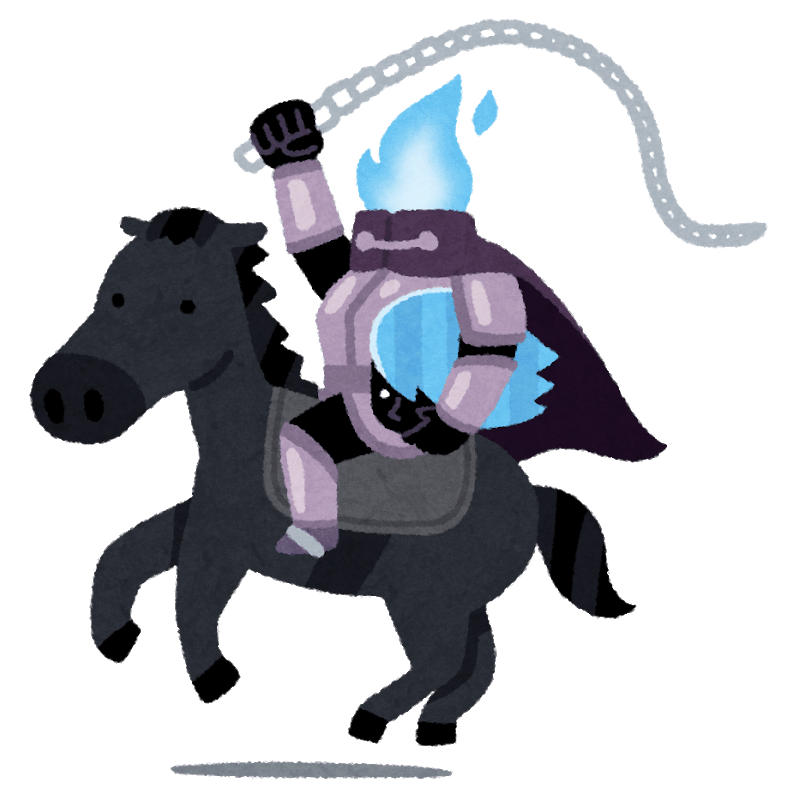
アイルランド地方に伝わる、伝説の首なし男。
甲冑を着た騎士の姿をしていて、小脇に自分の首を抱えています。
人間の死を予言し、それを必ず的中させるそうです。
姿を見た者は鞭で目を潰されるとか…。
アメリカの小説家ワシントン・アーヴィングの短編『スリーピー・ホロウの伝説』にその姿が描かれています。
・土蜘蛛

土蜘蛛は、平安時代の源頼光伝説に登場することで知られる巨大な蜘蛛の妖怪です。
いくつかのバージョンがありますが、土の中に巣を作っていた土蜘蛛が美女や僧に化けて人を襲い、頼光たちがそれを退治する、というようなストーリーです。後世には能や歌舞伎の題材に取り上げられました。
源頼光は合戦ではいまいちパッとしない武将ですが、多くの怪異退治の逸話で知られ、土蜘蛛はそのうちの1つです。
他に有名なのは酒呑童子退治でしょうか。その際に使われた刀は「童子切安綱」といって、天下五剣に数えられます。
ちなみに土蜘蛛を討った名刀は「膝丸」です。
・ナゾベーム

ラストはかわいい(?)ので締めましょう。
その名の通り「謎」な見た目ですが、この生き物は、ドイツの詩人クリスティアン・モルゲンシュテルンが生み出した空想の生き物です。鼻で体を支えてそのまま歩行ができるなんとも奇妙な姿ですが、どこか愛着を感じます。
モルゲンシュテルンは「ナゾベーム」と題した作品の中で自分が作り出したこの生き物について詠いました。
そしてその詩はドイツの動物学者ゲロルフ・シュタイナーに影響を与え、シュタイナーはなんとナゾベームを含む「鼻行類」という架空の生物群について解説した本を書き、出版してしまいました。
その本は学術論文のパロディの形式をとっていて、完成度はかなり高いそうです。2人とも発想が自由すぎない?(笑)
ここでは5つしか紹介できませんでしたが、架空の生き物って有名どころだけでも本当に数えきれないほどあるんですよね。個性的な見た目、性格など知れば知るほど面白いなと思うものばかりなんですが、全てマスターするには何年かかることやら…
現実世界に疲れたときには、別の世界で生きている彼らのことを考えて元気をもらってみてください。
あ、あと、いらすとやってまじでなんでもあるですね。びっくりした。
今回はここまで。
読んでくださりありがとうございました。
ではまた次回。
読んでくださりありがとうございます!スキ、フォローもしていただけたら嬉しいです🍀✨ サポートでいただいたお金は、今後の成長に必ず役立てます(^-^)ゝ
