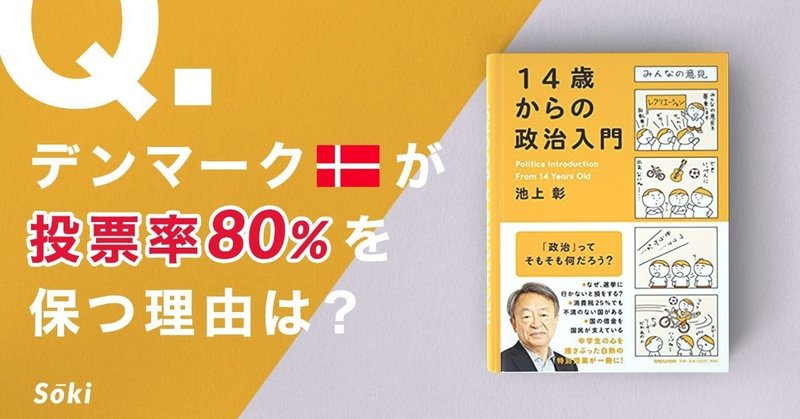
もはや社会人が読むべき「14歳からの政治入門」
今回の書籍は、池上彰著「14歳からの政治入門」です。
アラサー子持ちの私が14歳向けの本を読みましたが、、はい、正直、めちゃくちゃわかりやすくて、大変参考になりました。
これを読んでくれているママやパンの中にも、いざ子供に質問されたときに、わかっているようで上手く答えられなかったり、回答に自信がない政治・経済のことは多いと思います(私だけじゃないはず、、、!!笑)。
例えば「公務員てなに?」や「大統領と首相って何が違うの?」といった質問にあなたはすぐに自信を持って答えられるでしょうか?
本書ではこれらの問いを中学生でもわかるように、非常にわかりやすく書かれています。
本書を読み、想起学習を行うことで、子供の問いにドヤ顔で答えられるようにしましょう!
「本」の問題集とは?(※初めての方へ)
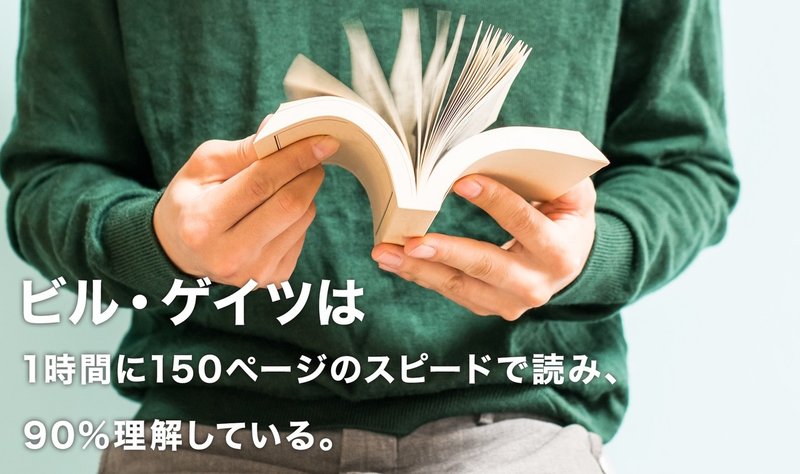
自分を変えたい、キャリアアップしたい。
そのためにひたすらビジネス書や自己啓発本を読み漁る方は多いと思います。ただ、一冊読み終わった後すぐにアウトプットできるほど、内容を理解している方は少ないのではないでしょうか。また、気が散って集中できず、「ながら読み」になってしまい内容がなかなか頭に入ってこない、なんて経験はないでしょうか。多忙な社会人ほど、本を買って満足し、読んで満足し、さらに内容を理解した錯覚に陥っているケースが多いのです。
一方、ビル・ゲイツのように、本を1時間に150ページのスピードで読み、90%理解しているという天才もいます。もちろん、これには生まれ持った遺伝子的な要素が関係しており、ビル・ゲイツは例外中の例外です。しかし、「知識の定着」という観点立てば、誰にでもそれが可能な(科学的根拠のある)学習方法があります。
それは、想起(recall)と再言語化です。
ここでいう想起とは「思い出す努力をする」ことです。いわゆる学生時代に行なっていたテストですね。つまり、忘れた頃に思い出す努力をすることによって、長期的な記憶を蓄え、いざ必要になった際にその知識を使用できるようにするという学習法です。
再言語化とは、自分の過去の経験を元に、自分の言葉で言い換えるということです。中田敦彦さんのYouTube大学をご覧になったことがある方は、イメージできると思いますが、歴史や政治、経済など、難しい用語がバンバン登場するジャンルでも、中田さんは自分の言葉に置き換え、わかりやすく、且つ面白くアウトプットしています(※記事の最後にリンクを貼っておきます)。例えば、第1章を読んだ後に「ここで言いたかったことって、つまり〜だよね」と自分なりに言い換えてみてください。今まで以上に理解が深まるはずです。このように、想起と再言語を行うことが、長期的な記憶と使える知識への近道なのです。
前置きが長くなりましたが、本サイトでは、
おすすめ本の紹介&「本の問題集」を提供します。
先述した想起学習をするために、「〜とは?」を繰り返し、本から得た知識を自分のものにする事が目的です。記事では、私の主観で大事で忘れたくないと思ったところや部下や友人、家族に話したいと思った箇所をピックアップし、問題形式にしました。
想起学習で重要なのは自分の言葉に置き換える事なので、ここでの回答(本書の引用)を一字一句正確に覚える必要はありません。
〈「本」の問題集はこんな人にオススメ〉
◆読んだ書籍の内容を復習したい人
◆読んだ書籍の内容を部下や友人、子供に伝えたい人
◆書籍を購入する前に、内容を確認したい人
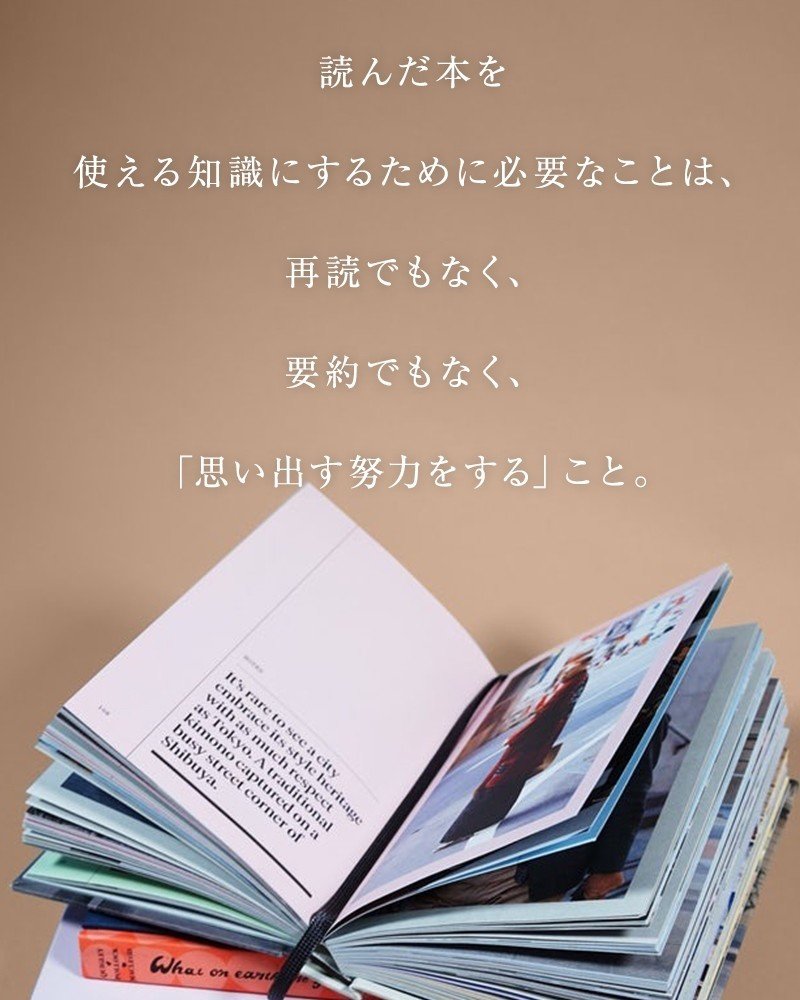
以下より、想起学習Q&Aになります。※回答を見たくない方は【目次】を利用して学習してみてください。
Q1.「政治」とは?
A.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
道路整備など、問題があるたびにどうすればいいか考え、ルールをつくっていくこと。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q2.ブータン5代国王が王政を廃止したいのはなぜ?
A.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
国王が全ての権力を持っていると、子孫にやばい奴が出てきたときに国が混乱すると考えたから。
これは、ブータンと同じく国王が国を統治するネパールで、起こった事件がきっかけ。ある王族の晩餐会で、国王の息子の1人が突然銃を発砲し、その場にいた国王含め王族のほとんどが死亡、犯人の息子も自殺した。その後、もともと評判の悪かった人物が生き残り、国王になってしまったため、案の定、独裁政治となって国民から大反発にあい、王政が廃止されたのである。それを近くで見ていたブータンの5代国王は、自国でも同じようなことが起こりかねないと考え、国民投票で首相を選ばせるといったルールに変更した。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q3.イギリスの国王が政治権力を持たなくなったのはなぜ?
A.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
西暦1300年頃、イギリスのエドワード3世がフランスに攻め込んだ。エドワード3世の母親がフランスの王女だったため、「自分はフランスの国王でもある」と主張したためだ。しかし、この王族同士の争いに巻き込まれた形となったイギリス国民が激怒し、国王の力を奪い取ってしまった。それ以降、国王も民衆の意見を聞かなければならないというルールがつくられ、今のエリザベス女王は、国王という地位にありながらも、政治的権力はないのである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q3.都道府県レベルの都市で、街の広場に集まり住民投票を行なっている国は?
A.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
スイス
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q4.「公務員」とは?
A.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
例えば、実際に道路ができたら道路を管理する人も必要になるので、みんなでお金を出し合って(税金)、仕事をしてもらうことになる。この人たちがいわゆる「公務員」である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q5.日本が普通選挙を行うようになった歴史的背景は?
A.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
日本で最初に選挙が行われたのは1890年。それまでは、国民に選挙権はなく、板垣退助が国民の自由を求めた後に殺害されるぐらい、民主主義とは程遠い国だった。1890年に行われた選挙では、一定の財産をもつ男子(税金を多く納めている)だけが選挙権を持っていた。その後、民主主義が広まり、1925年に全ての国民に選挙権が与えられる「普通選挙」が誕生した。しかし、この時の「全ての国民」は25歳以上の男子のこと。今のように女性も選挙権を持つようになったのは1945年以降である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q6.なぜ、選挙に行かないと不利になる?
A.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
選挙活動をしている候補者は、自分が当選するため、投票率が高い層に働きかける。現在、高齢者の投票率が約60%に対して、若い世代が20〜30%。つまり、これではお年寄りの年金制度や医療制度ばかりが充実するのだ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q8.デンマークが投票率80%を保つ理由
A.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
デンマークの消費税率は25%(そのかわり、幼稚園から大学までの授業料はほぼ無料。さらに、大学生には一人につき月7万が給付されるなど、税の還元制度が充実している)。25%も払っていたら、変な政治家を選ぶわけにはいかないので、投票率が高い。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q9.大統領、首相の違いは?
A.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大統領は国家元首のことであり、国のトップである。国民投票で大統領が選ばれるフランスでは、大統領が全権を握り、その下に首相がいる。しかし、ドイツのように政治の実権は国会議員の多い政党から選ばれた首相が握るため、大統領は外国との交流だけに留まる国もある。
アメリカの場合は、大統領が国家元首であり、政治権力も握っている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q10.イギリスでは、国会の開会時に、議員がバッキンガム宮殿に____される。
A.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
監禁
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
P11.共産主義とは?
A.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
みんなが平等であるべき、という考え。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q12.共産主義が上手く機能しない理由は?
A.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
真面目に働く人と不真面目な人が発生するため。その人たちが同じ給料では、結果平等ではなくなる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q13.「政治とカネ」の問題とは?
A.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
国会議員が自分の理想を実現するためには、何度も当選しなければなりません。しかし、そのためにはお金が必要です。例えばチラシを印刷するのにも印刷代がかかります。それを郵送すればさらにかかります。そのため、しょっちゅう国会議員の汚職事件が発生するのです。
1万人の人たちに毎月自分の活動報告をするだけでも毎月100万円、年間1200万円もかかるわけです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q14.日本の借金は◯◯円
A.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1000兆円
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q15.日本の国家予算で増えている◯◯費。なぜ増える?
A.
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
防衛費
戦後、日本は軍隊を持たないことを約束しました。しかし、それではあまりにも無防備過ぎるので、軍隊(戦力)ではない「自衛隊」として万が一に備え、さらにアメリカと日米平和条約を結び、何かあったら助けてもらう公約を取り付けました。しかし、アメリカの力が次第に弱まり、信用できなくなってきたため、国内から「もっと自衛隊を強化した方がいいのではないか」という声が高まり、防衛費が増えているのです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
以上です。お疲れ様でした。
ここでの問いは、あくまでも皆さんの手助けをするためのツールです。前述したように、自問し、自分の言葉で再言語化することで、より知識が定着します。
読書は、お金を払って購入し、貴重な時間を費やして得た知識です。読んだことで満足するのでなく、こうして定期的に思い出す努力を行い、いざという時に使える知識へと変えましょう。
では、忘れた頃に、またここに戻って来てくださいね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
