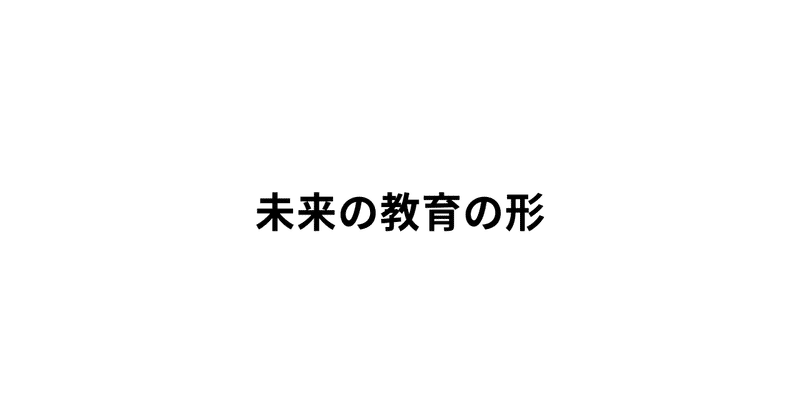
未来の教育の形
みなさんこんにちは!Purzambyのごうです!
今回は未来の教育の形というテーマで話していきたいと思います。これは僕個人の視点なので何かご意見などあれば是非コメントなどしていただければと思います!
今までの教育の形は終わり
ずっと前から言われていることではありますが、今までの詰め込み型の学校教育ではこれからの社会で生き抜いていくのは難しく、これからは、一人ひとりの個性や強みを活かす教育が必要だと考えています。
さらにテクノロジーの発展によって、オンライン授業や、オンデマンド型の動画コンテンツなどが誰でも使えるようになってきて、今までの教室に集まりみんなで同じものを学ぶという形態はこれからはなくなっていくと思います。
じゃあこれから学校ってどういうことするの?って思う方もいると思います。
私は、これからの学校は、「共有・対話の場」になっていくと思います。
事前に基礎学力を培う動画教材をみて、その上で一人ひとりがどう感じて、考え方を共有して議論する。その上で、その人がどんなことに興味を持ち、どんな視点で様々な事象をみているのかを知っていくことがこれからの学校像かなと思います。
いかに場所の格差をなくせるか
これからの学校の形が上で書いたようになるとして、人の集まり方がその地域によって差が出てしまうのではないかというのが僕の懸念点です。
例えば、今僕は岩手に住んでいて、なかなか同世代の人と話す機会があまりなく、リアルではほとんど喋っていなくて、時々オンライン上で人と話すという感じになっています。
今だからこそオンラインで話せる人がいますが、小学生や中学生になるとなかなかそのような繋がりがあまり持てていないんじゃないかなって思います。(#今の時代はそうでもないのか...?)
だからこそ、オンラインでの地域間の繋がりをいくつも持つということが、地方のまちづくりをしていく中で大切なことになってくるのではないかと思います。
姉妹校的なものをもっと複数同時に持つことが今後の価値観を広げる教育においては大事になってくるのかなと思ってます。
原体験の場
このような基本的なことはオンラインで完結できるよねみたいなことが増えていくと、その人だけの原体験が減っていってしまうんじゃないかっていう懸念点もあります。
「知識として知っている」のと、「知識としては形式化できていないけど、あの感情はなんなんだろう」みたいなものがあった場合、前者の相対的な価値は下がっていき、後者を得る機会をしっかり作ることが非常に重要だなって思います。
知識人間が大量生産されたところで、結局もっと創造的なことをできる人がいないと、これからの社会でやっていくのはなかなか厳しくなってくるんじゃないかなって思います。
各地域でしかできないような体験の場を持っておくことが地域の価値になっていく時代がこれからもっときそうな気がしてます。
実験場になれるか
そんな中、地域に定住する人たちからすると、さっき話した原体験の中のモヤモヤを晴らすことができる環境を作ることがとても重要だなと思います。
おそらく地域のあり方によってその環境で育つ子供たちの行動は二極化すると思っています。
他の地域に逃げるか、家に引きこもるか。(#ローランドみたい)
まずは、前者について話します。知識の範囲がグローバル化していることで知っていることが増えているのにその地域でできることが少ないと、そこに対する反発でどこか別の場所に移動したいと思う人が増えてきそうです。
もっというと、日本国内ではなく、海外に居場所を見つけて日本から離れていく人も全然いてもおかしくないと思います。
後者に関しては、ここでできないならもう家の中でなんでもできるんだから外に出る必要がないと考えて家の中にずっといるという生き方もありそうです。(#ちなみに今の僕はこっち側)
いわゆるメタバースという概念がもっと一般化した時には、どこにいても自分の好きな世界観、価値観の中で生きることが許される社会になっていくことも考えられます。
さいごに
ここまでいろいろ書いてきましたが、正直未来のことなんて誰もわかりません。ただ現段階で言えることは、今どんなことを課題として感じていて、それを解決するにはどんなことが必要で、どんなことができるかを考えることです。
是非僕とみなさんで明るい未来を作っていきましょう。これからの社会をになっていくのは我々です。
ということでかっこつけたところで以上です〜!
頑張っていきましょ〜!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
