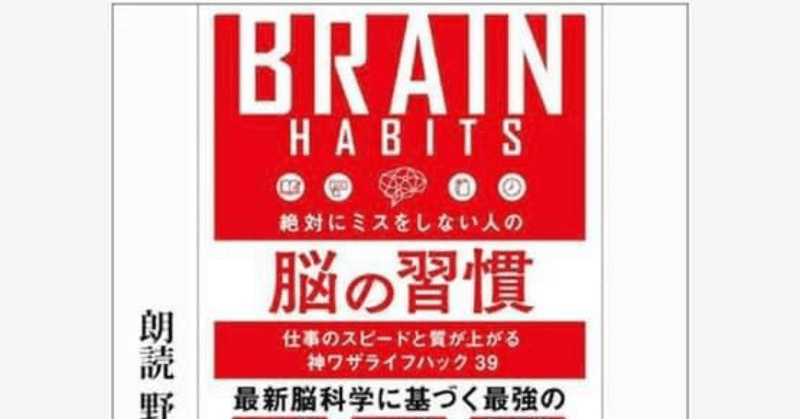
#3 絶対ミスをしない人の脳の習慣
絶対ミスをしない人の脳の習慣
著:樺沢紫苑
仕事でのミスが目立ち始めたこのタイミングで、危機感を覚え本書をAmazonオーディブルで聴きました。
読んでから、思考とやるべき行動が整理されて仕事のミスが減ってきています!
【intro】
○ミスが起きる4大原因
1.注意・集中力の低下
2.ワーキングメモリーの低下
3.脳疲労
4.脳の老化
※これらは全部繋がっている(関係し合ってる)
○4つの脳の働き
1.入力
2.出力
3.思考
4.整理
この4つの視点からミスについて深掘りしていく
○健康状態
絶好調⇄健康⇄未病(脳疲労)⇄病気
それぞれの関係を"⇄"で繋いだのは、未病の人が病気にもなるし、健康にもなる為。
左側へ移動していく為に4つの脳の働きからみる必要がある。
【入力編】
慢性的な疲労やストレスによりノルアドレナリンが減ると脳疲労の状態になり、集中力低下を引き起こす。結果ワーキングメモリー低下させミスを招く。
○ワーキングメモリーのフル活用が大事
PCでいうOSみたいなもの。
作業スペースが2つしかないのに3つの情報が入る(オーバーフロー)。
情報過多・オーバーフローがど忘れの原因。
○ワーキングメモリーを最大限生かす、増やす9つの方法
1.睡眠
2.運動
3.自然に親しむ
4.読書
5.記憶力
6.暗算
7.ボードゲーム
8.料理
9.マインドフルネス
○脳はマルチタスクを出来ない
交互に注意を向けているだけで、脳疲労しやすくミスや効率悪さを招く。
○音楽のデュアルタスク
記憶・学習効果を下げる
作業・運動効率を上げる
※課題によって音楽は有効活用出来る。
○メモは手書きが良い
記憶力上げる、ブローカー野を賦活される
○スマホの使い過ぎは4大原因を招く
○資格を取る
記憶力・集中力・認知機能を上げる
【出力編】
○ミスしやすい時間・曜日がある
・生理的に覚醒度が下がる時間
→3〜5時、14〜16時
→午前中は集中力↑
(集中力がいる仕事・作業をする)
・ゴールデンタイム:起床後2時間以内
・月曜・金曜はミス多発しやすい、火曜はミス少ない
(週末の溜まった仕事を片付ける、やりきろうとする為?情報過多状態)
○ウルトラディアンリズム
90分に1回集中切れやすい
→10分でも休む
○確認ミスする人は確認する事を忘れる
昔からミスする人はコレ
○毎朝TO DOリストを作る
緊急度×重要度の4象限+集中力
(緊急かつ重要、緊急だが重要じゃない、重要だが緊急じゃない、緊急でも重要でもない)
4つに分けた後、集中力がいる仕事・作業にチェックをつける
先送りの仕事はTO DOリストへ
急に言われた仕事はその場でリストに記載
途中の作業は途中であることを記載
○ホワイトボード術
1点TO DOリスト
→認知的不協和
○パーキンソンの法則
限られた時間をフルに使って課題を行なってしまう
※1時間の仕事を1時間半とったら1時間半使ってしまう
→対策:調整日を設ける(が、調整日をあてにしない)
○両面作戦はNG
2つ同時に物事を進めるとどっちも中途半端のクオリティになってしまう
○本や文章はいきなり100点を目指さない
→30点から加筆・修正しブラッシュアップする
→結果その方が短い時間で高いクオリティの物が出来る
●生理的反応や脳の性質・限界には争わない、それを踏まえた上で対策を講じることが肝。
●やっぱりTO DOリスト。可視化、意識化、情報の整理。
【思考編】
キーワード:自己洞察力
●入力・出力の対策は即効性があるが対処療法
●思考の対策は根治療法
○思考法3ステップ
1.4つの原因(集中力・注意力低下、ワーキングメモリー低下、脳疲労、脳の老化)が正常かモニタリング
2.原因探究
3.対策
○脳疲労している人は、自己洞察力低下している
→他人に指摘される状態は脳疲労を起こしている。他人の意見を受け入れる、可視化(客観視)する必要あり。
○思考力↑は、自己洞察力↑
→日記を書く(今日1日の辛かったこと、楽しかったこと3つずつ)
※ポジティブな感情で終わる為に上記の順で書く
○2回同じミスをしたらチェックリスト・持ち物リスト作成のサイン
○ミスをした後の対策を考えておく
→『ミスしたらどうしよう』は脳を疲弊させ余計にミスを招く為、ミスしてもリカバリー出来る策があることで自身を持って行動出来る
ミスをしたら対策を予定通り行うだけ
○今の状態は何点?朝の調子は何点?
→数値化することで自問自答する機会をつくる
●内省傾向にある人は自己洞察力が高い
ただ間違った課題・思考に注意を向けると無力化するかも。
●ミスすることも計算のうち。脳の限界、自分の能力に争わない。
●またまた可視化。日記、チェックリスト、自己採点。人は一気に沢山記憶できない。
【整理編】
●キーワード:脳の整理、ストレスの整理、睡眠
○脳の記憶の棚卸し(逆ツァイガルニク効果)
→アウトプット済みの本などを片付ける
→記憶を消して(気分的に)インプットする容量を確保する
○ぼーっとする時間を作る
(創造性の4B:bathroom、bus、bedroom、bar)
→デフォルトモードネットワーク
→通常の15倍脳が活性化している
→アイデアが生まれやすい
○失敗は反省・課題整理して忘れる、成功は噛み締める
○ストレスの整理
ストレス:コルチゾール増加→血糖値増加→認知症を引き寄せる
また、海馬の機能を抑制し、記憶力を低下させる
慢性的なストレス:コルチゾール減少→集中力低下
○対策として睡眠時間を+1時間する
→作業・パフォーマンス向上する
○笑い→アドレナリン減少(副交感神経↑)
○酒でストレス解消しない
→運動+睡眠がベスト
→睡眠は感情と記憶を整理する
→交感神経と副交感神経の切り替えが大事
●脳の中にいっぱいに詰めしこまずに、一旦出す(脳を空にする)事も重要
●忙しい人ほど睡眠を大切にする
●睡眠は未病からの脱却
【before】
何故読もうと思ったのか?
仕事も家庭もしょうもないミスややり忘れが多発していた。やるべき事を確実にこなす必要性を強く感じていた。
1.ミスをしない方法を知りたい。
2.ミスが起きる背景を知りたい。
【after】
何を学び、気付いたのか?
1.ミスをしない為には論理的な思考・理解・対策が必要
→ミスの背景には入力・出力・思考・整理の側面があり、それぞれに対策がある(個人で問題になる部分が異なる)
僕は昔からのミス・忘れの常習犯
→ミスによる焦りがミスを招く、やるべき事を記憶に依存しがち
2.内省傾向は高い方だと思うが、思考すべき事が違っていた
→4つの原因にフォーカスしてなかった
→弱点の克服をしようとしていた
→ミスする事を踏まえた対策は講じてなかった
3.絶対TO DOリスト、チェックリスト・持ち物リストは必要
【TO DO】
どう行動するか?
1.絶対TO DOリスト、チェックリスト・持ち物リストを作る
→行き当たりばったりにせずに準備・計画性を持つ
2.ミスや成功を都度都度立ち止まって分析する
3.未病の状態からの脱却は、リハビリの観点からも重要。生活習慣・睡眠・思考等その方に合った方法でマネジメントする
●ワーキングメモリーの最大活用9つを見れば見るほど、キャンプを想像する。
●脳や感情を常に整理し、ストレスフルな状態でい続けられるよう心掛けたい。
●自身の健康管理を客観視・客観的に評価する事を心掛けたい。
読んでくださり、ありがとうございました!
是非本書も読んでみて下さい^ ^
Amazonオーディブルだとながら聴きが出来るので忙しい人にはオススメです!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
