
東京外国語大学大学院学生さん達と「パーパスフルなキャリア」について講演会実施
先日、東京外国語大学大学院のキャリアパスについて情報を広めるMIRAIプロジェクトにご招待され、Project MINT代表の植山が講演をさせていただきました。
当日の講演会では、「パーパスの言語化とパーパスフルな働き方の実践方法とは?」というテーマでワークショップをオンラインで開催しました。
<当日の主なコンテンツ>
パーパスとは何か?
パーパスを言語化する方法
個に通じるパーパス
組織に通じるパーパス
社会に通じるパーパス
まず初めに、植山の自己紹介から入ります。
植山がなぜ大学院(ミネルバ大学院)に進学したのか?サラリーマン時代を経てからの転換点やそれには、幼少期の体験が大きく影響したこと、そして大人向けの21世紀型教育を浸透させるためProject MINT創設まで、どのように一歩を踏み出していったのかについて語りました。
学生さんからは早速多数の質問がチャットに埋め尽くされました。
「植山さんの人生のターニングポイントでロールモデルとなった方はいらっしゃるのでしょうか?」
「子ども向けの教育と大人向けの教育の共通点・相違点は何でしょうか?」
「なぜ大人向けの教育をやりたいと思ったのでしょうか?」
などです。
植山からは、
今のVUCA時代で働く環境は大きく変わったのに、教育現場は、ここ100年ほど変化がしていない現状をまず知ったこと。
そこで、学んでいくということが、これからの働き方を見据えていないのではないか? という疑問点から始まったこと。
植山自身がミネルバ大学院で、自分が21世紀型のアクティブラーニング環境での学びに2年間どっぷり浸かることで、不確実な課題に自分なりの答えを見出す重要性を感じたこと。
そして、自分なりの答えを出していくには、自分の内側のパーパスに耳を傾けることが大切だと気づき、Project MINT創設に至った話をしました。
パーパスとは何か?
ワークショップの本題は、まず「パーパスとは何か?」から始まりました。

パーパスとは、継続的に、長く(ほぼ永久的に)循環していくもの。一方、ゴールは的を定めた対象物が達成されたら、なくなるもの。
これをキャリアに置き換えて考えると、ゴールでは、「5年以内に年収100万円あげる」など客観的なゴールで、明確な期間内で設定することに対し、パーパスは「私は笑顔の循環を創り続ける」など、自分の主観的な指針に対して期限を設定せず自分の内側の中で掲げていきます。
一方、パーパスはその人の大切な指針となり永続的に存在し続けるものですが、その人のライフステージの変化や行動を通して新たに見えてきた境地から、パーパスの言語化する表現方法は変わってくることなども伝えていきました。
パーパスを言語化する方法 - 個に通じるパーパス編
まず、パーパスを言語化し、関係者や周囲の人に伝えていくことが大切になってきます。それが共感を生み出し、協力者を得ていき、自律的なキャリアを築いていく上で大切なことになります。
そのためには、まずは自分自身で、個に通じるパーパスをじっくりと内観し腹落ちした状態で言語化していくことが最初の一歩となります。

個のパーパスは、自分の内側の中に存在します。パーパスドリブンリーダーシップ理論の権威、ニッククレイグ氏は個人のパーパスはこの3つの領域を融合したもの、それを個人が自分が腹落ちした状態で言語化していくこと、と唱えます。

自分の奥深く眠るニーズや価値観を言語化していくには、ひとりで行っていくのにはどうしても自分の思考の癖があり、奥深く迫っていくには限界があるので、他者と対話をすることにより新たな自分の価値観を見つめていきます。
学生さんからは、
「まだ自分のパーパスがわからない状態で、他者には話せない状態だと思っていたから誰かに打ち明けることはためらってました。」
などの気づきがあったとコメントをもらいます。
パーパスを言語化する方法 - 組織に通じるパーパス編
個人のパーパスを、自己理解を深め言語化した後は、関わっている組織(勤めようとしている会社など)に通じるように自分のパーパスを言語化していきます。
そうすることで、その組織の人との相互理解を深めるだけでなく、自分がなぜその組織と関わっているのか、と意味付けをしていく上で重要となってきます。
ポイントは、"自分のパーパスと組織のパーパスが最初から全て合致するという前提でいないこと" です。
自分のパーパスは、自分のこれまでの人生の原体験でしか培うことができないので、自分のパーパスと組織のパーパスが完全に合致することはないということを理解することが大切になります。
そこを念頭に置いた上で、組織のパーパスから感じられる重要なエッセンスを5つ抽出し、自分のパーパスの重要なエッセンスと重なる部分を特定していきます。
その共通部分を言語化し、組織の人に自分のパーパスを紹介するときに、組織のパーパスの重なり部分を意識して言語化していくテクニックを紹介しました。

そして、組織の中のタスクで、自分のパーパスを体現できる仕事やプロジェクトを創り出したり、選択していくよう、ジョブクラフティングをし続けていくことの重要性を話します。
パーパスを言語化する方法 - 社会に通じるパーパス編
最後に、自分のパーパスを社会に通じるように言語化をしていくことで、自分が個人として、組織を超えてどんな土俵にいて活動をしているのか、ということを明確に発信していきます。
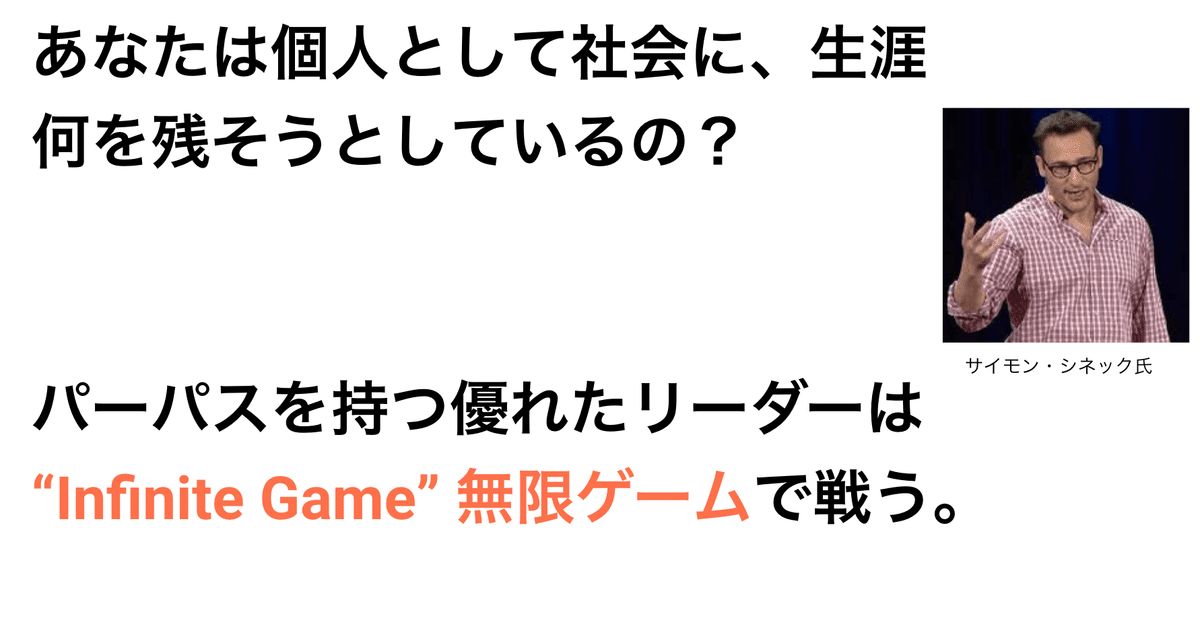
どんな果てしない無限ゲーム(すぐに解決しようがないが、大きな意義がある社会と自分がつながるもの)に取り組んでいるのか、を言語化していきます。
「市場競争に勝つ」「No.1になる」
ということではなく、
どんな普遍的な大きな意義に対してインパクトを残そうとしているのか?という意義を語ることです。
「人々の生活をより豊かにしていく」
などの言葉が出てくるイメージです。
他者を意識したゲームではなく、自分自身のゲームを突き進んでいく、ことです。
それを言語化していくことで、あらゆる組織の方からも、自分が何を目指そうとしているのか、を伝えることができます。

以上、盛り沢山な内容で、ワークショップを終え、学生さんからは、大変学びになった、と感想のコメントをもらいました。
<学生さんからのコメント>
アカデミアはまさに「有限ゲーム」の世界ですね。
パーパスは誰もが違う。個人的なもの。分かってもらえるものとは違う。パーソナルなものなんだ、ということが大きな発見でした!
ご紹介されたパーパスを伝えるイベントを、私たちの合宿でも是非やりたいです!
パーパスを見出す過程で、他者と対話することが重要なのだとわかることができ、とっても大きな気づきになりました。早速誰かに話してみたいです。
<Project MINT代表植山の感想>
今回の機会を創っていただいたのは、東京外国語大学に勤務されるMINTの修了生です。
彼がパーパスフルな道に進まれている姿も見られて、MINTの受講後のパーパスのさざなみが創られている実感が持て、この上ない幸せな気持ちでした。
その修了生は、彼のパーパスである、「対話の囲炉裏の場を作る」ごとく、まさに学生さんたちの火を灯す囲炉裏を創られていらっしゃる場に共に過ごすことができました。
これから学生さんたちが、自分の内なる可能性に向けて気づき、どんどん周囲の人を巻き込み幸せのさざなみを創っていくことをしていくことを願っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
