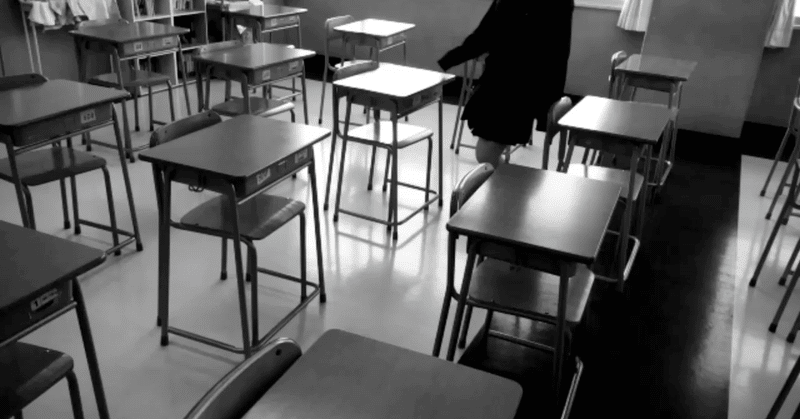
新書から考える(1) 「友だち地獄」(1) 〜私が疑問を持つに至った過程〜 #4
お久しぶりです。
この1年、明らかに私は本を読むことが増えました。
家にいる時間が長くなり(というか1日のほとんどを家で過ごすようになり)、自由に使える時間がかなり増えたこともありますし、正直画面越しでしかつながれず、本当に心と心が通じ合っているのかも分からないようなオンラインでの集まりにもほとほと疲れ果てたということもあります。
私が高校の入学前説明会に行った時、校長先生は「本を読みましょう。内容は何でもいいから、1冊新書を読みましょう。」と壇上で仰っていました。そして、私が1年生だった時、出席番号順で各クラス1人ずつが校長室に集められ、校長先生や他クラスの生徒の前で、自分が読んだ新書の説明やおすすめポイントを話すという行事がありました。つまり、各クラスで出席番号が1番の人が一緒に集まり、次の日は2番の人が一緒に集まり、次の日は3番の人が一緒に集まり…という感じで、1年生全員がそれに参加した訳です。
当時私はそこまで読書に興味がなく(多くの生徒も多分そうだったと思いますが)、正直何のためにこんなものをやっているんだろうと思っていました。
今、ようやっと読書のおもしろさが分かるようになりました。
読書をすることで広がる世界がありますし、分からないことも分かるようになりますし、やはり知的好奇心がくすぐられるのでいい刺激になります。
さて、私は本は本でも、やはり新書を主に読んでいます。
新書を読むと、やはりさまざまな気付きを得られる訳ですが、最近、読んで終わりでは、その気付きが自分の中で確かなものにならないような気がしてきました。そこで、読んだ新書の内容を自分の中で噛み砕くとともに、自分がひそかに疑問に思っていることに紐づけて考えていきたいなという欲望が芽生えてきました。そこでこのnoteで、これらについて論じていきたいと考えています。
1 今回考える疑問
今回考える疑問は、
「なぜ若い世代は、つながっていたいのか」という疑問です。
この疑問は以下のような点から生まれました。
(1)令和元年度青少年のインターネット利用環境実態調査(内閣府)の調査結果
高校生で、1日3時間以上インターネットを利用すると回答した人が66.3%おり、全体の3分の2を占めます。また「保護者・友人とのコミュニケーション」にインターネットを利用すると回答した青少年は、1時間未満が64.8%である一方、1時間以上2時間未満は23.9%、2時間以上と答えた人も11.3%いました。
3人に1人がコミュニケーションツールに1日1時間以上を費やしているという回答結果からも、若い世代にとって、LINEやTwitter、Instagramなどのコミュニケーション・ツールは重要なものであるということでしょう。
(2)ネット依存とSNSについてのニュース記事
また、中学生や高校生の頃、インターネットの正しい使い方について学ぶような授業がありました。そこではSNSでのコミュニケーションに溺れて時間を浪費してしまうような例が紹介されていました。「常にコミュニケーションをとっていないと落ち着かない」「すぐにメッセージを返信しなければ仲間外れにされる」…そのような例は極端かもしれませんが、しかし確実にそのような「SNS・ネット依存」状態か、あるいはその一歩手前の状態にいるような若い世代はいると、その時感じました。
上の記事では、ネット依存傾向の若者について記されています。本記事における調査では、ネット依存傾向の高い若者については、高校生が9.2%、中学生が7.6%、大学生が6.1%の割合でそれぞれ確認されたとしており、また、依存傾向がある人のうち、52.1%が「SNS上の人間関係に負担を感じている」と回答したとしています。
当時私が感じていたように、ネット依存の若者は確実におり、しかも半数以上がSNSでの人間関係に負担を感じているのです。彼らはSNSが楽しいのではなく、没入せざるを得ない状況に追い込まれているのではないでしょうか。
(3)周囲の学生の動き
私の身の回りにいる学生たちの動きからも感じました。
大学で通常通りの新歓ができないこともあり、オンラインでそれをやろうという動きが、全国の大学で広まったと思われます。私が通っていた大学も多分に漏れず「オンライン新歓」なるものが行われていました。
私は1年生だったので新歓「される」側でした。当時私は新型コロナが年単位の長期戦になるとは思っていなかったので、「そこまで焦る必要もないんじゃないか」と渋々思いながらも、「でも一応参加してみるか」くらいの気持ちで、それでものべ十数回参加していました。
楽しかったは楽しかったのですが、やはり画面越しの勝手のきかなさはありましたし、心が通じ合っているのかも分からないような感覚に陥ることもありました。そして何より、「そこまで焦る必要もないんじゃないか」というような気持ちが生じたように、当時は「なぜそこまでつながりたがるんだろう」という思いが芽生えたのです。
寂しいからという理由もありますし、部活・サークル側からしたら早く新入生を取り込みたいという理由が大きいでしょう。しかしそれでも、「なぜそこまでつながりたがるんだろう」という思いが拭えなかったのも事実です。
勿論、つながっていたいのは若い世代だけではなく社会人も同じであろうし、今年は特に対面で会えないからという理由で、いっそうつながろうとする動きが加速したと思われます。そこはあらかじめ断った上で、それでも若い世代のつながり方には、特有のものがあると感じ、またそれに疑問を抱いたので、今回書くことにしました。
2 今回取り扱う新書
今回取り扱う新書は、「友だち地獄ー『空気を読む』世代のサバイバル」(土井隆義氏著、ちくま新書、2008年)です。
宣伝文には以下のように書かれています。
誰からも傷つけられたくないし、傷つけたくもない。そういう繊細な『優しさ』が、いまの若い世代の生きづらさを生んでいる。周囲から浮いてしまわないよう神経を張りつめ、その場の空気を読む。誰にも振り向いてもらえないかもしれないとおびえながら、ケータイ・メールでお互いのつながりを確かめ合う。
つまり、昨今の若者の人間関係が生む生きづらさについて書かれた新書です。ここから、筆者は、現代の若者は誰かを傷つける/誰かに傷つけられることを恐れ、無意識的に気を遣いながら慎重に人間関係を育んでいると指摘しています。
なお、2008年の本なのでスマホがまだ普及しておらず、「ケータイ・メール」と古い言い方になっていますが、現在のSNSに置き換えれば十分でしょう。
この新書に紐づけて、次回以降、疑問と向き合って行きたいと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
