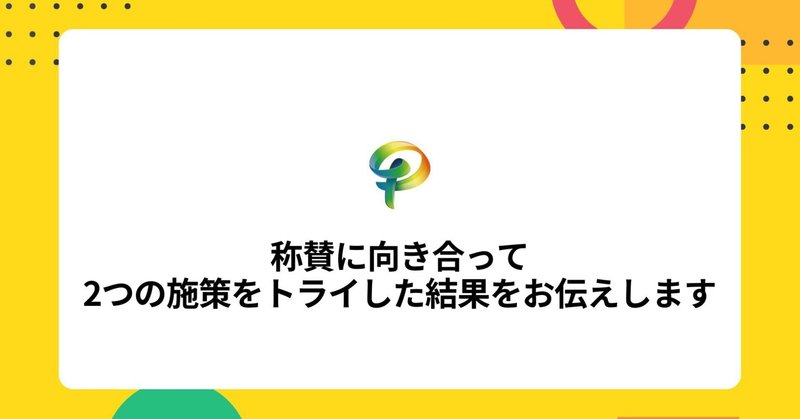
称賛に向き合って2つの施策をトライした結果をお伝えします
「称賛は、いつでもどこでもSlackで実施できる仕組みを作っているけれども、そこまで継続もしていないし、なんかもう少しうまいことやれないかな」
と感じることが直近数年間で多々ありました。
2019年ごろから「称賛」の重要性が高まり始め、ユニファさん中心に「称賛」を実施できるツールも増えて参りました。当社は割と、フィードバック文化は浸透しているのですが、「称賛」を積極的に実施する企業ではこれまでなかったので、そのカルチャーを作るべく称賛のツールを入れていたのですが、いまいち浸透していないのが本音でした。
ただ、2022年の11月から2つの称賛についての取り組みを実施してみたところ良い効果が生まれましたので、その内容を共有したいと思います。
0. 「称賛」の効能
「称賛は大事だ」と耳にしたことがある方がほとんどかと思うのですが、どのような効能があるのかを数値でご存知の方は多くはないかと思いますので、下記のデータをご覧いただければと思います。



こちらは、アメリカにある企業の調査結果になるのですが、この2つのデータを見たときに「本当か?」と思ったのが本音ではあるのですが、これが実態なのであれば、称賛をする仕組みを積極的に取り入れない手はないなと感じておりました。
ちなみに蛇足ですが、僕自身はメンバーに対して厳しいタイプだと思います。「よくやった」「すごかったぞ」という言葉をかける回数は、一般的な社会人と比較すると少ない方だと思っています。それでも、本当に頑張ったな/すごかったなと思うメンバーに対しては伝えるようにしているのですが、その回数が少ないと個人的にも思うことがあります。
繰り返しになりますが、上記のデータを拝見すると、称賛は仕組みとして取り入れるべきであり、社員のモチベーション向上、そして定着率の向上のためには意図的に、積極的に取り入れるべきだと感じておりました。
1. 「称賛」のツールを導入したのですが…
おそらく10社中9社が当社と同じような事態になっているのではないかと思うのですが、「称賛」のツールを導入したのはいいものの、そのツールを使って「称賛」をするメンバーはほとんどいませんでした。
ほとんどいません、というよりは、導入直後はメンバーが興味本位で称賛を送り合ったりするのですが、1週間経過すると半減、そしてまた1週間経過するとまた半減する。1ヵ月も経過すれば1週間で称賛が0件なんてこともざらにありました。
ただ、無理に称賛を実施してもらうのは本質的ではないと思っていました。「1日1回、必ず称賛してください」と言うのも、称賛する場面/相手がいなければあまり意味がないものだと思っていたのが本音でした。
2. 「リアルタイムフィードバック」との出会い
本ブログでは「称賛」にスポットを当てているのですが、当社のカルチャーの1つである「フィードバックを積極的に実施する」については浸透しておりました。ちなみに、フィードバックをするときは「良い点」と「改善点」に分けて実施するようにしていたのですが、シンプルに考えるとフィードバックにおける「良い点」は「称賛」と近しいのではないかと思ったのは、1つの気づきでした。
話が拡散するのですが、当時2022年の夏ごろに「ノーレイティング」という人事制度の在り方と出会いました。詳しくは、下記ブログをご覧いただければと思うのですが、ノーレイティングとは「評価しない」というわけではなく「ランク付けをしない」という人事評価の在り方です。これまでSランク、Aランク、Bランク等、半期に1度社員をランク付けしていたかと思うのですが、それは撤廃して「出来る限りリアルタイムにフィードバックはするんだけれどもランク付けはやめよう。なぜならば、時間と工数がかかるし、ランク付けをすることによるメンバーに対してのネガティブな影響が大きいから」という理由でした。
なぜノーレイティングの話をしたかというと、ノーレイティングを理解するために、僕の大きな気づきが「リアルタイムフィードバック」でした。人事評価面談を半年に1度実施している企業は、半年に1度メンバーに対してフィードバックを実施していると思います。最近では1on1ミーティングがトレンドになって参りましたが、月に1回程のペースで実施している企業は、月に1度フィードバックをしているかと思います。月1回ペースのフィードバックが多いのか少ないのかという議論はあるのですが、個人的にはフィードバックは「リアルタイム」であるべきだと強く思っています。なぜならば、フィードバックを受ける側からすると、数週間前、数ヶ月前の事象に対してのフィードバックを受けてもピンとこないですし、その時間的なギャップが無駄だと思うからです。
つまり、メンバー同士で限りなくリアルタイムにフィードバックを送り合う文化を浸透させて、その手段として称賛のツールを使おう、という説明を社員にすればより浸透するのではないかと感じたのです。
3. 毎朝5分間、誰か1人に対してリアルタイムフィードバックをしよう
2022年の11月に、当社の2つの事業部で試みた施策です。個人的には「称賛」よりも「リアルタイムフィードバック」と称して実施するほうが、当社の性にはマッチするかなと感じていました。ただ、やはり「称賛」をするためのツールを用いていたので、称賛に内容が寄っていったのは事実ではあります。
ただ、目に見える効果は出ており、1週間で65程度の「称賛(リアルタイムフィードバック)」が生まれており、昨年対比で23.4倍の数となっておりました。11月の1ヵ月間の合計数としては250程度になっており、この時期の数が当社設立以降は爆発的に多かった事は言うまでもありません。
4. 補足
ここで当社メンバーにも伝えていない補足ができればと思うのですが、先ほどからリアルタイムフィードバックと称して説明しておりました「称賛」について。どうしても下のメンバーから上のメンバーに対して、リアルタイムフィードバックを送る数が少なくなる事は予想しておりました。
称賛ツールを使うと、如実に称賛の数が見える化されます。そのため、どうしても称賛の数を得たメンバーにスポットが当たるのは致し方ないことではあります。そんな中 前述した通り、どうしても称賛は当社の年次が短く、アグレッシブに仕事をしている人に送られる傾向があります。なぜならば、年次が短いメンバーのほうが、どんなアクションをしたとしてもアグレッシブに評価されることが多いからです。ちなみに、僕も前職の時に「今月はものすごい活躍したな」と正直自画自賛をした1ヵ月があったのですが、称賛を1つももらえず「あれ?」と感じることもありました。
何が言いたいかというと、「称賛を用いることで、限りなく全メンバーが幸せになる事はできるものなのか」という課題に直面いたしました。
冒頭に記載いたしましたが、称賛を受けているメンバーのモチベーションや定着率は上がるというデータが既に出ています。そして「称賛」のツールを用いて称賛の仕組みを導入すると、年次が短いメンバーに称賛が集まることも当社のカルチャー的に分かってきました。これを継続するか否かのジャッジが必要だったのですが、2022年の12月は一旦この称賛の仕組みをストップしておりました。
5. これまでの称賛についての課題整理
様々な称賛にまつわる施策を投じてきたのですが、これまでに感じた/直面した課題を整理してみます。
(解決) 称賛をするカルチャー形成
(解決) 称賛をするためのツール/仕組みの形成
(解決) 称賛をする時間の確保/称賛数の増加
(未解決) 全メンバーが同じように称賛を受け取ることができる仕組み化
誤解がないように申し上げると、仮に精一杯頑張っていないメンバーがいた場合、そのメンバーが称賛を受ける事は難しいでしょう。なぜならば、頑張ってる姿も見えないですし、称賛する側からしてもする理由がないからです。ただ、自社を棚に上げて話をすると、当社において頑張って「いない」メンバーは限りなく少ないと個人的には思っています。頑張る「尺度」には違いもあるかもしれませんが、それは個人差であり、頑張っているという姿勢についての称賛は必要だと考えていました。
そのため、全メンバーが称賛を受ける仕組みをどのように作っていけば良いのかと感じていました。また、個人的にはもう1つ課題を感じておりました。それは、
「称賛に温かみがない」
デジタルネイティブの時代において、称賛するという行為において、PCやスマートフォン、ツールやアプリを使わない選択肢はないと思っています。ただ、Slack上で「称賛を受け取りました」という通知が来て、文章が書いてある。その文章を読むと自分への称賛が書いてある。もちろんこれは嬉しいことであり、嬉しいことを表現するスタンプを押して反応する。もしくはスレッドにて嬉しい旨は返信する。そういった行為がなされているかと思います。
これは僕個人的に感じた事なのですが、この一連の行為に対して、人間と人間がコミュニケーションを取り合う温かみを感じていないのは事実でした。僕は今37歳で社会人15年目になりますが、これまでの人生において称賛を受け取るのは「対面」が普通でした。「対面」で受け取る称賛と「デジタル」で受け取る称賛を比較すると、「嬉しさ」の度合いで言うと体感値としては2〜3倍くらい「対面」の方が勝っていたと感じておりました。
6. 悩んだ上で実施した「対面」での称賛機会の実施
当社は、社員総会や忘年会の前に全社員におけるワーク時間を確保しているのですが、これまではミッション/ビジョン/バリュー/カルチャーについて全メンバー間で鑑賞する機会をとっていました。
ただ、今回は良い機会だと思い、1時間半程度の時間を使って全メンバーが称賛を送り合う場を対面で実施してみることにしました。
どのように実施したかを共有できればと思います。
6-1. 称賛相手の振り分け
今回の目的の1つに全メンバーが称賛を受け取り合う、と設定しておりましたので、各メンバーが称賛相手を自由に選ぶことができると、結果的に称賛相手が固定化されてしまうと感じておりました。
そのため、全メンバーを事業部ごとに羅列して、誰が誰に称賛を送ると全メンバーに行き渡りやすいのかを振り分けてみました。

上記は実際の振り分け表になるのですが、称賛相手については近すぎず遠すぎずと言いますか、日頃の仕事で接する者同士のメンバーを中心に、少しだけ離れたメンバーも選定しておりました。
6-2. 自由枠の設定
称賛相手を会社側できちっと設定してしまうと、そのメンバーが心から称賛を送りたい相手に送ることができません。そのため、2名のみ「自由枠」を設定し、各メンバーがそれぞれ送れる余地を作っていました。
6-3. ポストイットの活用
これはよくあることかもしれないのですが、メンバーが称賛を送り合う際に使用したのはポストイットでした。ポストイットに称賛の文章を書いてもらい、これを対面で渡すことを想定していました。繰り返しになりますが、デジタルの活用は今回は避けていました。
6-4. 称賛の贈呈タイム
ポストイットに書かれた称賛のメッセージを、称賛相手に贈呈する時間も確保しました。これは、各メンバーが称賛相手を社内で見つけて、その場でポストイットに書かれた全文章を読み上げてくれ、という設定にしていたのですが、正直照れくさい文章を書いていたメンバーが多かったため、皆 照れ臭そうに文章読んでいました。はにかんだ表情をしているメンバーが多かったことが印象的でした。
7. メンバーへのアンケートの実施
この時間を終えて、個人的には想定通りの効果は得られたのかなと思っていたのですが、称賛を送り合ったメンバーはどのように感じていたのかを知るためにアンケートを実施してみました。アンケートは下記のような内容です。

そして、結果についてもこの場で共有できればと思います。
平均満足度:9.5
意見:
- 普段面と向かって言うのが難しいことも言葉にして伝えることができた。
- 照れ臭かったですが、普段思っていてもなかなか言えないことを伝えることができて温かい気持ちになりました!
- こんなところを見てくれていたんだと気付かせてくれたのが嬉しかった、これから自分の伸ばしたい方向性の一つを考えられた。
- ながら作業で賞賛や御礼を送るのではなく、「何かを伝える」ということに向き合えた良い時間だった。
この結果については、個人的には想定以上の数値となりました。
最後に
皆さんいかがでしたでしょうか。
※当社の採用/人事組織系支援にご興味がある方はお気軽にお声掛けください。
最近リリースしたポテンシャライトのノウハウを取り入れたATS Opela(オペラ)にご興味をお持ちの方はこちらよりご連絡ください 👇
今後も採用/人事系のアウトプットを続けていきます。
よろしければフォローもよろしくお願い致します(左上クリックいただき、「フォロー」ボタンがあります)👆
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
