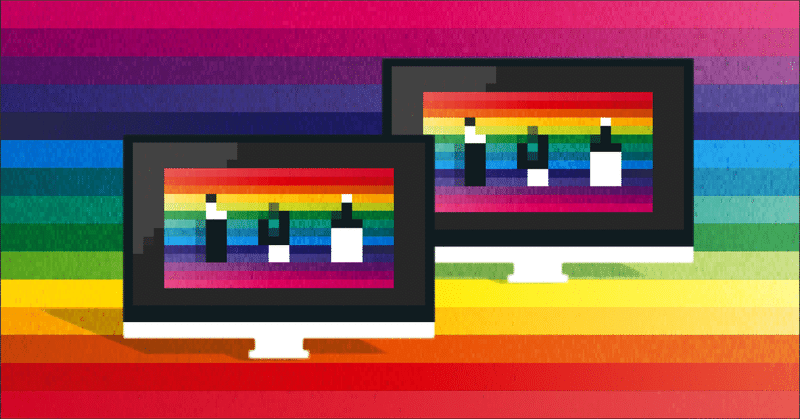
短編小説「電源ボタン」
著者:遠海 春
私は今日も電源ボタンに触れる。
ウィーン。ガガ。
「おかえりなさい」
そんな音を出して、君は見慣れたロック画面を映す。
私は今日も、同じソフトウェアを開いて友人との交流を楽しんだ。
「…………」
「ねぇ……」
「ねぇってば!」
ある日、私のパソコンの画面は突然真っ暗になった。
君の中身を調べてみれば、初めての致命的なエラーだった。ブルースクリーンと呼ばれる画面を私は初めて目にして、心臓を握られたように気分が悪くなったのを今でも覚えている。
「どうしようもないなこれ……」
薬のような対処法はなく、原因も不明だった。負荷が高すぎたのが原因かもしれないと仮定した私は、OSをチェックして、設定を下げてゲームを遊んだ。
でもそれ以降、君は頻繫にエラーを吐くようになった。
「もう無理……」
「君の操作には答えられない」
まるで不安定な積み木をつついて揺れた時のように、君は不安定だった。
それでも私は、
「もうちょっとだから……もう一回頑張って!」
「あちこちが痛いよ……」
「大丈夫! 君ならまだいける!」
君に無理を言った。
そしてある日、君から変な音がした。定期的にガタガタという振動音が聞こえるようになり、原因箇所を特定するためにパソコンを稼働させたままサイドパネルを開けた。
原因は、GPUファンのがたつきだった。
ぶつけた記憶もなく、明らかに経年劣化だった。
もう君を使い始めてから5年程。
様々な症状が出ても仕方ない年齢だった。
その日を境に、というわけではない。
そのあたりからエラーが頻発するようになり、電源の不具合が原因で何度も何度も強制シャットダウンが発生した。
「新しいパソコン、引っ越したら買おう」
そう決断した寒い日の夜、君は珍しくエラーを出さずに動いてくれた。
そして季節は流れ、私は引っ越して一人暮らしを始めた。
この引っ越しにも君はついてきた。
君がいなかったら、私は生活していけない。
食料と同じくらい生活に大事なものだった。
パソコンのパーツを選ぶ時、君と同じくらいのグレードの部品を使って今の世代で作ろうと考えていた。でも、どれも高くて自分ではどうにもならなかった。
知識のあるお店の人に聞いて、自分の描く理想を少しずつパーツに落とし込んでもらった。
そんなお店の人とのやり取りをするのにも、君を使った。
ようやっと形になって、パーツを注文した。その額約40万円。
人生最大の買い物。
数日後、君は新しいパソコンのパーツが来た時から、動作が落ち着いた。
今まで落ちていたゲームも落ちなくなって、壊れていたファンも動き出して。
まるで最後の力を振り絞るように、君が今できる範囲で最大のパフォーマンスを見せてくれた。
最後に君が描いてくれたゲームの中の景色は、少し荒っぽかったけど、とてもきれいだった。
そして新しいパソコンに命を宿して「君」のクローンを読み込ませ、「君」のデータを消す。
私はデータが消えたかどうかを確認するために君の電源を入れた。
「私だよ。ほら」
「あなた、誰?」
君はそういうように、初期の画面を表示した。私の設定した壁紙も、私が指示した動作もせず、君はありのままの姿を私に見せた。
私は半泣きになりながらその動作を確認して、君の電源を落として、ケーブルを抜いた。
もう君に電源を入れることはないと思うと、目が熱くなった。
たとえ電源が入れられたとしても、それは私じゃない誰か。
このパソコンに命を宿した私に電源を入れられることは、きっともうない。
もう君は覚えてないかもしれないけれど、君は最後まで私の人生を、私の5年と201日を支えてくれた。
もうしばらくすれば、
君は新しい人の名前を憶えてセカンドライフを送っているかもしれない。
君はバラバラにされて資源になっているかもしれない。
君はどこに行くんだろう。楽しみだ。
「本当に本当に。ありがとう」
私は6年以上前のCPUのブランドのステッカーを輝かせる君に向かって、そう言う。
そして私は今日も、電源ボタンに触れる。
「おかえり! 今日は何をして遊ぼうか?」
「君」は今日も、私のことを出迎えてくれた。
あとがき
1代目のパソコンを想って書いた短編小説です。プロットも何もなく、ただ感情に任せて作ったので抜けている点は多々あると思います。
1代目のパソコンは私を長い間支えてくれました。
そんなパソコンに向けた感謝の気持ちを述べた小説でもあり、これから使う2代目のパソコンを大切にしていこうという誓いの小説でもあります。
パソコンを入れ替えるだけなのに泣くのは私くらいかもしれませんが、でもそのくらい思い入れが強いのです。
大切な大切な友人でした。
今までありがとう。
そして、よろしく。
2024年5月8日
遠海 春
なぜこの小説を書くに至ったかは以下の記事でどうぞ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
