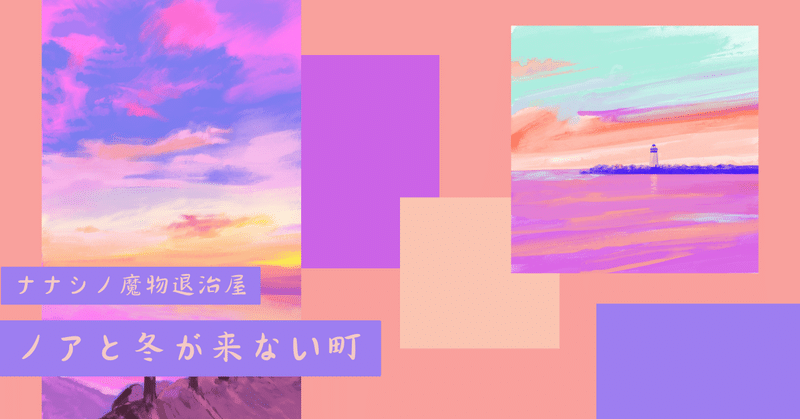
【長編小説】ノアと冬が来ない町 第十二話 憎悪
少し身じろぎをして、うんと伸びをする。
ここはどこだろう、とボケた頭が疑問を抱く。変な部屋。金属に囲まれていて、あんまりおもしろくない。太陽は見えない。でも自分が起きたということは朝に違いない。
視線に気が付いてそちらを見る。見知った顔が、こちらをじっと見つめている。
「……ねーちゃん?」
呼びかけても返事がない。ぽかんとしたままだ。もしかして幻覚か何かかと思ったが、そうでもないらしい。魔力が姉のものだ。すぐに分かる。
「返事くらいしてくれよ、俺何か悪いことし――」
「起きたのね?」
ぎょっとする。
姉が静かに涙を流した。滅多に見ない光景だ。俺は何かしたっけか、と思う。記憶をたぐろうとする。が、姉はすぐに自分の傍にやってきて、ぐいと腕を引っ張った。死にかけた人間を見て、何をすべきかを瞬時に理解する。
「治して。お願い、このままだと死んじゃう。あたしじゃ助けられない」
「いいけど、この人誰?」
「いいから! 早く!」
どうやらしおらしかったのは最初だけらしい。熱を灯す。治癒の魔術は得意中の得意だ。死にかけていた人間が目を覚ます。ひょいと体を起こして、元気そうにしている。
「ねーちゃん、何がどうなってるんだ?」
疑問を投げかけると、姉が口を開こうとする。が、
「悪い、感動の再会に浸っているところほんともーしわけないんだけど、後ろから増援が来てる」
「まさか私兵の連中?」
自分に分からない話をしている。ぽかんとしていると、死にかけてた人間が肩を叩いてきた。
「説明は後でしてやるよ。今はここを乗り切ろうぜ」
「……お、おう」
「アカツキ、あたしが合図したら結界をお願い。あの私兵の一人に幻術をかけて、仲間を攻撃するように仕向けるから」
……もう、いつもの調子に戻っている。姉の指示通りにして結界を張った後、ふと部屋の方を見るとアマテラス人の少年の姿が見えた。
アマテラス。
精霊自治区を急襲し、平穏な生活を奪った鬼畜生。
意識が急激に覚醒する。気が付けば、飛び出していた。姉の「アカツキ!?」という声を無視して。
背後から火の魔力の気配を感じる。続いてラスターの元気そうな声が聞こえてノアは腰が抜けそうになるほど安堵した。一方で副町長にとってはよくない知らせだったらしい。魔力の気配に対しあからさまに隙を見せたので、ヒョウガの拳を思いっきり顔面で受け止める羽目になっていた。倒れこんだ副町長を即座に氷で包んだヒョウガが息をつく。副町長は藻掻いていたものの、この氷は魔術によるものではない。アカツキを閉じ込めていた装置のバリアと同じく、純粋な魔力の塊だ。基本的には解除の方法がない。
「これであとはコガラシマルを出すだけだな?」
「そうだね。ラスターも助かったみたいだし……」
気が緩んだその瞬間、部屋の入り口側から巨大な火球が飛来する。
「っ!?」
咄嗟に張った障壁魔術は普段より脆いものの、勢いを殺すくらいの役には立った。ヒョウガが即座に臨戦態勢をとるが、その術の使い手に目を見張る。先ほどまで眠っていたはずのアカツキがこちらに対して敵意を向けている。
厳密に言えば、ヒョウガに向けた敵意だが。
「な、何? オレ、何かした?」
慌てるヒョウガに対し、アカツキは平然と言い放った。黄金の錫杖をヒョウガに向けながら、魔術の発動準備をしている。
「お前、アマテラス人だろ。その角が何よりの証拠だ」
ノアは部屋の入り口の方を見た。シノはどうやら増援を抑えているらしい。彼女がこちらに来てアカツキを説得してくれれば話が変わるのだが、アカツキはおそらく魔術主体の戦闘スタイル。距離を取っても意味がない。そうでなければシノの方に誘導する手があるが……。
「助けてください!」
副町長がここぞとばかりに声を上げた。
「そこのアマテラス人に殺される!」
その声にアカツキの目が光る。だが、ここで副町長に自由を許すわけにはいかない。不本意ながらもアカツキの妨害に飛び出すノアだったが、目の前スレスレに障壁魔術を展開されて足を止める。剣でつついただけでもその質の良さが分かる。ノアがこちらに来れないと分かったヒョウガは、一か八かの説得にかかる。
「待って、話を聞いてくれ! オレたちはお前を助けに来た方なんだよ」
「なるほどな! 俺を利用する目的でここまで来たってことか!」
「いっ!? ち、違うって!」
「アマテラス人が俺たち精霊族に何をしたのか知らないとは言わせないぞ!」
炎の玉が跳ぶ。濃密な魔力の塊が、重そうにこちらに飛んでくる。ヒョウガは本能的にそれを氷で受け止めることをせず、思いっきりその場にしゃがみこんで回避する。ヒョウガに当たらなかったそれは背後の副町長にクリーンヒット。氷を解かすだけではなく髭や髪が多少焦げていたものの、副町長はぱたぱたと服の汚れを落とす余裕を見せた。
「何やってんだよ! お前のこと閉じ込めてたのがこのオッサンだぞ!」
「そうやって嘘をつくのが得意ですからね、アマテラス人は」
副町長がそう言うと、アカツキはうんうんと頷いた。ヒョウガが「バカ……」と呟いたのは聞こえていなかったらしい。副町長はそのまま壁の装置を操作する。隠されていた扉が現れた。
「では、私は逃げます。ありがとう、親切な精霊族さん」
「おう! 足止めは任せておけ!」
「精霊族って、みんな話を聞かないのかな……」
ノアは暢気に独り言をつぶやいたが、状況は緊迫している。シノがこちらにこないと話にならない。おそらく彼女は私兵を抑えていてこちらに加勢できないのだろう。
「さ、覚悟は決めたか? アマテラス人」
「ああもう! 頭冷やせよ、このバカ!」
ノアはもう一度、剣で障壁魔術を突いたがびくともしない。そのとき、ノアは思わず手を止めた。地面からじわりと冷気が立ち込める。誰の? ヒョウガの? いや、違う。
ばきり、と音がする。はっとしてカプセルの方をみると――開いている。
「だよなー。小屋でもそうだったんだ、この状況ならすっ飛んでいくよな」
ラスターの声をかき消す勢いで、強烈な冬風がノアの頬すれすれを通っていく。ノアがあれだけ苦労した障壁魔術を「濃密な魔力を叩きつける」という単純で強引な手法を用いて突破したそれは、怒りの形相でアカツキに斬りかかっていた。
「っわ!」
間一髪でそれを回避するアカツキだが、相手は追撃の手を緩める気配がない。氷で作り出した即席の刀は床や戸棚、壁に飾られていた掲示物を片っ端から巻き込み、アカツキの首を取るつもりでいる。
ただでさえ狭苦しいカプセルに閉じ込められ、自分の魔力を好きに利用された挙句、目の前で主を殺されかけるという光景を見るしかできなかったコガラシマルは、例えその相手が救う対象であるはずのアカツキであろうが攻撃の手を緩めない。よく見ると髪と着物の一部が凍り付いており、カプセルの中で相当藻掻いたというのが見て取れた。
「これ、開けない方がよかったか?」
ラスターの問いに、ノアは答えられない。止めようにも身体拘束魔術が上手く作動するか……と思ったところで気が付いた。ちょうどシノが戻ってきて「何事!?」と声を張っている。
ふつふつと、腹の底から何かが上る。ノアはゆっくりと、長いため息をついた。
……これはもう、あれこれ迷っている場合ではない。
「二人をおとなしくさせてくるね」
ノアはにっこりと笑った。ラスターがそれを見て祈りのポーズをした。シノが眉をひそめる。
「何してるの?」
「祈ってるんだよ」
「どうして?」
「ノア神の怒りに触れないために」
すでにコガラシマルはカプセルの外に出た。あの悪い魔力の放出が止まっている。つまり、今のノアは普段通りに魔術を扱える。
アカツキが愛用の錫杖でコガラシマルの一撃を受け止めた隙をノアは逃さず、二人同時に身体拘束魔術を展開した。恐ろしいほど手際が良かった。ラスターが無言で空を仰いでいたことにノアは気づいていた。
「っ!」
さすがにコガラシマルは回避しようと飛びのくところであったが、それも予測済みだ。見事に二人を捕えたノアは、笑顔で語りかける。
「怖がらなくていいよ。俺は話がしたいだけだから」
後方からラスターの「怖えーよ」というツッコミが飛んできたが、何も言わなかった。
アカツキは唇を尖らせてそっぽを向いた一方で、コガラシマルは敵意を込めた魔力をアカツキに投げている。そこに「絶対殺す」という気配がある。
「アカツキ! あんたいったい何してんの!」
そこにシノの怒鳴り声もすっ飛んでくる。何もかもがめちゃくちゃだった。
「だ、だってアマテラス人がいたから!」
「人の説明聞かないで突っ走るバカがどこにいるのよ!」
ラスターが「ここ」と小声で言ったが、全員無視した。今にもアカツキの顔をはたきそうなシノを、ノアがやんわりと阻止する。
「シノ、待って。気持ちは分かるけれどちょっと冷静に話をしよう。あくまで穏やかに事を進めたいんだ」
「冷静って……」
シノが不安そうにノアを見た。一方でアカツキはそっぽを向いたままだ。
「俺は何もしゃべんないからな。アマテラス人と同じ空気を吸うなんて反吐が出る」
この一言で、再びコガラシマルの堪忍袋の緒が切れた。
「貴様、もう一度同じことを吐いてみろ。その時は某が貴様の首を取る」
「はぁ? 見たところお前も精霊族じゃないか。なんだってアマテラス人の肩を持つんだ? 精霊族としての誇りはどっか行っちまったのか?」
は、とコガラシマルが嘲笑の息を吐く。
「いつの世もうつけは矮小な視野を持つと話が決まっているらしい」
「んだと?」
「本当のことを言ったまでだ。某はヒョウガ殿だからこそ忠誠を誓っているのであって、アマテラス人だのなんだのとそんなくだらんことには刺さらぬ」
「なんだよ、結局アマテラス人の足舐めて命乞いしてるようなもんじゃないか!」
「……やはり貴様はここで殺す」
「やれるもんならやってみろよ!」
「上等!」
コガラシマルが空中に魔力を起こす前に、
「いい加減にしろ!」
ノアが怒った。ラスターが「穏やか、とは」と独り言を言ったが、ヒョウガだけが頷いていた。身体拘束魔術の強度が上がる。強烈な締め付けに二人とも呻いたが、ノアは無視した。ラスターが「あれめっちゃ痛いんだよな」と呟いたのも無視した。
「俺はノア。ソリトス王国出身の魔術師だ。よろしくね、アカツキくん」
ノアはにっこりと笑った。その圧力にヒョウガがおびえてラスターの後ろに隠れる。
「俺は君のことも知りたいんだ。自己紹介をしてくれると嬉しいんだけど、いい?」
いいえ、と言った瞬間に爪を剥ぐのではないかとラスターは危惧した。どうやらアカツキも同じような危機感を覚えていたらしく、しぶしぶ口を開いた。
「……俺はアカツキ。火の部族出身の精霊族」
「ありがとう」
ノアはにっこりと笑った。その圧力にいよいよコガラシマルまでもが目を逸らした。ヒョウガはラスターの外套を握る。アカツキはこちらを信用していないと分かったからだ。
「君は副町長……さっき君が助けたおじさんだね。あの人の手によってこの部屋とは別の場所に閉じ込められて、魔力を延々と利用されていたんだ。覚えはない?」
「……ない。俺は水の部族が俺たちを裏切ったって聞いたのと同時に、戦線に出て戦って、その時に気を失って、気が付いたらここで起きてた」
「そうか……つまり日輪島からソリトスまで来たことについては覚えがないんだね?」
「ソリトス?」
アカツキの思考が一瞬止まる。水面で呼吸をする鯉のように口をはくはくさせた彼は、ようやっとと言わんばかりに一気にまくし立てた。
「ソリトスだって!? ここは日輪島じゃないのか!?」
「そうよ。ここはソリトス王国の小さな町、ナボッケの町。日輪島じゃないわ」
アカツキは唖然として、姉とノアの顔を交互に見た。そして、項垂れてしまった。
「話をしてもいい?」
ノアが尋ねると、「好きにしろ」という返答が飛んできた。
「精霊自治区で戦ってた、っていうのは?」
「……アマテラスの連中が精霊自治区に来て、水の部族が即座にアマテラス側についたんだ。連中はその後俺たちの、火の部族の区域に侵略を開始した。だからそれを食い止めるために俺も戦ったってだけ。……結局、どうなったかはわからないけど」
「……精霊自治区は五日で陥落し、今はアマテラスが好き勝手にのさばっている」
コガラシマルの一言に、アカツキの瞳孔が開いた。
「適当言うな! 精霊族だぞ? アマテラスがいくら強くたって、精霊族がそんな簡単に負けるわけねぇだろ! そうだよな、ねーちゃん?」
「本当よ。それに、五日持ったのだって風の部族が三日抗戦したからなのよ。地の部族に関しては部族長を失ったわ」
絶句するアカツキに対し、シノは言葉をつづけた。
「あたしは、あたしはあんたがソリトス行きの船に乗せられたって情報を聞いて、あんたを追いかけてきたの。でも港からどこに行ったのかが掴めなかった……。だからアマテラス側に捕まらなかったってだけ……」
コガラシマルは無言だった。何も語ることがないのかもしれないし、誰にも言いたくないだけなのかもしれない。
「……じゃあ、精霊族は全滅した、ってことか?」
「アマテラスに奴隷にされてたり、精霊自治区で抵抗運動をしていたり、あとはあたしみたいに逃げたのもいるわ」
いよいよアカツキは黙り込んでしまった。自分が眠っている間に精霊自治区が最悪の事態に陥っているとは思っていなかったのだろう。
「それで、俺はアカツキくんにこの先のことについて考えてほしいんだ」
アカツキの返事はない。ノアは構わず続けた。
「君はもう自由だ。ソリトスで新たな暮らしを始めてもいいし、日輪島に戻って再び戦いに身を投じてもいい」
シノが何かをいいかけたが、ラスターがそれを制した。
「俺たちは今からあの副町長を追わないといけない。あの調子なら、新しい精霊族を仕入れて実験を開始してもおかしくないからね」
「…………」
静かに感情をかみしめるアカツキに対し、ふとコガラシマルが口を開いた。
「話の腰を折るが、あの副町長を追いかける以外にもやることがひとつある」
「何?」
「外は冬だ。某の魔力を悪用した装置の魔力が、まだ外の世界に降りている。本来であれば装置を止めればよいはずのものが、何故か未だにのさばっている。あれはもう某の手を離れた冬で、某にはどうにもできぬものだ。止めるにはあの膨大な魔力を分解する必要がある。装置のものと某のものと……」
「冬の範囲は?」
「装置の影響範囲から漏れることはなかろう。が、ずっと夏の環境下にいた民が急激な冬に耐えられるのかと言われると……難しいものがある」
「そっちも急がないといけないのか」
ラスターが、んー、と考える。その時だ。
「外の魔力なら、俺が浄化できるかも」
アカツキが口を開いた。
「あの装置が付与する魔力って、一種の呪術に近いものっぽいし。それなら俺の浄化魔術で何とかなると思う」
「本当?」
ノアの問いにアカツキが頷いた。ノアはにっこりと笑ったが、アカツキは少し身を引いた。
「それなら、任せても大丈夫ってことかな?」
「ま、まぁな」
「ありがとう。それなら君に任せるよ」
「ここから外に出られそうだぜ」
ラスターがぽちぽちと壁の機械を操作している。先ほど副町長が逃走に使った扉が開く。
「人が乗れる昇降機だ。あんまり沢山は乗れそうにないが……」
「二、三人が限度かな。二人ずつ行こう」
「ならオレたちが先にいくよ」
ヒョウガが自分の胸元をとん、と拳で叩きながら告げた。
「外が冬だとしたら、オレとコガラシマルなら立ち回りやすいし」
「分かった。お願いするね」
うん、うん、とコガラシマルは感慨深そうに頷く。
「ノア殿、某も早速参りたいところではあるのだが……」
「はいはい」
ノアはさくっと、コガラシマルにかけていた身体拘束魔術を解除した。ヒョウガは近くの戸棚に立てかけてあったコガラシマルの二振の愛刀を手に持ち、昇降機の方へと急いだ。
「それじゃあ、次は……」
「先に行って」
ノアの言葉を遮って、シノが言いきった。
「今の状態だと、アカツキとコガラシマルをあなたの目の届かないところで一緒にするのはあまり得策じゃないから」
「……分かった。ラスター、行こうか」
ノアはアカツキにかけていた身体拘束魔術を解除して、ラスターとともに昇降機に向かった。機械の稼働する音が響く。
ノアとラスターは何か話している。その内容は聞こえない。
「……ねーちゃん」
代わりに、シノは弟の声を聴いた。
「なぁに」
「俺のことずっと探してたって、ほんと?」
「本当よ。……やっと信頼できる人を見つけて、協力してもらったの。あたし、一人でなんとかできると思ってた。でも、案外そういうことって少ないものよね」
「…………」
アカツキはじっと黙っていた。白磁の目がわずかに揺れていた。
ナボッケの町は凶悪な冬に閉ざされていた。コガラシマルはふう、と息をつく。美しくない冬だと思う。あの最悪な装置に閉じ込められたせいで、こんな醜悪なものを見る羽目になるとは思わなかった。
「来ると思ってましたよ!」
副町長の声が響く。コガラシマルは愛刀を抜いた。持ち主の魔力を吸う代わりに絶大な威力を誇るこの刀は、あの凶悪な夏の支配下では抜けなかった。今は問題なく操れる。
「せっかくですから、餌の時間といたしましょうかね」
ヒョウガも構えを取る。副町長の後ろでうなり声を上げるキメラの頭には、人の顔らしきコブがある。あれは、とヒョウガは問いかけようとしてやめた。
コガラシマルが静かに怒りを抑えている。
「それは、なんだ?」
もっとも、口調は、どうにもならなかったが。
「キメラですよ。精霊族をもとにしたキメラです。私のペットでしてね、かわいらしいんですよ」
「…………!」
ヒョウガの顔が凍り付く。あの霊山の山頂で見たおぞましいものたちは、みんなアレを作るための材料だったというわけか。
「この子たちは肉が好きなんですが、とりわけ精霊族の肉が好きでして……」
「ヒョウガ殿! 今すぐ昇降機に乗ってシノ殿たちに――」
ひゅん、とキメラが姿を消す。コガラシマルはヒョウガの腰に腕を回してそのまま体を抱き上げ、空へと飛んだ。先ほどまで二人が立っていた空間に、キメラがかぶりついている!
「は、速い――!」
ヒョウガの悲鳴が風に流れる。
コガラシマルは木の枝に降り立ち、キメラの動向を伺う。倫理なき獣は舌なめずりをして、頭上の餌をおいしそうに見つめていた。
気の利いたことを書けるとよいのですが何も思いつきません!(頂いたサポートは創作関係のものに活用したいなと思っています)
