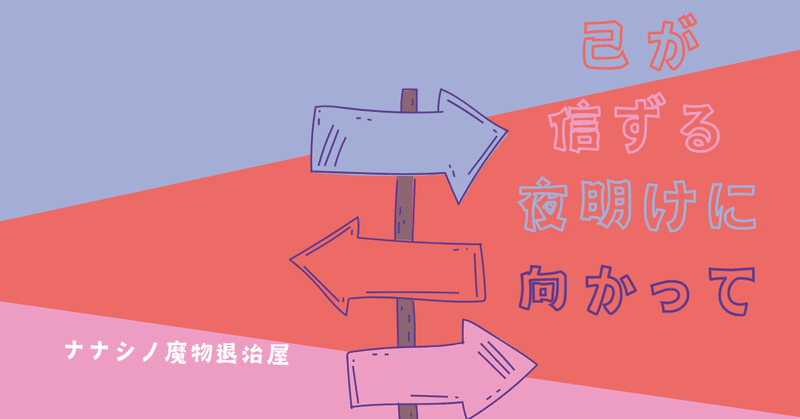
【短編小説】己が信ずる夜明けに向かって 3話
――数刻前。
地区の店はコガラシマルにとってちょうどいい。澄んだ冬の空気を思わせる肌の色は、彼が明らかに人ではない何かであることの証明で、多種多様な人々の往来がある商業都市においても注目の的だった。しかし地区に入ると話が変わる。地区の人々は通りすがりの他人のことなどかまける余裕がないのだ。慣れていないアカツキは「ここ、入っていいのか?」と繰り返しコガラシマルに聞いていたが。
手近な食堂に入り、飲み物を注文する。アカツキも適当にミルクコーヒーを頼んでいた。
「お前も俺を止めるつもりか?」
アカツキの問いに、コガラシマルは首を振る。
「……某もそなたと同じだ」
「同じ?」
「あの島で最後まで抗戦するつもりでいた。……叶わなかったが」
「負けたのか」
「ああ」
お冷のコップにコガラシマルが指先を添える。中の水がゆっくりと凍っていく。
「魔力切れを起こした。一人で戦っていた弊害だ。もっとも、某の能力は集団戦には不向き。敵味方問わず吹雪で凍えさせては数の有利を生かせぬ」
「火の部族たちはどうして負けたんだ?」
「詳しくは某も分からぬが、単純な魔力の相性問題ではないか?」
アカツキの目が細められる。
「水の部族かぁ……」
店員が来る。ミルクコーヒーと一緒に運ばれてきたのは冷たい緑茶だった。
「そなたの魔術に活路はあるか?」
「結界術、治癒、解呪、祝福、身体活性の他の能力向上系の補佐魔術なら得意だ。応用すれば多少の攻撃魔術も扱える」
「調和が取れているのはいいことだ」
コガラシマルが茶を口にする。コップに集っていた結露の雫が緩やかに硬さを得ていく。
「某はそうはいかなかった」
自分たち以外の客がいない、静かな店の片隅で、アカツキは少し慎重に息をした。自分が寝ている間に物事は大きく動いていて、直視したくない現実がじわじわと首を絞めてくる。
置き去りにされている。この世界のすべてから、自分だけがぽつんと独りぼっちだ。
「お前は島に戻るつもりはないのか?」
「ああ。某の護るべきものはもうあの島にはない」
脳裏にヒョウガの姿がぼんやりと浮かぶ。それなら納得だ。ヒョウガがこっちにいるのなら、コガラシマルが島に戻る道理はない。
「そなたはどうだ?」
「……俺?」
「あの島に戻り、アマテラスと戦い、成し遂げたいことがあるのか?」
コガラシマルの声は穏やかだ。初対面でいきなり斬りつけてきたときの苛烈さはない。
「俺が戦ったときは、まだなんとかなるって思ってた。水の連中が裏切って攻めてきたときだって……。頑張れば元の生活に戻れるって……そう、思ってた。でも、あいつら説得にも耳を貸さなかった。風の方はどうだったんだ?」
「……問答無用で斬り殺したが?」
空気が凍る。さすがのコガラシマルも今のは失言だと思ったのだろう。口元に手を当ててしばし何かを考えていた。
「その、なんというか、すまぬ」
「……うん、まぁ、お前ってそういうところあるよな。なんか分かる」
「も、もしかしなくとも、そなたに斬りかかったことを根に持っているのか?」
「そういうつもりじゃないんだけど……覚悟が決まってるよなぁって」
「いや、まぁ、水の部族からの使者は返したが、そのあと攻め込んできた連中は風の部族が一丸となって全員返り討ちにしたというだけであって……他の部族もてっきりそうなのかと……」
そんな早々に交渉決裂を断定し、意識を同胞から仇敵に切り替えられるものなのだろうか。確かに精霊自治区だって一枚岩というわけではなく、多少利権は絡んでいた。が、精神の奥底には「同じ精霊族」の意識があったはずだ。
風の部族が三日持った理由が分かる気がした。彼らの傾向として意識の切り替えが恐ろしく速いのだ。だからあの時も、自分を斬り殺すことを躊躇わなかったのだ。
「どのみちゆっくり考えるとよい。某は島を出てよかったと思っているが……全員が全員そうであるとは限らぬ」
「やっぱりヒョウガがいるから?」
「某がヒョウガ殿と契約を結んだのは島を出る前だが……ある意味ではそうかもしれぬ」
「そっか。お前はヒョウガのために島を出る道を選んだんだな」
「自分のためでもある。あの島に残っていたら某は今頃」
不自然に言葉が切れた。コガラシマルの魔力がわずかにざわついたのがアカツキには分かった。
「……何か楽しいことを教えてくれよ。俺をここに引き止めたいのなら」
硬直した雰囲気が急にへにゃりと柔らかくなる。コガラシマルは浮ついた声で答えた。
「それならヒョウガ殿の料理と酒が一番だ」
アカツキは伝票を持って会計に向かった。銀貨は姉からもらってある。
コガラシマルが慌てた様子で、残っていた緑茶を一気に飲み干したのが見えた。
「ラスター殿から良い店を紹介されている。なんでも、酒が美味いが飯は不味い店だそうだ」
「それほんとにいい店なのか?」
「ラスター殿の情報は基本的に信用できるが……」
看板を見る。髑髏の円舞、ここで間違いない。
コガラシマルは扉を開いた。入店を知らせるベルが鳴る。いらっしゃいませ、と老人の声がした。おそらく彼が店主なのだろう。
「アカツキ!?」
その直後に飛んできた声にコガラシマルは浮いた。
「ねーちゃん!?」
後ろからも声が飛ぶ。コガラシマルはそっと道を開けた。そしてすぐに、己の行動を後悔することになった。
……姉弟喧嘩である。
「あたしも島に戻るわ」というシノの決意から始まったそれは、どんどんどんどんボリュームが上がっていく。すさまじい勢いの怒鳴りあいは外野が聞き取る努力を放棄するレベルの代物で、コガラシマルは迅速に二人を店から追い出す。
「ねーちゃんが島に戻ったら意味ないじゃん!」
「意味がないってどういうことよ!」
追い出した時点で扉を閉めるコガラシマルは、完全にかかわる気がないらしい。そのまま扉を見つめて「どうしたものか」と考え込む。
「おい、そこの精霊族」
そこにコバルトの声が飛んだ。コガラシマルは声の方を向いて、少しためらいつつも近づいて行った。店主が暖房の操作を始めた気配があった。
「某に何か?」
「頼まれごとをするつもりはないか?」
「頼まれごと?」
「……お前さんの同族がね、ここの近くで好き勝手してるんだよ」
「それは、失礼した」
コバルトは喉をぐうぐう鳴らした。
「違う違う。まぁそういうやつらもいるが、中には礼儀正しい連中もいる。それで、その礼儀正しい連中がね、地区住民のために――」
コバルトが口をつぐんだので、コガラシマルは警戒を強める。
外から、何かが爆発する音がした。
コバルトが舌打ちを繰り出した。
「遅かったか」
「遅いとはどういう意味だ?」
「地区も一枚岩じゃないってことさ」
コバルトはそう言って、銀貨を数枚カウンターに置いて出ていった。コガラシマルは何が何だか分からなかった。とりあえずは、ヒョウガと合流するのが最善手だろうか。
店主が「コバルト! 足りないぞ!」と怒鳴るのを聞き流しつつ、コガラシマルは外に出た。火薬の臭いが、わずかに鼻を掠めていった。
「なっ、な、何事!?」
少々呂律の回っていないヒョウガがノアとラスターを交互に見た――つもりだったが、ラスターは既に姿を消していた。情報を集めにすっ飛んでいったようだ。
「精霊族の魔力の気配がある」
「アカツキじゃないよな?」
「それは大丈夫。アカツキが得意なのは主に支援に関する魔術だって話だから」
自分たちの視線の先から、人々が逃げまどってくる。ここをさかのぼるのは危険だ。逆に言えば爆発の現場が向こうにあるという証明になる。
「ここって、屋根の上走れるのかな」
「ちょっとガタガタするけど、不可能ではないかな」
ん、と簡単な返事を繰り出したヒョウガは、颯爽と氷の足場を作った。表面がしっかり凍り付いているので、滑る心配は基本的にはない。ヒョウガが先に屋根に上り、ノアがそれに続く。黒い煙がもくもくと上がっているのが見えた。
「行こうか」
二人は屋根の上を駆けた。時々変に何かがきしむ音がするのだけは勘弁してほしいところだった。
爆発現場が見えてきて、人が集っているのも見える。ギルドの人たちだ。そこから少し離れたところで怪我人が応急処置を受けているのが分かる。
「この辺で降りようか」
ヒョウガが再び氷の足場を出す。それに気づいたギルド職員が、ノアの顔を見て目をぱちぱちさせた。
「屋根の上を歩いてきたんですか?」
「人の流れと逆を行くのは危ないからね」
「まぁ、確かにそうですね。それに我々からすれば人手はありがたいですから」
「何があったの?」
ノアの問いに、職員は答えなかった。代わりに二度目の爆発が地区を襲った。
「!」
反射的に障壁魔術を展開したノアは、その壁の向こうに人影を見た。警戒を強めるも、相手は両手を挙げている。抵抗の意志がないという証明だ。
「なんだよみんな怖い顔しちゃって」
その人影――ラスターは目をしぱしぱさせながら、ちょっとおどけた声を出した。
「犯人が歩いてきたのかと思った」
ヒョウガが少し声を潜めてそんなことを言う。
「映画の見過ぎだな」ラスターは笑って、両手を大きく広げながら歌いだした。「ああ、なんて最高な日。都に大きな花が咲き、人々は静かに黒く焦げる――」
「それより爆発の原因は?」
「……花火だよ」
「花火?」
「地区に逃げてきた精霊族たちが、地区の面々にお礼を伝えるのに花火を準備していたらしい。ここの小屋で保管していたのが……」
ヒョウガが「ひえっ」と小さな悲鳴を上げた。ラスターはノアにだけ分かるように、自分の後ろを指し示す。精霊族の女性らしき人が泣いている。その足元では男性がうずくまって号泣している様が見えた。「どうして、どうして……」と嘆く声が、わずかにこちらに届いている。
「ヒョウガ殿!」
空から颯爽と降り立ったコガラシマルが、少々切羽詰まった声を出す。ヒョウガ以外の全員が少し驚いていたが、ヒョウガはすぐにコガラシマルの背中を叩いた。
「あの泣いてる精霊族たちに、地区の花火にかかわっていた精霊族全員の受けている加護と司るものを聞いてきてくれ」
コガラシマルは返事もなく、ヒョウガの指示通りに動く。ラスターが少し首を傾げた。
「その二つで何が分かるんだ?」
「火薬がうっかり爆発するかどうかが分かると思う。人が作るのと違って、精霊族はその性質によってはものの危険性を抑えられるから」
「そうなのか?」
「コガラシマルは冬の精霊だから、寒さに強い、みたいなそういう感じ」
へー、とラスターは納得した。ヒョウガの勘は正しいようだ。一人の精霊族が爆発現場近くで何やら術を展開している。コガラシマルが小さく頷いているのも見える。
現場の惨状はすさまじいものがあるが、その割にはだいぶ落ち着いていた。ノアは少しだけ安堵した。コガラシマルが少し深く頭を下げて、こちらに戻ってくる。ヒョウガが「どうだった?」と聞く前に、彼は口を開いた。
「精霊花火プロジェクトなるものの参加者は五人。うち一人は地区住人。精霊族は四人絡んでいたそうだ。大半は火薬をいじったことがないようだが、一人は自治区で花火職人をしていたそうだ。薬と音の加護を受け、火花を司る精霊だそうだ。火薬の扱いを間違えたとしても、爆発させないことができる熟練の職人。彼の存在がプロジェクトの発足を後押ししたくらいだ」
「他のメンバーは? そいつらが火薬をポンとやっちゃった可能性は?」
ラスターの問いに、コガラシマルは首を横に振った。
「その他の面々は花火に触れることはなく、加護の種類についても火薬を誤って爆発させる類のものではない上に、山と煙の加護を受け、灰を司る者もいた。あれだけ派手な爆発が生じたというのに、被害がこの程度なのは、その者の貢献があったからであろう」
ラスターはわずかに目を細めた。内輪の面々に犯人が不在であれば、考えられる可能性は――。
「誰か医者はいませんか!」
その矢先に新たなトラブルがすっ飛んでくる。ギルドの女性職員が半泣きで叫んでいるのが見えた。
4/11 21時頃 更新予定
気の利いたことを書けるとよいのですが何も思いつきません!(頂いたサポートは創作関係のものに活用したいなと思っています)
