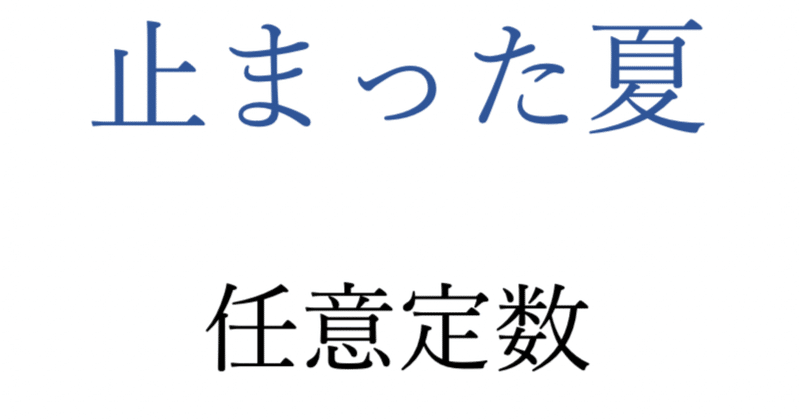
止まった夏
これは私の永遠に止まったままの夏の物語
その日は夏を感じるには十分すぎるほどの日だった。
清々しい空、カッと照る太陽、白さを輝かせる雲、命を燃やして鳴く蝉。
私はその全てを感じながら部屋に一人いた。
よく晴れた夏の日差しが差す屋外とは対照的に私の心の中はどんよりと曖昧でどこか溶けそうなそんな様相だった。
曖昧な私は曖昧な意識のまま立ち上がると台所へ行きコップを手に取った。
水をグビグビと胃に流し込む。コップが空になったらまた水を注ぎまた飲む。何度かこれを繰り返した。私のお腹は水で満たされていた。
『ぬるい』と思った。私は製氷機を開ける。コップを氷で満たしていく。氷を入れたならやることはただ一つ。
私は部屋に戻っていた。部屋の机の下を漁る。ごちゃごちゃと散乱した本や書類の山の中に私の探しものはある。『あった』心のなかで喜ぶ。赤いキャップをひねって中身をコップに注ぐ。ツーンとアルコールの匂いが鼻腔をかすめる。カチカチと氷に亀裂の入る音がする。そう、焼酎のロックの完成だ。
私は腐れていた。昼間から酒を飲むほどに。
病んでいた精神の調子が本格的に崩れ冬から春にかけて閉鎖病棟に3ヶ月入院した。しかしまだ心は立ち直る事ができず療養のために大学を休学した。ところが療養のために空いた時間を私は持て余してしまいアルバイトをたくさん入れた。動かずにはいられなかったのだ。完全に立ち直っていなかった私にのしかかるアルバイトの重責。私はこれに勝てるはずがなかった。バイトが終わっては夜更けまで飲み、処方されている薬もODし、アルバイトのない日は起きた瞬間から寝るまでお酒と薬を飲み続ける。時には過食しそれを吐いた。もう自分が何をやっているのか何をしたいのか分からなかった。
そんな生活をしていたからだろう。医者から
「8月から入院しましょう」
そう告げられていた。
私はコップの中身をグビグビと飲んだ。喉が焼ける感覚がする。しかしこれがたまらない。私はまたも赤いキャップをひねりコップを焼酎で満たす。それを飲む。もっと世界が曖昧になってきた。私は部屋を漁る。お目当ての薬を見つける。それを焼酎と共に流す。曖昧な世界に一縷の幸せを見つけたような気さえした。それで良かった。今の私にとってはこれが最高の瞬間なのだから。辛い現実から目を背けることができるのだから。
”ガチャリ”
ドアを開ける音がした。急いで振り返ると母親が立っていた。
「何やってるの!!今日、入院準備のための道具を買いに行くといっていたじゃない。またお酒飲んだでしょ」
母親が近づいてくる。そうだった。今日は入院のための日用品を買い揃えに行くと決めていた日だったのだ。『せっかくだし行きたいな、まだそんなに酔ってないし薬も飲んでいない。余裕だ』と私は思う。
「薬まで飲んだの!?もうこんなんじゃ今日は連れていけないわ」
母親は私のゴミ箱を漁り薬の殻を見つけそう言った。ゴミ箱まで漁られ連れて行かないと言われた私は酔って薬が回っていたせいもあっただろう子供のように
「嫌だ、行くから」
と意地を張った。これが私が生きていた夏の最後の瞬間だったかもしれない。
「こんなフラフラしそうなあなたを連れていけるわけないじゃない」
そう母親が言い放つと私は机に置かれていた剃刀を手に取った。
母親は焦った顔をして私から剃刀を取り上げようとする。私は即座に
「出てって!!」
そう叫んだ。
どれくらい時間が経っただろうか。夕立が降り、そして止んだ。私の目に映るのは縦横斜め無数に切り傷の入った腕と切れ味の悪くなった剃刀。
部屋を見渡す。相変わらず荒れ果てた部屋だった。それらをぼんやりと見ていた。母親に向かって叫んだときのあの高ぶった感情はどこに行ったのか分からないほど私の心は鈍っていた。
”ガチャリ”
再び部屋のドアが開いた。私は虚ろな目で見る。母親だった。母親は私を暑いアスファルトの上で干からびるミミズを見るような目で私を見ていた。
「えぇ…また…」
母親が呟く。私はひどく惨めな気持ちになって早くこの状況から逃げ出したくてガーゼを手に取った。手慣れた手付きでガーゼを切りテープで止める。これで傷は隠せた。私は思い切って口を開いた。
「ねえ、もう大丈夫だから買い物行こうよ」
これは禁じ手なのではないか、そう思いつつも母親の顔を伺う。
「うん、じゃあ、行こう」
母親は静かに言った。
買い物中私は終始苦い思いをする羽目になった。
禁じ手で連れてきた母親はずっと渋い顔をしていて買い物どころではなかった。母親の機嫌をこれ以上損ねないようにするために必死になっていた。
こんなことなら買い物なんか来るんじゃなかったと心底後悔していた。
家に帰った時、私はひどく疲れていた。考えてみれば元々のメンタル不調に日々のアルバイトの疲れそして買い物前の一悶着にリストカットに買い物中の母親のご機嫌取り。疲れても無理はない。
私は自室に籠もると帰り道で買った缶チューハイとエナジードリンクと焼酎を混ぜて薬と共に胃に流し込んだ。
私の世界は崩れ始めていた。
深夜になった。私は死にたくてたまらなくなっていた。終わりの見えない報われることのない光の差さないこの毎日に終止符を打ちたかった。
『死んでみてもいいかもしれない』
私の中の何かがそう囁いた。
私はその声に突き動かされた。いつでも死ねるようにと用意していたロープをハングマンズノットにロープを結んだ。半袖のワンピースを着た。昼間に切った傷のガーゼの白色が目立った。薬を何シートも持った。
私はリビングを堂々と突っ切って玄関へと向かった。つっかけを履く。ドアに手をかけ私は外へ出た。
外の空気は夏にしてはひんやりと落ち着いていた。私はまず体の中で不足しているアルコールを補おうと、いや最期の一杯を飲もうとスーパーに行った。
鈍っていた私は度数の高いお酒をレジへと持っていった。
「年齢確認のため身分証明証をお願いします」
と店員は言い、『こんな酒飲むのが未成年なわけないだろ』と思いつつも私は持っていた学生証を見せる。その時だった。腕に隠し持っていたロープがレジ台へと落ちた。
店員はハッとしたような顔をして私を見る。そして気付く間もなく店長とやらが呼ばれてきた。奥では先程の店員がどこかへ電話をかけている。
私は焦った。頭が混乱した。
「これから最期の一杯をやろうっていうのに邪魔しないでくださいっ」
そう言い切ってそして店長の制止を振り切り酒とロープを手に店を後にした。
しばらくぼんやりと夜の風に当たりながら酒を飲んでいた。視界にはパトカーがいる。『何だろう、物騒だな』と思いながら歩き始めた。首をくくるのにうってつけの鬱蒼とした公園があるのだ。10分くらい歩いただろうか。表通りに出た時
「お姉さん、ちょっといい?」
誰かが話しかけてきた。振り返れば警察官そしてパトカーがいた。
「腕、見せてください、ね」
『まずい』自分の中で全てが繋がった。スーパーの店員が電話をかけていた先は警察で視界に入っていたパトカーは連絡を受けて配置されたものだったことに。今まで裏通りを歩いていて警察の目にはつかなかっただけだったのだ。
「今、急いでいるので。すいません」
私は足早にその場を過ぎ去ろうとした。しかし永遠と警察官は付いてくる。「お姉さん、どこ行くんですか?ちょっと腕見せてください」
「いえ、急いでいますので」
「お姉さん、手に持っているそのロープ何に使うんですか」
「これから縄跳びをします」
そんな訳のわからないやり取りを何十分と繰り返しずいぶん遠くまで来てしまった。
「はい、ここで止まって」
別の声がした。
ふと周りを見たら6人ほどの警察官に周りを取り囲まれていた。私はどうしたものかと回らない頭が重たくてへなへなと道に座り込んでしまった。しかし相手は警察官、座り込んだところを取り押さえられて警察署まで連れて行かれた。
私は警察署のソファーに座らされていた。知らないうちに持っていたハンドバックやロープは取り上げられていた。
私は訴えていた。
「私は何も悪いことしてないじゃないですか!だから早く家に帰らせてください!!」
「そうだよ、お嬢ちゃんは何も悪いことをしていない。だからこんな自由な部屋にいるんだよ」
「だったら帰らせてっ!」
私はドアの前で警察官のおじさん相手にぶつかり合っていた。しかしなかなか帰れる気配がない。
「ね、しばらく一緒に座ってようよ」
女の人の声がした。
振り返ると若い女性の警察官がいた。
「腕の傷大丈夫?」
と尋ねてきた。私の腕に雑にくっついているガーゼには血が滲みていた。
「血が…」
とそっぽを向きながら私は答える。何かの拍子に傷が開いたのだろう。
「ちょっと待っててね」
女性の警察官はそう言うと救急箱を持ってきた。
「痛そうだね」
私の腕の傷を見ながら女性の警察官は言った。そしてきれいなガーゼを丁寧に貼ってくれた。昂ぶっていた心が少し鎮まった気がした。
それから私は女性の警察官と話していた。とてもたわいない話だった。警察手帳を見せてもらったり階級についての話を聞いたり警察学校について話してもらったり、私は珍しく笑っていた。
「じゃあ、行くよ」
突然声がかかった。
『やっと帰れる!』そう思った。
時計は2時を過ぎていた。
外に出るとパトカーが止まっていた。
「乗って」
と言われ乗り込んだ。すると私を挟むように先程の女性の警察官、男性警察官が乗り込んできた。『家に帰るだけなのに仰々しいな』と思いながら乗っていると車は家に向かうどころか高速道路へと入っていく。
「どういうことですか!!」
私は動揺を隠せない。
「病院に向かうんだよ」
と助手席にいる警察官が答える。
私は絶望した。とても嫌な予感がしたのだった。
「怖いよ、嫌だよ、行きたくないよ」
狼狽した私は隣りにいた女性警官の手を握ることしかできなかった。
着いた先はいつも通っている精神科病院だった。”救急外来入り口”という表示が煌々と光っている。私は引きずられるようにして院内へと入って行った。
気がつけば警察官たちはいなくなっていた。お世話になったのにお礼も何もせずだった、と座らされた椅子の上で思っていた。
目の前には医者らしき人物が二人座っている。
そして横を見るとなんと両親が来ていた。両親は私を憐れむような目で見ている。最悪の状況だった。
「あなたは自分を傷つけようという意思がありますね」
医者が口を開く。
ここで折れてたまるかと私は
「いいえ、全く思っていません」
と素知らぬ顔をする。
「あなたは自殺の意思がありますね」
医者が再び問い詰める。
「いいえ、全く思っていません」
シラを切るつもりで言った。
しばしの沈黙が走る。
医者が何かを書き始める。
隣に控えていた人が紙を受け取り私の元へやってきた。
「あなたはただ今より、措置入院となります」
私は受け入れられなかった。
『私は何も悪いことしていないのに。なぜ?私はただ、ただ、頑張っていただけなのに。今入院なんてしたらきっとしばらくは外に出ることができない。8月からの入院が始まる前にやりたいことがたくさんあったのに。嫌だ。嫌だ。そもそも原因の母親はなぜあんなところで高みの見物をしているの。おかしい。許せない。謝ってよ!』
そう思った瞬間私は手に持っていたスマートフォンを母親に向かって投げていた。
ガンッ
スマートフォンはただ壁に当たって落ちただけだった。
私は数人の男性に取り押さえられていた。そして病棟に行くエレベーターに無理矢理押し込まれた。私はその間ずっと頭に浮かぶ限りの罵詈雑言を叫び続けた。けれど誰にも届くことなどなかった。
私が連れて行かれた先は俗に言う”保護室”だった。監視カメラがありマットレスが床に直に敷かれ、ドアのないトイレがあるだけの部屋。私はそこに着くと服を全て脱がされ病衣に着替えさせられた。看護師たちは足早に出ていった。
木枠に入った時計は3時半過ぎを指していた。
私は眠ることができなかった。眠れるはずなどなかった。
次々に湧き上がる憎悪、焦燥感、そして後悔。
『私をこんな目に遭わせた奴は許さない』そう心に誓った。
感情が私を次々に刺激した。泣きたいような感情だったが涙は出なかった。朝日が昇り始めた。太陽が部屋を照らしつけた。空は雲ひとつなかった。蝉がぽつりぽつりと鳴き始めていた。
長い長い夜が明けた。
朝食が運ばれてきたが私はそれに口をつけることはなかった。
『もういっそ餓死してしまえばいいんだ』と思っていた。
心配した看護師が血糖を測りに来た。やはり低かったようで
「このままだと注射で糖を補給しないといけなくなるよ」
と脅しをかけて去っていった。
部屋に置かれた水のボトルを一気に飲み干した。そしてまた1本また1本とグビグビと胃に流し込んだ。私のお腹は水で満たされていた。
ガチャリ
保護室の重たい扉が開いた。見ると主治医が立っていた。
主治医は私を見ると言った。
「こんなはずじゃなかった、って思ってる?」
私の世界は崩れ去った。
私は頭を抱えた。
「こんなはずじゃない…こんなんじゃない…私は…私は…私は…」
『私は…私は…私は…わたしは…』
私は、私の夏は、あの夏らしい日の保護室の中で永遠に止まっている。
私の文章、朗読、なにか響くものがございましたらよろしくお願いします。
