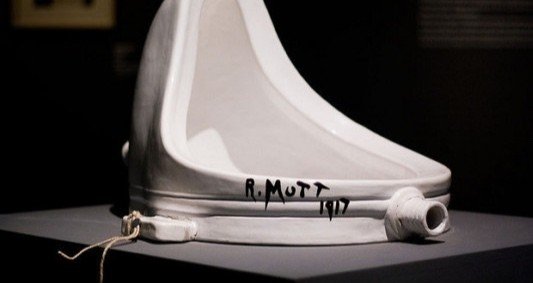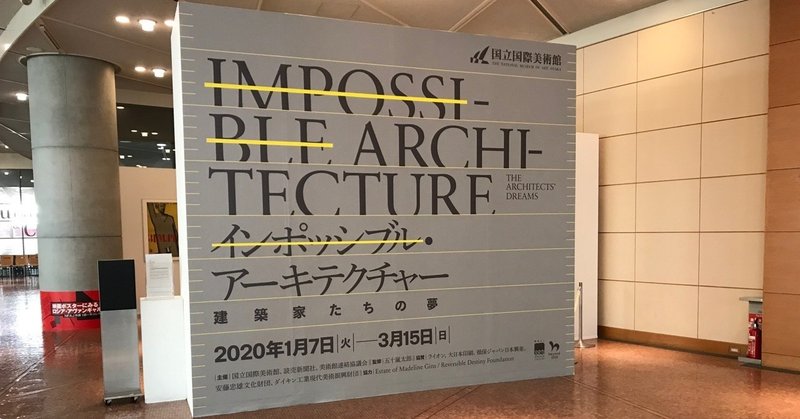2020年1月の記事一覧

「見えないかかわり」イズマイル・バリー展とWhat's Karl Gerstner? Thinking in Motion
2020年から兼業を開始した。 転職という選択肢もあるかと思うけど、新しい職場で一からポジションを取るのは、正直しんどい。けれども昨今の転職市場では、デジタルの人材は引く手数多、年齢もあまり関係がない。こうした状況は2025年あたりをピークとして2030年までは継続すると思う。ひとつの会社で年収を上げていくよりも転職をうまく使ってキャリアを形成していくというのもひとつの考え方だとは思う。 僕の勤務先が副業を認めていることもあり、デジタルの知見を本業と競合しない形でサービス