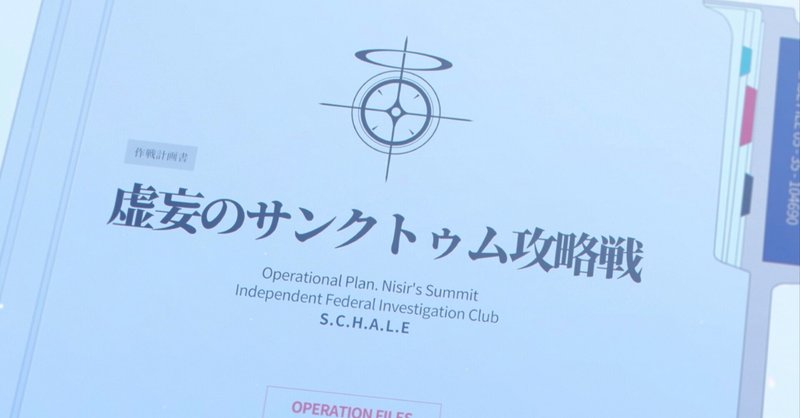
客体化される日本サブカルチャー──『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』からみる文化の交換可能性について
Ⅰ はじめに
本稿は2021年にサービス開始された、スマートフォン向けゲームアプリ『ブルーアーカイブ -Blue Archive-」』(NEXON Games開発・Yostar運営)を足掛かりに、近年存在感を増すスマホゲーム市場に見られる興隆を国内の文化的な流れの中に位置付け、さらにその現状と本作の将来的可能性を検討するものである。
『ブルーアーカイブ -Blue Archive-』(以下、「ブルアカ」)は、「学園都市キヴォトス」に赴任した先生(=プレイヤー)が、そこで発生する数々のトラブルを生徒(=キャラクター)たちと共に解決していく物語を描くRPGとされている。メインテーマを〈学園×青春×物語〉とし、公式サイトでは「学園の日常を小さな奇跡へ」と謳われている。
一見するとありきたりな文句ではあるが、その宣言に至る外部の過程を読み解くことによって、普遍的な価値としてのガラパゴス化されない経済・文化的な要素、日本における社会性の“かけら”を発見することができる。この将来性を模索することは、現代社会のアイデンティティ、その指標を提起することはもちろん、僅かながらも80年代以後の「日本サブカルチャー」の役割を肯定する一助ともなるだろう。
Ⅱ サブカルチャーの分析と抽出
まず、『ブルアカ』を考える上で重要なのは、〈学園×青春×物語〉のようなありきたりな標語、それ自体についてではなく、むしろなぜ、ある種の尖り・独自性を表面化させず、陳腐ささえ内包する標榜をあえて行ったかということである。むろん、こうした日常、青春の希少性、一回性というものを物語の中で次第に明らかにしていくという丁寧な作劇のスタンスをとっているわけだが、現に本作は、2023年1月の二周年記念イベント期間中において、ようやく一時的なセールスランキング1位(iOS,Android それぞれにおいて)を獲得し売上記録を更新しようとしているものの、サービス開始以来、これまで月次売上平均は配信初月を一度も上回っていない。では、なぜ今、激化する強大なスマホゲーム市場において、このような保守的なテンプレートに沿わせる必要があったのか、こうした慎重さを得るにあたってどのような外的要因があったのか、順を追って確認していきたい。
冒頭で述べた通り、本作は開発をNEXON Games《 *1994年韓国にて「NEXON Corporation」創業、2000年にソリッドネットワークス社が資本提携の上、「株式会社ネクソンジャパン」として日本でのサービスを開始、2002年に資本提携を解消し、「NEXON Corporation」(現 NEXON Korea Corporation)出資比率100%の日本法人として「株式会社ネクソンジャパン」(現 株式会社ネクソン)を設立。》、運営をYostar《*2014年中国にて設立された「上海悠星網絡科技有限公司」を母体として2017年日本現地法人「株式会社Yostar」が設立。》が担当し、それぞれ韓国・中国系資本を母体とする企業体制を有している。これに伴い人的な資本も海外から招集されている。
こうした沿革を前提とした上で興味深いのは、上記の〈学園×青春×物語〉のようなプレイヤーにとって「凡庸さ」を感じる要素が、一度海を渡り、「日本的なもの」として再構成された上で逆輸入されているという実態である。Yostarの代表取締役社長 李 衡達は会社インタビューの中で『弊社は中国で作られた日本風のゲームを、日本で展開する会社です。』と端的に述べている。また、同時に彼は元々日本の「オタクコンテンツ」の熱心なファンでもあり、ゲーム業界に入る前から日本のゲームやアニメに大きな影響を受けていたことを随所で語っている。
こうした境遇は関連他社の経営者やクリエイターにも見られる。「株式会社ネクソン」出身で『ブルアカ』の統括プロデューサーを務める 김용하 (Yongha Kim)もそうした人物の一人である。彼は「ネクソン開発者カンファレンス2014」にて日本サブカルシーンにおける「萌え」概念に関する講演を行なっている。この中でKim は自身があくまでプログラマー出身であること(ポリティカルな側面を一旦除外しあくまでデータ化を徹底するという意味で)を前置きしながら、日本の「萌え」概念を進化心理学的な観点からある程度理論化することができると説いている。
東浩紀のポストモダニズムに関する論考を読めば、一般的にこのような「萌え」の好みは社会現象であって、一つの流行として解釈されています。しかし、おっしゃる通り「萌え」が人間の本能を刺激するものであるのなら、未来にも「萌え」はまだ残っていると思われます。人類共通の神経回路を刺激する「萌え」のベクトルが存在するものと考えられるからです。……ですから場合によっては人間の「萌え」に対する好みはずっと続いていくものと私は考えます。これが遺伝的にハードコーディングされた部分だと見るからです。BLを進化論的にどう説明するかという議論があります。これに対する回答を私がどこで知ったのかは忘れましたが、同性愛もそれが進化に無意味ではなかったから、というのが進化心理学的な観点なのです。
── 講演後質疑応答でのKimの発言(筆者訳)
当然、日本においても様々なサブカル、オタク文化論的な議論が存在するのだが、ここで注視すべきは、定義も曖昧な日本のサブカルチャーが、経済・文化的な外側からも客観的に分析され、これが逆輸入の為のローカライズの基礎理論へと繋がっている点である。既に述べた通り、『ブルアカ』の製作陣がこうした日本の文化に早くから関心を持ち、その純粋な情熱とリスペクトが「より日本的なもの」への追求の原動力となっているのだが、ここで本章のはじめに挙げた疑問に戻れば、それ故に丁寧な「再現性」が本作には基礎付けされていると言えるのである。プレイヤーが初見に感じる凡庸さというのはむしろ、異質さを意図的に取り除いた上での技巧であり、局所的な文化が「普通に」受容されることがまず何よりも特筆されるべき事柄なのである。
Ⅲ 「からっぽな」日本、虚妄のサンクトゥムと「機軸」の不在
ここまで、「送り手」側の事情を確認してきたが、ここからは「受け手」側の状態として日本の文化・市場についても歴史を遡りつつ整理していきたい。
私はこれからの日本に大して希望をつなぐことができない。このまま行ったら「日本」はなくなってしまうのではないかという感を日ましに深くする。日本はなくなって、その代わりに、無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜目がない、或る経済的大国が極東の一角に残るのであろう。それでもいいと思っている人たちと、私は口をきく気にもなれなくなっているのである。
── 三島由紀夫『果たし得ていない約束──私の中の25年』1970年 7月 7日 サンケイ新聞夕刊
小説家、三島由紀夫は1925年(大正14年)に生まれ、「行動する作家」として優れた作品を残しつつ、「行為」の実践として政治的な活動にも積極的に関わりを持った。上記の高名な一節は彼の晩年の思想を照らす重要なものだが、彼の思う「日本」「文化」というものは天皇を中心として確かに存在し、それを護持すべきだという主張を一貫して行なっていた。
三島は学習院初等科、中等科、高等科を卒業し、東京帝国大学法学部卒業後は大蔵省に勤務、程なくして作家業に専念したが、東京帝大在学中には戦時召集を受け、戦争と死生観を同期させるような時代も経過している。三島にとっての昭和「日本」はその来歴からも読めるように、彼自身の実存と深く結びついている。そして、彼が提起する通り、日本にとってのアイデンティティの確立は戦後、あるいはそれ以前からの重大な問題であった。
同じく東京帝大に属した政治学者、丸山眞男は1914年(大正3年)の生まれであり、三島より少し上の世代となるが、彼も戦争を経験し「生き残ってしまった」人のひとりである。卒業後は助手として大学に残り、後に東大法学部教授となる。日本政治学界を牽引し、戦後民主主義思想の展開にも大きな役割を果たした。
三島は丸山に対し立場上の批判、つまり彼の東大教授としての権威主義的な在り方に大正教養主義以来の知性主義、「オールドリベラリスト」としての側面があると批判していた。丸山はそうした当時の(アメリカ追随的な)戦後民主主義批判の仮想敵とされたが、本人はこれに応じるようなかたちで日本の政治思想史研究を戦後の民主主義まで見通した上で包括的に体系化している。以下は丸山の代表作『日本の思想』における冒頭の一節である。
一言でいうと実もふたもないことになってしまうが、つまりこれはあらゆる時代の観念や思想に否応なく相互関連性を与え、すべての思想的立場がそれとの関係で──否定を通じてでも──自己を歴史的に位置づけるような中核あるいは座標軸に当る思想的伝統はわが国には形成されなかった、ということだ。私達はこうした自分の置かれた位置をただ悲観したり美化したりしないで、まずその現実を見すえて、そこから出発するほかはなかろう。
── 丸山眞男『日本の思想』1961年 岩波新書
この表明からも見て取れるように、丸山にとっての日本は「からっぽ」で然るべき存在であった。戦後、アメリカの占領によって押し付けられた理念としての「民主主義」「平和」に寄り添うべきか、決別すべきか。あるいは全てを明治維新からの歴史的産物として捉えるか。個々によって様々な「日本」アイデンティティがあろうが、むしろその多様な「雑居的無秩序性」に彼は可能性を感じていた。近代日本の出発点、明治の「帝国憲法草案審議」には既にこうしたアイデンティティを巡る問題意識が現れている。
抑、欧州ニ於テハ憲法政治ノ萌セル事千余年、独リ人民ノ此制度ニ習熟セルノミナラス、又宗教ナル者アリテ之カ機軸ヲ為シ、深ク人心ニ浸透シテ、人心此ニ帰一セリ。然ルニ我国ニ在テハ宗教ナル者其力微弱ニシテ、一モ国家ノ機軸タルヘキモノナシ。
── 清水伸『帝国憲法制定会議』議長伊藤博文の所信
丸山は伊藤がこの「機軸」の不在に代わるものとして「天皇制」を建てたとして、日本思想の根本的混迷を説いている。そうした上で、先の日本における「雑居」性をさらなるコミュニケーションによって「雑種」化することを次の課題としている。異なる思想が空間的に交わらず、ただ同時存在しているだけの「雑居」から、多様な思想が本当の意味で内面的に交流し「雑種」という新たな個性の誕生を目指すという意味においてである。話を現代に戻すと、驚くほど器用な文化の再現には「文化」そのものではなく、それを扱う人々の側に主体性が現れている。世界のグローバル化は遠回りをしつつも、自己のイメージを獲得するという意味での、真の「他者」を発見しつつあると言えるだろう。
丸山は自身の研究の所信について、『大日本帝国の「実在」よりも戦後民主主義の「虚妄」の方に賭ける。』と述べている。(『増補版 現代政治の思想と行動』1964年)無批判的な東西融合論や現状追認的な自己弁護には常に警戒しなければならないが、たとえ機軸としてのサンクトゥムが「虚妄」であったとしても、私たちは私たち自身に「主体性」を創造し実践していかなければならない。それこそが文化に裏付けられる、アイデンティティ、それ自体の建設に他ならないからである。
Ⅳ 再構築の契機あるいは“交流”としての“交換”
日本人が掴みきれなかった「文化」はその本質の発見を待たずして、客体化され、内実はどうあれ一つのアイデンティティとして浸透しつつある。文化人類学者の太田好信は、観光を通じて見られる文化の客体化において、その政治的力関係の編目を利用した、自己の文化ならびにアイデンティティの創出が見られると分析する。
今では、遠野市と『遠野物語』の両者を切り離すことはできない。ちなみに、1991年刊行の統計によれば、遠野市の人口は3万人を割ったが、その反面、年間の観光客は40万人を超えている。遠野市の行政も『遠野物語』が重要な観光資源であることは十分に認識している(遠野市1991)。岩手国体のあった1970年から、市は「民話のふるさと遠野」をキャッチフレーズに観光施設を整備してきた。現在では、駅に降り立つと、真向かえのロータリーには「遠野物語碑」が立っているし、左手には「カッパの田助(彫刻)」が迎えてくれる。駅前通りを真っすぐ進むと、柳田が泊まった高善旅館を移築した「柳翁宿」があり、他に「物語蔵」と「宴蔵」とを合わせて「とおの昔話村」を形成している。……まさに、遠野市は柳田の『遠野物語』にそって街を表象してきたことになる。換言すれば、観光産業に依存するようになり、遠野の人々は自己の生きる世界を民族学的な表象の世界としてイメージし始めた。
── 太田好信 文化の客体化──観光をとおした文化とアイデンティティの創造──
ここでも外部から与えられたイメージが、「観光」という資本主義経済の力によってではあるが、新しい自己の確立に影響を及ぼしている。元々あったかもしれない「純粋な文化」が一度外に持ち出され、再度流入することによって文化創造という主体性の回復を行なっているのである。柳田國男がかつて見たような「遠野」は失われてしまったが、遠野市民にとっての「遠野」は誕生したと言える。
文化の存在理由が人々のより良い自己形成、自己肯定にあるのであれば、既にそれは道具あるいは手段として向き合っていかなければならないものである。今回、「NEXON Games」「Yostar」が解釈し、投げかけてきたものは、確かに「マイノリティ」で「局所的」な文化である。だがそれこそが、文化の本来的な母体であり、それに対し、主体的に依拠することを選択した個々人にとっては重大な「アイデンティティ」の問題なのである。
『ブルアカ』によって交換された「より日本的なもの」という文化が、真に「より日本的なもの」であるかどうかは重要ではない。文化を通じて、そこに宿るクリエイターの主体性が消費者との交流に向かうこと、同じように受け手側が主体性を持って応えることは、丸山の信じたような新たな文化、雑種性というものを生むのではないだろうか。80年代以後、傍流としてあった「日本サブカルチャー」はいかにも「虚妄的」な代物であったが、ここにようやくひとつの文化アイデンティティを巡る思想的闘争、その「戦後」としての時代が始まるのではないか、そうした可能性を本作には垣間見るのである。
Ⅴ おわりに
作中の舞台となる「学園都市キヴォトス」では、思想も種別も異なる生徒たちが、それぞれの共同体を作り、いかにも雑居的な世界を創出している。中央の「サンクトゥムタワー」には、「連邦生徒会」が機軸として聳え立ち、ひとつの連邦制国家を為している。もはや云うまでもなく、機軸は虚妄であり、その攻略こそ生徒たちに組織横断的な主体性を与えた。
「株式会社Yostar」その母体である「上海悠星網絡科技有限公司」。現CEOの姚蒙(Yao Meng)は、中国の複雑な社会情勢、政治政策が経済界に与える影響の大きさを念頭に、将来的には「日本に軸足を置いて、グローバルパブリッシングを」目指したいと語っている。そこには確かに経済を基調にしつつも、「文化」を尊重する人々の普遍的な態度が見られる。
現在、世界が直面する国際政治学的な諸問題は、各国の自己アイデンティティの再形成の問題であり、当然にそれは日本にとっても同様の事柄である。必要なのは、我々が、我々自身の精神的内面に交流を促すこと、そして、それによって誠実な主体性を獲得することである。──それこそが他ならぬ私たちにとっての「虚妄のサンクトゥム攻略戦」となるのである。
参考資料
丸山眞男 1961『日本の思想』岩波新書
三島由紀夫 2006『文化防衛論』筑摩書房
山本昭宏 2021『戦後民主主義』中公新書
太田好信 1993『文化の客体化』民族学研究
豊島圭介 2020『三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実』
webサイト
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
