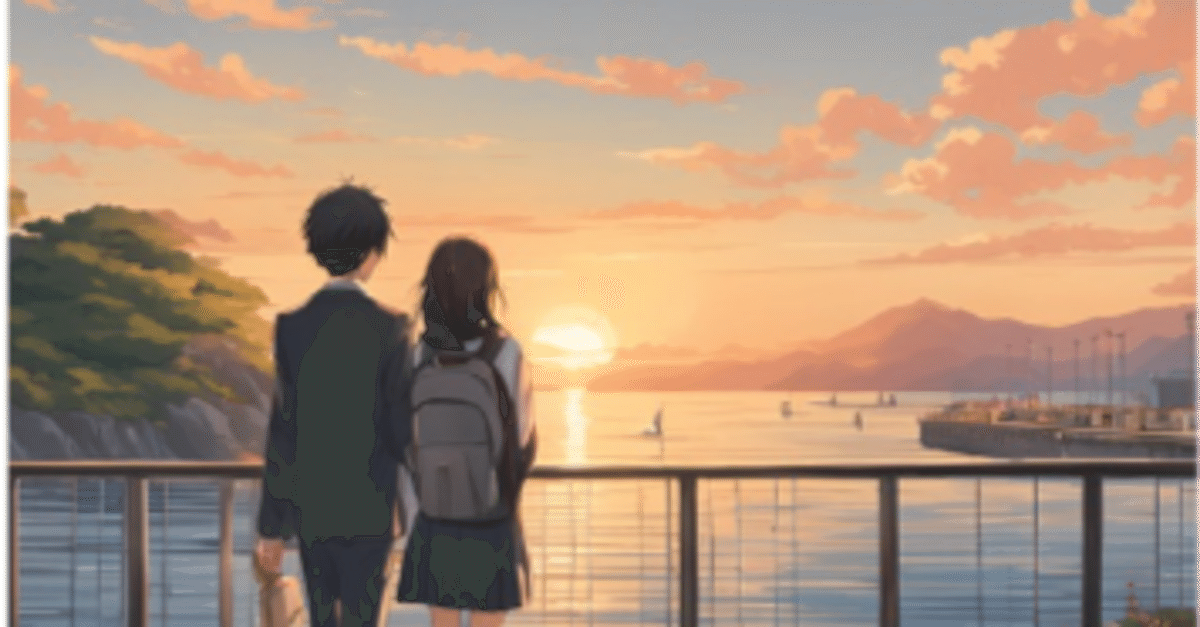
早川沙織からの手紙 #13
沙織ふたたび1
廊下で、沙織が木嶋と親しそうにしゃべっているのを見かけた。
ぼくは、(へー、意外な組み合わせだな)と思った。
たまに3組の教室を見ることがあるけど、沙織が小田桐ヒナ以外の女子といるのをはじめて見た気がする。
木嶋は明るい髪をしてるし、ネクタイを緩めて、スカートもかなり短い。6月に入って衣替えの時期だけど、制服の着こなしからして対極的なふたりだ。
ぼくは、沙織に近寄って声をかけた。
「なに話してたんだ、木嶋と」
「面白い人ね、彼女。陽気というか、畳みかけるように話してきて。同じバンドに彼氏がいるのね。知ってた?」
「知ってるもなにも、大学生のヤツだろ。まえにライブを見にいったことあるけど、チャラそうだった。そんなこと聞いたのか」
「チケットを譲ってもらったのよ。ライブを見にきてくれって」
「売れ残りを捌きたかっただけだろ。……もしかして、行くつもりなのか」
「今日の18時みたい」
「やめといたほうがいいって」
「どうして? せっかく仲良くなったのに」
「早川さんが行くような場所じゃないし。絶対、へんな男にからまれる」
「平気よ。ライブぐらい、何度もいったことあるのよ」
「だから、そういうコンサートみたいなのじゃないし。3Bって聞いたことない?」
「なにそれ」
ぼくは、やれやれって思った。
お嬢さま育ちの沙織は、アイドルのコンサートみたいに思ってる。
ライブハウスは、純粋に音楽を楽しむ場所かといわれれば、そうではないと、ぼくは思う。ヨシオの付き合いでたまに行くことがあるけど、音楽をきっかけに出会いや交流を求める場所だ。ようするに可愛い女子を見つけて、引っかけようとするバンドマンは多い。
「ぼくも行ってやろうか。早川さん、ひとりだと心配だし」
「そういうと思って、楠くんのももらっておいたわよ。1500円だって」
沙織は、右手を出した。
アイソよく笑ってる。ぼくを見て、いい金ヅルだって思ってるみたいに。
「ちゃっかりしてるなぁ」
放課後、ぼくと沙織は自転車で市の中心部へむかった。
ライブハウスは、若者が集まるセンター街の近くにある。
バスは中央駅を経由するので遠回りになるけど、自転車だと地下道をショートカットできるので時間的には変わらなかったりする。
ライブまで時間があるので、近くの駐輪場に自転車を停めて、沙織とアーケード街をブラブラすることにした。
市の中心部だけありにぎやかで、学校帰りの学生が多い。観光客っぽい外国人の姿もある。
ぼくはこっちにあんまり来ないので、アウェーに来た感じだ。
「試験終わりとかに、ナオミやミカとよく歩いて回ってたのよ。買い物とか。この先にケーキの美味しいカフェがあるの」
「へー、このへんは早川さんのテリトリーか」
「電車通りを渡って、地下街を抜ければ市立図書館があるでしょ」
「そっちはあんまり行かないな。用事もないし」
「ねえ、これ見て。かわいい」
沙織はシューズショップにふらりと入った。
飾ってあったスニーカーを手に取って眺める。
「うちの学校って、シューズは自由でしょ。革靴の人もいるけど、スニーカーやバッシュや、個性があるわよね。まえの学校では、女子はみんなローファーだったのよ。校則で決められてるってわけじゃないけど、入学するときに学生手引きみたいなのがあって、そこに革靴が書いてあるの。あれって刷り込みよね。自分ひとりだけちがうのってなかなか選びずらいでしょ」
「シューズだけじゃなくて、髪型も自由だよ。制服だってネクタイをしてれば、カーディガンを羽織ってようが、ジャージを着てようが注意されないよ。さすがにスカートやズボンを履いてなかったら連れてかれるけど」
「ふふっ、そうね。そういうところが大事なのよね。場所によって、どういう服装をすればいいのか自分たちで考える力をつける。立派な教育よね」
沙織は、ナイキのスニーカーと、アディダスのスニーカーを手に取った。
どっちも女子が好きそうなおしゃれなデザインで、値段は16000円ぐらいする。
「ねえ、どっちがいい」
「買うの?」
「今日は見るだけ。つぎに来たときに買うかもしれないでしょ。参考に」
「通学用なら、これがいいんじゃない」
ぼくは、アシックスの白のスニーカーを勧めた。
アシックスのいいところは、日本人の足の形に合わせて作ってあるところだ。デザインはアディダスやナイキには劣るけど、機能はほとんど変わらない。
陸上部のときに履いてたシューズもアシックスだった。
「シンプルで、値段も手ごろだろ。履いてて疲れないし、嫌味もない。もし気に入らなかったらランニングで履き潰せばいい。靴はすこし汚れても平気なぐらいがいいよ」
「さすが元陸上部の意見ね」
2年で辞めたけどね、とぼくは付け加えた。
ライブハウスは雑居ビルの狭い階段を降りた地下にある。
通路には、大量のチラシやステッカーが乱雑に張ってあって、そこだけ下北沢のライブハウスのような、ストリートパンク的な雰囲気がある。
会場は足元が見えないほど薄暗い。100人も入れば身動きが取れなくなるような小さな箱で、ステージには大きなスピーカーやアンプ、ドラムなどの楽器が並んでいる。
見たところ20人ほど客が入っていた。そのうちの半数は、ぼくらと同じような学校帰りの女子高生で、ほかに女子大生っぽいのがチラホラいた。半分以上が女で、男はぼくをいれて数名しかいなかった。
(まあ、こんなもんだよな)
と思った。
ステージには4組のバンドが出演して、後半になるにつれて、それなりに集客力のあるインディーズバンドが登場するので客が増えてく感じだ。
最初に木嶋の参加してるバンドが登場した。
木嶋はギターを担当している。すごく美人ってわけじゃないけど、ブリーチをかけててスタイルがよくて、おまけに制服姿なので、おのずと目立つ。
腕前だって、なかなかのもんだ。そのへんの軽音楽部のヤツよりうまいんじゃないかと思う。
「すごい音。木嶋さん、かっこいいわね」
「なに? 聞こえない」
「木嶋さん、かっこいいわねっていったの」
沙織は、スピーカーの爆音にかき消されないよう大きな声を出した。
ぼくは、「ああ」と大きな声でうなずいた。
「この曲、なに?」
「イエモンだろ」
「なにそれ?」
「THE YELLOW MONKEY。SPARKかな。知らない?」
「知らない。いい曲ね」
イエモンの歌はセクシャルな歌が多いけど、この曲はとくにそうだ。女を口説くために書いたような歌詞をしてる。
あらためて聴いてみると、いままでとはちがった感想が自分の中にあることに気づく。
なにか暗示めいたモノを感じる。
とくに《暗闇の中 すがりつくように 血がめぐるのを確かめている》の部分は、まるで暗い洞窟の夢のことをいってるみたいだ。ぼくの考えすぎだとは思うけど。
最前列には、制服姿の女子高生(?)が陣取り、ステージに手を伸ばすようにしてノリノリで応援してた。
たぶん、追っかけのファンかなんかなんだろう。
アマチュアバンドだって、そういうファンはかならずいる。
沙織はスクールバッグを肩に引っかけて、リズムに合わせて体を揺らしてた。ライブハウス独特の雰囲気を楽しんでいるみたいだ。
(へー、ノリいいんだな)
と感心した。
K-POPやあいみょんも聞くといってたのは、あながちウソではないんだ、と。
もともと活発なタイプだし、こういう人が集まる場所も好きなんだろう。
やっぱりライブは臨場感がちがう。ワアっと盛り上がる感じがして、一体感があるのがいい。日常から切り離された独特の世界があって、学校のことや勉強のことを忘れられる。
4曲続けて演奏をして、木嶋たちのバンドが引っ込んだ。
つぎのバンドと入れ替わるまでのあいだ、ぼくは後ろのバーカウンターにいって、沙織の分も飲み物をもらってくることにした。チケットにはワンドリンクサービスがついてて、無料でもらえる。
ふと沙織を見ると、隣に黒いTシャツの若い男に立ってた。金髪で耳にピアスをした、見るからにチャラい。
なにやら沙織に熱心に話しかけている。ナンパかよ、と思った。
(あいつ、木嶋の彼氏だろ。大学生の)
見覚えがあると思ったら、さっきまでステージにいたボーカルの男だった。
たぶんステージで歌ってて、沙織に目をつけたんだ。
親しそうに声をかけながら、液体の入ったグラスを渡してた。おそらく、ジンジャーエールかオレンジジュースかなにか。ここからは、はっきりとはわからない。
飲むように勧めてる。
沙織が笑顔で返事をするようにグラスに口をつける。
ぼくは、(浮かれて、なにやってんだ)と思った。
すぐに駆け寄ると、沙織の腕を掴んで出口に引っ張った。
「なによ、急に」
「用事はすんだろ。帰るぞ」
「ちょっと痛い」
沙織は、ぼくが腕を強く引っ張ったんで、おどろいたみたいだった。
「オイ、俺がまだ話してるだろ」
大学生の男が、後ろからぼくの肩を掴んできた。
腕にタトゥーが入ってて、ヤバそうな感じだった。
ここで引き下がったら絶対にダメだと思って、一発殴られる覚悟で相手の顔をにらみ返した。
「ぼくの女に、なんか用ですか」
周りには、ほかの客もいるし、警察を呼ばれたら、それはそれでいいと開き直ったわけだ。
大学生の男は、舌打ちをしてどっかにいった。
ドアを出て、沙織の腕を引いて階段を登る。
外はまだ明るかったけど日がかなり傾いてて、学生の姿も少なくなってた。かわりに仕事帰りのサラリーマンや、やんちゃそうなマイルドヤンキー、派手なメイクのギャルが増えていた。
「早川さん、バカなの。声かけられたぐらいで、すぐ浮かれて」
「なによ。英語で赤点取ってる、楠くんにいわれたくないわ」
「知らないヤツにもらったジュースを飲んで。なにか入れられてたらどうするんだよ」
「ふーん。先生みたいなことをいうのね」
「もっと警戒したほうがいいっつー、話だろ。そういう事件も多いんだし。あんなチャラそうな男」
「楠くんこそ、木嶋さんと楽しそうにしてたくせに」
「いつの話だよ。だいたい木嶋は関係ないだろ」
「教室でデレデレしちゃって、バッカみたい」
「あのさー。どうしてケンカ腰なんだよ」
駐輪場まできたところで、沙織の顔がやけに赤いことに気が付いた。
はじめは、怒ってて顔が赤いのかと思ったけど、どうもちがう感じだ。
目が潤んで、トローンとしてた。
「早川さん、大丈夫?」
ぼくは、心配してたずねた。
「大丈夫よ」
「ぜんぜん、そうは見えないけど」
「ちょっと頭がボーっとするかも。お酒が入ってたかな」
「家まで送るよ」
「ひとりで帰れるわよ。そんな遠くないし」
「こんな状態で、自転車に乗るほうがマズイだろ」
沙織の自転車は、駐輪場に置いておくことにした。明日、取りにくればいい。
ぼくは、不機嫌そうな沙織を後ろに乗せて、自転車をこぎだした。
銀杏通りを、通行人を避けるように進む。警察官に見つかったら注意されるけど、いまはそんなことをいってる場合ではないような気がした。
「ねえ……さっきのセリフ」
「なに?」
「私って、楠くんの女なんだ」
「しょうがないだろ、あの場は。マジで殴られそうな雰囲気だったし」
「ま、いいわ……今日は特別に許してあげる」
「やけに素直じゃん」
「なんか調子悪いのよ。すごく眠い」
「だから、いっただろ。家はどこだよ」
「あっち。市役所のほう」
「市役所っていってもさ。このへんはくわしくないのに」
「あれ、見えるでしょ」
「あれ?」
市役所の奥に、でっかいビルが見えた。
もともとは大学があった場所で、土地の広い田舎に移転して、そこに3年ぐらいまえに再開発で建ったタワマンだ。県内で一番高いってニュースになってた。
「もしかして、あれに住んでるのか」
「そう」
「すげえな。やっぱお嬢さまじゃん」
「だから、ちがうって……」
沙織の声がどんどん小さくなっていってた。
タワマンの入り口は、大きなガラスの自動ドアに、ピカピカの大理石の床と柱があって、中を覗くと1階がホテルのロビーみたいに広々としてた。
自転車から降りた沙織は、酔っぱらいみたいに足元がフラフラしてた。
目が虚ろで、自分ひとりでは歩けない様子だ。
「おい、しっかりしろよ。顔色、ヤバいぞ」
ぼくは、あわてて沙織を支えた。体の芯が溶けたみたいに、ぐにゃっとしている。
「失敗した……気持ち悪い。楠くんが3人いる」
「部屋までもどれそう? 救急車、呼ぶか?」
グラスのジュースを半分も飲んでないはずなのに、かなり酩酊してる。なにかわからないけど、ドラッグを盛られた様子だ。
ぼくも、どうしたらいいのかわからずに混乱した。
救急車を呼んで付き添って……それより、タワマンの親御さんを呼んだほうが早いか。どっちにしろいろいろ事情を聞かれて、学校に連絡がいってめんどくさいことになりそうだぞ、とか想像した。
「……すこし横になってたら平気、たぶん」
「本当か。無理すんなよ」
「……私、これでも医者の娘よ」
「この状況でいわれても、説得力ないだろ」
ぼくは、どこか休めるような場所はないかと周りを見回した。
このへんは市役所の近くで、高いビルが多い。
タワマンの目の前には、ランニングをするのにちょうど良さそうな芝生の公園があり、とりあえずそこで様子を見ることにした。
ベンチに座らせると、沙織はぼくの肩に寄り掛かるようにして、スース―と眠りはじめた。
膝にスクールバッグを置いて、電池が切れたみたいに熟睡モードに入ってた。
(子供みたいな顔してら……もうちょっとで大変なことになってたぞ)
日も完全に落ちて、すっかり暗くなった。
昼間はちょうどいいぐらいだけど、夜はまだ肌寒い。
ぼくは、縄抜けをするみたいに着ていたパーカーを脱いで、沙織の肩にかけた。
あご肘をついて、(なにやってんだ)と思った。
なるべく体を動かさないようにして、公園を散歩する人や犬を眺めてた。
目の前にそびえるでっかいタワマンには部屋の灯りがともり、季節外れの巨大なクリスマスツリーのように見えた。
(早川さんの家は何階だろ。眺め、めちゃくちゃいいだろうな)
と思った。
夏の花火大会とか、部屋の方角にもよるけど最高のビュースポットだ。
家賃も高そうだと考えて、こういうのは賃貸じゃなくて分譲なんだと思った。
(やっぱ1億円とかすんのかな。サラリーマンの年収何十年分だろ)
とか考えた。
なんか自分がすごく卑しい人間のような気がした。
人の家を値段で計ろうっていう考えがせこい。沙織に対しても失礼だ。
(起きたら、早川さんを叱ってやろう。本人のためにもならない)
そう思ってはいるものの、ぼくの肩に寄り掛かってスヤスヤと眠る沙織を見ると、憎めないよなぁとか思って信念が揺らぐ。
結局、沙織を怒りたいのか甘やかしたいのか、どっちなのかわからなくなる。
とにかく今日のことは注意しとかないといけない。
それだけは、強く自分に言い聞かせる。
沙織が目を覚ましたのは、たっぷり2時間ぐらいしてからだった。
そのあいだ、沙織のスマホが何回も鳴ってた。
たぶん、帰りが遅いのを心配した親だろう。
ぼくが出るわけにもいかないので、無視をしてた。
(娘が、すぐ下の公園で寝てるとは思わないよな)
とかノンキに考えてた。
「楠くん、いま何時?」
ぼくは、答える代わりにスマホの画面を見せた。
沙織は、大事な模試でE判定を取ったみたいな顔をしてた。
ベンチから立ち上がる。
まだ足元がフラついていた。
「まだ無理しないほうがいいんじゃ」
「そうもいってられないわよ……ごめんね。こんな遅くまで足止めして。とにかく、あとで連絡するわ」
「ああ、はやく家に帰って、風呂でも入って寝たほうがいい」
「そうする……おやすみなさい」
沙織は、ぼくを見てどっかホッとしたような顔をしてた。
スクールバッグを抱えるようにタワマンの入り口に駆けていった。
一時はどうなるかと思ったけど、たいしたことなかったみたいで一安心だ。
「あっ……パーカー」
気づいたときには、沙織の後ろ姿はエントランスに消えていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
