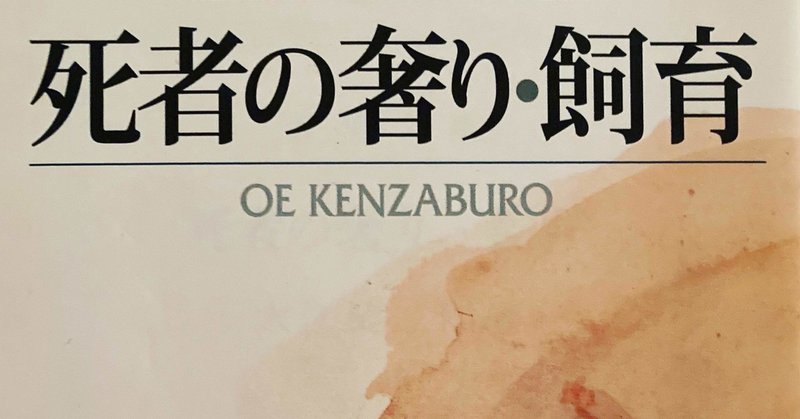
死者の奢り・飼育
"死者たちは、濃褐色の液に浸って、腕を絡みあい、頭を押しつけあって、ぎっしり浮かび、また半ば沈みかかっている"1957年発表の著者デビュー作『死者の奢り』そして当時23歳で最年少での芥川賞受賞となった1958年発表の『飼育』含む本書は実存主義、時代の閉塞感を感じる寓話的な初期作品集。
個人的には、著者の『万延元年のフットボール』を課題図書にした読書会を開催する事もあり、勉強のために手にとりました。
さて、そんな本書は『万延元年のフットボール』や『同時代ゲーム』といった、既読の長編作品–どちらかと言うと難解な作品から入った私にとっては、比較して【無機質かつ瑞々しく】とても読みやすい印象を受ける初期の短編、屍体処理室の不条理なアルバイトを描いた『死者の奢り』脊髄カリエスの少年たちの哀歌『他人の足』黒人兵と寒村の子供たちとの悲劇『飼育』外国兵の理不尽な仕打ちと傍観者への侮蔑を込めた『人間の羊』など6編が収録されているわけですが。
まず、やはり中では、デビュー作にして、屍体と妊婦など様々な形で生と死を繰り返し対比させた『死者の奢り』ありがちな黒人兵と子供たちの心の交流を描くどころか"黒人兵を獣のように飼う"と家畜として扱う『飼育』が【内容や主題にインパクトがあって】印象に残りました。(しかし屍体処理のバイトって、私が学生時代にも都市伝説的に話題になったのですが。実際どうなんでしょうか?)
また、残りの4作品『他人の足』『人間の羊』『不意の唖』『戦いの今日』についても。それぞれに敗戦後の日本社会の閉塞感や世界的な影響を与えていたサルトルの【実存主義の影響を強く感じる不条理さ】そして、後期の作品にも繋がるような【閉じられた集落の異質さ】が感じられると共に、次第に【作品が洗練されていく変化】も伝わってきて興味深かったです。
著者作を読み始める最初の一冊として、また敗戦後の昭和の空気感漂う作品や不条理な寓話的な短編が好きな人にもオススメ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
