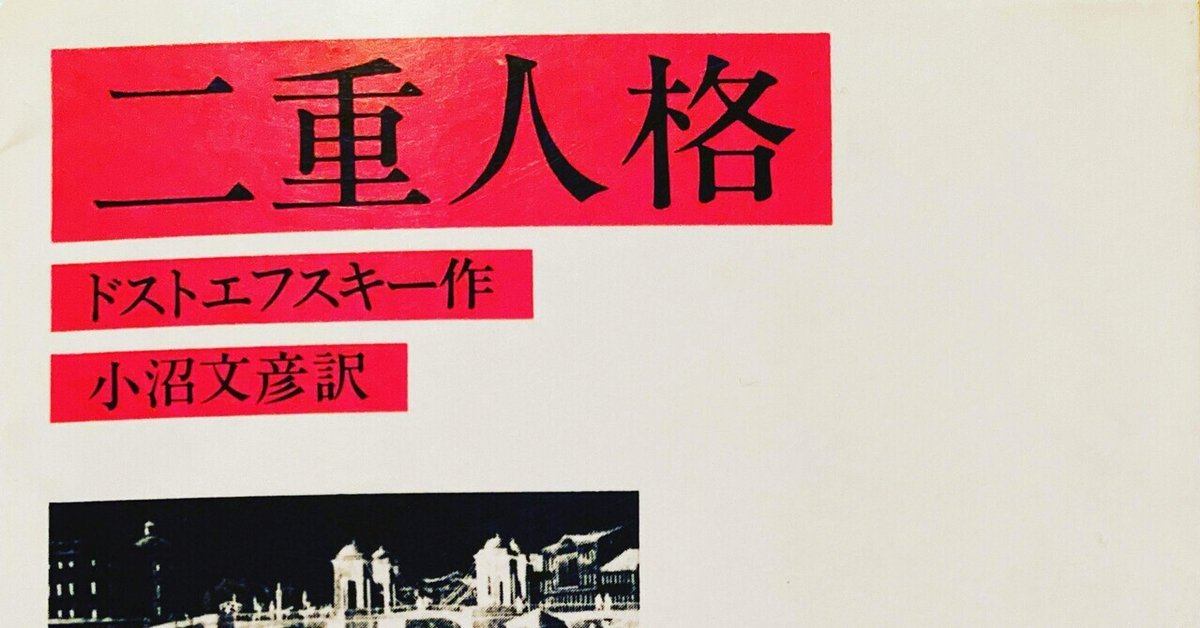
二重人格
"誰かがいま、たったいま、彼のかたわらに、彼と並んで、同じように河岸の欄干にもたれていたように、彼には思われたのである"1846年の本書は(『分身』とも訳される)著者、20代における第二作目にして『嗤う分身』として2013年に映画化もされたゴーゴリの強い影響下で書かれた、どこかユーモラスな心理・幻想小説。
個人的には寒くなってくると『こってりとしたラーメンが食べたくなるような気持ち』で著者作の中ではあまり有名ではないと思われる本書を手にとりました。
さて、そんな本書は現代にもいるであろう、野心こそあるも小心で引っ込み思案、それでも家柄や才能はない不安定な立場なりに九等文官にまではなった(日本のビジネスパーソンで言えば主任、係長くらいでしょうか?)小役人、ヤーコフ・ペトロヴィッチ・ゴリャートキンが恋する女性の誕生パーティーにて手痛い失敗を犯して追い出された帰り道【自分と同姓同名、瓜二つの男】に出会い、しかも次の日には同じ職場で再会したことから破滅に向かった悲喜劇が幕を開けるわけですが。
まず【物語以前の前に】訳者があとがきで『くどいまでの反復描写、冗長とさえ思われる叙述にうんざりする読者も多いことと思われる』と書いているように(原文はしらないが)そして良くも悪くも著者のハイテンションなテキストは(こってりと)魅力的な部分であるとはいえ、本書では特にただでさえ馴染みにくい名前『ヤーコフ・ペトロヴィッチ・ゴリャートキン』がある見開きページでは、本文中に10回以上繰り返されたりするのは【率直に言えば拙い印象でうんざりした】(おそらく現在なら発表前の編集段階で修正されると思う)
一方で、デビュー作にして絶賛も浴びた往復書簡形式の既読の中編『貧しき人びと』がしかし、物語的にはシンプルな恋愛小説だとすると、若き25才の著者が兄に"『貧しき人々』よりも十倍も上の作品です"と伝えたように、未だ尊敬していたゴーゴリの『外套』や『狂人日記』の影響は強く感じるも、本書の現実と虚構が入り乱れる内容は確かに【工夫が感じられるや野心作】だと思うし、現代読書の1人としては後の時代の【カフカ的不条理文学を先取り】しているようにも感じられて【終始救いのない主人公に同情するも】全体的にはエンタメ作として楽しめました。
19世紀を代表する文豪の若き時代の野心作として、また虚実入り乱れる心理・幻想小説好き、ゴーゴリ好きにオススメ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
