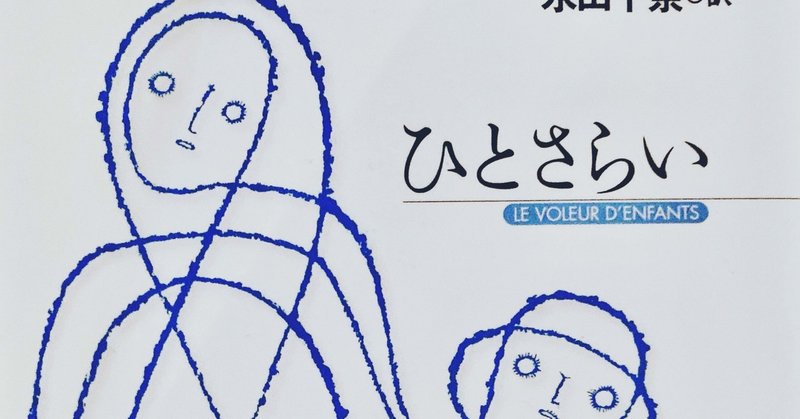
ひとさらい
"南米に帰るなら、どうしてもパリの女の子を連れてゆきたい。パリじゅうの少女から私の娘を選び出すのだ。"1926年発刊の本書は、フランスとウルグアイの複眼的な視点で知られる著者による"擬似家族"を築き、愛すれば愛するほどに孤独になる心優しい誘拐犯の悲哀を描いた一冊。
個人的には本好きの友人にすすめられて、著者の作品は初めて手にとったのですが。
まず印象に残るのは、やはり【一人称と三人称が混然と溶け合う文体】でしょうか。著者自身が後年になって本書の続編もあわせて戯曲化、こちらも成功を収めたことも納得させられる【童話のようで、群像劇のように流れていく】本書はポエティックな言葉遣い"ふたりのあいだに沈黙が広がるのが聞こえてきた。ふたりは深く見つめ合うために、沈黙しているのだ。"もあって、イメージが湧き上がってくるような不思議かつ独特な読み心地でした。
また、本書の主人公の『ビグア大佐の行為』社会的には成功をおさめ、何不自由なく暮らしているにも関わらず【ただ子供が欲しい】その欲求のままに子供たちを次々に誘拐し、出産時の逸話をでっちあげてでも【妻との間に愛情溢れる擬似家族をつくりあげていく】姿は、悪人なのか?善人なのか?それとも単なる変わり者なのか?誘拐された子供たちは不孝なのか?幸福なのか?【様々に価値観を揺さぶり、判断を混乱させてくる】感覚があって、とても考えさせられました。
フランスと南米の魅力が溶け合ったような不思議な物語が好きな人へ、またポエティックに読みやすい独特な文体が好きな人にもオススメ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
