
旅籠とは「旅に籠る」こと 越後湯沢のHATAGO井仙
当日の朝。その日に泊まる宿を予約する。
そんな日々が日常となった今、それでも「予約の過程」の時間を惜しまない。
最近、明日はどこへ行くの?と聞かれても、
「泊まりたい場所が見つかった場所へ」としか答えていない気がする。
「農業と観光の未来」を探索して。

HATAGO井仙。越後湯沢駅前にある旅館。こちらの宿を経営する井口氏は、南魚沼市でも旅館ryugonを経営、そして雪国観光圏の代表理事も務める。
雪国観光圏は2008年に「豪雪地の文化を発信して、地域に人を呼び込もう」と雪国ガストロノミーツーリズムとして発信。南魚沼市、魚沼市、津南町、湯沢町、十日町市、と栄村、みなかみ町、と共に設立された。
コロナ渦は「ようやく、日本人の旅行の仕方が劇的に変わるきっかけ」だという。


旬の地元食材や保存食、発酵食などの創作料理を提供するレストラン。

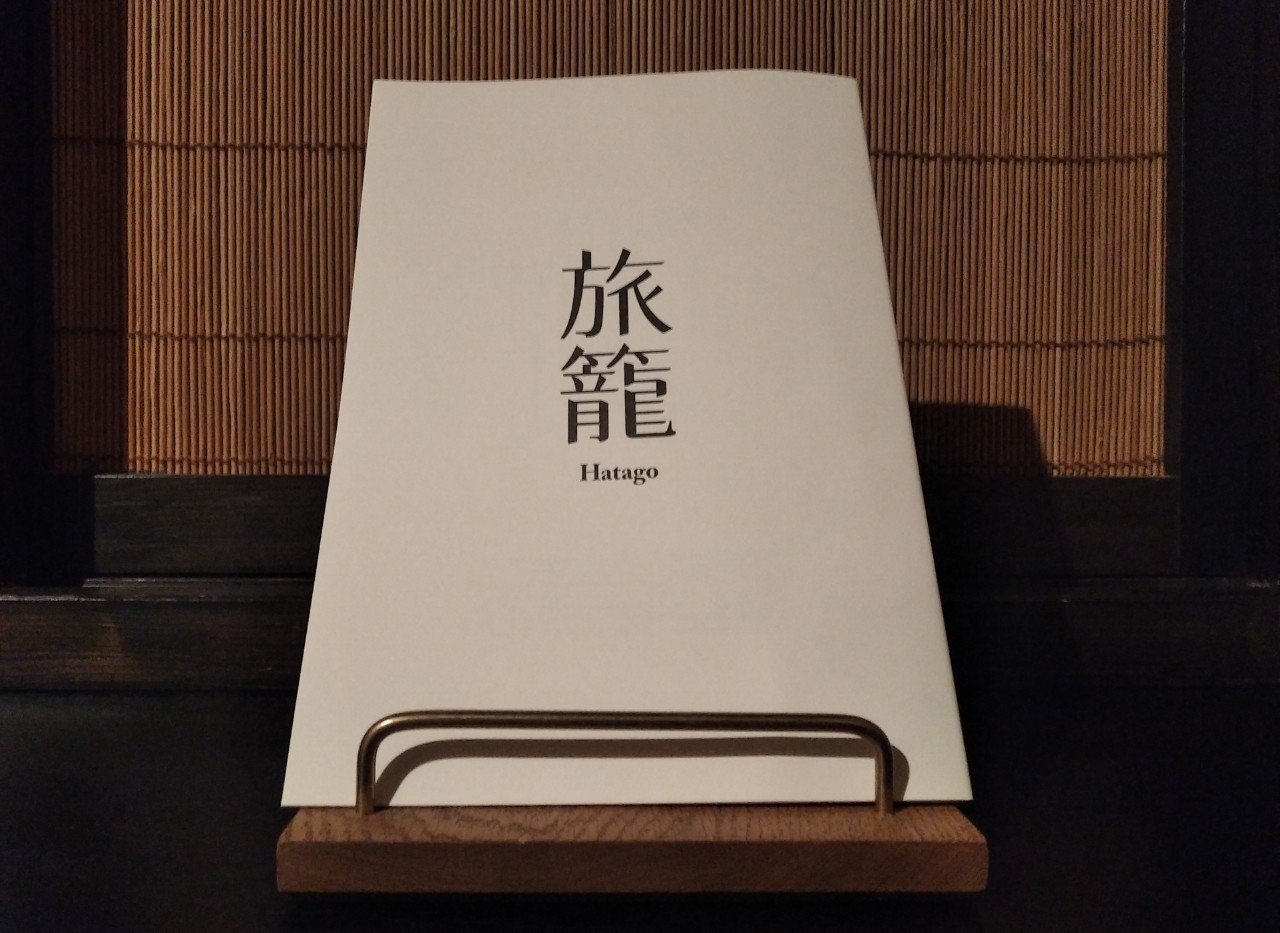
そうか、「旅籠」って「旅に籠る」と書くんだった。部屋に籠る、カフェに籠る、何かの内に籠るような感覚だけれど、それは旅という、もっと大きな、包み込んでくれるような、外に開けた「籠る」でもあるんだ、となぜか、解放感すら感じた。

「旅籠-はたご-」とは、もともと旅の時、馬の飼料を入れて運んだ竹籠のこと。旅行用の食べ物や日用品を入れたこともあるそうです。それが門口にぶらさげてあれば、旅の宿の目印に。そして江戸時代には食事や風呂を提供する宿屋を意味するようになりました。旅籠とは旅の宿であり、旅のアイコン。そして今「旅に籠(こも)る」、そう読み替えてみたら、イメージが広がりました。


南魚沼市のryugonでは、雪国の食文化を体験してもらえるよう、地域のお母さんが旅行者に料理を教える「土間クッキングクラス」スペースを設けた。
雪国文化を未来に託そうと、同じ思想をもった事業者同士が、お互いに切磋琢磨しあいながら、自社の価値を高める努力をする。そのことが、結果的に地域の価値を高めることにつながる。

越後妻有、大地の芸術祭の里が来年開催される地域も近い。
"HATAGO井仙は魚沼の入り口です。
滋味あふれる魚沼の食材、越後湯沢の温泉、温泉水を使ったコーヒー。
食や温泉を通して「魚沼」と出会ってください。
流れる時間も土地のままにゆったり。
籠るのはもちろん温泉街の散策や
外湯もおすすめです。"
出会えて良かった。
いいなと思ったら応援しよう!

