
秩序ある自然界に人間がもたらした禍【本:沈黙の春】
改めて、「沈黙の春」とはよく言ったものだと思う。花々が咲き誇る、新しい学期が始まる、明るい季節であるはずの、沈黙。静けさではなく、闇と気味悪さを感じる。2020年の春、古本屋で買いたかった本を見つけた後、レジへ向かおうとした私の目に、この本がとまった。ちょうど、コロナで一時帰国をした直後。自然が、というよりも、自分の環境が、「沈黙の春」とでもいうような、閉塞感と闇を感じていたので、今が読むタイミングなんだろうなと、手を取った。

翻訳者の解説で、この本の初版の題名は『生と死の妙薬』だったことを知った。題名とは、とても運命を左右するものだなと思わざるを得ない。
著者レイチェル・カールソンが、この本を捧げたかったのは、アルベルト・シュヴァイツァー氏。
そのシュヴァイツァー氏の言葉でこの本は始まる。

「未来を見る目を失い、現実に先んずるすべを忘れた人間。そのゆきつく先は、自然の破壊だ。」
・シュヴァイツァー氏は、医師、神学者、哲学者、オルガニストであり、アフリカでの医療活動に生涯を捧げ、その功績でノーベル平和賞を受賞した方で、「密林の聖者」と呼ばれていた。29歳の頃、読んだ宣教師の活動冊子を読み、「30歳になったら人に奉仕する活動を行おう」と思っていたことを思い出し、医学部に入学。38歳で医学博士の学位を取得し、自らの著作の印税や演奏会活動での収入を資金として、医療施設に困っていたアフリカの赤道直下の国ガボンのランバレネへ。
戦時中、捕虜となり、母国に送還されながら、再度資金調達のためヨーロッパ各地での講演会の実施を行い、ガボンへ戻り、診療所の建設、病院の周辺にエデンの園をつくり、食糧を確保などを行った。
私は、この本を読むまで、シュヴァイツァー氏のことを知らなかったけれど、何よりも「欧米的」だなぁと思ったのはノーベル平和賞受賞での賞金の半分を使いシュヴァイツァー賞を制定し、2年に一度、平和活動に貢献したヨーロッパの人たちに賞金を贈呈したこと。残り半分は、ランバレネのシュヴァイツァー病院の隔離病棟等の建設に充てた、とのことだけれど、なによりも、同胞の方々への「育成」「未来への投資」という意味での賞金贈与はとても心強い。
・1958年1月だっただろうか。オルガ・オーウェンズ・ハキンズが手紙をよこした。まえに、長いこと調べかけてそのままにしておいた仕事を、またやりはじめようと、固く決心したのは、その手紙を見たときだった。どうしてもこの本を書かなければならないと思った。
・資料をたくさん集めて本を書くとなると、優秀な図書館員の腕がものをいう。
・人間だけの世界ではない。動物も植物もいっしょにすんでいるのだ。その声は大きくなくても、戦いはいたるところで行われ、やがていつかは勝利がかれらの上にかがやくだろう。そして、私たち人間が、この地上の世界とまた和解するとき、狂気から覚めた健全な精神が光り出すであろう。
・土壌深くしみこんだ科学薬品は地下水によって遠く運ばれていき、やがて地表に姿をあらわすと、空気と日光の作用をうけ、新しく姿をかえて、植物を滅ぼし、家畜を病気にし、きれいな水と思って使っている人間のからだを知らぬまにむしばむ。
・アルベルト・シュヴァイツアーは言うー《人間自身がつくり出した悪魔が、いつか手におえないべつのものに姿を変えてしまった》
・合衆国だけでも、毎年五百もの新薬が巷に溢れ出る
・化学物質の大部分は〈自然と人間の戦い〉で使われる
・農作物の生産高を維持するためには、大量の殺虫剤をひろく使用しなければならない、と言われている。だが、本当は、農作物の生産過剰に困っている。農地削減に対する補償などをして生産を押さえようとしているが、作物はやたらとつくられ、1962年度には、余剰食糧貯蔵費総額十憶ドル以上を、私たちアメリカ人は税金として納めている。
・人間が密集して住んでいるようなところ、そしてそれも天災、戦争、極度の貧困破滅に見舞われて、とくに衛生設備がいきとどかないときに、疫病を伝播する昆虫が問題となり、防除対策をたてなければならなくなる。だが、科学薬品を大量に使ってもその成果はごくかぎられ、へたをすると逆に事態をいっそう悪化させるばかりである。
・イギリスの生態学者チャールズ・エルトン博士著作『浸食の生態学』
私たちに必要なのは、動物個体群や、動物と環境の関係についての基礎的な知識で、こういうことを知るときにこそ、《大発生や新しい侵蝕の爆発的な力を押えて、均衡を押し進めることができるだろう》
・化学薬品の死の雨が降る
・正確な判断を下すには、事実を十分知らなければならない。ジャン・ロスタン《負担は耐えねばならぬとすれば、私たちには知る権利がある》
・合成化学薬品工業が、急速に発達してきたためである。それは、第二次世界大戦のおとし子だった。
・第二次世界大戦を境にして、無機系の殺虫剤から、《奇跡》の炭素分子の世界への転換が行われたが、むかしの殺虫剤すべてが姿を消したわけではなかった
・DDT (Dichloro-diphenyl-trichloroethane) は、1874年にドイツの化学者がはじめて合成したものだが、殺虫効果があるとわかったのは、1939年のことである。たちまち、昆虫伝播疾病の撲滅、また作物の害虫退治に絶大な威力があるともてはやされ、発見者パウル・ミュラー(スイス)は、ノーベル賞をもらった。
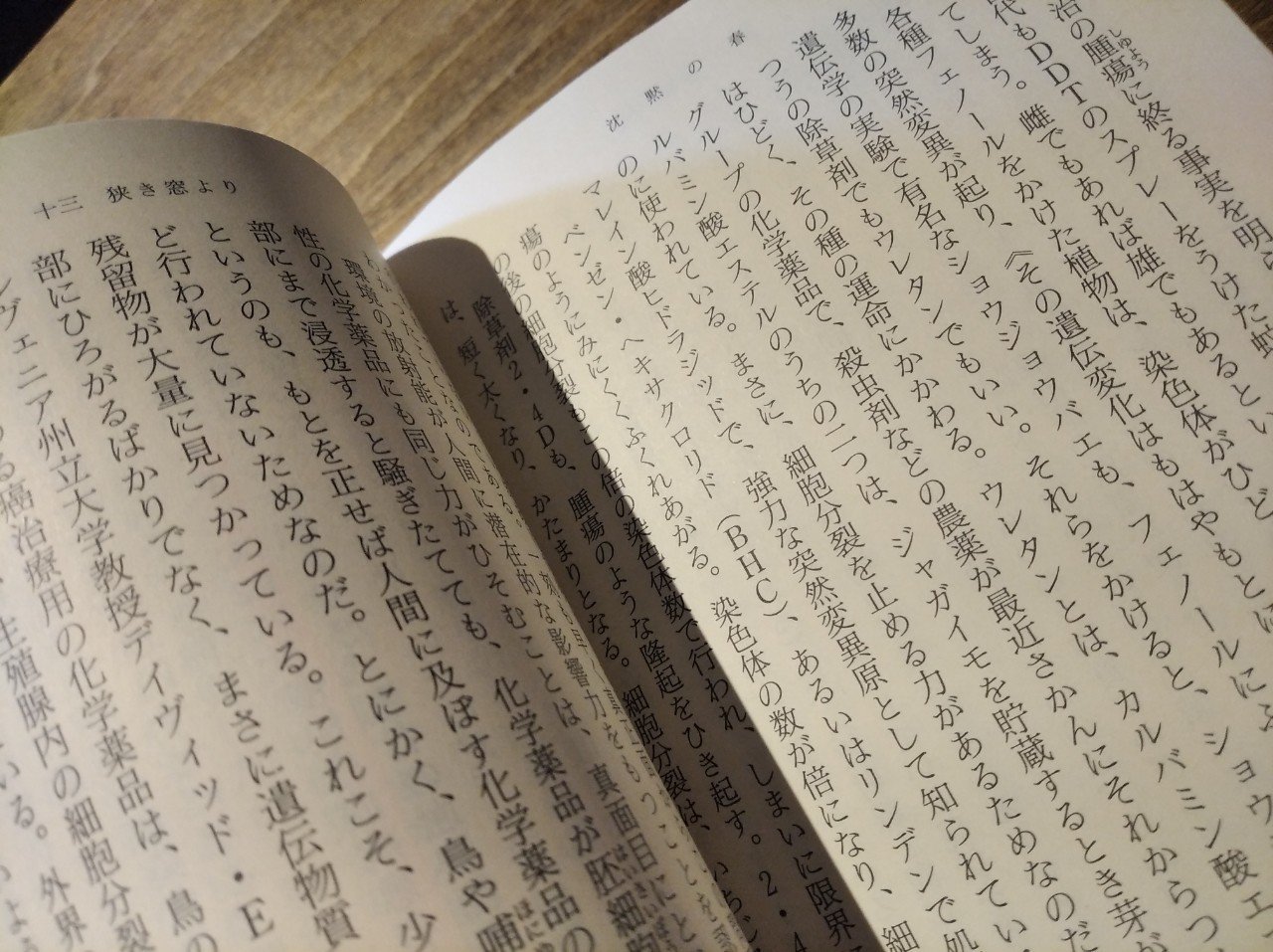
・WHO (世界保健機関) のマラリア撲滅の大運動
ジャワ西部でWHOがマラリアを撲滅しようとしたとき、おびただしい猫が死んだ。ヴェネズエラでも同様。シェルダンの殺虫剤スプレーの犠牲になったのは、野生の動物や、飼犬、飼猫だけではない。羊や食肉用の牛も同じような目にあっている。
・1930年代の終わり:有機リン酸エステルに殺虫力があることがわかった。ドイツの科学者ゲルハルト・シュラーダーが発見している。そのころ、ドイツ政府は、これをひたかくし、人間対人間の戦いに利用しようと、こっそり研究を進めた
・パラチオンは、最もおそろしい毒薬のひとつ。いまでは、フィンランドで自殺と言えば、パラチオンと言われている。世界各地でもパラチオンによる死亡率は、1958年インドでは100件、シリアでは67件、日本では毎年平均336件を数える。
【メモ】パラチオンは、エチルパラチオンともいう。1944年にドイツのバイエル社で開発された有機リン系殺虫剤のひとつ。 DDT、BHCに次いで登場した強力な殺虫剤であったが、急性毒性も強いために人の中毒事故が発生し、農薬としての使用が禁止された。
・動物用浸透殺虫剤は、主に牛につく寄生虫の幼虫の退治に使われる。家畜に大きな被害をあたえるこの寄生虫を防除するために、宿主である家畜の血や組織のなかに殺虫力のある毒をまぜるわけだが、家畜自体はきずつかないように、細心の注意をはらわなければならない。適量をきめるのはきわめてむずかしく、政府の獣医が指摘しているが、少量でもくりかえし殺虫剤を注入すると、家畜のいろんな器官を保護している酵素、コリンエステラーゼをしだいに弱め、今度はそこへ少しでも殺虫剤が入ると、家畜が急性中毒を起こすという。
・奇妙なパラドックス。自然資源のうち、いまでは水が一番貴重なものとなってきた。地表の半分以上が、水ー海なのに、私たちはこのおびただしい水をまえに、水不足になやんでいる。海の水は、塩分が多く、農業、工業、飲料に使えない。
・殺虫剤による水の汚染という問題は、総合的に考察しなければならない。原子炉、研究所、病院からは放射能のある廃棄物が、核実験があると放射性降下物が、大小無数の都市からは下水が、工場からは化学薬品の廃棄物が流れ込む。
・汚染そのものは、実際に目に見えることが少ない。何百、何千匹という魚が死んでみて、はじめてわかる。だが、少しもわからないこともある。
・チャールズ・ダーウィン
本「ミミズの活動による栽培土壌の形成ーならびにミミズの習性の観察」
ミミズが土壌の運搬に基本的な役割を果たすという考えは、ここにはじめて述べられたといってよい
・1960年土壌生態学の会議にシラキュース大学に集まった専門家
《人間のほうでちょっとした間違いをしたために、実り豊かな土壌がだいなしになり、節足動物がこの大地をのっとることになるかもしれない》
・かつて生命に溢れていた世界は無残にも破壊していた
・秩序ある自然界では、草木はそれぞれ大切な、かけがえのない役目を果している
・皮肉なのは、ほかに選択制スプレーという完全に健全な方法があることがわかっているくせに、いままでのやり方にしがみついている
・野生生物にあたえる殺虫剤の影響を調査する研究費用は、自然調査局からイリノイ州議会に提出する年予算の要求に含まれていたが、いつもまず最初にけずられる。1955年、ほそぼそと続いていた研究費は支給されなくなった。
・イリノイ州の生物学者たちは十分研究費がもらえず、最低の被害しか調べられなかった。8年間に支給された野外調査研究費は、わずか6000ドル。同じ期間に防除に州から支払われた金額は375000ドル、さらに中央政府から何千ドルかが追加されている。科学的防除予算から研究費にさかれた費用は、全体の1パーセントにすぎない。
・自然の美しさ、自然の秩序ある世界ーこうしたものが、まだまだ大勢の人間に深い、厳然たる意味をもっているのにもかかわらず、一握りの人間かことをきめてしまったとは。
・ブリティッシュ・コロンビア州:少なくとも、主な4つの河川のサケは文字どおり全滅した
【メモ】河川か。メコンデルタの河川では、今何が起こっているのだろう。生態系。まだ、何も知らない。
・フィリピン、中国、ベトナム、タイ、インドネシア、インドでも同じようなことがある。こうした国の海岸沿いには、浅い池が散在していて、サバヒーが養殖されている。サバヒーの幼魚がどこで生れるのかは明らかでなく、突然どこからともなく幼魚の群れが沿岸海域にあらわれる。網にかかった群はすぐに池に放され、養殖される。東南アジア人、またインド人などの米食民族にとってサバヒーは動物性たんぱく質の大切は補給源なので、太平洋科学会議は国際的に学者の協力を求めて、神秘につつまれたこの魚の発生地を探り、大規模な養殖をはじめようとしていた。だが、化学薬品スプレーのため、いまある池がすでに大きな被害をうけ、フィリピンでは、蚊防除のため養魚場経営者がひどい損害をうけた。ひとつの池に約12万匹のサバヒーが飼われていたが、たった一度飛行機が上空を飛んで撤布したがけで、半数以上が死んだ。あわてて、すぐに池の水を入れかえて毒をうすめようとしたが、手おくれだった。
・問題は重大であるのにくらべて、研究費はあわれなほど少ない
・1958年頃はじまったヒアリ駆除計画。ただ、ヒアリは、いろんな昆虫、それも人間に害をあたえると思われる昆虫を主に食べる。ミシシッピ州大学の調査やアラバマの研究の意見。《過去5年間、植物がヒアリの被害をうけたという報告は一度もない》
・かげで糸を引く資本家にだまされていい気になっているが、ふつうの市民は、自分たち自身で自分のまわりを危険物でうずめている
・合衆国には食品薬品管理局という機関があって、消費者に殺虫剤の害が及ばないように管理しているが、思うとおりに活躍できない。第一に、州から州へと動く食品を管理するだけで、一つの州内部で生産し消費される食べ物にまでその力は及ばず、どんなにひどいことが行われても、口をさしはさめない。第二に、食品薬品管理局の検査官の人数が少ないことも致命的である。範囲がひろくいろんな仕事があるのに、全部門をあわせて600人もいない。そのひとりからきいたところによると、いまの能力でチェックできるのは各州のあいだで取引される作物のごくわずか、1%にもみたない。これでは、統計的にサンプルとしてチェックする意味がない、という。
・いまは合衆国では学童の死因の第一位がほかの病気ではなく癌
・私たちみんなが《発がん物質の海》のただなかに浮かんでいるとはある学者の言葉だが、このようなことをきけば、だれもがあわてふためいて、ああもうだめだ、と思いがちだ。《望みはないのではないだろうか?》《このような癌発生の原因になるものを、私達の社会からなくそうとしたって無理じゃないだろうか。そんなむだなことはやめて、癌をなおす薬の発見に力をそそいだほうがいいのではないのか》ー最後におちつくのは、たいていそんなところだ。ヒューバー博士は、何と答えるだろうか。何年にもわたって癌研究の分野で数々のすぐれた業績をあげ、その発言が高く評価されている博士の答えは、こうした問題に思いをこらし、一生を捧げた人だけがもつことのできる豊かな経験と判断の正しさに裏うちされている。博士の答えはこうだー癌と私たちの関係は、19世紀の終りごろいろんな伝染病がはやったのに似ている。病原となる有機体があって、そのためにいろんな病気が蔓延することを明らかにしたのは、パスツールやコッホのかがやかしい業績だった。

・人間の環境に病気を発生させる無数の微生物があることがわかりはじめた。こうして、ほとんどの伝染病が押えられ、なかには事実上姿を消してしまった病気もある。このかがやかしい勝利がおさめられたのは、予防と治療という2つのことがあったからだ。《魔法の弾薬》とか《奇跡のクスリ》のためだと、ふつうだれでも考えるが、伝染病を押えることができた本当の理由は、環境から病菌を消し去る対策をとったことにある。100年以上も前にロンドンでコレラが大流行した。そのとき、ジョン・スノーというロンドンの医者がコレラ発生の地図をつくり、その発源地をつきとめた。その地域の住民は、ブロード街にある一つの井戸から水をくんでいたのだった。さっそく、井戸のポンプの把手をはずしてしまった。これこそ疑うまでもなく予防医学の模範的な実践そのものだった。コレラ菌を殺す魔法の薬ではなく、環境からコレラ菌を絶滅することにより、伝染病を押さえることができたのだ。
・自然は逆襲する
自然淘汰という手段に訴えて、昆虫たちは一族をあげて化学薬品に反撃を開始してきた。科学雑誌を開いてみれば、1958年にすでに、自然の均衡がくずれて大量発生した50種類あまりの昆虫があがっている。化学薬品スプレーは、まさに押さえようとしたその昆虫が、スプレー後、大発生する。
・化学工業の大会社が大学に金をつぎこむ。殺虫剤研究の資金を出すからなのだ。ドクター・コースの学生たちは、たっぷり奨学金が与えられ、魅力のある就職口がかれらを待ち受けている。だが、生物学的コントロールの研究にそんなにお金が出ることは決してない。生物学的コントロールの研究など援助すれば、化学工業はみずから自分の首をしめることになるという簡単な理由からだ。そしてまた生物学的コントロールの研究は、州や中央政府所属の機関にまかせられている。しかもそこにつとめている人たちに払われている給料は、はるかに低い。
・人間がかかるいろいろな病気が昆虫と関係があるのは、周知の事実である。疾病と病菌媒介者、または伝播動物との関係をならべてみれば、発疹チフスーキモノジラミ、ペストーネズミノミ、アフリカ睡眠病ーツェツェバエ、いろいろな熱病ーダニ類など数かぎりがない。
・殺虫剤に抵抗力をみせる昆虫の数はおびただしく、各大陸、各群島、そういう報告のない国はない。
・1945年から46年にかけての冬には、200万あまりの日本人、韓国人がシラミにとりつかれていた。1948年には、スペインにチフスが流行し、このときにもDDTが使われたが、このときは失敗している。
・ブリーイエ博士《私たちはほかの防除方法を目指して研究にはげまなければならない。化学的コントロールではなく、生物学的コントロールこそ、とるべき道であろう。》
・私たちは心をもっと高いところに向けるとともに、深い洞察力をもたなければならない。残念ながら、これをあわせもつ研究者は数少ない。
解説
・人におくれをとるものかと、やたらに、毒薬をふりまいたあげく、現代人は根源的なものに思いをいたすことができなくなってしまった。こん棒をやたらとふりまわした洞窟時代の人間にくらべて少しも進歩せず、近代人は化学薬品を雨あられと生命あるものにあびせかけた。精密でもろい生命も、また奇跡的に少しのことではへこたれず、もりかえしてきて、思いもよらぬ逆襲を試みる。生命にひそむ、この不思議の力など、化学薬品をふりまく人間は考えてもみない。《高きに心を向けることなく自己満足におちいり》、巨大な自然の力にへりくだることなく、ただ自然をもてあそんでいる。
・化学薬品は一面で人間の生活にはかりしれぬ便宜をもたらしたが、一面では自然均衡のおそるべき破壊因子として作用する。
・家畜や作物は、いずれも野生生物から進化した。人間の利用目的にかなうように、改良されたもの。この改良という言葉自体、はなはだ人間本位の用法である。人間の利用する部分、豚ならば肉、稲ならば種子、キャベツならば葉、ダイコンならば根、といった各器官を、人間の利用に有利なように改造することをさしているわけだが、自然界の生物としていたらどういうことになるか。それは身体の一部の器官だけが、他の器官とくらべて不釣合に肥大化させられることを意味している。つまり生物としては畸型(きけい)になり、生活能力において脆弱化する。---それらを育てるためには、人間の手による”保護”が不可欠となる。その保護こそ、家畜については飼育技術、作物については栽培技術にほかならない。土壌をやわらげ、水はけや空気の流通をよくし、日照条件を考え、大量の肥料を投入する。そうなった田畑は、ある種の野草(雑草)や野生動物(害虫)にとっても、いよいよ絶好の生活環境と化する。そこでそれらを排除するため、人間の介入がいっそうエスカレートせざるを得ない。農業の発達とは、とりもなおさずこのイタチごっこのくりかえしであった。

・解決策は、いぜん暗中模索のさなかにある。1973年3月 評論家
読み終わったあと、心に残ったのは、「自然」や「化学薬品」という言葉ではなく、「人間の政治権力」であった。削られる生物学的コントロールの研究予算。化学工業の大会社は、ドクターコースの学生に大金をつぎ込む。
人間対人間の戦いに利用される化学薬品。人間が自ら招いた禍。同時に、国の国家戦略としての農業政策、そして食の安全保障としての研究費用への投資、薬品だけを全否定するのではなく、世界の人口増に伴う生産量の増加が必須とされる環境下での今の代替案が求められていると思った。
レイチェル・カーソン
1907年、アメリカのペンシルヴァニア州で生まれる。ジョンズ・ポプキンズ大学の大学院に進学し、動物学を専攻。25歳で学位を得て、アメリカ合衆国漁業局につとめる。そのころから勤務のかたらわ、海洋生物にかんするエッセイを書きはじめる。45歳のとき、文筆に専念する目的で、いっさいの官職をしりぞいた。1964年の春、日本語訳の初版が公刊される直前に、亡くなった。
創造の場所であるカフェ代のサポートを頂けると嬉しいです! 旅先で出会った料理、カフェ、空間、建築、熱帯植物を紹介していきます。 感性=知識×経験 மிக்க நன்றி
