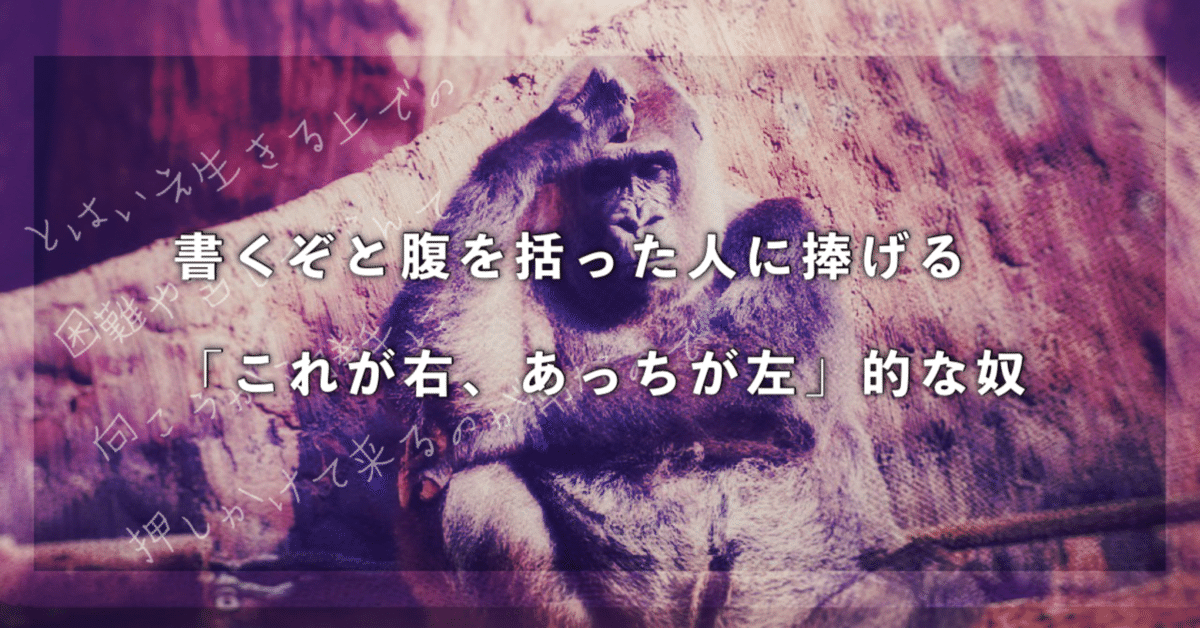
5000字以下の掌編を書くメソッド:中編
掌編の書き方についてアレコレ書く記事、中編です。
(前回の記事はこちら↓)
主にマインドセット(と、発破掛け)を行っていた前回に対して、今回は実践編として具体的な手法であったり、書く上での考え方などについてまとめたつもりです。
前回に引き続き、
・3,000~5,000文字程度の
・1つのテーマを
・1場面で語り切る作品
という作品形態(以降「掌編」と呼びます)での執筆を想定した話となっております。
ですが、その他の長さでも応用の効く所はあるかもしれません。
皆様の執筆活動の一助となれましたら幸いです。
結局のところお前は誰についての何を書くのか?という話
とっぱじめから面倒くさい話を始めてしまいますが、小説って何なのでしょう。
辞書によれば、このような意味あいだそうです……
(英novel の訳語) 文学形態の一つ。
作家の想像力・構想力に基づいて、人間性や社会のすがたなどを、登場人物の思想・心理・性格・言動の描写を通して表現した、散文体の文学。
一般には近代小説をさすが、国文学史では、古代の伝説、中古の物語、中世の草子、近世の読本などの散文体文学をもさす。
(iOS版『精選版 日本国語大辞典』より。改行と太字強調は筆者の手によるもの)
この、「登場人物を通して」という部分に表現形式としての肝がある、というのが個人的な解釈です。
では具体的にどう表現するのか?…の答えは、書き手によって様々です。
が、こと掌編における語り方でしたら『主人公』と『主人公を観察する別の誰か』の、2人の登場人物を出すというやり方を筆者はお勧めします。
『主人公』が物語のテーマを体現し、それを『別の誰か』の視点で描写する……という形式です。
読み手にとっても書き手にとってもわかりよく書きやすいのがお勧めする主な理由となります。
役割分担を明確にすると、書きあぐねた際にも要素の整理整頓を行うことで
問題点の洗い出しがしやすいのです。
個人的にそこそこの数の掌編をものして来た中でも、メインキャラクターを2人出して話を転がすのがやりやすい書き方の一つでした。
ではそれ以上の数、あるいはそれ以下(つまり1人)のキャラクターを出すのはNGなのか?というと、決してそんなことはありません。
ですが、2人の登場人物による役割分担の考え方はそれ以外の人数構成の話づくりにも応用の利くものですので、まずは基本形と思って一読いただけると幸いです。
コイツはどんな奴で、ナニをしでかしてくれるんだ?を捏ねて丸めて大きく振りかぶれ
しかし、物語のテーマを体現する『主人公』といっても具体的にどのようなものを指すのでしょう?
また、登場人物のどちらを主人公に据えるべきかわからない、あるいはどちらも同じくらい重要なキャラクターなのだ、という場合も有るかと思います。
まず最初に断っておきますが、主人公か否かというのはキャラクターに優劣が付くことを意味している訳ではありません。
あくまで便宜的な役割分担と捉えていただければと思います。
マンモスを狩るために槍を片手に何キロもぶっ通しで駆けられる奴も居ます。
そして狩った得物を平等に分配できるスキル(例えば、なんと20までの数を数えられるとか!)を持った奴も居るのです。
どちらもコミュニティには必要な能力です。
そんな感じの話です。
ということで、どっちがどっちの役回りに向いてるのか?のざっくりとした判別法を書いておきます。
2人を比較して、より「面白い奴」が『主人公』。
より「喋れる奴」が『別の誰か』です。
漫才に例えてボケが『主人公』でツッコミ向きだと『別の誰か』……という説明ですんなり刺さる方もいらっしゃるかも。
あるいは、登場人物のいずれかに対して「物語を通じて、ある一面を引き出したい」と作者が望んでいる場合も簡単です。
その人物こそが、これから書こうとする掌編の主役たり得ますから。
先ほど、『別の誰か』を「より『喋れる』方」と形容しました。
ただこれにはちょっと補足が必要かなとも思います。
まず、必ずしも対外的に弁の立つ人物でなくて良いです。
「このキャラは口下手って設定だから駄目だ……」と思わないで欲しいのです。
そもそも寡黙な人物というのは概して思慮深いもの……という要因もあるのですが、そもそもの『別の誰か』の役回りとは『主人公』をその思考や価値観でまなざすことです。
ここで発見される何がしかが、物語のテーマとなります。
前編で述べた通り、掌編のテーマは1つに絞り込むのが基本です。
発見される物事についても一言で意味あいが説明できると良い感じ。
テーマが「顔が近い」ならば『別の誰か』に「まつ毛長いな……」と言わせたり思わせたる。
テーマが「健康は大事」ならば『別の誰か』に「ああはなるまい」と思わせたり、あるいは「やっぱりコイツは好物を食べて笑ってる方が良い」と思わせたりすればOK!……といった感じ。
そして、発見に至るまでの間にどのような交流があるのか(あるいは「そんなものは無かった」も十分にストーリー足りえます)を、書く。
すると、そこには何らかの物語が立ち上がっている。
……ことが多いです。
ここまでは『主人公』と『別の誰か』の両者がある程度、心理的/物理的/社会的に近いのを想定しておりましたが、登場人物の間にこれといった明確な関係が取り結ばれていなくても物語を成立させることはできます。全然余裕です。
不意に遭遇した見知らぬ誰かの言動や振る舞いに何かしらの感慨を抱く……というのは、割りによく見られる光景です。
「ファーストフード店でだべっている女子高生の会話を脇で聞いていて色々な感想を抱く」
という、SNSでもよく見るフォーマットのアレですね。
特定のコンビが前提となった話なのだけれど、片割れがその場に居ない時の姿を活写したいのだ、という時などにはかなり使えます。
これで「どんな人物を登場させ、何を書くのか」をある程度定めることができました。
次項では「では、どのように語るのか?」について掘っていくことにします。
神の奴はけっこう面倒くさい、あるいは本文をどうするかについて
構想ヨシ!パッションヨシ!水分とおやつの準備ヨシ!
準備万端でさあ本文を書くぞ!
……といった段階でで手が止まった経験はありませんか。
筆者はあります。それも、沢山。
「一人称と三人称、けっきょくどっちで書けばいいのさ!!?」
こんな調子で頭を抱えて塩漬けになったテキスト群は数知れず。
と、いうのもですね。
一人称とは、登場人物自身の主観による語り口であり、三人称とはいわゆる神の視点から物事を描写するものです。
これの厄介な所は、同一の作品内でこれらの記述を混ぜて書いてはいけない――少なくとも、そういうことになっている――ところに有ります。
つまり、最初にどちらの書き方を採用するかをきちんと決めないと本文に取り掛かることができないのです。
(途中で方針が変えた場合、異なる人称で書かれた文章はほぼほぼ全捨てとなります。というか、下手に改稿する方がよほど手間がかかってしまうので……)
これ、結局はどちらが正解というものでも無いのですが、人称をどうすると、どんな意味があってどっちがどういう風に何に向いているの?という指標が無いと起こりがちな迷いです。
結論から述べると、筆者のお勧めはまず一人称で書くことです。
が、書き手による向き不向きというか、作風や書き手の性格次第でどちらが得意かけっこうはっきり分かれます。
(少なくとも「三人称による文体が掌編に不向きである」という主張を展開したい訳では全く無いです。……というのを念のため補足しておきます。何なら現在の筆者はむしろ三人称を得意としております)
無謬性とかが気になるお年頃
では、まず最初に三人称視点の特徴について。
神の視点による文体、つまり三人称視点を採用した時のメリットとデメリットを簡単に挙げると
・メリットは「書ける物事の自由度が高いこと」
・デメリットは「書いても構わない物事の範囲がべらぼうに広いこと」
になります。
はい、おんなじ事を言ってますね。
神さまの視点とは、人物の内面や隠している物事、生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答えなどの全てがつまびらかに観測できて、しかも決して間違うことの無い、そうした代物です。
で、あれば、神の視点を借りて書くということはどういうことか。
物語を形作る世界であったり、人間であったり、と、いった情報のなにをどこまで書くべきか、書かざるべきか、書くとしてどのようにしたためるのか、それら全てが作者の手に委ねられているのを意味します。
書く/書かないを定める基準はただ一つ。「そうした方が面白いかどうか?」です。
このフレーズに燃えるタイプの人、三人称向きです。
信じるままに進んでください。
描写は一人称で煮詰めていけ
なお、つい最近までの筆者は、三人称視点のそうしたバカでかい許容範囲に完全に気後れしていました。
「自分の文章の型」のようなものすら曖昧だった時期でしたので、1文字タイプする毎に常に判断を迫られているも同然だったのですね。
そういう場合、逆説的ですが執筆にあたって、ある程度の縛りを設けるのが打開策となり得ます。
例えば、語り手を一意に定めてしまって、その人物が認識している範囲の情報だけを扱うこと。
つまり、一人称による文体です。
主観人物を決めることの最大の特徴は「当人がその場で知らない・知りようがない物事は書けない」という覆せない縛りがあることです。
そしてこれは前述した神の視点と同じく、利点と欠点が表裏一体であることも意味します。
しかし、主観人物とはすなわち意志と思考を持つ、独立した一個の主体です。
(話によっては人間ではない場合があるのでこのような迂遠な表現を用いております)
その場でわからない事はあれど、今手元にある物事をつきあわせることで、
当人なりに真相を推理したり、予測したりすることはできます。
これってつまり、物語の中の「葛藤」にそのまま繋げられるのです。
ある宙ぶらりんな物事があります。
語り手(=主観人物)がその周囲を回りながらあれこれと考えを巡らせたり、真実を知るために行動を起こしたりします。
結果、宙づりであった物事が収まるべき所へ収まり語り手に真相が開示されたり、あるいは謎めいたまま語り手が取り残されたり。
……もうお気づきかと思いますが、こうした一連の流れは、そのままストーリーのあらすじに成り得ます。
語り口のうねりというか、ストーリーの起伏というか、文章の緩急というか。
一人称の自由でなさには、こうした味付けがやりやすいという側面もあります。
ある程度人物の情念と対話で話を転がすスタイルの人ならば、一度挑戦してみる価値はあると思います。
小説執筆におけるEXP加算タイミング
当記事、というか筆者のスタンスは「なるべくなら完成させてった方がええよ」です。
が、一方でこれを数年前の自分にまんま言ったらほぼ間違いなくキレられるか、心を閉ざされるのがオチだなとも思うんですよね……。
今現在の筆者としてはエンパワメントのつもりで書いてはおりますが
そんなん余計なお世話というか、単なるプレッシャーにしかならない場面、あります。
そういう時に有用な方策は、また別の道にあるのでしょう。
これは、書こうにも書けない時期を潜り抜けた身としての実感です。
とりあえず当時を振り返って思うのは、なんか楽しいことして、十分な休養を取るのがなんだかんだで一番効いたな……という事ですね……!
という訳で、小説のことは忘れても頭の隅に引っ掛かったままでも構わんくらいの感じで各位なんやかんや生きてくのが良いんだろうな、と。
物書きとはクソゲーと見つけたり
で、ここからは通り抜けた先の話になるのですが……。
単純な文書生成のスキルは、これはもうやればやっただけ身につく類のものです。
が、いわゆる表現力という分野――端的に、また小説に関してならば
「どう書くか?」に相当する部分――は、執筆から遠ざかっている時期にも
モリッと上達していることがね、あるんですよ!
いわゆる人間の幅という奴がモロ跳ね返って来るのが、それ!ということでもあります。
あるいみ怖い話です。
なのでもう、身も蓋も無いんですが、人生が丸ごと芸の肥やしみたいな側面、あります。
とはいえ生きる上での困難や苦しみなんて向こうから勝手に押しかけて来るのが常なので敢えて苦痛を拾いにいく必要は無いかなあ、とも。
それが貴方にとって楽しい、あるいは必要な行いであるならば、大いに遊んだり、観たり読んだり、歌ったり踊ったり……するのを許していく。
それがより良い文章を書ける自分を手に入れる近道、の、ようです。どうやら。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
