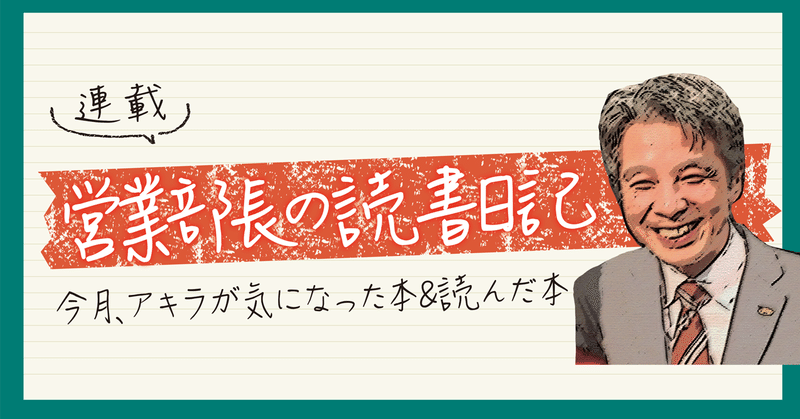
■読書日記<第13回> ハラスメント研修を機に「働き方」を問い直す
理不尽に領土を侵されたウクライナ紛争の解決はいつになるのでしょうか。21世紀となり、いくら技術や思想が進んでも、人類は戦争をなくすことができずに残念です。まるで現代の問題すべてが集約された縮図を見せつけられているようですが、まだまだ予断を許しません。
さて、GWの「子どもの日」3連休は、久しぶりに再開された「上野の森親子ブックフェスタ」に、PHP研究所のブースを出店して参加しました。いくら世界で凄惨な紛争が続こうが、新型コロナウィルスの猛威が収束しなかろうが、晴天のなか、平和な日本には子供の歓声が満ち溢れました。なにしろ上野には、パンダの動物園や恐竜の博物館があります。上野駅前に降り立てば、立派な幾歳月の樹齢を重ねた銀杏の木も迎えてくれます。直接的に小さな読者(お子さん)に弊社の児童書をお薦めできたのは、久しぶりに嬉しい経験となりました。大事そうに児童書を胸に抱える子供たちの未来に、幸多かれと祈ります。
≪最近の購入リスト≫
『働きやすさこそ最強の成長戦略である』大槻智之(青春出版社)
『800日間銀座一周』森岡督行(文春文庫)
『読書会という幸福』向井和美(岩波新書)
※八重洲ブックセンター八重洲本店のイベント参加時に購入。大槻さんのビジネス書は週間ベスト1位でした
『李陵・司馬遷』底本篇・図版篇・注解篇/中島敦(中島敦の会)
『日本人の戦争』ドナルド・キーン(文春学藝ライブラリー)
『ひとり灯の下にて』一般財団法人ドナルド・キーン記念財団編(新潮社図書編集室)
※県立神奈川近代文学館で購入
『地政学でわかる わたしたちの世界』ティム・マーシャル(評論社)
※上野の森親子ブックフェスタの出店ブースで購入。
『歴史とは何か』E・H・カー(岩波書店)
※三省堂書店そごう千葉店にて、お世話になった店長さんの退職連絡を受けて挨拶にうかがった際に購入
『希望の教室』ジェーン・グドール(海と月社)
『ホーキング,ホーキング』チャールズ・サイフェ(青土社)
※三省堂書店有楽町店にて、これもまた、お世話になった店長さんの退職に際して購入
『シリーズ歴史総合を学ぶ① 世界史の考え方』小川幸司編/成田龍一編(岩波新書)
『不条理を乗り越える 希望の哲学』小川仁志(平凡社新書)
※近所の住吉書房保土ヶ谷店にて購入
『本屋という仕事』三砂慶明編(世界思想社)
※著者よりご寄贈いただきましたが、後日、八重洲ブックセンター本店にて改めて購入
■6月1日
『李陵』『運命』⇒はかりしれない運命をせいいっぱい生きぬく
前回のトルストイ『ハジ・ムラート』からの連想で、中島敦『李陵』、幸田露伴『運命』を書棚から取り出しました。
作家・中島敦は享年33歳(先だって紹介した織田作之助と同じ)、中島撫山(ぶざん)という著名な漢学者を祖父にもつ漢学系知識人の家に生まれ、漢学のみならず英語もこなし、南洋諸島から古代中国、アッシリア、エジプトと、小説の舞台をみれば世界文学をも希求したといえる作家です。中国古典伝説に立脚した『山月記』は中国語に翻訳されて上海で世評を得たことに、評論家の中村光夫は感嘆しています。
ちなみに中島敦33歳(没年齢)と同年、1909年生まれの文学者に、太宰治38歳、大岡昇平79歳、埴谷雄高87歳、松本清張82歳、坂村真民97歳、まどみちお104歳がいます(文学者に関して言えば豊穣の年ですね。ちなみに大女優の田中絹代67歳、映画評論家・淀川長治89歳も同年生まれでした)。
若くしての夭逝作家ということでいえば、織田作之助同様ですが、作風は異なり、どちらかといえば”硬文学”といわれています(戦後の高等学校の生徒はみな『李陵』に心酔していたと、評論家の半藤一利さん振り返っています)。岩波文庫の歴代アンケートトップは『きけ わだつみのこえ』だそうですが、もちろん『山月記・李陵』も上位です。
中島敦の作家としての活動は実質、亡くなる直前のわずか数年間で、主要な作品も、ほぼ短編ばかり十数篇。世評の認める傑作は『李陵』『弟子』ですが、私には迷いの多い時期の『わが西遊記』『かめれおん日記』も心に残っています。芥川賞を逃した『光と風と夢』は、スティーブンソン(『ジキル博士とハイド氏』『宝島』などの大衆的な英文学者。じつは夏目漱石も愛読者でした)を採り上げた貴重な作品で、『山月記』ともども作家のあり方を考えさせるものでした。
中島敦の作品では、知名度としては教科書でお馴染みの『山月記』がトップでしょう。1950年、『新国語』にいち早く収録され、以後2019年までに262冊に採用されています(中島敦と一高、帝国大学時代の友人だった文部省教科書国語課長の計らいだそう)。いったい何千万人? の学生が読んだことでしょうか。
話は逸れますが、かつて谷沢永一さんは、『山月記』の詩人になれずに虎になった李徴(りちょう)が資質としては第一流のものであるにも関わらず、国語のテストで、「第一流の作品となるのには、何処か(非常に微妙な点に於いて)欠ける所があるのではないか」の「欠ける所」とは何か、という本来は答えるべからざる設問をあえてする現代国語指導要領の設問に憤慨されていました。
「昔も今も一流の芸術が成立する『原因』など、決して誰にも解りはしないのである~文学の理解を余りにも低次元に、安易に傲慢に割り切る現代国語は、人間性に対する深い畏れを欠く故に、いっそ無い方がましであろうと思われる」と怒っています(「現代国語自惚れ鏡」電波新聞1981年9月8日)。授業で読むぶんにはいいですが、テストにしちゃいけないようです。
さて、中島敦の作品『李陵』ですが、トルストイ『ハジ・ムラート』同様、敵方に投降した騎都尉(きとい/前漢以降の官職名)・李陵(りりょう)を主人公とした物語です。漢の武帝の時代、匈奴征伐に名乗りを上げるも、種々の事情からやむなく無謀な戦いに赴くことになり、武将として善戦するも敵方に投降し、ついには死処を失い英雄になりそこなった人物です。
また、その囚われの李陵を弁護して屈辱的な宮刑(きゅうけい/去勢する刑罰)を受けた司馬遷も登場し、『史記』成立の経緯も語られます。さらに三人目の登場人物に蘇武(そぶ)がいて、司馬遷と同じく胡地(胡国の土地。未開・野蛮の地)に囚われながら、あくまでも節を曲げずに帰郷を果たす姿に感動を覚えました。天と人との相克を扱った優れた歴史小説です。つい一緒に読み返した短編小説『弟子』(ていし)の、師・孔子を慕う子路(しろ)の君子としての壮絶な生き(死に)ざまも忘れられません。
一方、幸田露伴の『運命』は、中国を題材として最も成功した日本文学といわれます。初出は雑誌『改造』1919年4月創刊号。中国明時代初期の骨肉を争う内戦を採り上げたものでした。何度かチャレンジしていますが、いまだに読み切れていません。なにしろ、幸田露伴とは培ってきた教養の質が違います。本当をいうと、児童向けに翻案(?)した田中芳樹『運命 二人の皇帝』(講談社文庫)を読んで感心したことがあるのを思い出しました。
田中芳樹は、幸田露伴『運命』を「巨大なはかりしれない運命のもとでせいいっぱい生きぬいた人々の姿をあざやかに描き出した。その作品は、つぎのように書きだされている。”世おのづから数(すう・運命)といふもの有りや。有りといへば有るが如く、無しと為せば無きにも似たり……”」と、引用を最後に『運命 二人の皇帝』を終えています。
幸田露伴の『運命』を読むに、ほるぷ出版のふりがなと注が丁寧に用意されたものを買いました。いずれ森鴎外の『舞姫』のように、平易な現代語訳も発刊されるかもしれませんが、なんとか、その前に読了したいものだと思います。
武田泰淳は中島敦全集推薦の辞として、杜甫の詩句「偶題」から「文章は千古の事、得失、寸心知る」を挙げていました。意は「文章は永遠不滅の大事業であるが、文章の可否得失については、心で見分けることができる」。中島敦の真価を知る寸心は、すべての人に脈々と受け継がれているといいます。大切なことは心で見なくっちゃね。
■6月18日
『検察側の証人』⇒「この結末は誰にも話さないでください」
個人的に参加している「深夜の読書会」で指定されたテキストを読みました。またもや法廷ものミステリーです。
アガサ・クリスティ著『検察側の証人』(『死の猟犬』ハヤカワ文庫所収)
アガサ・クリスティ著『検察側の証人』(戯曲・ハヤカワ文庫)
ビリー・ワイルダー監督映画『情婦』(20世紀フォックスホームエンターテイメントDVD)
最初にクリスティが短篇の『検察側の証人』を書いたのは1925年、二つの世界大戦の端境期でした。クリスティ35歳、創造性全開の時期となります。その翌年には、名を成した『アクロイド殺人事件』が執筆され、私生活で謎のクリスティ失踪事件も起きたころでした。
その数十年後、1954年に敏腕プロデューサーのピーター・ソーンダーズに見出され、当時、興隆を極めていた舞台演劇の脚本として『検察側の証人』は生まれ変わりました。クリスティ63歳、精力的に儲かる戯曲執筆をしていた時代です。
さらにハリウッドでマレーネ・デートリッヒを擁して映画化されたのが、4年後の1957年です(当時、最高の原作金額で『情婦』として映画化)。当初の作品と異なる点は、舞台、映画ともに第二次世界大戦の傷痕が色濃く残されたことです。イギリス人の主役の一人レナード・ボウル(短篇33歳、戯曲27歳という設定。映画の俳優は総じて高齢気味かも)は、戦争でドイツに赴き、憎むべき敵国人の恋人を連れ帰った帰還兵という設定になります。移民問題も影を落としていました。
知り合った老婦人を撲殺した疑いで逮捕されたレナードは、戦争で調子が狂ったといいながらも、あくまでも明るい誠実さで無罪を主張します。その天性の魅力は数多の年上女性だけでなく、老練な弁護士まで籠絡してしまいました。このあたりの機微が、本作品の読みどころでしょうか。もちろん、その後のミステリーならではの展開が肝ですが。短篇と舞台・映画とでは、結末が異なります。法廷のシーンはロンドンのオールド・ベイリー(中央刑事裁判所)が舞台だそうで、覗いてみたい気がします。
とにかく、小説、戯曲を読み、映画とたどると、メディアミックスというよりも、これはコンテンツの必然的な発展形態なのかなと思えます。優れたコンテンツはマスをめざします。近年になっても、本国BBCやフジテレビ制作による同名のテレビドラマまで放映されているのは、その現れです(ドラマ未見)。
私としては、やはり最後にたどり着いた映画の結末がいちばん印象的でした。映画や舞台では「この結末は誰にも話さないでください」と喧伝されただけのことはある、どんでん返しの連続ですが、私は病気(糖尿病?)で満身創痍の愛すべき映画版の弁護士が、騙されっぱなしが判明したあとでも新たに全力で弁護すべき被告を見出し、戦闘態勢に入る結末に希望を感じました。映画の弁護士役は、チャールズ・ロートンというイギリスの名俳優です。舞台でも同じ役を演じ、舞台登場初代のエルキュール・ポワロの探偵役も演じたそう。いつか機会があれば、本作品の舞台を劇場で観てみたいものだと思いました。
■6月25日
『働きやすさこそ最強の成長戦略である』
⇒誰もが幸せになれる「働き方」とは?
八重洲本店さんのイベントに参加した帰りに購入した本書には、深く考えさせられました。法学部出身で労働基準法も勉強したはずですが、憶えていません(苦笑)。著者は、「近い将来、働きやすい日本の社会を実現できると信じています」と力強く説きます。本当に幸せな社会をつくる夢を持たれている方で、すばらしいと思います。
みんなが幸せになれる働き方って何でしょう。少なくとも私は、これまで自分が「働いている」「働かされている」という意識はなかったように思います。ずいぶん無茶な働き方をしてきたかもしれませんが、心身の健康を害することがなかったので、個人的には幸いでした。感謝しかありません。
私個人はさておき、やはり一緒に働く人、関わりのある人すべてが幸せな社会が理想ですので、これからも考えていかなければなりません。著者は、働き方としての旧来の「メンバーシップ型」と新しい「ジョブ型」を対比し、そこに「フリーランス型」を合わせようとしているのかなと思いました。現代のさまざまな問題が集約される「働き方」について考える際には、有効なビジネス書だと思います。
といいながら、じつは会社でハラスメント研修を受けたばかりだったので、つい買ってしまった一冊です。上司が営業マン個々人に割り振った販売目標にしても、会社の事業計画に基づいた数字なのでべつに問題ないと思っていましたが、いまは社会通念に照らし合わせて妥当な目標かどうかが重要で、過剰な目標はパワハラになり得るとかで、勉強になりましたし、部員の「働き方」を見直す契機となりました。
最後に、PHP研究所のビジネスマン向け刊行物に、電子季刊誌『[実践]理念経営Labo』(PHP理念経営研究センター)が新たに加わりました。人と組織の可能性を発見する研究誌です。創刊号(2022.4-6)の特集は「理念浸透のしかけ」、理念を大事にしている魅力的な経営現場を紹介しています。無料配布の刊行物ですが、紙版もあります。ぜひ一度お目通しいただき、お役に立てていただければ幸いです。

